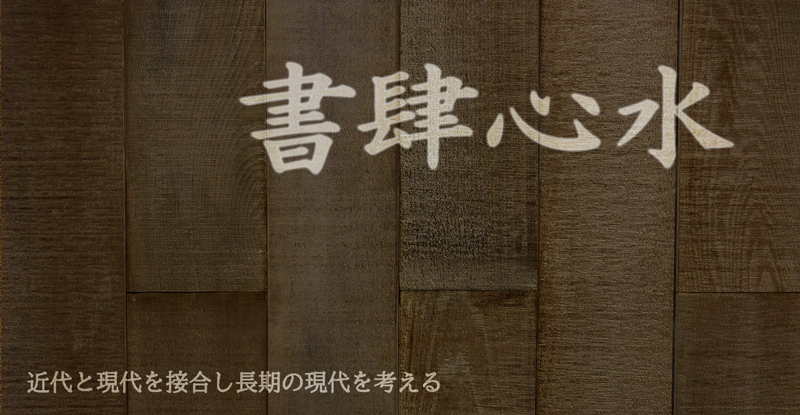
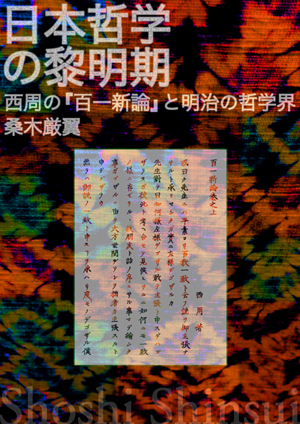
|
日本哲学の黎明期――西周の『百一新論』と明治の哲学界
「哲学」という訳語が生まれた頃
電子書籍(Kindle版)
フィロソフィアを「哲学」と訳した日本最初の哲学者西周(にし・あまね)の「百一新論」(百教一致の新論)が日本の近代化に持った意義とは何か。西田幾多郎の京都学派に対して東大教授として日本のアカデミズム哲学の基礎を築いた桑木厳翼。桑木が残した論文と講演より明治の哲学界に関する貴重な証言を選出。
ここのリンク先で本書のなかをご覧いただけます(PDFファイル)
著者 桑木厳翼
書名 日本哲学の黎明期――西周の『百一新論』と明治の哲学界
体裁・価格 A5判上製 256p 定価4180円(本体3800円+税10%)
刊行日 2008年7月30日
ISBN 978-4-902854-47-3 C0010
●著者紹介
桑木厳翼(くわき・げんよく/1874-1946)
哲学者。帝国大学(現東京大学)哲学科卒業。在学中はケーベルや井上哲次郎らに学ぶ。1900(明治33)年、日本人による初の信頼すべき『哲学概論』を出版。1902(明治35)年、東京帝国大学助教授、1906(明治39)年、京都帝国大学教授、1907〜09(明治40〜42)年、ドイツおよびフランス、イギリスに留学、1914(大正3)年〜1935(昭和10)年、東京帝国大学教授。大正期の民本主義啓蒙団体黎明会に参加し、文化主義を提唱。新カント派の哲学を摂取しカント研究の先駆者となる。主著『カントと現代の哲学』。日本のアカデミズム哲学の基礎を築いた。

|
初版(紙版)書影
●目 次
第一部 西周と津田真道
西周の哲学――明治初期の哲学的傾向
西周の百一新論
明治の一先覚者・津田真道
第二部 明治の哲学界
明治哲学界の傾向
日本に於けるドイツ哲学
第三部 訳語の問題
哲学用語由来記
言葉と哲学――現代文化の一批判
第四部 先進の追憶
大西祝博士と啓蒙思想
森鴎外の思想
附録 その後の内外哲学界
日本哲学界の傾向
日本に於けるデカルト哲学研究の現状
パリに於ける両国際的学会――心理学と哲学