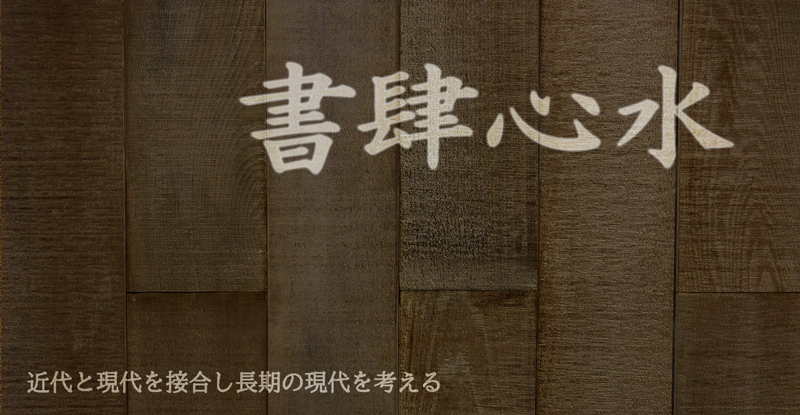
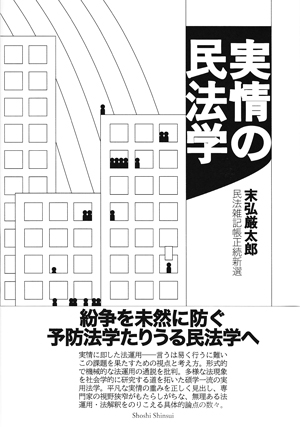
|
実情の民法学――民法雑記帳正続新選
末弘厳太郎[著]
紛争を未然に防ぐ予防法学たりうる民法学へ
実情に即した法運用――言うは易く行うに難いこの課題を果たすための視点と考え方。形式的で機械的な法運用の通説を批判。多様な法現象を社会学的に研究する道を拓いた碩学一流の実用法学。平凡な実情の重みを正しく見出し、専門家の視野狭窄がもたらしがちな、無理ある法運用・法解釈をのりこえる具体的論点の数々。
ここのリンク先で本書のなかをご覧いただけます(PDFファイル)
造本 四六判上製 320p
価格 定価6930円(本体6300円+税10%)
刊行 2024年12月
ISBN 978-4-910213-57-6 C0032
目 次
第Ⅰ部
民法の独自性
民法の商化と民法の将来
予防法学としての民法学
行政的解釈の法源性
日本民法学の課題
技術の貧困
目的ある権利と目的なき権利
人格概念の中毒
法人学説について
私法学説としての国家法人説
三の団体型
無償契約雑考
委任雑考
信託法外の信託
無過失賠償責任と責任分散制度
不法行為としての殺人に関する梅博士の所説
被害者としての家団
同時存在の原則に対する疑い
第Ⅱ部
民法学と民事政策
判例の法源性と判例の研究
法源としての条理
理論と立法者の意思
法律関係と道義則
事実たる慣習
法定の型と実在の事実
死亡の認定
実在としての法人と技術としての法人
機関関係の理論的考察
公法人私法人の区別
任意的記載事項の法律的性質
人格なき社団財団の法人化
団体財産と信託法理
一般信託法形成の必要とその方法
土地の概念
定義規定の解釈方法――天然果実の意義について
考え方の順逆
法定果実
株式配当金と法定果実
名義貸与者の責任
時効期間の逆算
立木の売買と民法第百九十二条
消極的契約利益
Clean handの原則
再びClean handの原則について
不法行為法の再編成
不法行為と「法なければ罪なし」の原則
殺人と賠償額算定方法
団体責任の原理
第Ⅲ部
法源としての学説
適法行為による「不法行為」
音響・煤姻等の災害と法律
法律と慣習――日本法理探究の方法に関する一考察
立法学に関する多少の考察――労働組合立法に関連して
●著者紹介
末弘厳太郎(すえひろ・いずたろう/1888-1951)民法学者、労働法学者。判例研究、法社会学の創始者とされる。1912年東京帝国大学法科大学独法科卒業。アメリカ等に留学。1920年法学博士。1921年東京帝国大学法学部教授。穂積重遠と学部内に民法判例研究会を設立。1946年退官。1947年中央労働委員会会長。主著『物権法』『農村法律問題』『労働法研究』『民法講話』『民法雑考』『嘘の効用』『法窓閑話』『法窓雑話』『法窓漫筆』『法窓雑記』『法学入門』『民法雑記帳』『続民法雑記帳』『日本労働組合運動史』等。