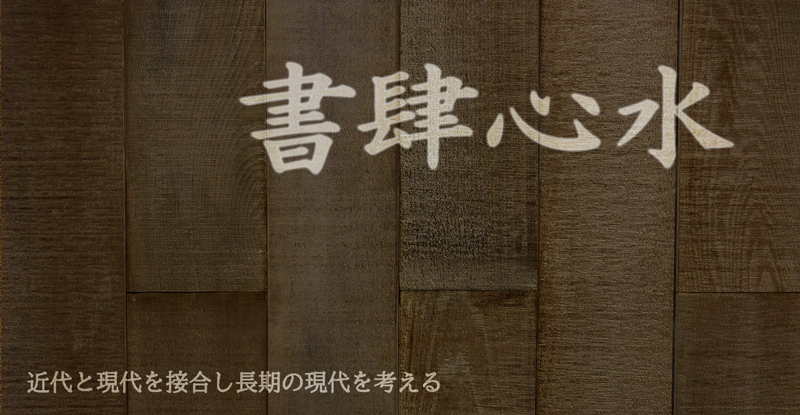

|
田口卯吉の日本開化小史
京口元吉[著]
電子版限定企画
日本史学の近代化、その画期的著作を概説
明治の名著『日本開化小史』の要約と解説であるとともに、明治維新までの日本の文化的発展に注目して政治と社会の変遷を簡約に描く前近代日本通史ともいえる入門書。
「史家の苦辛は、歴代許多の状態を蒐集するに在らず。その状態の本づくところを究むに在るのみ」という考えで「年表ではない歴史」のありかたを追究し、従来の政治史を脱して文化史/文明史のさきがけをなした画期作『日本開化小史』。
明治期の代表的名著として知られ、昭和初期には既に文庫本として普及したものの、文語文のため今では読みにくいものとなってしまった『日本開化小史』。その要点を講演の文体でやさしく説いた貴重な概説書。
※底本、京口元吉著『田口卯吉の日本開化小史』(1941年、日本放送出版協会刊行)
電子書籍(Kindle版)販売サイト
著者 京口元吉
書名 田口卯吉の日本開化小史
刊行 2025年9月
分量 約11万字
●目 次
序 講 日本開化小史の文化史的意義
一 日本開化小史とその著作年代
二 田口博士の略歴と学問的地位
三 『日本開化小史』の著者としての田口卯吉氏
第一講 王朝時代末期までの開化
第一章 神道の濫觴より仏教の弘まりしまで
第二章 漢学の渡りしより京都の衰えしまで
第七章 日本文学の起原より千八百年代まで
第二講 鎌倉時代の文明開化
第三章 封建の権輿より鎌倉幕府創立に至るまでの地方の有様
第四章 鎌倉政府の創業よりその治世の間の有様
第八章 のうち 鎌倉政府成立以後の日本文学
第三講 室町時代の文明開化
第五章 鎌倉幕府の滅亡より南北朝の戦まで
第六章 南北朝の戦乱以後戦国に至るまで
第八章 のうち 室町時代の文学
第四講 戦国時代の状態
第九章 戦国乱離の有様より二千三百年代の半頃まで
第十一章 第十二章 のうち 戦国時代の文化
第五講 江戸時代の文明開化
第十章 徳川氏禍乱を戡定せしより二千五百年代の末に至る
第十一章 徳川氏治世の間に世に顕われたる開化の現像
第十二章 徳川氏治世の間に顕われたる開化の現像
第六講 明治時代文化の胎動
第十三章 徳川治世の間勤王の気の発せし事
終 講 田口博士の学風と著作
●著者紹介
京口元吉(きょうぐち・もときち/1897-1967)
日本史学者。1926年、早稲田大学文学部史学科卒。1933年、早稲田大学附属高等学院教授、1940年、早稲田大学助教授。1941年、講義内容が自由主義的だとして退職させられる。1946年、同大学に復職し、翌年、教授。著書に『高田早苗伝』『日本文化史』『やさしい日本歴史』『大正政変前後』『秀吉の朝鮮経略』『日本近世史要』など。訳書に『歴史哲学概論』(オットー・ブラウン著)、校訂書に『大隈伯昔日譚』『売笑三千年史(改訂増補)』(中山太郎著)がある。
田口卯吉(たぐち・うきち/1855-1905)
経済学者、文明史家、実業家、法学博士、東京府会議員、衆議院議員。号は鼎軒。大蔵省翻訳局の官費生となり『日本開化小史』『自由交易日本経済論』等を著作。『東京経済雑誌』を創刊、自由貿易を唱えて政府の経済政策を批判した。その他の業績に『群書類従』『国史大系』『大日本人名辞書』『日本社会事彙』の編纂・刊行等がある。