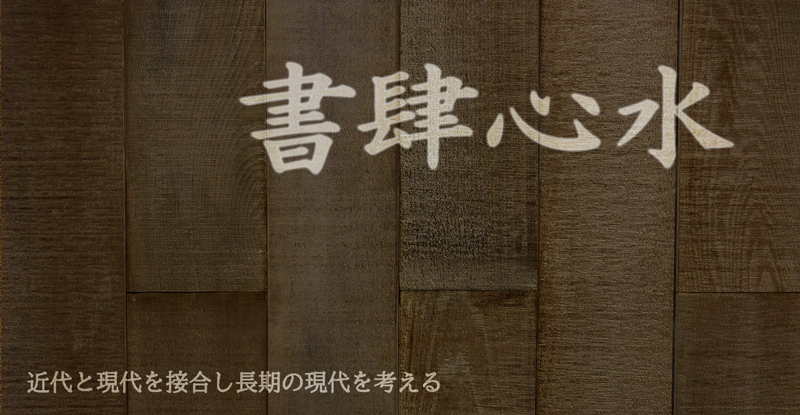

|
政権が横暴にふるまう時、ノモス主権論がよみがえる
従来の主権概念では、国民の総意に基づく数の横暴を認めざるをえない。ソフィストVS.ソクラテス以来の大問題を法哲学の立場で論じ、実力概念から責任概念へと改鋳された主権を提唱する。
ここのリンク先で本書のなかをご覧いただけます(PDFファイル)
著者 尾高朝雄
書名 天皇制の国民主権とノモス主権論 政治の究極は力か理念か
体裁・価格 A5判上製 288p 定価6930円(本体6300円+税10%)
刊行 2014年3月
ISBN 978-4-906917-26-6 C0032
●尾高朝雄既刊書
ノモス主権への法哲学/自由・相対主義・自然法/実定法秩序論/法と世の事実とのずれ/法思想とは何か
●著者紹介
尾高朝雄 (おたか・ともお)
1899年生、1956年歿。法哲学者。朝鮮に生まれ東京に育つ。1923年東京帝大法学部卒業後、京都帝大文学部哲学科で学ぶ。京城帝大教授、東京帝大法学部教授(法理学、のち法哲学講座担任)を歴任。欧米留学時代(1928〜1932年)にはウィーンでH・ケルゼンに、フライブルクでE・フッサールに師事。1956年5月ペニシリン・ショックのため急逝。代表的著書に『国家構造論』(学位論文、1936年)『実定法秩序論』(1942年)『法の窮極に在るもの』(1947年)『法の究極にあるものについての再論』(1949年)『数の政治と理の政治』(1949年)『自由論』(1952年)がある。また在欧中にオーストリアで刊行したGrundlegung der Lehre vom sozialen Verband〔社会集団論の基礎〕(1932年)はドイツ、オーストリアで高く評価され現在も刊行中(Springer刊)。
●本書の主張と意義
1) 憲法制定時の国体論議を検証し、象徴天皇制においても国民主権が十全に機能することを示します。また、国民が望めば国民主権と並存する象徴天皇制の継続にも積極的意味があることを示します。
2) 憲法制定権力である国民の主権(国民の総意)が万能の力であることに疑問を呈します。国民主権のワイマール憲法体制は結局数の力でナチ政権の確立へと至りました。現在の日本でも国民の総意に基づく政権が強引な政治を行っています。主権が無制限の力であるならば、そのなりゆきを否定することができません。
3) 主権の所在論(国民にあるのか王にあるのか)を超えて、従来の主権概念の上位に「ノモスの理念」を組み込む事でこのアポリアに道を開き、主権概念を刷新します。
●目 次
序 論
第一部 国民主権と天皇制
第1章 新憲法をめぐる国体論議
1. 新憲法による国民主権主義の宣言
2. 新憲法成立の経過
3. 国体に関する論議
第2章 主権概念の批判
1. 実力としての主権
2. 法の理念としての主権
3. 法の理念と現実の権力意志
第3章 国民主権の原理
1. 国民主権主義と君主制
2. 国民主権主義と国家契約説
3. 法の理念としての国民の総意
第4章 天皇統治の伝統
1. 天皇統治の実体
2. 天皇統治の理念
3. 現実政治による天皇統治の理念の悪用
第5章 新憲法における国民主権と天皇制
1. 国民の総意による政治
2. 象徴としての天皇
3. 新憲法における国民主権と天皇制の調和
第二部 ノモス主権論をめぐる論争
第6章 ノモスの主権について
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
第7章 事実としての主権と当為としての主権
1.
2.
3.
●本書について
本書の底本は尾高雄著(1954年青林書院刊)『国民主権と天皇制』です(古書での入手は困難です)。初版の刊行は1947年ですが、初版刊行の後に本書の「ノモス主権論」などをめぐって尾高朝雄(東京大学教授・法哲学)と宮沢俊義(東京大学教授・憲法学)の間で論文による論争が起きました(その経緯は本書第7章第1節に記されています*1)。本書の底本は、その「親しい同僚同士の論争*2」を踏まえて第6章と第7章が加えられた増補版です。論争の中心となった「ノモス主権論」は法学の議論として大きな射程を持つもので、国民主権と天皇制の関係論にとどまるものではありません。
本書の論点を分析的に言うならば、「国民主権と天皇制の関係論」と、その議論に応用された「ノモス主権論」の二つからなっています。著者は国民主権と天皇制の関係を考察するために本書を著したのですが、法哲学者としての議論の重点はむしろ「ノモス主権論」にあったといえるでしょう。この法哲学上の大問題の帰趨に比べれば天皇制に関する問題は二次的なものにすぎないという考えを著者は示しています*3。
そこで、本書の特徴をよりよく示すために、今回刊行のこの新版においては書名を「天皇制の国民主権とノモス主権論」とし、また著者の立場の特徴を示すものとして「政治の究極は力か理念か」という副題を加えました。
尾高朝雄は論争相手の宮沢俊義にくらべ、現在一般にはほとんど無名です。その理由としては、1956年5月にペニシリン・ショックのため急逝したこと(尾高は1899年生)など、さまざまな事情が考えられるでしょうが、憲法学界にとってはその理由は明白で、尾高・宮沢論争の結果が宮沢の勝利とされて、その後、尾高の「ノモス主権論」は折にふれて振り返られることはあっても、積極的に検討されることがほとんどなくなったからであるといわれています*4。宮沢が憲法学界に大きな影響力を持ち、その学問の継承者である芦部信喜らもまた憲法学界に大きな影響力を持ったことも無関係ではないでしょう。
本書は50年以上も前の出版物ですが、国民主権と天皇制の関係を法学的に論じたものとしては、両者の関係を積極的に合理化するという点でユニークなものです。またノモス主権論についても、法哲学の議論としては、果たして尾高・宮沢論争をもって解決済というべきかどうか再検討する価値があるでしょう。
また、底本の刊行された時代と現在では国民主権と天皇制の関係を論じる条件が異なってきています。現行憲法制定時には、そもそも国民主権と天皇制が両立するものであるかどうかが問題となりましたが、憲法施行から65年以上を経た現在、「国体」というテーマをめぐって議論されることは全くなくなり、国民主権と象徴天皇制の並存は歴史的に定着したというに十分な時間が経過しています。そして国民主権も天皇制も廃される現実的な見通しは当面ないといってよいでしょう。天皇制廃止の意見をもつ最もまとまった集団である日本共産党においても、「天皇制を『容認』したとする報道が一部にみられますが、それは事実に反します」としつつ、「日本国憲法は国民主権を明記し、国民代表たる国会を通じた変革を可能とする政治制度を定めています。あらゆる進歩を阻んだ戦前の絶対主義的天皇制とは違って、天皇の制度が残ったいまの憲法のもとでも、日本共産党がめざす民主的改革は可能です。」としています*5。すでに相当な年月のあいだ現に存在し、なお今後も社会に大きな変化が生じないかぎりは継続して存在すると推測するに十分な理由がある国民主権と天皇制の並存は、どのように説明しうる事態なのでしょうか。本書はその点においてユニークな議論を展開する稀有な存在意義をもっています。この意義は、本書が刊行当時にもっていたそれとはまた違ったものであるといえるでしょう。
2014年 書肆心水
註
*1 本書246-254ページ。
*2 本書254ページ。
*3 例えば本書225ページ。「この種の考え方を克服しようとする私の『法哲学的』な理論が、実力としての主権の否定に到達することは、やむを得ない。この大問題の帰趨にくらべれば、『天皇制のアポロギヤ』のごときは第二次的な問題にすぎない。」
*4 時本義昭著「ノモス主権と理性主権」の「はじめに」。『龍谷紀要』第29巻(2008)第2号(CiNii 論文PDFオープンアクセス)。なお、この論文の冒頭に掲げられた「要旨」には次のようにある。「尾高朝雄のノモス主権論においては、抽象的な理念であるノモスに主権が帰属させられる。また、純理派は、革命期において、主権の帰属主体が『個別的で具体的』であったことが議会による無制限な支配や多数派による圧制をもたらしたとして、抽象的な存在である理性に主権を帰属させることを主張した。いずれにおいても、主権の帰属主体が抽象化されることによって主権の帰属主体自らによる主権の行使は不可能となり、その結果として主権の帰属と現実における主権の行使とが分離され、主権の行使は内在的に制限される。ところで、カレ・ド・マルベールの国民主権論における国民も抽象的な存在であることから、ノモス主権=理性主権=国民主権となる。さらに、宮沢俊義の国民主権論も、『誰でも』によって構成される国民が抽象的な存在であることから、この等式における国民主権に含まれる。その結果、意外にも、主権の帰属主体に関する限り、宮沢・尾高論争における理論的な対立要素はなくなるのである。」
*5 2004年2月4日『しんぶん赤旗』「天皇制を『容認』したか?」(https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-04/0204faq.html)