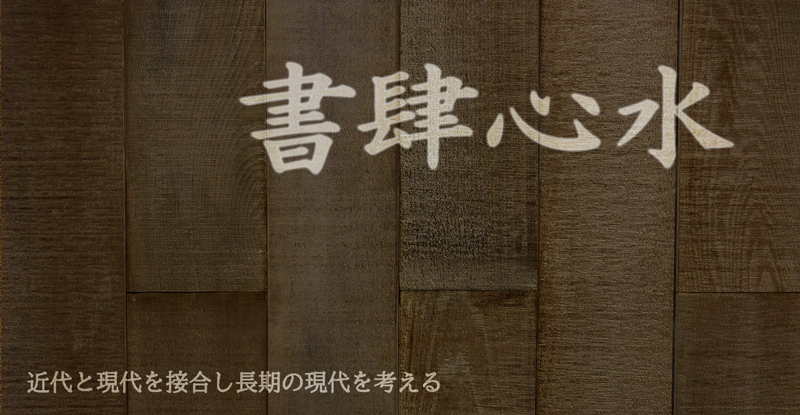
※こちらは更新・記録を既に終了した旧ファイルです。リンク元が現存している関係で公開継続しています。
書評紹介
新聞雑誌類に掲載されたものの抄録です
●イスラーム研究/中東問題
●イスラームの構造(黒田壽郎 著)
●イスラーム法理論の歴史(ワーエル・B・ハッラーク 著)
●イラク戦争への百年(黒田壽郎 編)
●イラン・イスラーム体制とは何か(吉村慎太郎 著)
●翻訳文学/翻訳思想
●ひとつの町のかたち(ジュリアン・グラック 著)
●言語と文学(モーリス・ブランショほか 著)
●私についてこなかった男(モーリス・ブランショ 著)
●ブランショ小説選(モーリス・ブランショ 著)
●アミナダブ(モーリス・ブランショ 著)
●さなぎとイマーゴ(岩切正一郎 著)
●憂い顔の『星の王子さま』(加藤晴久 著)
●境 域(ジャック・デリダ 著)
●外国歴史新説
●真説 レコンキスタ(芝修身 著)
●地図から消えた国、アカディの記憶(大矢タカヤス他 著)
●哲 学
●宮廷人と異端者(マシュー・スチュアート 著)
●西田幾多郎の声(西田幾多郎 著)
●師弟問答 西田哲学(西田幾多郎・三木清 著)
●エッセンシャル・ニシダ[全3巻](西田幾多郎 著)
●リオタール哲学の地平(本間邦雄 著)
●アジア主義/近代日本問題
●頭山満言志録(頭山満 著)
●アジア革命奇譚集(宮崎滔天 著)
●評伝 宮崎滔天(渡辺京二 著)
●滔天文選(宮崎滔天 著)
●俗戦国策(杉山茂丸 著)
●百 魔(正続完本)(杉山茂丸 著)
●アジア主義者たちの声(入門セレクション)
●社会思想/文化文明論
●『モモ』と考える時間とお金の秘密(境毅 著)
●出版巨人創業物語(佐藤義亮・野間清治・岩波茂雄 著)
●愛国心をめぐって(内村鑑三 著)
●仏教・東洋伝統思想
●死生観(加藤咄堂 著)
●味読精読 菜根譚(洪自誠 原著/加藤咄堂 著)
●医術と宗教(富士川游 著)
●仏教統一論(村上専精 著)
●仏陀(オルデンベルク 著)
●芸術批評・精神医学
●シンフォニア・パトグラフィカ(小林聡幸 著)
●美と生命(高村光太郎 著)
●夢野久作の能世界(夢野久作 著)
*当社全般
●イスラームの構造(黒田壽郎 著)
●イスラーム法理論の歴史(ワーエル・B・ハッラーク 著)
●イラク戦争への百年(黒田壽郎 編)
●イラン・イスラーム体制とは何か(吉村慎太郎 著)
●翻訳文学/翻訳思想
●ひとつの町のかたち(ジュリアン・グラック 著)
●言語と文学(モーリス・ブランショほか 著)
●私についてこなかった男(モーリス・ブランショ 著)
●ブランショ小説選(モーリス・ブランショ 著)
●アミナダブ(モーリス・ブランショ 著)
●さなぎとイマーゴ(岩切正一郎 著)
●憂い顔の『星の王子さま』(加藤晴久 著)
●境 域(ジャック・デリダ 著)
●外国歴史新説
●真説 レコンキスタ(芝修身 著)
●地図から消えた国、アカディの記憶(大矢タカヤス他 著)
●哲 学
●宮廷人と異端者(マシュー・スチュアート 著)
●西田幾多郎の声(西田幾多郎 著)
●師弟問答 西田哲学(西田幾多郎・三木清 著)
●エッセンシャル・ニシダ[全3巻](西田幾多郎 著)
●リオタール哲学の地平(本間邦雄 著)
●アジア主義/近代日本問題
●頭山満言志録(頭山満 著)
●アジア革命奇譚集(宮崎滔天 著)
●評伝 宮崎滔天(渡辺京二 著)
●滔天文選(宮崎滔天 著)
●俗戦国策(杉山茂丸 著)
●百 魔(正続完本)(杉山茂丸 著)
●アジア主義者たちの声(入門セレクション)
●社会思想/文化文明論
●『モモ』と考える時間とお金の秘密(境毅 著)
●出版巨人創業物語(佐藤義亮・野間清治・岩波茂雄 著)
●愛国心をめぐって(内村鑑三 著)
●仏教・東洋伝統思想
●死生観(加藤咄堂 著)
●味読精読 菜根譚(洪自誠 原著/加藤咄堂 著)
●医術と宗教(富士川游 著)
●仏教統一論(村上専精 著)
●仏陀(オルデンベルク 著)
●芸術批評・精神医学
●シンフォニア・パトグラフィカ(小林聡幸 著)
●美と生命(高村光太郎 著)
●夢野久作の能世界(夢野久作 著)
*当社全般
イスラームの構造

2005.1月(上・中旬合併)号 『出版ニュース』誌 「ブックガイド」欄
2004.10.20刊 黒田壽郎著 『イスラームの構造――タウヒード・シャリーア・ウンマ』

イスラーム世界をめぐる論議は盛んだが、その実はほとんど核心に迫るものがないという現状だ。 ……(中略)…… イスラームに対する短絡的思考に対し、その本質を論じる上で有意義な論考といえる。
2004.12.26 『東京新聞』書評面 子安宣邦氏評 (「2004年・私の三冊」) [評者ご紹介ページ
 ]
]
2004.10.20刊 黒田壽郎著 『イスラームの構造――タウヒード・シャリーア・ウンマ』

(1)イスラーム世界への理解の眼を閉ざしたまま、日本人は中東の戦争にコミットしてしまっている。すでに倫理性が問われているわれわれの認識を、根底的な形でイスラームの世界に開いてくれるのが本書。(子安宣邦・思想史家)
2004.12.19 『朝日新聞』書評面 依田彰記者インタビュー (「著者に会いたい」)
2004.10.20刊 黒田壽郎著 『イスラームの構造――タウヒード・シャリーア・ウンマ』

衰退した世俗国家の現状をよそに、世界のムスリム十数億人の心をいまなお魅了し続けるイスラム文明の核心とは何か。
構想10年。本書はその答えに迫り、文明全体の構造を明示した日本語による初めての労作かもしれない。研究歴40年になるイスラム学の第一人者、黒田壽郎(くろだ・としお)さんが本書で最も重視したのは、イスラム教の基本的な世界観(タウヒード)の分析だった。
……(中略)……
「私は専門家として、いまイスラム地域が米欧主導のグローバリゼーション、覇権主義のもたらすものに身をさらし、それに対していかに反応し、いかに自己主張しようとしているか非常に興味があります」
黒田さんはまた、シリアのスーク(伝統的市場)を長年調査し、イスラム経済の研究も重ねてきた。そして国家と資本主義を超える開かれた共同体の可能性を模索している。
[全文は『朝日新聞』(
 )をご覧下さい]
)をご覧下さい]
2004.12.9号 『週刊文春』書評欄 立花隆氏評 (「私の読書日記」)
2004.10.20刊 黒田壽郎著 『イスラームの構造――タウヒード・シャリーア・ウンマ』

×月×日
黒田壽郎『イスラームの構造』(書肆心水 三八〇〇円+税)を読んだ。
最近、さまざまのイスラーム論、イスラーム社会論が出ているが、イスラームの教えの核心部分に対する理解を欠いたものが多く、枝葉の説明に終始して、イスラームへの無理解がかえってはびこるばかりという黒田の指摘は、その通りだと思う。
黒田は、類書が軽視しているイスラームの教えの核心部分は(……)
……(中略)……
イスラーム社会とキリスト教社会は、このような原理的世界認識の部分で根本的に対立している。
アメリカのネオコンは、イラクの民主化に成功すれば、民主化の波が周辺諸国に波及し、中東全体が民主主義になると信じる頭の単純な人々だが、彼らの考えの根底には、イスラーム社会に対する蔑視と、キリスト教文明とその帰結としての民主主義の絶対的優位性に対する信仰がある。
しかし、イスラーム側にいわせると、真の民主主義は、タウヒードの原理の上にこそ築かれる。
(……下略……)
イスラーム法理論の歴史

2012.3. 『史学雑誌』第121編第3号新刊紹介 水上遼氏評
2010.12.30刊 ワーエル・B・ハッラーク著 『イスラーム法理論の歴史』

本書は、イスラーム法の根幹ともいえる、法理論(ウスール・ル・フィクフ)に関して、歴史的展開を追いつつ論じる概説書である。本書の最大の目的ともいえるのが、冒頭で著者が、また巻末で訳者が指摘しているように、イスラーム法理論はこれまで考えられてきたような、新しい解釈を許さない閉鎖的なものではなく、むしろ様々な「ヴァリエーション」をもって現在に至っていることを示すことである。
次に、本書の内容を章ごとに概観する。
(……中略……)
以上のことから、具体的な用語の解説・分類や議論などが詳述されている本書は、イスラームの法理論の概説書として有益であるだけでなく、著者の通説とは異なる新しい見解が随所に散りばめられている点も特徴であるだろう。また、日本語で読めるイスラーム法理論を扱った数少ない本であるという点も重要な意義といえるだろう。
最後に、より深い理解を得るために、著者のもう一つの著作である『イジュティハードの門は閉じたのか――イスラーム法の歴史と理論』(奥田敦編訳、慶応義塾大学出版会、2003)も合わせて読むことを勧めたい。
ひとつの町のかたち

2006.1月号 『GINZA』書評欄(年末年始に必読の、ブックマニアが選んだ傑作選。) 松浦弥太郎氏評
2004.11.20刊 ジュリアン・グラック著(永井敦子訳) 『ひとつの町のかたち』

'05年は旅の一年だったので、旅に関する本を手にすることも多かった。その中から最高級の新刊2冊を。『アルゴールの城』『森のバルコニー』で知られるシュルレアリスムの巨匠、地理学者ジュリアン・グラックの『ひとつの町のかたち』。少年時に過ごした町ナントを母胎的と語り、その風景と記憶を晩年になってたどりなおした好著。新しいセンス・オブ・プレイス論がここにある。
2005.10月号 『high fashion』書評欄 佐伯誠氏評
2004.11.20刊 ジュリアン・グラック著(永井敦子訳) 『ひとつの町のかたち』

(……上略……)
緩みがちな日本語をきびしく拒む、ということで傑出した訳業といえるのが、永井敦子によるジュリアン・グラックの『ひとつの町のかたち』だ。忘却されていたかのようなグラックの旧作は1985年に刊行されたものというから、ずいぶん永らく美酒を眠らせていたものだ。ナントの町で寄宿舎生活を送ったグラックの回想記だが、いたずらにノスタルジーに耽るというところがなくて、硬い脛をコンパスのようにひろげてナントの町を歩く少年が先導する。ある固有の土地について書かれた文章ということでは、その濃密さにおいてちょっと類例がないかもしれない、せいぜい谷崎潤一郎の『吉野葛』くらいだろうか。
なめらかな日本語というのとはちがう、むしろ「歩きグセ」をつたえることに心を砕いたといった態の、よく練り上げられ彫琢された日本語がすばらしい。ややもすれば耽美へと傾きかける巨匠には与しないで、むしろ地理学者としてのグラックの視線にこそ寄りそうようにしている、その盲従しない敬愛の距離はどうだろう。
さまざまな工夫があって、たとえば、「癖」という語に「折皺」とルビを振ることで、コトバを一義性に縛りつけることをしない。こうしたルビはあちらこちらに仕掛けられていて、上すべりになりかける歩行の躓きの石になる。周到でいて懇切な註は、章末や巻末ではなく、ページごとに用意されていて、たっぷり道草をするたのしみにもこと欠かない。なによりも50ページにも及ぶ訳者解説のおかげで、これまでにないような精密な講読をすることができる。
(……下略……)
2005.1/2合併号 『みすず』(2004年読書アンケート) 加藤幹郎氏評 [評者ご紹介ページ
 ]
]
2004.11.20刊 ジュリアン・グラック著(永井敦子訳) 『ひとつの町のかたち』

加藤幹郎(映画学)
(……上略……)
一方、グラックの『ひとつの町のかたち』は、いかにしてナントがグラック第二の故郷となったかが、グラックならではの瑞々(みずみず)しくも絢爛たる文体で語られます。しかしグラックのことですから、この都市エッセイが一筋縄でゆくはずもなく、これは都市じたいがそうであるような多面的時空間を構成します。じっさいこの翻訳書は2004年最大の収穫ではないでしょうか(わたし自身はこのナント物語を Yves Aumont, Alain-Pierre Daguin, Les lumières de la ville : Nantes et le cinéma と併読していますが)。
2005.3.17号 『週刊文春』書評欄 鹿島茂氏評 (「私の読書日記」)
2004.11.20刊 ジュリアン・グラック著(永井敦子訳) 『ひとつの町のかたち』

×月×日
リスボンに旅して以来、路面電車の走る町が気になりだした。日本でいえば岡山規模の地方中都市にこそ路面電車はよく似合う。つまり、路面電車に揺られながら終点まで行ってもせいぜい二、三十分の距離の町というのが、人間の住む都市としての適正規模のような気がする。どうも、東京は巨大すぎて、町の正しい味わい方ができない。
……(中略)……
この路面電車についての記述に見られるように、グラックは、ありきたりのトポスがまるでエピファニーのように突然の明るさを帯びる瞬間に恍惚を感じる。
「もっとも気の滅入る部類の労働によって醜化されているはずの通りが、ほんの少しの太陽の光がもたらす一瞬の幸福で変容するのだ。(中略)そんなとき、私たちはとても素朴な感情に包まれる。ここにいるのは賢いこと、生命はここでその失われたあかしと生来の律動を取り戻し、世界はにこやかな短いめくばせで私たちとの婚姻関係を更新し、強めてくれるという感情」
これぞ、街路のシュルレアリスムである。
2005.1.21号 『週刊朝日』書評欄(1ページ書評) 高橋源一郎氏評
2004.11.20刊 ジュリアン・グラック著(永井敦子訳) 『ひとつの町のかたち』

『ひとつの町のかたち』を読みはじめる時、まずぼくが感じるのは、いつもの読書とは違う経験をしている、ということだ。そして、しばらくして、今度は、こうも感じるのだ。
でも、昔、ぼくはこんな風に本を読んでいたのではなかったろうか?
この本はゆっくり読まなければならない。なぜなら、いまぼくたちが読んでいる本は、殆ど、読みとばすために書かれているからだ。しかし、そうではない時代もあったのだ。
これは一つ一つの文章にただならぬ力や想像力がこめられていた時代を代表する作家の本なのである。
……(中略)……
グラックを読んでいると、過去というものの豊かさが骨身に滲みるほどわかる。だが、それにもかかわらず、高齢にもかかわらず、グラックは過去を懐かしがっているのではない。現在を生きるためには、過去とその入れ物としての町(とかたち)が必要だと言っているのだ。それは、未来の小説への、友情ある忠告ではないだろうか?
2005.1.6 『日本経済新聞』書評面(夕刊) 陣野俊史氏評(「目利きが選ぶ今週の3冊」)
2004.11.20刊 ジュリアン・グラック著(永井敦子訳) 『ひとつの町のかたち』

★★★★(読みごたえたっぷり、お薦め)
(……上略……)
本書は、一九八五年にグラックが上梓したものの全訳だが、ナントという町でグラックが過ごした数年を元に、ナントが生き直される。いや、グラックの言うところによれば、町が人を生かすのであり、そこには相互作用がある。
……(中略)……
地形と地図と地名が、現実の都市と、記憶の中の都市との間で呼び交わされ、静かに呼吸する。無数の文学作品が縦横に引用される。読むのが惜しくなるくらい、贅沢な時間を経験した。本当に久しぶりだ。大変だったに違いない訳業にも感謝。注も丁寧で○。
言語と文学

2005.4月号 『情況』書評面 松本潤一郎氏評
2005.12.20刊 モーリス・ブランショ ジャン・ポーラン 内田樹 ほか著 『言語と文学』

ボナパルのか、テロルのか。あるいは、修辞(レトリック)か、字義通り(リテラル)か。さらに、敢えて言えば、「空虚な代表制」民主主義か、「対話を拒否する野蛮な」原理主義か。このような選択肢に「政治」の範列が規定されているかにみえる現状を思考するにあたって、本書は多くの示唆に富む。ポーランはここで、文学論的体裁を取りつつ、修辞派と言語嫌悪派の対立を、政治的に問うているからだ。この視点から、近代(モデルニテ)と呼ばれる閉域の、ここ百数十年の政治と言葉の複雑な絡み合いを、「総括」することができる。
(……中略……)
したがって『中身のない人間』でアガンベンも指摘するとおり、ポーランによる言語への耽溺か嫌悪かという対立的問いは、相互を前提とする代補関係にある。むろんこのように代補関係を指摘する脱構築(デリダ)的視点もまた、この対立内に書き込まれる。評子にいまひとつ分からないのは、この閉域、この悪循環(ループ)の中に、20世紀に存在していたということの必然がまったく理解できない、あの倒錯者(ドゥルーズ)もまた書き込まれているのかどうか、という点だ。
(……中略……)
むろん出来事という効果/結果は、それが起きたということ自体の効果/結果としてのみ、閉域内の私たちには触知される。そして(しかし)ここには「言葉嫌い」も「修辞」もなく、只管に出来事としての意味を生産する過程がある。「結果の結果」から超越論的探究を開始するというこの倒錯の挙措は、ブランショそして現在内田氏が実践(おじさん)する「面従腹背」路線と、挨拶を交わすことがあるのか。さらに、1930年代に花田清輝が採った『復興期の精神』の搦め手(レトリック)路線は、仏独の1940年代と[いかに]交差するのか。それが、評子の目下の関心事である。
*原文でルビ(振り仮名)になっている文字列は( )括り表記として、傍点部分は太字として引用しました。
2005.3.21 『公明新聞』書評面 難波江和英氏評
2005.12.20刊 モーリス・ブランショ ジャン・ポーラン 内田樹 ほか著 『言語と文学』

古典の復活。それも何重もの意味で。
フランスの作家ジャン・ポーランの『タルブの花』。この翻訳を中心にして、その外側にフランスの批評家モーリス・ブランショの『タルブの花』論を含む三つの論文、さらにその外側にポーラン=ブランショに関する内田樹と山邑久仁子の二つの論文が並んでいる。このそれぞれが、いまや先行するテクスト読解の古典であるばかりでなく、『タルブの花』をめぐる同心円を構成して、ポーランの古典そのものを言語・文学・政治の結節点として蘇らせる。
そこから浮かびあがるのは、「私たちは常套句をぬきにして語れるのか」という問題である。
(……中略……)
それでは、この背理をクリアする方法はあるのか。ポーランの回答は、驚くほど逆説にみちている。それは常套句を使うことによってである。私たちは常套句になれきっているので、その存在を意識さえしなくなっている。換言すれば、常套句の魔力は、言葉としての存在が消えると同時に、その空白がそのまま思想の裸形のように見えてくるところにある。たとえば、南極調査隊の男性に届いた日本の妻からのメッセージ――「あ・な・た」。これは言語か思想か。いや、ありふれた人称代名詞が姿を消したところから、ふいに立ちあらわれた生身の人間たちの日常性の重さ。
2005.3月(下旬)号 『出版ニュース』誌 「ブックガイド」欄
2005.12.20刊 モーリス・ブランショ ジャン・ポーラン 内田樹 ほか著 『言語と文学』

モーリス・ブランショ(1907-2003)は、文学者・批評家として文学の可能性とその極点のあり様を追究し続けてきた。 ……(中略)…… 占領下における文学とテロルの問題を突き詰めた歴史的メッセージといえる。
2005.3.12 『図書新聞』(書評専門紙) 郷原佳以氏評 [評者ご紹介ページ
 ]
]
2005.12.20刊 モーリス・ブランショ ジャン・ポーラン 内田樹 ほか著 『言語と文学』

[記事見出し] 言語によって言語に抗する 言語そのものに内在する言語化の不可能性
本書は、戦前戦後のフランスにおいて大手文芸出版社の編集人として辣腕をふるい、数多くの才能を世に送り出した「文学界の黒幕」ことジャン・ポーランの主著『タルブの花』(一九四一)と、その書評として執筆されたモーリス・ブランショの「文学はいかにして可能か」(初出一九四一)他二篇の評論を一冊にまとめ、二人の訳者および内田樹氏による力の入った解題を併録した日本独自編纂の言語・文学論である。ブランショの論文はすべて山邑氏による読みやすい新訳であり、初出版との異同も丁寧に調べ上げられていて参考になる。
(……中略……)
しかし本書は、過去の理論の単なる懐古にはとどまらない。それどころか、当時の問題が今日でもけっして解決済みのものとなってはいないことを、読者は痛感させられることだろう。
(……中略……)
いささかの飛躍を承知でいえば、ここにあるのは法としての言語の問題である。いかにしても言語なくしては書くことはできない以上、言語という法から逃れようと思えばランボーのように沈黙するしかない。
ブランショがポーランから出発して独自の議論に展開したのは、ひとえにこの言語のアポリアの問題だといってよい。本書には彼の評論が三篇収められているが、そこで行われているのは、一貫して、このアポリアを文学の始原的な力として捉え直すことなのである。
(……下略……)
イラク戦争への百年

2005.6.5 『新潟日報』書評面 板垣雄三氏評
2005.1.30刊 黒田壽郎編 『イラク戦争への百年』

イラク戦争の泥沼は深まるばかり。イラク再建の曲折が心配されている。サマワに自衛隊を出した日本の復興援助も宙に浮きかねない。
ところが、その日本では、イラクとは無関係に「戦後60年」、「日露戦争百周年」が記念されている。米国はイラクを日本になぞらえ、日本の「戦後」を「イラク民主化」のお手本にしているというのに。
また「日露戦争から百年」は、実は「イラク戦争への百年」に当たるのに。日露戦争は、欧米の中東分割の起点だった。エジプトとモロッコの分配を決めた英仏協商、イランを南北に切り分けた英露協商、ドイツのイラク進出を支えたバグダッド鉄道建設は、日露戦争と切り離せないのだ。日本人が拘束されたり殺されたりしたときだけイラクを思い出すようでは、日本社会のこれからが思いやられる。
こんなとき、イラク人自身が、またパレスチナ人自身が、自らの意志で自らの運命をきりひらく自主性をもたなければ、借り物や押しつけの「民主化」など、民主主義から、また中東問題の解決からも、ほど遠いことを、明快に証明する本書が現れた。
本書の問いは、日本のわれわれ自身にはね返ってくるものだ。国際大学名誉教授の編者は、前後して同じ出版社から『イスラームの構造』という学術的な仕事をものしたが、本書は、より広い読者に向けられている。地域文化学会に属する六人の編・著者たちは、いずれも中東問題に造詣深い専門家たちであり、中東のこれからを考えるための基礎作業として、これまでの百年をあざやかな眺望のもとに描き出した。
国際法からみたイラク戦争の違法性、イスラエルの横車、大国政治の不公正、パレスチナ人の離散と苦難にこめられた普遍性、イスラム世界の怒りの意味などについて本書の著者たちはじっくりと語る。その「語り」は、中東に強い関心をもつ人だけでなく、テレビ画面にもどかしさを覚え中東問題はなじみが薄いと感じている人にも、遠目のきくすっきりとした視界を開いてくれるだろう。
(C) Y. Itagaki (All rights reserved)
2005.4月(上旬)号 『出版ニュース』誌 「ブックガイド」欄
2005.1.30刊 黒田壽郎編 『イラク戦争への百年』

アメリカの武力行使による大義なき戦争と占領は、中東地域に新たな不安定要因をもたらした。本書は、イラク戦後の混乱の構造を明らかにした上でイスラーム世界の百年の歴史を概観し、この地域の主権回復と民主化へ向けた将来像を探りだす。
(……中略……)
外側からの押しつけの民主主義は、侵略や内政干渉であることを歴史的に学んできた民衆にとって容認できない。イラク、パレスチナの行方を論じる上で示唆に富む共同研究。
2005.*.*(日付・原紙未確認) 『日刊ゲンダイ』
2005.1.30刊 黒田壽郎編 『イラク戦争への百年』

イラクの混迷が象徴する中東問題の本質を歴史的視点から読み解く論考集。
アメリカによる武力行使を法的側面から分析する一方で、テロを誘発する原因を探りながら第2次大戦前から現在にいたる中東情勢一般を論じる。さらにイランとアフガニスタンにおけるイスラム政権の成立とその役割や、イスラム世界の革新運動を率いたエジプトの歴史、そしてパレスチナ問題まで。この地域の人々が体験してきた歴史と現状を考察しながら、中東に民主化が根付く条件を模索する。
[出所
 ]
]
2005.2.20 『東京新聞』『中日新聞』書評面 笈川博一氏評 [評者ご紹介ページ
 ]
]
2005.1.30刊 黒田壽郎編 『イラク戦争への百年』

(……上略……)
特別な印象を受けたのは北村文夫の「エジプト革新運動の高揚と挫折
 」である。アラブのみならず、第三世界全体に大きな影響力を持ったナセル主義の栄光と破綻がダイナミックに描かれている。色あせたナセル主義の代替探しはまだ続くのだろう。
」である。アラブのみならず、第三世界全体に大きな影響力を持ったナセル主義の栄光と破綻がダイナミックに描かれている。色あせたナセル主義の代替探しはまだ続くのだろう。
『モモ』と考える時間とお金の秘密

2006.12月号 『ecocolo』 書評欄 辻信一氏評
2005.3.30刊 境毅著 『『モモ』と考える時間とお金の秘密』

……(上略)…… このことを、前回も紹介した『モモ』(ミヒャエル・エンデ 岩波書店)という物語を丁寧に読み解くことを通じて、ぼくたちに教えてくれるのが、境毅さんの『『モモ』と考える時間とお金の秘密』です。小さな出版社から出ている地味な本ですが、ぼくにとっては大切な本。
2005.4-5 時事通信社配信(地方諸紙掲載) 乾侑美子氏(児童文学研究家)評
2005.3.30刊 境毅著 『『モモ』と考える時間とお金の秘密』

[記事見出し] エンデの言葉で「解釈」
(……前半略……)
地域通貨システムなどを紹介しながらの示唆には、生協活動や民間非営利団体(NPO)活動を長年続けている著者ならではの説得力がある。
「モモ」を論じた本は多い。その中で、本書に特筆される魅力になっているのは、エンデ自身の明確な易しい言葉を無理に難しく考える必要はない、むしろ、その明確さに気付くことから出発すべきだと、あざやかに示してくれている点だ。それも、マルクス、アインシュタイン、ソシュール、ハイデッガーなど、西欧のさまざまな英知を縦横に引きながらなので、読者も著者とともに知的な冒険をしているような気分になる。
改めて、エンデという人の大きさ、深さを思った。「解釈される」ことを嫌った人だったはずだ。あえてその「解釈」をしながら、エンデ自身の言い残したことの一端を言い得ているような本書を前に、彼岸のエンデはどんな顔をしているだろう。
私についてこなかった男

2005.8月号 『文學界』(書評欄) 丹生谷貴志氏評 (「味読・愛読/文學界図書室」長文書評エッセイ)
2005.4.30刊 モーリス・ブランショ著(谷口博史訳) 『私についてこなかった男』

(……上略……)
『私についてこなかった男』(1953年)は同時期に立て続けに書かれた『望みのときに』『最後の人』と、三面鏡のように互いを映す一種の三部作を成す。全部を読めば謎が解き明かされる訳でもないから全てを読む必要はないが、そこには言葉に於ける生と死の、責務と詐称の窮迫の、厚みなく逼迫した「戯れ」が、絶望と幸福の不思議な明るみのなかに、ほとんど微分計算的な進行によって広がって行く。『私についてこなかった男』はその中でもとりわけ難解な作品であろうが、筋というなら単純極まりない。ブランショにおいて特権的な場所である「部屋」、そこにおそらくは「書き手」である「私」と、誰であるのか、さしあたり「彼」と記入される者とがいる、それだけであり、事件らしい事件はほとんどなにも起こらない。
ブランショにおいて「部屋」は生の真昼から陥没し夜の荘厳からも隔離された中有の場所である。言い換えれば、死への傾斜に囚われた生の宙づりの場、ホスピス的な場所であり、つまりは約束なき言葉が書かれる、そうした逡巡の場である。「私」は自らが書くだろうものが観念的な殺戮ではなくて、言葉に於ける永世への約束であるだろうことを、その疑念の摂理を、「彼」に問い続ける。……ではそれを問われる「彼」とは誰か? 「あなたは書いているのですか?」と無責任に(そう、無責任に)応答し続ける「彼」とは誰か? ……穿ち過ぎの性急さを恐れずに言えば、「彼」とはおそらく、言葉そのものと称され、それでいて自らは一言も書かず、書かせることにおいて約束となった「男」、つまりは「キリスト」、である。
例えばD・H・ロレンスはキリストを描いた切実な小品に『死んだ男』という題名を与える。あらゆる輪廻から解放された真の死を死んだ仏陀と同じく、キリストは歴史上ただ一人真の死を死んだ男として、書くことがその真の死への捧げであることを宣言する。言葉において死ぬものは、絶対的な御言葉としての「彼」、キリストにおいて言葉の永世に刻まれるのだ、と。
……こうして『私についてこなかった男』は新約聖書に記載されなかった引き延された余談の欲望、言葉そのものであるキリストと「書く者」である誰であってもいい誰かである使徒=私による、終わりなき対話におけるアポカリプスの書字となる。ブランショにおいて近代文学はそれ自体が新たに絶え間ない福音書の注釈者の、責務と権能……その彷徨いそのものとなるのである。書くことの罪業が、言葉において「いまここ」を殺し続ける作業が、言葉の永世への供犠であり祝祭への約束となろうとする、そうした約束への終わりのない問いかけ……。
(……下略……)
2005.7.2 『図書新聞』(書評専門紙) 鈴村和成氏評
2005.4.30刊 モーリス・ブランショ著(谷口博史訳) 『私についてこなかった男』

ブランショ。懐かしい名前である。私はこの作品、『私についてこなかった男』を、15年ほど前に翻訳しようと思い立った。今度、訳書を手にして、ああ、やっと、という歓びとともに、かつてフランス語で何度も読んだ、まさに「テクストの快楽」としか言いようのない感動が、翻訳によって裏切られるのではないかという危惧が交錯し、複雑な思いに捉えられた。
さらに言うと、1953年にフランスで出版されたこの本が、2005年の日本で初めて翻訳されて、わが国で60年代に畏怖とともに語り継がれたブランショの、晦渋な魅惑を湛えた思想が、いまや色褪せて見えるのではないか、という不安もあった。
結論から言えば今回のこの翻訳は、それらの危惧を一掃して余りあるみごとなものだった。あらためて、デリダやデュラス(わけても『アンデスマ氏の午後』。本書同様、午後の日を主題とする)の先駆者としてのブランショの新しさが浮き彫りにされ、鮮明になった印象だ。
(……以下略……)
ブランショ小説選

2005.11.26 『図書新聞』(書評専門紙) 鈴木創士氏評
2005.9.30刊 モーリス・ブランショ著(菅野昭正・三輪秀彦訳) 『ブランショ小説選』

(……上略……)
とはいえブランショの足取りがしるされた地盤そのもののエレメントはきわめて複雑である。本書に収められた「謎の男トマ」や「永遠の繰言」執筆の時期は右翼の論客であった時期とたしかに重なってはいるが、それにもかかわらず新版『謎の男トマ』におけるおびただしい旧版の削除部分の意味を単に「転向」のなかに探しに行っても無駄である。政治的言語からの撤収はあっても、ブランショの道程のどこにも政治的思考全般からの撤収を認めることはできないし、ブランショの語る「忘却」や「マラルメ的問題」の意義を軽率にその沈黙のなかに求めることなどできるはずもない。つねに最後の救済として立ち現れる「不和の、殺害の、そして終焉の天使」である「政治」は、ブランショのすべての著書において明らかにつねに顕在化している。ここに見出されるのはもちろんジャーナリズム言語の問題などではない。それはエクリチュールにとって、歴史にとって、抑圧それ自体にとって、はるかに深刻な問題を含んでいると言わねばならない。
現実を、現実性のあらゆる現動的振舞いを再構築する沈黙、それは時間の断絶そのものと化しているはずだ。ブランショがそこに何度となく書きしるした「終末」とは、この沈黙の終焉、最後の時間の身震いを意味していたのだろうか。すべては終わる。すべては終わらなければならない。2003年2月20日にモーリス・ブランショは死去する。だが、ブランショの死とともにひとつの時代が終わったわけではないのである。
(……下略……)
イラン・イスラーム体制とは何か

2006.11月号 『地理と歴史――世界史の研究』(山川出版社刊)書評欄 山岸智子氏評
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

(……上略……)
読者(特に本稿の筆者)として、本書の記述の粘り強さには脱帽せざるをえない。イラン国内の政治変動と国際関係の変化を示す主要なポイントはすべて盛り込み、そのアクターや思想や背景の説明に手抜きがない。また「イスラーム」は、革命過程ではシンボリックなものとして、王政打倒後は権力闘争を勝ち抜くことのできた政権構想として、イラン・イラク戦争期にはイデオロギーとして働き、時期によってその政治化の様相が異なることを明らかにしている点も高く評価されてしかるべきだろう。これだけしっかり書き込んであると、「○○派」と分析される集団は短命で便宜的なものでしかなく、実際にはもっと細かな合従連衡が「ジグザグ」パターンをもたらしているのではないかと想像することができる。
(……下略……)
2006.9月号 『イスラム世界』(日本イスラム協会)書評欄 富田健次氏評
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

イラン近現代史の古典ともいうべき加賀谷寛著『イラン現代史』が出版されたのは1975年である。それからちょうど30年を経た2005年に刊行された当著は、単に基礎的な文献資料だけでなく、現地のニュース媒体も渉猟し、これらを踏まえて本格的にイラン現代史を扱った大著である。
(……下略……)
2006.9 『歴史学研究』(歴史学研究会編集)書評欄 桜井啓子氏評(長文学術的書評)
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

本書は、1979年のイラン革命、あるいは「イスラーム革命」と呼ばれる一大政治変動を、革命に先立つパフラヴィー王朝の独裁と革命から現在に至るまでのイランの政治変動の座標軸上に位置づけ、「イラン・イスラーム体制の成立の背景とその後の変転の諸相を明らかにしよう」(37頁)としたものであり、イランの内政とそれを取り巻く国際情勢の双方が分析の対象となっている。
本書は、上述のテーマに沿って著者がこれまでに公表してきた論文を加筆・修正したうえで、時系列的に配置したものであるが、一部書き下ろしも加えられている。そのため各章は独立した論文としての性格を強く持っているが、「変転の諸相」(37頁)を明らかにするという著者の視点は、いずれの論考にも生かされているために、イランの政治的通史として読むことも可能である。時代の求めに応じて、時々のイラン情勢を分析した論考が多いなか、イラン研究者による本格的なイラン近現代政治史として、高く評価することができる。
(……下略……)
2006.4.26 『聖教新聞』書評欄 (評者名「雅」)
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

今、イランの動向が耳目を集める。核開発疑惑、それに対するアメリカの先制攻撃を世界が恐れている。
本書は多くの資料を渉猟し、詳細な記述で、イラン現代史への確かな視座を提供してくれる。
(……中略……)
今の現象しか見ず、複雑な歴史を知るプロセスを無視する風潮は、歪んだ判断力の支配を生み出す可能性があると、著者は指摘する。その危機感から本書は書かれた。
膨大な資料を縦横に使い、安易な断定を避け、事実を丹念に追い求める著者。イラン現代史のみならず、複雑な事実の「実相」に分け入るその姿勢は、確かに、複雑な諸問題の解決が望まれる現代社会に必須のものだろう。
2006.1月(下旬)号 『出版ニュース』誌 「ブックガイド」欄
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

世界に衝撃を与えた1979年イスラーム革命、その後の長期にわたるイラン・イラク戦争、さらに米国からの「悪の枢軸」呼ばわりと、イランをめぐる現代史は波乱に満ちている。
(……中略……)
〈イランは何が起きてもおかしくない〉国だが、「悪の枢軸」でくくれるほど単純ではない。イスラーム世界を理解する上でも、不可欠のものがイランの政治史から引き出すことができる。
2006.1.8 『日本経済新聞』書評面 日本経済新聞社評
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

[見出し] 政治力学理解への視点を示す
過去四半世紀あまり、イランは国際社会の中できわめて個性的な存在であり続けてきた。1979年の王政打倒の革命、97年の改革開放派ハタミ政権の登場、昨年の大統領選での保守強硬派アハマディネジャド氏の大勝……。イランの政治は専門家も予想できないような振幅で動き、中東を巡る国際関係を大きく変える契機にもなってきた。
こうした劇的変化が、なぜ起こるのか。本書は、ひと口に「イスラム共和制」と呼ばれる革命後のイラン内部で、どのような政治の葛藤と路線対立があったのかを、歴史的な背景や国際情勢の推移と重ね合わせて整理している。
(……中略……)
「保守派」「急進派」「現実派」。著者はイランの政治勢力を大きく三つに分けて経済、外交、文化に関する政策スタンスの違いを説明し、各勢力内部の多様さも指摘。保守かリベラルか、政教一致か政教分離か、といった二元論的対立とは異なるイランの政治力学を理解するための視点を提示している。やや難解な学術論文的な内容もあるが、主要登場人物の紹介を加えるなど、一般読者の理解を助ける工夫も凝らした現代史だ。
2005.11.20 『中国新聞』(著者インタビュー) 佐田尾信作記者
2005.10.30刊 吉村慎太郎著 『イラン・イスラーム体制とは何か』

[記事見出し] 中東に目向けたい
(……上略……)
いくつかの論考をまとめ、小説のような登場人物一覧、索引、年表などを付けて読みやすくした本書。日本の大学教育の現状を憂える気持ちも、出版の動機の一つだ。
「今の学生は優しい言葉で情報交換はできる。でも、現象に追われ、物ごとの原因と結果の分析ができない」。中東やイスラムの歴史を高校までの教育で十分教えないことは一因だが、「テロ」「イスラム原理主義」などの言葉だけが独り歩きしているのも現実だ。
「日本ではイランの体制が『政教一致』と批判されるが、それはバイアスのかかった見方です」とみる。79年の革命は「時代遅れの宗教復興現象」ではなく、度重なる大国の干渉に対する民族の自己回復への努力の結果。しかし、イスラム革命の理想を政治はゆがめてきた。イスラムの精神を生かせない責任は人間にある、とも考える。
今、悔やまれるのは、2001年9月11日の米中枢同時テロ。97年の選挙で圧勝したハタミ前大統領は「文明間の対話」を提唱していたが、9.11を境にその条件を失い、国際関係に生かされないままだ。そして「ヒロシマは中東問題にもっと関心を持つべきではないか」と思う。
(……下略……)
出版巨人創業物語

2006.3月(中旬)号 『出版ニュース』誌 「情報区」欄
2005.12.20刊 佐藤義亮・野間清治・岩波茂雄著 『出版巨人創業物語』

文の雄、談の雄、学の雄――『出版巨人創業物語』は、新潮社佐藤義亮、講談社野間清治、岩波書店岩波茂雄。それぞれの分野で一家をなした3人の、これまで一般の目には触れることの少なかった体験談を収録したもので、読みものとしても面白い。
「佐藤義亮」は『新潮社四十年』(S11年・新潮社・非売品)所収の「出版おもいで話」を収録。『新声』の創刊(M29年)から『日本文学大辞典』(第1巻・S7年)まで。新声社から新潮社への間のつなぎは、〈可なり暗い一幕がある〉と。『新潮』の創刊を決めたが金が一文もない。そこで敷金の少ない家へ引越しその差(約150円)を利用したという。『新潮』と幸徳秋水、堺枯川の『平民新聞』との意外な接点も明らかにしており興味深い。
「野間清治」は、野間著『私の半生』からの創業期前後の部分を抄録。野間曰く〈この本を読んで、読者諸賢は驚かれるかも知れない。私のいう事なす事、従来の私の本とはまるで違う。野間清治が別もののように感ぜられるかも知れない。(中略)いわばこの本は、失敗談、悔恨談とも申すべきもの。(中略)それ故、一般の善良な方々には、今度のこの本は余り為にならない、或は害になるかも知れません…〉。講談社といえば「面白くて為になる」がキャッチフレーズとなるのだが…。
「岩波茂雄」は、『茂雄遺文抄』(S27・岩波書店・非売品)を底本の「回顧三十年」などから。岩波文庫、岩波全書、岩波新書創刊の周辺についても書いている。現代人の常識教養を向上させようと出したのが「岩波新書」(S13)。第1冊目はクリスティ著、矢内原忠雄訳『奉天三十年』(上下)。これを第一に入れたのも偶然ではなく、〈わが同胞が王道楽土建設と称しながら満人を同胞視せず、天照皇太神宮を移し祭って事足れりとして居るのに反し、英国人にすら人類の理想のためには民族を超越し、満人のため一身を犠牲にしている崇高な者のいることを、警告するためであった。〉
2006.2.17 『週刊読書人』(書評専門紙) 塩澤実信氏評
2005.12.20刊 佐藤義亮・野間清治・岩波茂雄著 『出版巨人創業物語』

(……上略……)
端から見たら失敗して当然と思われる無謀の船出だったが、成功へと導かれていったのは、佐藤には分身的存在の義弟や田山花袋など明治中期以降文壇に登場した作家の手厚い協力を得たこと、野間には群馬の教師時代の同僚、後年に名を成す東京帝国大学生の雄弁家の尽力があった。岩波は安倍能成、阿部次郎ら、アカデミックな人材に恵まれたことだった。
資金繰りでは、約束手形の夢にうなされたり、午後二時の銀行からの電話に震えあがった彼らが、見事な図書目録を残せたのも、財産としての人間関係に恵まれたからとみて間違いはない。
このように、文の雄の新潮社、談の雄の野間清治、学の雄の岩波茂雄の生き様を比較できるのも、一冊の本に出版人の大先達を収録できたからだろう。社史、自伝は手前味噌であり、自慢話のかたまりであるから読まれない本とされているが、個性、出版姿勢の異った成功者を一冊にしたことで、読める出版側面史ができた思いが強い。(しおざわ・みのぶ氏=出版ジャーナリスト)
2006.1.29 『毎日新聞』書評面 毎日新聞社紹介記事
2005.12.20刊 佐藤義亮・野間清治・岩波茂雄著 『出版巨人創業物語』

日本の出版界の基礎を作った三人の創業者の自伝をまとめた『出版巨人創業物語』が書肆心水から出版された。新潮社の佐藤義亮、講談社の野間清治、岩波書店の岩波茂雄が社史などに執筆した自伝を収録。創業を決意した経緯や雑誌創刊の苦労、出版人としての信念や哲学を紹介している。野間氏は『少年倶楽部』創刊時を振り返り、自身の教師経験にも触れながら「少年に必要な家庭教育の不足を補いたい」と語る。
頭山満言志録

2006.11月号 『東京人』書評欄 鹿島茂氏評
2006.1.30刊 頭山満著 『頭山満言志録』

坂口安吾が、天皇制とか武士道とかは、それ自体では真理でも自然でもないが、そこに至る歴史的な発見や洞察においては、軽々しく否定できない意味を含んでいるというようなことを『堕落論』で述べているが、これは読書についても当てはまる。
つまり、ある本の内容が空疎で常識的なことしか述べられていなくても、その本が非常に多くの人に影響を与え、歴史を動かしてきたとするなら、その本は、「凡庸さの重要性」という一点で読むに値するということである。
現在、書肆心水という小さな出版社から続々と刊行されている頭山満、杉山茂丸、宮崎滔天など、いわゆる大陸浪人系の右翼の大物の著作は、ほぼこのケースに相当する。すなわち、著作の内容そのものとは別のところで、これらの本は大きな意味を持っているのである。
その典型は、国権主義的右翼団体「玄洋社」を設立し、民間右翼の大物として維新から敗戦に至る時代に重きをなした頭山満の著作を集めた『頭山満言志録』である。(……下略……)
2006.3.19 『毎日新聞』書評面 山内昌之氏評
2006.1.30刊 頭山満著 『頭山満言志録』

歴史には、名前がよく知られていても言説となると不詳という人物がたまに登場する。明治初年から昭和前期にかけて活躍した右翼民権論の巨頭、頭山満もさしずめその一人であろう。福岡藩の下級武士の家に育った頭山は、政治結社の矯志社や玄洋社の首領であるが、戦後の日本人にとってなじみがなかった。それは、戦中に岩波書店から刊行される予定の『頭山満翁正伝』が戦災に見まわれる奇禍にあったせいもある。
頭山は西郷隆盛の崇拝者でもあったが、出版社のオリジナル編集になる『言志録』は、巻頭に「大西郷遺訓を読む」と「英雄を語る 西郷南洲」を収めている。次いで「立雲談叢」なる往年回顧、人物月旦、時評などが配されており、最後に異色推理小説『ドグラ・マグラ』の著者・夢野久作の「頭山満先生」を付録として加えている。
(……中略……)
時論にも軽快愉快な洞察が多い。警察が中国人留学生の取締りを強化するのは、「見つとも無い」「弱い者に、キツクやる事はみぐるしい」「騒ぎなぞは感情に基いて居るから、猶更(なおさら)用心せぬと感情はつのり安いものぢやから、こちらまでが感情でやつてはいかぬ」などは、辛亥革命と孫文を援助した頭山らしい。朝鮮統治についても、「一国を作(な)して居つたものを、天に代つて仁を施してやるのぢやから、余程其の心が徹る様にせぬと」といった塩梅である。
アジアは西洋という大きな蛇のために臍まで呑み込まれており、腹から上の頭くらいの日本だけが呑まれずに残っている。そこで日本が「義気を出して、うむと一骨折つてやらねばならぬ」というのだ。英国のインドに対する植民地支配は「無理を通り越して非道であつた」故に、「必ずや反動は来る可きぢや」。果たして、第二次大戦後にインドは独立した。
頭山は、アジアを支配し戦場とした日本にも、英国を非難したように「無理は不可(いか)ぬ、無理が永続した例が無い」と批判していたかもしれない。しかし、一九四四年十月に九十歳で死んだ頭山に日本の悲惨なアジア経営の感想を聞くことはできない。日本のアジア主義を理解する上でも大切な書物が出版されたものだ。
全文は『毎日新聞』ウェブサイトでご覧下さい。

2006.4.5号 『ダカーポ』書評欄 吉田司氏評
2006.1.30刊 頭山満著 『頭山満言志録』

(……上略……)
そう、つまり鄭永善はその経済「どん底」のハルビンからやってきた娘であり、戦前日本の中国侵略と今度の事件は無縁ではない。いや、ある意味その隠された深層原因のひとつですらあり得る……。
だから今日は哀しみをこめて、西郷南洲(隆盛)思想の継承者『頭山満言志録』のこのアジア主義の2つの言葉を読もう――頭山満って知ってるかい!? 日本近現代の愛国右翼運動のゴッドファーザーみたいな存在だ。今年はその頭山満生誕150年の年でもあるんだってね。
「南洲翁が常々いはれてゐたといふ言葉に『日本は支那と一緒に仕事をせんければならぬ。それには日本人が日本の着物を着て、支那人の前に立つても何にもならぬ。日本の優秀な人間はどしどし支那に帰化してしまはねばならぬ。そしてそれらの人々によつて、支那を道義の国に、立派に盛り立ててやらんければ、日本と支那とが親善になることは出来ぬ』といはれてゐたものぢや。今日までも日支親善を説くものはあるが、支那人になれといふものは一人も見当たらぬ」
満州侵略や南京虐殺に帰結していった《大アジア主義》の思想だがその「はじめの一歩」はこうした民族ナショナリズムを越えてゆく自由民権的な視点を有していたし、次のような「痩せ蛙 負けるな一茶ここにあり」的な義侠心にも満ちていた。「中国の反日デモ」くらいでオタオタしている日本外交や排外主義をあおる者たちに読み聞かせたい言葉だ。
「支那の留学生が騒ぐと云つて、警察が手を出したのは、見つとも無い。日本から見れば弱いものぢやから、弱い者に、キツクやる事はみぐるしい。……殊に、弱いものには、唯でさえヒガミ心が有りたがるものぢやから普通でも面白くなくなる、余程気をつけて、優しくしてやらぬと。(中略)支那の学生達から利益を得よう位の了簡ではいかぬ、政府も民間も、共になつて親切にしてやらぬと。……日本人を教ゆるでも、西郷南洲の塾とか、吉田松陰の塾とか云ふものは、月謝など取つた話は聞かぬようぢや。月謝は先生から出す、食料まで出す、命まで投げ出して教へて居る様ぢや。これ丈の親切と覚悟で平常やつて居れば、今度のような出来事の時には、一言で治まらう。もし之に従はぬ様では、罰が当る、と云ふ感じを起さする位でなくては」
モチロン園児殺害の悲惨と犯罪性については論を俟たないが、しかし、いまこの〈支那の留学生〉という部分を鄭永善と読み替えて考える日本人は有りや無しやと、私などは深く心を打たれるのである。これから少子高齢化の「老人大国ニッポン」は数十万の外国人労働者の移動するパワーの助けを必要とするだろう。その時に狭い島国ナショナリズムを捨てよと説く頭山精神は聞くべき重さを持っていると思うのだ。もっとも頭山の本質は、尊皇・愛国右翼であるから、彼のそうしたアジア主義もやがて「狭い日本にゃ住み飽いた、海の向うにゃ支那がある」という〈大陸浪人〉的な対外侵略を主張する国家主義へと変質してゆく。頭山の組織した「玄洋社」は、日清戦争前に多くの壮士を朝鮮に送りこみ、戦争の導火線の役割を果たし、日露戦争には玄洋社の流れから内田良平の「黒龍会」が壮士を送りこむなど、日本近現代の国家主義的右翼運動の源流となった。また、中国独立の父・孫文や朝鮮近代化の金玉均、インド反英運動のビハリ・ボースらを支援するなど、西欧列強の植民地支配に対抗する《大アジア主義》のシンボル的存在として活躍した――〈アジアを助ける義侠精神〉と〈アジアを侵略する日本帝国主義〉の2つの顔をもったヌエと言うべきであろう。
ところでナゼいまこの本を紹介するか、(……下略……)
2006.2.26 『西日本新聞』書評面 西日本新聞社紹介記事
2006.1.30刊 頭山満著 『頭山満言志録』

(……上略……)西郷隆盛に関する講話などを集めた「大西郷を読む」と「立雲談叢」の二部構成。「立雲談叢」は“自己を語る”“人物・逸話”“時評・訓話”の表題ごとに、頭山の談話を収録。「如何(いか)なる大事業にも、決して多勢は要らぬ。一人でいゝ、誰一人誰が何と云(い)っても俺(おれ)がやりぬくと云ふ、真に決心有る者が立てば必ずや大成するものぢや」など、頭山の人となりを感じさせるものも多い。(……下略……)
宮崎滔天 アジア革命奇譚集

2006.秋号 『道標』(人間学研究会)書評欄 勝木みゆき氏評(「滔天の狂気」/長文書評)
2006.3.30刊 宮崎滔天著 『宮崎滔天 アジア革命奇譚集』

(……上略……)「狂人譚」で滔天はこう言った。「狂と覚とは実に一転瞬の齟齬である」。狂人とみなされた浪花節語りに自分の信じる真理をちりばめた。さらに滔天は問う。「狂人は常識はずれの行動をする者というならば、その常識はなんなのか」。キリスト、釈迦、ナポレオン…。偉人たちは皆、常軌を逸する行動を通じて真理に到達した人ばかりではないか、と。
その言葉は普遍性をもって百年後の現代人にも響いてくる。今私たちが信じている常識の世界は多くの人間が共有するスタンダードといいながら、その時代の一握りの権力者や国家のエゴ、功名心によって作り出された価値観の塊ではないか。世間の常識をまず疑ってみよ。そんな常識を自己の行動や判断基準とせずに、自分の足で立って思考し行動しているのか。
中国では教科書に滔天が必ず登場するという。一方、日本の教科書では国内の出来事に影響力をもった政治家、官僚、軍人の名が連なり滔天は出てこない。恥ずかしながら私も滔天が孫文の中国革命に果たした役割がこれほどまで大きかったとは知らなかった。近代日本の歴史観については、国家という枠組みが先に立ち、ややもすれば国内史に終始しがちだ。アジア史を国際的視野からとらえる上で、滔天の著作から学ぶべきことは多い。
評伝 宮崎滔天

2006.6.8号 『週刊文春』書評欄 鹿島茂氏評 (「私の読書日記」)
2006.3.30刊 渡辺京二著 『評伝 宮崎滔天(新版)』

×月×日
……(上略)…… 私が宮崎滔天『三十三年之夢』を読んだのもこのシリーズでだったが、その宮崎滔天の小説「明治国姓爺」「狂人譚」が『アジア革命奇譚集』というタイトルで書肆心水から出版されたと思ったら、渡辺京二『評伝 宮崎滔天』が同じ版元から新版として出た。この書肆心水なる新興出版社、ブランショやグラックなどのフランス関係書と並行して、北一輝、頭山満、杉山茂丸など、大陸浪人系の右翼人脈につらなる人々の本をまとめて出している不思議な本屋だと思っていたが、『評伝 宮崎滔天』を読んでいて、ようやく謎が解けた。どうやら、……(中略)……
それはさておき、『評伝 宮崎滔天』は日本にしか現れないであろうタイプの浪漫主義的革命家宮崎滔天を描き切って間然するところのない傑作評伝である。熊本協同隊を組織して西郷軍に加わった宮崎八郎を兄に持つ滔天は、繊細でアイロニカルな文学的資質にもかかわらず、「最後の幻の協同隊員」として革命に身を捧げようとしたがために悲喜劇を生きざるを得なかったパラドキシカルな人物である。……(中略)……
私なりに表現するなら、宮崎滔天とは、西郷隆盛になろうとして挫折した太宰治のような存在である。日本には、あらかじめ失墜を予定されたこのイカロス型の革命家がじつに多いのだ。この意味において、宮崎滔天は再検討に値する思想家なのである。
滔天文選

2006.秋号 『道標』(人間学研究会)書評欄 西東靖博氏評(「『肥後のワマカシ』は何処へ」/長文書評)
2006.6.30刊 宮崎滔天著 『滔天文選』

(……上略……)ワマカシをこういう風に語ってくれる滔天は、私たちに彼の新しい側面を見せてくれたが、今やワマカシという肥後人気質は絶えて久しい。言葉そのものも、死語に近い。「ワマカシが屈折した心理の所産であるのはたしかだとしても、朗々と突き抜ける気分もまたワマカシの本質」であり、滔天もまた「のびやかで朗々たる人格であった」と解説にある。ワマカシの「朗々と突き抜ける気分」が持つ響は新鮮である。そんな気分に少しだけでも近づければ、いやそれは所詮、人間の器に帰着する。
2006.10.1 『読売新聞』読書面 戸部良一氏評
2006.6.30刊 宮崎滔天著 『滔天文選』

(……上略……)本書は戯文、紀行文・随想、人物論の順で編まれている。だが、私としては、最後の「亡友録」から読むことを勧めたい。彼を革命に導いた実兄の彌蔵や、朝鮮の独立改革運動家・金玉均などについての回想を通して、滔天の言行の原点をつかむことができるからである。あとは、巻末の年譜を見ながら、彼がどんな境遇のときに書いたかを頭に入れて各作品を読めばよい。そうすると、滅茶苦茶な筋立ての戯文や、酒の話から革命論を経て浪花節談義に至る随想や、浪曲一座を率いた地方興行の一見取り止めのない日記から、滔天が抱えていた深い苦悩と、それにめげない革命家の意気地が滲み出てくる。
俗戦国策

2006.10.19 『東京新聞』夕刊書評面 東京新聞紹介記事(今週の本棚/人物伝)
2006.4.30刊 杉山茂丸著 『俗戦国策』

杉山茂丸著『俗戦国策』は、在野の国士として明治・大正・昭和の政財界の舞台裏で活躍した著者(故人)の奮闘録。
2006.7.30 『読売新聞』西部本社版文化面 読売新聞西部本社紹介記事
2006.4.30刊 杉山茂丸著 『俗戦国策』

生涯を一人一党、無官無位で通した福岡出身の国士、杉山茂丸の大著。『頭山満言志録』『宮崎滔天 アジア革命奇譚集』など、玄洋社ゆかりの人物を扱った書籍を次々と出版している書肆心水が放つ待望の復刻本。(……中略……)正史には決して出てこない裏面史としてひじょうに興味深く、思わず噴き出してしまう場面も。日本近代史の考察に深みを与えてくれる。(……下略……)
百 魔 (正続完本)

2006.9.28号 『週刊新潮』 福田和也氏評 (「福田和也の闘う時評 217」)
2006.8.20刊 杉山茂丸著 『百 魔(正続完本)』

黒幕、フィクサーと呼ばれるような人士が、姿をけしてしまいました。現存で、そう目されるのは福本邦雄氏ぐらいのものでしょうか。もちろん、さまざまな業界や領域などのミニ・フィクサーの類はいるのでしょうが、やはり本物、と思わせるにはある種のオーラが必要です。……(中略)…… こうした大物たちのなかで図抜けた存在感を誇っているのが、杉山茂丸です。自ら「法螺丸」を称し、「国事犯」になることが道楽というデタラメさ。「其日庵」と自ら名乗ったように、そのフィクサー業もとんでもなく、息子である夢野久作はこのように書いています。……(中略)……
その杉山の存在感を支えていたのが義太夫にたいする深い見識と、その素養から生まれた文業でしょう。『浄瑠璃素人講釈』は、斯界の大名著として知られる伝説的な作品です。……(中略)……『浄瑠璃素人講釈』は、長期にわたって稀覯本中の稀覯本として、高値がついていましたが、一昨年岩波文庫に収録され、好事家の話題となりました。「道楽国事犯」の右翼の著作が、岩波文庫に入ったのですから、愉快なことです。同書とならぶ、杉山の名作に『百魔』があります。一種の自伝ですが、その登場人物も事件も奇怪なものばかりで、抱腹絶倒、痛快無比の快著です。『百魔』は、昭和六十三年に講談社学術文庫に収められましたが、間もなく絶版になっていました。その『百魔』が、学術文庫版には収録されていなかった『続百魔』とあわせて、このほど正続完本として復刻されたのです。版元の書肆心水は、渡辺京二氏の『評伝宮崎滔天』や『頭山満言志録』、モーリス・ブランショやジュリアン・グラックの小説、イスラム思想書など意欲的なラインナップで、業界の事情通が揃って現在最も動向が気になる出版社と評価しています。
私も、『続百魔』は、今回はじめて読みました。『続』の方は、茂丸自身の経験ではなく、その周囲の人々の活躍譚が書かれているのですが、本当かいなと思うような、聴いたこともない話ばかりを、若い人に語りきかせるという趣向になっています。……(下略)……
アジア主義者たちの声(全3巻)

2008.4.6 『日本経済新聞』書評面 フロントライン
2006.3.30刊 入門セレクション『アジア主義者たちの声』

アジア主義者の系譜紹介 (……上略……)書肆心水は2004年の創業以来、戦前のアジア主義や国家社会主義の思想家が残した文章を重点的に復刻したり選集を編んだりしてきた。「日本や東アジアの近代史を論じる際に避けては通れない分野の基礎文献を世に残したい」と清藤洋社長は語る。今回の入門シリーズはこれまで個々に著作を刊行してきたアジア主義者の系譜を「構造的につかめるように編集した」(清藤社長)。
さなぎとイマーゴ――ボードレールの詩学

2006.10.27号 『週刊読書人』 湯山光俊氏評
2006.8.30刊 岩切正一郎著 『さなぎとイマーゴ――ボードレールの詩学』

(……上略……)この書物の宝石は引用されるボードレールの詩句に結晶化されている。そこには聞いたことのないボードレールの声が響いている。読まれるべきは岩切正一郎氏によって日本語で歌われるボードレールの歌なのだ。そこには未曾有のイマーゴが震えるように響きあい、作者とボードレールは混ざり合いひとつとなってもはや区別のつかないものになっている。さなぎは、美しい成虫(イマーゴ)へと姿を変えて、あたりいちめんに羽ばたくのである。
死生観――史的諸相と武士道の立場

2006.10.26 『中外日報』 中外日報社評
2006.9.30刊 加藤咄堂著 『死生観――史的諸相と武士道の立場』

加藤咄堂は明治の終わりごろに本紙主筆を務めた。彼の関心は仏教にとどまらず哲学・修養・国民教化にまで広く及んだ。著書は宗派にとらわれない総合的な考察が巡らされ、大衆にも受け入れられた。 ……(中略)…… 咄堂の死後、その名も膨大な著書も忘れられつつあるが、本書復刻によってその精神の後継者の出現が望まれる。
2007.1.18 『仏教タイムス』 仏教タイムス社評
2006.9.30刊 加藤咄堂著 『死生観――史的諸相と武士道の立場』

(……上略……)古今東西の書物や人物(民族)に触れながら、その死生観を叙述する。ある意味で比較思想の分野でもある。「武士の死生観」では、法然とその信奉者、日蓮とその信奉者らの最期を記す。「露とおき露ときえぬる人の世や 難波のことは夢のまた夢」と遺した豊臣秀吉など戦国武将の言葉も簡潔に紹介されている。本書巻末で宗教学者の島薗進氏が解説を付しているが、咄堂の関心と1980年代以降のデスエデュケーションやホスピス運動と密接な「死生学」とも重なるところが多いと指摘する。「死生観」は古くて新しい課題といっていいだろう。(……下略……)
味読精読 菜根譚

2007.1.18 『仏教タイムス』 仏教タイムス社評
2006.10.30刊 洪自誠原著・加藤咄堂著 『味読精読 菜根譚』

(……上略……)咄堂は、儒仏道の三教の思想が融合されているとし、「東洋思想の結晶」と評価。「前集二百二十五、専ら処世の要諦を示し、治世産業に及び、後集百三十四、主として引退後の立言に関し修養の玄旨に入る」とする。すべて漢文タイトル、読み下し、原文、解説の構成で、咄堂の気の利いた解説を楽しめる。(……下略……)
医術と宗教

2011.1.1 『仏教タイムス』 仏教タイムス社評
2010.10.20刊 富士川游著 『医術と宗教』

(……上略……)「日本医学史の父」が語る医術と宗教の本質。救済と技術をめぐる根本的洞察は、初版から70年以上が経過した今でもそのまま通用するだろう。「宗教は我々人間の生活を円満にする上に、必要欠くべからざる精神の作用にして、有っても無くても善いというべきものではない」と現今の風潮を厳しく批判する。(……中略……)仏法が時代を超えた教えであることが改めて感じられる。
仏教統一論

2011.5.19 『仏教タイムス』 仏教タイムス社評
2011.4.30刊 村上専精著 『仏教統一論』

(……上略……)著者は仏教学に歴史的視点と批判的態度を導入したとされるが、序論をみるとそれが理解できる。その第一章は「研究の困難」という見出しである。漢字蔵経・満字蔵経・蒙古蔵経・西蔵蔵経の四種に加えパーリ語蔵経にあたることの難しさについて言及している。大乗非仏説について、「およそ大乗仏教なるものは、たとい釈迦説となすも、常識を以て見るべき人間としての釈迦説にはあらざるなり」と述べ、結論に到った理由を三点に集約している。価値ある復刻本。
仏 陀

2011.12 『寺族春秋』 寺俗春秋誌評
2011.5.30刊 ヘルマン・オルデンベルク著 『仏陀――その生涯、教理、教団』

オルデンベルクの『仏陀』は、ブッダ研究の世界的古典として、また今日ではニーチェが読んだブッダ論のひとつとして有名です。内容的には、ブッダの歴史的存在と初期の教団の姿を文献学的手法で立証しています。この本は1881年の初版以来名声を博し、数度の改訂を経て、英語版、ドイツ語版原典は今なおペーパーバックで読み継がれる名著となっています。
(……中略……)
さて、西洋諸国から移植されたインド哲学が、明治37年(1904)に初めて東京帝国大学で開講されて以来約80年の間に、文献学的な手法はわが国に根付きました。
仏教各宗派は明治期に相次いで専門学校を創立し、大正期にその多くが大学に昇格、宗学と並んで仏教学を導入しました。南條文雄を学長にすえた大谷大学や渡邉海旭・萩原雲來を擁した大正大学などはその代表格です。
しかし、日本の仏教学は、仏教の思想・教理の研究に重点がおかれ、ともすれば文献の裏づけを離れた思弁的な傾向があると、内外から批判されてきました。戦前の仏教学者による思想史的研究は、文献学的な実証を欠き、随筆的試論に終わっていると批判されてきましたが、戦後の仏教研究にあっては、文献学的な実証が欧米の仏教研究のレベルの厳格さを加え、人文科学とはいえ精密化学の色を濃くしています。
最初に紹介した本書の序文で、木村泰賢は「これを全体として見れば、その体系に於て、解釈法に於て、問題の取扱方に於て、他の追随を許さぬ特長を具備し、あらゆる類書中、嶄然頭角を抜くものである」と結んでいます。
その意味でも、明治の仏教学研究が、「標準」とした文献学をもとにしたブッダ研究の「解釈法、問題の取扱い方」を眺め、またニーチェがこの本から何を読み取ったかに思いを潜めるのも、またとない読書の楽しみとなるでしょう。
愛国心をめぐって

2007.1.10 『聖教新聞』 聖教新聞社評
2006.12.10刊 内村鑑三著 『内村鑑三小選集 愛国心をめぐって』

偏狭な国家主義を超え、人類益に資する国益を追求する――その視野に立ち、国益に供する時、人は自己の重みを真に感得する。それゆえ、愛国心は自己への愛に通じる一方で、「愛国心を欠きたる人類愛は、偽りの人類愛と称せざるを得ない」と、明治の思想家・宗教者の内村鑑三は述べる。その鋭敏な批評眼で、日本人特有の宗教・歴史・平和観を的確にとらえつつ、愛国心のあり方を探る。
宮廷人と異端者

2012.7.28 『図書新聞』 仲田教人氏評
2011.11.30刊 マシュー・スチュアート著 『宮廷人と異端者――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』

(……上略……)こうして筋を書き起こしてみるだけでも、あらためて興味深い。だが、本書のおもしろさの肝は、こうした主張が論証されていくプロセスそのものにある。本書の思想史の方法は、ある思想家の思想を、かれの生き方と書いたものの複合として理解しようというものだ。王道の手法であるように聞こえるかもしれないが、じつは特異である。本書は徹底しているからだ。本書では、「性格こそが哲学である」という警句と、ニーチェの「どんな偉大な哲学も、その作者の個人的な告白であり、思わず知らず書かれた一種の自伝である」という言葉が、くりかえし引用される。ここで重要なのは、著者がまさに心身並行論のように、生とテクストを一体のものとして理解しようとするところである。たとえばあるテクストを理解するために、ある人生のエピソードが参照されるのではない。その逆でもない。一方は他方に還元されない。両者はコインの裏表のように、一体なのだ。
(……中略……)本書はなにより読み物として愉しく、スリリングで、読みごたえがある。ライプニッツとスピノザの著作を読んだことのない読者でも、十分に楽しめる。
2012.3.2 『週刊読書人』 平井靖史氏評
2011.11.30刊 マシュー・スチュアート著 『宮廷人と異端者――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』

俗世間の猥雑さから超脱して、必然という名の真理だけを語る「異端者」としてのスピノザ。現世の名声と金銭に対する欲に取り憑かれて奔走した「宮廷人」ライプニッツ。こうした使い古された対比のステレオタイプを上塗りするだけの書物だと高をくくっていた読者も、ひとたび本書を繙けば、豊富な資料に裏付けられた有無を言わさぬ圧倒的な描写(相応の脚色がつきものであることは言うまでもないが)のただ中に引き込まれ、この二人の天才哲学者の接近と邂逅、そして離反の軌跡に、まさに自分自身が立ち会っているかのような錯覚に陥るはずである。驚嘆に値するこの迫真のリアリティに、本書の最大の美点は存しているように思われる。
(……下略……)*後半は批判的な論調。
2012.1.29 『朝日新聞』書評面「ニュースの本棚」
2011.11.30刊 マシュー・スチュアート著 『宮廷人と異端者――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』

「スピノザが来た――危機に強いぞ 高潔な異物」
哲学史の異物。難解かつ分類不可能。そんな17世紀の思想家スピノザの潮がひたひたと満ち来ている。昨年はその名のついた本が次々と刊行された。(……中略……)
昨年秋に出た『宮廷人と異端者』には同時代の大知識人ライプニッツがスピノザの思想に強烈にひかれつつ、世情をおもんぱかって真意を隠すさまが生々しく描かれている。デカルトの信奉者たちもまた「正統性」を主張するために攻撃に回った。(……下略……)
2012.1.15 『東京新聞』書評面
2011.11.30刊 マシュー・スチュアート著 『宮廷人と異端者――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』

微積分記号を考案した哲学者・数学者ライプニッツと『エチカ』で知られる神学者・哲学者スピノザ。17世紀に活躍しデカルトと並んで合理主義の開祖とされる二人は、前者が宮廷に取り入る策士だったのに対し、ユダヤ人の後者は無神論者とみなされレンズ磨きを生業とした。スピノザの哲学を理解するがゆえに憎悪したライプニッツの格闘を斬新な視点と構成で描いた。
2011.12月(中旬)号 『出版ニュース』誌 「ブックガイド」欄
2011.11.30刊 マシュー・スチュアート著 『宮廷人と異端者――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』

〈スピノザは、近代世界を作ったわけではないが、おそらく最初に近代世界をよく観察した人間である。古来の哲学的問題に対して、はっきりと近代の視点から解答を試みた最初の人間である〉 1676年11月、30歳のライプニッツは、43歳のスピノザにオランダで会った。それは哲学史にとって運命的な出会いであった。本書は、邪悪にして光り輝く時代といわれる17世紀において、交差した二人の天才哲学者、宮廷人ライプニッツと異端者スピノザの哲学的対決のドラマを描く。未邦訳のライプニッツ文書から明かされるライプニッツの生身の姿から思索の軌跡が鮮やかに甦り、近代がヨーロッパに突きつけた問題が二人の哲学者を通して浮き彫りに。
西田幾多郎の声

2011.3.6 『読売新聞』書評面 山内昌之氏評
2011.1.30刊 西田幾多郎著 『西田幾多郎の声――手紙と日記が語るその人生』

西田幾多郎の手紙と日記にある言葉で哲学者の人生を語らしめた書物二巻である。
東西思想を融合させた大哲学者も、凡俗と変わらぬ苦悩や喜怒哀楽の念をもっていた。西田は、家族や弟子の将来を厳しくも誠実に思いやる人物であった。大正15年・昭和元年(1926)の記事は、京大で志を得ない愛弟子三木清の行く末を心配するものばかりだ。「大学へどうのこうのということを離れ、単に三木という男をよくするということから私はこの際誠を以てかれに忠告して見たいと思います」と。
子どもらの死去や妻の病気もあって、西田は人知れず苦悩を深める。「私のこの十年間というのは静かな学者的生活を送ったというのでなく、種々なる家庭の不幸に逢い、人間として堪え難き中を学問的仕事に奮励したのです。そして正直に申し上げれば、今は心の底に深い孤独と一種の悲哀すら感ずるのです」(昭和4年)
(……下略……)
師弟問答 西田哲学

2007.12.17 『公明新聞』 2007年 私の3冊 神谷幹夫氏評
2007.2.28刊 西田幾多郎・三木清著 『師弟問答 西田哲学』

西洋哲学を突き抜けて、合理に、論理に烈しく迫る師(西田)の哲学。だがその奥には「底知れぬ闇」が、「デモーニッシュなもの」がある、と弟子(三木)は見る。その神霊(ダイモーン)が動きはじめる、その闇の中から光が出てくる。仄暗さと哲学の生まれ出るディナミスム。哲学の深さが人間のつよさ・すごさに収斂してゆく。『師弟問答 西田哲学』は哲学の生誕、というよりもむしろ「人間の発見」を綴った美しい書である。
2007.4.30号 『プレジデント』 藤沢久美氏評
2007.2.28刊 西田幾多郎・三木清著 『師弟問答 西田哲学』

米国に行くと、現地のベンチャーキャピタリストや起業家の方々のなかに、禅や東洋思想について勉強されている方が多いので驚いている。IT化によって将来社会はどう変わっていくのかを知るヒントが、東洋思想にあるというのだ。そのため、日本人だからと、こうした思想について質問されることが増え、私も書店で東洋思想や禅のコーナーに足繁く通うようになった。
……(中略)……
グローバル社会において「日本人とは何か」が問われ、IT社会において、「人間とは何か」が問われている。その答えを西田氏は、三木氏の問いに答える形で、すでに語っている。
非言語と言語、無と有など相反するものを一つにしていく「絶対矛盾的自己同一論」を確立し、東洋思想と西洋思想の融合を実現した西田哲学は、今、再び新しい光を放っている。
2007.4.6号 『週刊ポスト』 宇波彰氏評
2007.2.28刊 西田幾多郎・三木清著 『師弟問答 西田哲学』

[記事見出し] 思想だけでなく、「人間・西田」をも想像できる入門書
本書は、弟子にあたる三木清の質問に対して、師である西田幾多郎が答える「師弟問答」と、三木清が西田幾多郎の思想について述べた文章を集めた「師を語る」とから成る。つまり「師弟問答」の部分は、西田幾多郎自身による自分の哲学の解説であり、「師を語る」は、弟子である三木清の西田哲学の解説であるといえる。「師弟問答」は1935年、36年に行われたものである。それは共産主義国家ソ連の発展と、ナチス・ドイツの台頭という急激な世界情勢の変化のなかで、現実と思想とが密接にかかわりあう「危機」の時代であった。「師弟問答」は、この状況を微妙に反映している。
……(中略)……
「師を語る」は、単に西田幾多郎の哲学を説明するだけではない。師に対する三木清の限りない畏敬の念がよく表現されている文章である。そこには西田の思想だけでなく、師の日常生活の一端が、さりげなく描かれている。たとえば、和服を着て靴を履くという西田の服装の描写に、読者は生きた人間としての西田の面影を想像できる。西田哲学の入門書として推薦に値する。
憂い顔の『星の王子さま』

2009.10月 『Revue japonaise de didactique du français Vol.4, no2』 (日本フランス語教育学会) 遠藤史子氏評
2007.5.22刊 加藤晴久著 『憂い顔の『星の王子さま』』

(……上略……)
本書について、特に次の2点を高く評価したい。著者は Le Petit Prince の翻訳批評を批判し、内藤訳の誤りや不適切さを徹底的に指摘し、新訳を厳しく点検する。著者の口調は、直截的で、激しい。しかし、このような批判は必要であり、しかも、前向きな論法が用いられる。これが第1点である。批判することで、翻訳批評や翻訳そのものの誤りや見当違いを看過せず、その欠陥をはっきりと浮き上がらせる。批判は問題点を見定めるために必要なのだ。そればかりか、著者は、批判の理由・根拠を必ず付け加える。翻訳批評の誤りを批判し、それが何故誤りなのか、的外れであるのかを説明する。内藤訳の問題箇所を指摘し、それが何故誤りなのか、不適切なのかを解説する。著者が原作をどのように理解しているか、どのような日本語の表現に移し替えたらよいのかも提案する。原作の読みの正確さと日本語の表現の適切さが検討されることで、本書における批判は、あるべき翻訳への道筋を指示する、前向きな、建設的なものと言える。
第2点は、批判の理由・根拠を示す説明・解説が充実していること。実に、教示に満ちている。例えば、原作の語句の意味を正確に把握するために、一般の学習者向けの仏和辞典や仏仏辞典を調べ、原作の他の箇所での用例に当たる他に、著者は、サン=テグジュペリの他の作品での用例や、日刊紙の一般的な用例を参照する。広い範囲の資料を調べている。原作内容を理解する上でのキーワード―― apprivoiser, rites, doux/douce ――の意味をとりわけ綿密に検討し、原著者が語句に込めた意味に相応しい訳語を探している。これは熟読に値する。原作内容の展開につれて何度か用いられる語句の呼応関係を把握するという、原作の深い読み方も示唆に富む。
Le Petit Prince の翻訳例が検討される際に、他の作者の原作の翻訳例もいくつか引き合いに出される。その中でも、ミラン・クンデラ『冗談』のフランス語訳をめぐる事件の紹介がとりわけ興味深い。ボーボワール『第二の性』の新訳出版までの経緯が注記で紹介されるなど、誤訳・悪訳を乗り越えるために努力する訳者や出版社に関する、心強い情報もある。
ただ、主に記述の提示の仕方について、気になったことがある。2点を挙げる。
(……中略……)
本書は Le Petit Prince の翻訳批評というだけにとどまらない。他の作品にも応用できる翻訳の実践マニュアルでもあり、何よりも、翻訳という営みについての厳しいが真摯なメッセージに満ちた翻訳論でもある。長年定番とされてきた訳書の後を受け、新たな翻訳を試みるには、旧訳の欠点を見定め、これを克服するような翻訳を目指すべきである。翻訳者とは、原作と原著者を愛し、そのためにも原作を正しく伝えるという、読者への倫理的責任を負う。原作と読者の間の橋渡し役なのだ。このような役割を持つ翻訳者が目指すべき翻訳を、ミラン・クンデラに倣い、うつくしく忠実な翻訳、と著者は表現する。原作に忠実でありながら、別の言語で新たに創造されたうつくしい作品であるような翻訳を実現するのは、本当に難しい。
フランス語のクラスで、あるいは独学で、Le Petit Prince の原作を読み、日本語に移し替えようとする意欲的な学習者には、格好の手引書として、また、翻訳をテーマとするゼミなどで、フランス語翻訳の貴重な参考文献として、本書が大いに活用されることを切望する。 遠藤史子(北海道大学)
2008.1月号 『論座』私が選んだ3冊 2007年の収穫本 木村衣有子氏評
2007.5.22刊 加藤晴久著 『憂い顔の『星の王子さま』』

(……上略……)
その内藤訳の問題点を子細に指摘し、さらに、出版権の期限切れに伴って刊行された14冊の新訳も手厳しく分析したこの本、フランス語に明るければもっと面白いのだろうけれど、そうでない自分にもこんなに面白く読めていいのかと戸惑うほど、爽快な読み口だ。大学名誉教授らしいきっちりした文章の中に時おり〈ウソつけ!〉〈勝手に下手な作文をしている。許しがたい〉など、からい言葉が混じる。それは単なる言いがかりではなく、翻訳の〈うつくしさ〉を守りたいがための言葉だ。だから、爽快なのだ。
2007.8.20 『日経ビジネス』書評面 岩下正氏評
2007.5.22刊 加藤晴久著 『憂い顔の『星の王子さま』』

(……上略……)
著者の真意も、内藤訳をこき下ろすことではなかろう。むしろ、1つの訳が神格化され、自由闊達な翻訳批評がはばかられる雰囲気が醸成されてしまう我が国の独特の状況を、是が非でも打破することにある。文学作品は皆の共有財産。翻訳者であれ誰であれ、その私物化を許さない著者の情熱には拍手を送りたい。
それにしても、本書を読むと、翻訳とはこれほどにも深く、難しいものか、とため息が出る。同時に、文学作品のみならずあらゆる書を通じて、我々がこれまで目にした翻訳書には、実はトンデモ本が多数あるのでは、と疑心暗鬼になってしまう。(……下略……)
2007.6.24 『読売新聞』書評面 河合祥一郎氏評
2007.5.22刊 加藤晴久著 『憂い顔の『星の王子さま』』

加藤晴久先生は怒っている!
五十年以上翻訳権を保持してきた『星の王子さま』の訳は誤訳だらけだったというのだ。そしてその翻訳権が二〇〇五年に切れたとたんに次々に飛び出してきた『星の王子さま』の新訳(二〇〇六年十一月までの十四種)へも怒りの矛先を向ける。新訳を手がけた名立たるフランス文学者も小説家も、この加藤フランス語教室では、実名入りで○×△がつけられて厳しい講評を受けてしまう。そこが何よりおもしろい。
日本語に凝る前にまず原文を深く理解しろと喝破した翻訳論にもなっているが、どの新訳が及第(?)なのかを楽しみつつ、フランス語を勉強できるのが魅力の本だ。(……下略……)
真説 レコンキスタ

2008.2 『世界史の研究』(山川出版社)新刊紹介面 山本勝治氏評
2007.5.17刊 芝修身著 『真説 レコンキスタ』

世界史学習の目的の一つは、多文化共生のあり方について歴史的な事象を通して考察を深めていくことであると考える。本書で扱われているスペイン中世史は、正にこうした学習目的に沿った最適の単元であると言えよう。
(……中略……)
芝氏は、メノカル著『寛容の文化』(本誌第五九四号に塚原氏による新刊紹介あり)に対しては平和共存を美化しすぎているとして批判を加えているものの、宗教対立を主眼としたレコンキスタ観に基づく中世スペイン史像を否定している点では共通する。教科書においても、「十二世紀のルネサンス」などイスラーム世界とヨーロッパ中世世界の関連性に関する記述が以前より増えてきた。芝氏も述べているように、当時のイベリア半島における「三教徒の共存と葛藤」は、「今日の社会にも通じる問題」なのである。
2008.1 『史学雑誌』新刊紹介面 阿部俊大氏評
2007.5.17刊 芝修身著 『真説 レコンキスタ』

(……上略……)
本書の優れた点は、我が国における中世スペイン史研究に刷新へ向けた刺激を与えるべく、「レコンキスタ」概念を中心として欧米での研究成果がコンパクトにまとめられ、多様な情報や視点が紹介されていることにある。従来日本語で書かれることの少なかったイスラム=スペイン側の情報や、軍事的制度についての記述が充実している点も本書の有用性を高めている。「真説」という大上段に構えたタイトルや、擬古的な文体には抵抗を感じる読者もあるかもしれないが、統治制度や経済など本書でカバーされていない側面に詳しい既刊の他の中世スペイン史概説書と合わせて一読されることを是非お勧めしたい。
2007.8.26 『毎日新聞』書評面 毎日新聞書評委員「昌」氏評
2007.5.17刊 芝修身著 『真説 レコンキスタ』

スペインのレコンキスタ(キリスト教徒による再征服運動)は、ムスリムに対する「西方十字軍」や「聖戦」と考えられてきた。しかし著者は、むしろ物欲や世俗的な動機に支えられた領土拡大の戦いだった点を強調する。十一世紀以降の欧州の人口増や長子相続制の普及によって、貴族の次男以下は手っ取り早く土地を手に入れるために、分捕りがたやすい手近なスペインのイスラーム領に目をつけたのだ。
(……下略……)
2007.7.9 『公明新聞』書評面 太田直也氏評
2007.5.17刊 芝修身著 『真説 レコンキスタ』

かつてバルセロナでオリンピックが開催された時のこと、公用語にはスペイン語(カスティーリャ語)とカタルーニャ語が採用された。スペインが多様な地方から構成され、文化的に一様ではないということを示す出来事であった。そのスペインの成立に大きな影響をもたらしたのがレコンキスタ(キリスト教勢力によるスペインの国土回復運動)であるということを否定する者はいないであろう。
昨今、イスラーム世界とキリスト教世界との対立を扱う出版物、特にその原点を探ろうとする書の数は夥しい。それらの中でふたつの文化の交差点・共存地としてのスペインの歴史が語られることも多いが、本書ほどレコンキスタに焦点をあて、詳細にその歴史(第I部)と理念(第II部)を記したものは類を見ないだろう。
さらに、本書における論述は最新の研究動向と成果を踏まえており、従来の書物で主張されてきた学説に欠けていたものを補足し、また誤りを正している。労作であり、敬意を表するに値する。格調高い文章も魅力的だ。
(……下略……)
エッセンシャル・ニシダ 即の巻 西田幾多郎キーワード論集
エッセンシャル・ニシダ 命の巻 西田幾多郎生命論集
エッセンシャル・ニシダ 国の巻 西田幾多郎日本論集

2007.9.30 『毎日新聞』書評面 毎日新聞社紹介記事
2007.8.30〜9.30刊 西田幾多郎著 『エッセンシャル・ニシダ』(全3巻)

(……上略……)『キーワード』には「場所」「絶対矛盾的自己同一」など、西田哲学の核をなす論文10編を収録。『生命』では人類普遍のテーマを追究し、『日本論』に今なお論議を呼ぶ「国体」などを収めた。終戦の直前に没してから62年。哲人の仕事を3方向から跡付けるユニークな構成だ。
地図から消えた国、アカディの記憶

2010.9 『cahier 06』(日本フランス語フランス文学会)書評面 小畑精和氏評
2008.6.20刊 大矢タカヤス/H.W.ロングフェロー著 『地図から消えた国、アカディの記憶』

(……上略……)
そこで大矢が明らかにしていくのは、「(英仏)二つの権力の間をなんとか泳ぎぬけようとしてきた」アカディアンの努力であろう。アカディはケベックと同時期にフランスによって植民が進められながらも、ある時期からケベックよりも冷遇され、それでもイギリス領になったあとも、カトリック信仰・フランス語・フランス文化を守ろうとしてきた。この第二部を読めば、アカディがケベックとは異なるアイデンティティになぜ拘るのかがよく理解されよう。
(……中略……)
毎年八月になると世界各地からアカディアンたちがニュー・ブランズウィックに集まって祭典を開く。民族に必要なのは共通の言語でも共通の文化でもなく、共通の記憶なのである。アカディアンの場合、それが「大追放」であることは間違いあるまい。
昨年カナダ国営放送SRCのニュース番組で、偶然大矢のことが取り上げられているのを見た。日本でもアカディの失われた歴史が教えられているといった内容のものであった。大矢の情熱にあふれた講義風景が今も印象に残っている。
2008.11 『ふらんす』書評面 恒川邦夫氏評
2008.6.20刊 大矢タカヤス/H.W.ロングフェロー著 『地図から消えた国、アカディの記憶』

(……上略……)
著者は再三現地を訪れ、自らの足と目で史実を検証しながら、仏文学者らしく、仏系移民の「アカディアン」の《物語》に感動・共鳴して、当地でのフランス語教育のあり方や、フランス語話者の減少にも気を配っている。その肩入れの仕方が、一見公正を欠くようにも見えるが、本書を書かせる情熱の源にもなっていて、単なるブッキッシュな知識の披露ではない生彩を本書に与えている。仏語圏の台頭は歴史が浅いので、一種のフィールドワークの余地が残されていて、めぼしい作家や研究者に会って話を聞いたり、ホットな議論に自説を開陳したりする機会に恵まれる。そこに著者が従来携わってきたバルザック研究とは一味違うリアルタイムの臨場感が生まれ、著者のみならず、読者をも引き込む魅力が生まれるように思われる。
本書は《仏文学研究》の新地平を示唆する意味でも興味深いのではないだろうか。
2008.6.22 『日本経済新聞』書評面 日本経済新聞社紹介記事
2008.6.20刊 大矢タカヤス/H.W.ロングフェロー著 『地図から消えた国、アカディの記憶』

カナダ東岸、ニューブランズウィック州を中心とした地域は昔、アカディと呼ばれた土地だった。十七世紀にフランスからの移民「アカディアン」が定住し、英仏の植民地争奪戦で一時は強制移住の憂き目に遭いながらも、仏語を核にした共同体意識を守ってきた。その苦難と再生の歴史を仏文学者の著者が掘り起こす。十九世紀米国の詩人ロングフェローが流浪するアカディアンの乙女をうたった長編詩「エヴァンジェリンヌ」も併せて収録する。
アミナダブ

2009.2.14 『図書新聞』書評面 郷原佳以氏評
2008.10.30刊 モーリス・ブランショ著(清水徹訳)『アミナダブ』

とある建物の前を通りかかったトマは、その上階の窓から女性が彼を招いているような気がして、中に入ってみることにする。彼が一歩足を踏み入れ、読者も一緒にそこに連れ込まれたが最後、三二〇頁におよぶ長大な物語は、ついにその「家」から出ることがない。「家」といってもそれは、いっぷう変わった集合住宅である。物語は終始一貫、その集合住宅の中で展開されるのだが、ではそれはいったいどのようなタイプの住宅なのか。
(……中略……)
このように、長大な小説の舞台であるにもかかわらず、この住宅について語ろうとするや、最低限の説明でもひどくあやふやなものになってしまう。結局のところ、この建物がどのようなものであるのかは、最後まで判然としないのだ。描写や説明がないというのではない。それどころか、物語といってはそのほとんどすべてが家の描写と説明――間取り、家具、装飾、部屋の用途の変遷、仕来り、規則、住人の種類、住人同士の関係、等々――に費やされているといってよい。
(……中略……)
だとすれば、ここから翻って確認されるのは、「長篇小説(ロマン)」の眼目は、起伏に満ちた豊かなストーリー展開などよりも、あくまで探索の行程における細部の描写や説明にあるということである。
(……中略……)
「家」の全体像と同様、小説の全体像も見失わせるまでに肥大した細部が読者一人一人を呼び止める、『アミナダブ』はそんな小説なのである。
シンフォニア・パトグラフィカ

全文掲載の特集ページがこちらにあります……◎クリック◎
2009.3 『精神医学』書評面 松浪克文氏評
2008.9.30刊 小林聡幸著『シンフォニア・パトグラフィカ――現代音楽の病跡学』

本書は、著者が2000年から2008年の間に現代音楽の作曲家について積み上げてきた病跡学的研究を中心に組まれた論文集である。著者は第一章に「20世紀作曲家の病跡学」と題して現代音楽の作曲家群像について解説し、幅広く現代の作曲家の置かれた音楽情勢を描き出したうえで、本書で取り扱われる特異な作曲家たちの位置づけを与えているが、よほどこの現代の音楽の質に肌が合い、日頃から親しんでおられるものと思われ、一般にはあまり著名でない作曲家にまで言及して解説しており、その鑑賞領域の広さにまずは驚嘆させられる。本論の個々の議論に立ち入ることはできないが、各病跡学的議論の中に織り込まれた楽曲分析、病状論、気質論、さらには哲学的議論も、それぞれがさまざまな問題意識を喚起し、静かな学問的興奮を覚えて読了した。
(……中略……)
こうした内容の濃さを指摘すると、なにやら重たい読み物のようであるが、実は存外、軽く読み進める。それは、著者が作曲家の生活史や人物描写を実に手際よく、読み物として読ませるようにとりまとめていること、豊富な写真資料を取り込んでいること、著者の文体に、「現代」の芸術を論ずる文章にありがちな晦渋なタッチがないこと、などがその理由であろう。また、著者が随所に、非常に平明な解説を付けていること、各章の終わりに当該の作曲家の「音盤紹介」が用意されていること、などは読者の便宜を図った努力として好感が持てた。評者もこの音盤紹介に導かれて、本書を手にする前には聞くこともなかったはずの、いくつかの現代音楽をこれからじっくり鑑賞し、著者が展開した楽曲構造と作法の分析と精神構造や心理的傾性との関係を吟味しようと考えているところである。(虎の門病院精神科)
2009.3 『臨床精神医学』書評面 馬場存氏評
2008.9.30刊 小林聡幸著『シンフォニア・パトグラフィカ――現代音楽の病跡学』

(……前半略……)
音楽の病跡学は、著者も指摘しているように、論じるのが難しい。作品そのものが言語体系でできていない一方で論考は言語で行わなければならないし、音楽着想は超越的なものとの邂逅や生活史上のエピソードとの関連で論じられることが多いものの、それは音楽創造においては必然でもあり、その音楽家に特異的な要素ではなく音楽家一般にみられる非特異的な(音楽創造全般に共通の)現象といえる。そのため、議論は特定の音楽家というよりも音楽家全般や音楽体験全般を論じた非特異的なものになりやすい。さらには音楽を語る場合には感情移入が伴うことも多く、音楽家の病跡を客観的な視点から論じるには困難さが伴う。こういった、しばし突き当たる壁を著者は軽やかに乗り越えている。各音楽家の生涯や人となり、そして社会との関わりなどが丁寧に拾い上げられ、それらが作品や音楽活動と有機的に結びつけられて議論されている。考察は節度が保たれ、まっすぐで爽快である。精神病理学的側面ではテレンバッハ、カールバウム、ラカン、木村敏、宮本忠雄、加藤敏などが的確に引用されながら論じられ、そのうえで作曲家の置かれた社会状況や、作品の音楽的分析も含めて包括的に検討されており、各作曲家の作品を鑑賞するにあたり著者の推薦する盤も詳細に解説されている。また、精神医学の術語や音楽用語にも適宜解説が付され、それぞれの専門外でも読みやすいよう配慮されている。その論は、音楽を言語の側に引き寄せるのではなく、音楽が音楽らしくあることを尊重しながら進められていく印象を持った。このような多面的な姿勢には、著者のバランスのとれた深い見識が感じられる。
そして何よりも、著者の音楽への愛が感じられる心温まる書物でもある。音楽は投影を受けやすく、音楽や音楽家への愛、音楽を語りたい熱情はともすると自己愛と表裏一体となる。もちろん趣味としての音楽ならばそれでよく、それもまた音楽の役割の一つなのだが、著者の愛はむろん自己愛ではなく、敬意に満ちた利他的な愛であるように感じられた。そしてその著者の気持ちに巻き込まれて読み進めるうちに、あげられた作曲家たちの愛すべきキャラクターと直に接したような感覚さえ生じる。評者は、もちろんこれまでの不勉強のせいもあるが、これほどまでに現代音楽に興味を抱かされたことはかつてない。さまざまな意味で楽しく、読後感も爽やかで豊かな気持ちにさせてくれる書物である。(東邦音楽大学)
2009.No.2 『精神療法』書評面 山中康裕氏評
2008.9.30刊 小林聡幸著『シンフォニア・パトグラフィカ――現代音楽の病跡学』

凄くマニアックな本である。現代音楽が対象であるだけでもそうなのに、木村敏ら訳、エトヴィン・フィッシャー『ベートーヴェンのピアノソナタ』ばりの表紙の装丁といい、扉にツィンマーマンの無伴奏ソナタの楽譜の冒頭部分を配し、各章の終わりには音盤紹介として、そこで取り上げられた曲を聴くための手がかりが実に懇切に紹介されている。
しかも、対象とされた作曲家は、ヤナーチェク、バルトークの二人は何とか人口に膾炙しているが、著者本人がはしがきで「よほどの好事家でないと知らない」と書き、あとがきでも「訳の分らない音楽ばかり」と書いていることでも知られるように、ハンス・ロット、ルーズ・ランゴー、アラン・ペッテション、コンロン・ナンカロウ、ベルント・ツィンマーマン、アルフレード・シュニトケと、十二音技法の作曲家などを含んで、通常耳にしない作曲家ばかりなのだ。
(……中略……)
ともあれ、とても面白く興味深く、本書が出色の力作であることには変わりない。(京都ヘルメス研究所)
2009.6(77号) 『日本病跡学雑誌』書評面 山内美奈氏評
2008.9.30刊 小林聡幸著『シンフォニア・パトグラフィカ――現代音楽の病跡学』

「現代音楽」はムズカシイ。
そこそこのクラシック愛好家を自負する私でも、「現代音楽」と聴くと怯んでしまうし、実際この『シンフォニア・パトグラフィカ』を手に取っても、その半分ほどしか名前を知らない。ヤナーチェク、バルトーク、ランゴーまでならなんとか分かるが、ロット? ペッテション? ナンカロウ? その存在すら知らない現代音楽家の病跡など、果たして読んで理解できるのものナンカノウ? と、恐々としながら項を捲った。
ところが項を進めると、畏れていた「現代音楽」の暗雲はなく、予想以上に読みやすい。丁寧な出来上がりに、暗雲どころかやわらかな知識の光が射し込み、やがてその光は優しく広がってゆく。およそ理解できないだろうと思っていた「現代音楽」の病跡が、だんだんと拓けてくるのだ。
まず圧巻は序章である。「20世紀作曲家の病跡学」と題されたその序章で、小林は大胆にも「病跡」についてまず語り始める。「『天才と狂気は紙一重』とは手垢の付いた言葉だが、『厳然として紙一重の差がある』とみるか『紙一重の差しかない』とみるかで、両者の関係には『紙一重』以上の違いが出る。そのあたりに切り込んでいくのが、パトグラフィー、すなわち病跡学という学問である」というのが冒頭であり、どうやら小林は、病跡学の門外の読者も想定しているらしい。病跡学を学んでいると「病跡学とは」と意識して考えることは少ないが、小林の説く病跡学は挑戦的だ。「人間の創造性がどこに由来するかは未だ説き明かせぬ問題であるが、少なくとも疾病と創造性が『変質』であれ何であれ、同じ根を持つとは考えられない。しかし、個別には病と創造性が不可分といえる天才もいるかも知れないし、同根とはいえないまでも何らかの相関関係を持っているかもしれない。そうした領域、創造性の根源を病理を介して解き明かしたいというのが病跡学の欲望である」とし、さらに音楽の病跡学について様々な例を引きながら、「かように音楽とは、様々な人間的事象の交差する領域に位置する。そこに精神医学的にアプローチすることは、困難な作業ではあっても、肥沃な鉱脈を掘り当てる可能性があるのではないか」と括る筆からは、小林の興奮が浮かぶようである。
序章の後半は、現代音楽史である。現代音楽は聴くのが難解なら全体像を把握するのも難解だ、と思っていたが、小林に解かれて現代音楽の歴史的な「流れ」がやっと少し掴めた(「現代音楽の本」ではなくて「現代音楽の病跡の本」のはずだが、「現代音楽」の入門書としてもこの本はかなり有用である)。
(……中略……)
まず、第1章に颯爽と登場するのは(比較的有名な作曲家から順に並べてあるようであるが、実は単に生年順だそうだ)、レオシュ・ヤナーチェクだ。小林の病跡各論のスタイルはシンプルで、まずその人物の概略を述べ、次に人物の成育史と音楽における業績を詳らかにし、その後精神医学的な人物考察を行った上で、最後にその創作と精神の関係を大胆に纏め上げる。つまり、「〈音楽学〉→《病跡》←〈精神医学〉」という構造が非常に明確なのである。そのどちらからの矢印が不完全でも《病跡》は成り立たないと気付かされる、正しい学問的姿勢である。
さて、ヤナーチェクは小林が「先進的な田舎作曲家」とするチェコの作曲家である。精神医学的には、小林はヤナーチェクを類てんかん気質〜中心気質者とし、「中心気質者は、天真爛漫で、うれしいこと、悲しいことが単純にはっきりしていて、周囲の具体的事物に対して烈しい好奇心を抱き、熱中もすればすぐ飽きる。動きのために動きを楽しみ、疲れれば眠る。明日のことは思い煩わず、昨日のことも眼中にない」と初学者にも明解な説明を加えながら、今度は音楽学的に、「ヤナーチェクの表現主義とは、情緒の変動のこの上もなく豊かな幅、優しさと荒々しさの、怒りと安らぎの、つなぎ目がなく、凄まじい緊迫した対決のことなのだ」という特徴を採り、その精神医学的な特徴と音楽学的な特徴の関係を論じ進め、「ヤナーチェクの音楽は過去から未来へと流れる線的な時間構造(中略)を欠き、感情が今の感情であるという意味において、極めて現在に密着した音楽といえるのである。他方、そのような従来の構造を欠く点で、伝統的な視点からは素人的で奇妙な音楽と判断されたのであろう」と纏めたが、その「音楽学と精神医学の知識を練り合わせて病跡学的な考察を行う」という作業が実にダイナミックで面白かった。また、老年期の(ほぼ片思いの)恋と、それによって高まった創作の独創性もかなり詳しく紹介されていて興味深い。
(……中略……)
思い出すのは数年前、私が病跡学会で発表するテーマを選んでいたときのことだ。「『ヒカルの碁』の漫画が大好きなんです。この漫画をテーマに、イマジナリー・コンパニオンと関連付けて発表してみたいけれど、『ヒカルの碁』じゃ知名度が低いので、『ドラえもん』にしようかな」と迷っていた私に、一言、小林は「『ドラえもん』はダメ。愛してやまないものをやれ」と言った。
「愛してやまないものをやれ」と言ったその言葉に、小林の病跡学への真剣な態度を感じたが、そんな学問への愛情あふれる眼差しに満ち満ちているこの本である。
「しかし筆者の目論見は作曲家たちの診断ではない。作品から、その創作者たる作曲家の心、あるいは精神構造体としての作曲家の姿をたどろうという試みである」と言う小林の病跡学研究の集大成を、ぜひとも手に取ってみられたい。(愛媛県立南宇和病院)
リオタール哲学の地平

2009.5.1号 『週刊読書人』 藤井薫氏評
2009.2.20刊 本間邦雄著 『リオタール哲学の地平』

待望の我が国初のリオタール論が上梓された。著者は1970年代に直接リオタールに師事され、その後、丹念にリオタールの思想を汲み上げてこられた本間邦雄氏である。これまで我が国では「ポストモダン哲学」についての紹介・翻訳は数多く行われてきた。だが、その良質な研究書は驚くほど少ない。特にリオタールについては、これまで一冊の学術書も存在しなかった。(……中略……)
全編を通し、リオタール哲学を理解するために、カント、メルロ=ポンティ、バタイユ等の思想を織り交ぜ、かつ芸術論が挿入される。そのため、本書はリオタール論であるよりも、フランス現代思想の優れた入門書の意味を持っている。
(……下略……)
境 域

2010.12.11号 『図書新聞』 安原伸一朗氏評
2010.7.30刊 ジャック・デリダ著 『境域』

(……上略……)丁寧になされている本訳書は、この点で、訳注が必要最小限にとどめられ、ごく短い補足が本文のなかに埋め込まれているため、本文と訳注との行き来をほとんどせずに、たえず躍動感あふれるデリダの文章のリズムに乗って読み進められる。また翻訳においては、たとえば「「到着」〔l'arrive.造語。音の上では岸辺(la rive)と聞こえる〕」と記されるなど、デリダが配慮する原語の音にも周到な注意が払われている。(……下略……)
2010.10.8号 『週刊読書人』 西山雄二氏評
2010.7.30刊 ジャック・デリダ著 『境域』

(……上略……)訳者・若森氏はデリダのやはり難解な『絵葉書』(水声社)の訳業も成し遂げており、『境域』も適切な訳語と文体でその読みやすさは賞讃に価する。70年代のデリダ翻訳の範例的スタイルが確立されていると言ってもいい。「あとがき」で「デリダの文章は論理的」という確信が語られるが、これはデリダ読解の第一の重要な分岐点だろう。(……下略……)
高村光太郎秀作批評文集 美と生命

2010.5.2 『朝日新聞』書評面 情報フォルダー
2009.3.30刊 高村光太郎著 『美と生命』

詩人で彫刻家の高村光太郎が残した多くのエッセーの中から、批評として優れている約100編の文章を選んだ『美と生命』(前後編)が、書肆心水から出版された。「智恵子の半生」「彫刻十個条」などストレートな題材から、「しゃっくり病」「たべものの話」など珍しいものまで、談話筆記も含めて集めている。
夢野久作の能世界

2010.1月号 『ミステリマガジン』書評面 ミステリ・サイドウェイ 松坂健氏評
2009.9.30刊 夢野久作著 『夢野久作の能世界』

『夢野久作の能世界』(書肆心水)は喜多流の能をよくした久作の能についての文章を集めた異色の本。どのエッセイも語り口が『ドグラ・マグラ』そのもの。名調子だ。
書肆心水

2006.12月号 『論座』「出版魂」欄 論座編集部・中島美奈氏記
『北一輝思想集成』、『頭山満言志録』、杉山茂丸『俗戦国策』『百魔』(正続完本)、宮崎滔天『アジア革命奇譚集』『滔天文選』を立て続けに刊行した。人名を見れば、明治、大正に活躍した「右翼」の大物と目される人ばかり。でもなぜ今?……(下略)……