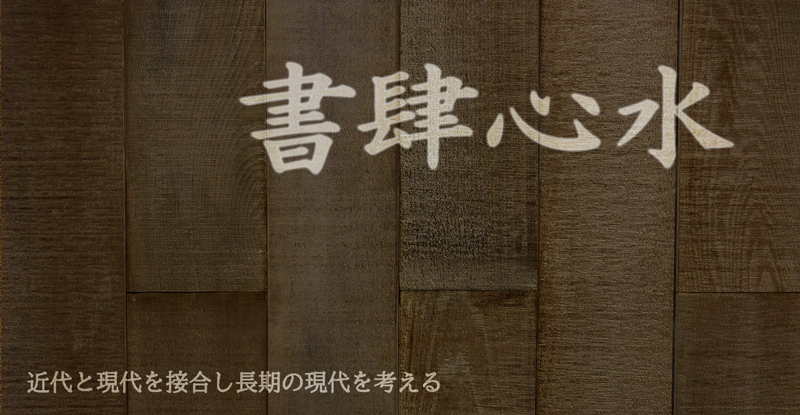
最新刊のご案内
2025年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
恒藤恭・和田小次郎・尾高朝雄著
日本国憲法の哲学――法哲学者が語る民主主義日本への意志
●初心と由来――法哲学者が世界史的/思想史的に見た日本国憲法
現憲法制定同時代の代表的法哲学者が、法哲学的/政治哲学的立場から平易に語る。現憲法を貫く統一的理念/基本思想としての哲学。明治憲法から新憲法への交代になぜ高い価値があるのかを経験的に知る世代が、民主主義国日本の出発に際して示した要点。天皇を象徴として存置することで過去との切断を回避した民主主義国家、そして交戦権を放棄した独立国家。――それを支えるものは何か。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部42ページ分をご覧いただけます。
2025年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
小林聡幸編
精神・医学・宗教性――臨床に纏綿する救済
●心の病と宗教の微妙な関係
病と苦悩――医学の救い、宗教の救い。精神科医療は宗教を拒むべきか、受け入れるべきか、或いはむしろ活用すべきか。心の病の治癒における医療と宗教的なものの境界、心の病の宗教性をめぐる問題の最前線。
大塚公一郎・小畠秀吾・小林聡幸・佐藤晋爾・野間俊一・深尾憲二朗・森口眞衣[著]
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部47ページ分をご覧いただけます。
2024年12月
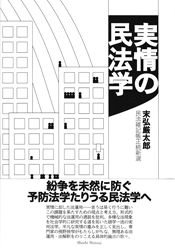
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
末弘厳太郎著
実情の民法学――民法雑記帳正続新選
●紛争を未然に防ぐ予防法学たりうる民法学へ
実情に即した法運用――言うは易く行うに難いこの課題を果たすための視点と考え方。形式的で機械的な法運用の通説を批判。多様な法現象を社会学的に研究する道を拓いた碩学一流の実用法学。平凡な実情の重みを正しく見出し、専門家の視野狭窄がもたらしがちな、無理ある法運用・法解釈をのりこえる具体的論点の数々。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部44ページ分をご覧いただけます。
2024年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
深井英五著
日本銀行・通貨調節・公益性――金本位制から管理通貨制への経験と理論
●金利政策と公益、通貨量と生産力――近代日銀歴代総裁きっての国際派、深井英五の著作選集
日銀が視野に収めるべき公益とは何か――近代の経験からの示唆。第13代総裁が語る中央銀行通貨調節の基本。金本位制の有無を超越して貨幣経済に共通なるべき道理を探求した思索と実務の記録。実際的で理論的な、ドグマなき日銀経営の経験。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部56ページ分をご覧いただけます。
2024年10月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
三宅晴輝著
日本銀行近代史――創設から占領期まで
●総裁の権力、通貨の信認、その歴史性
激動の日本近代の諸局面において、日銀は何を守り誰を救ってきたか。日本資本主義の建設と発展に大きくあずかった近代日銀。1882年の日本銀行条例による営業開始から、1942年の日本銀行法を経て、1997年の新しい日本銀行法により現在に至るまでの日銀――その簡潔平易な前半史。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部38ページ分をご覧いただけます。
2024年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
大森洪太著
異譚綺聞 裁判夜話――裁判夜話/裁判異譚/裁判綺聞 抄(1)裁判篇
●英国伝統の正義の風
大審院判事等を歴任の高級法曹が、或いは見聞し、或いは調査して収集した、西洋の犯罪と裁判に関する奇譚集。古風なスタイルとセンスの語りが往時のリアリティを醸し出し、興味ある旧い事件と法廷に関する実話を今に伝える。『裁判夜話』『裁判異譚』『裁判綺聞』から選別して再配列した第一分冊、裁判篇。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部25ページ分をご覧いただけます。
2024年9月
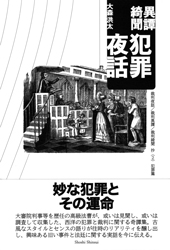
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
大森洪太著
異譚綺聞 犯罪夜話――裁判夜話/裁判異譚/裁判綺聞 抄(2)犯罪篇
●妙な犯罪とその運命
大審院判事等を歴任の高級法曹が、或いは見聞し、或いは調査して収集した、西洋の犯罪と裁判に関する奇譚集。古風なスタイルとセンスの語りが往時のリアリティを醸し出し、興味ある旧い事件と法廷に関する実話を今に伝える。『裁判夜話』『裁判異譚』『裁判綺聞』から選別して再配列した第二分冊、犯罪篇。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部30ページ分をご覧いただけます。
2024年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
末弘厳太郎著
末弘厳太郎評論新集――資本主義・法治・人情・デモクラシー
●「嘘の効用」の末弘厳太郎、『法窓閑話』『法窓雑話』『法窓漫筆』『法窓雑記』からの新集
資本主義化、近代化のなかで法を民主主義的に働かせるための視点と施策。法治近代化の来し方であり、あるいは今なお行く末の課題でもあり、また深く張られた禍根でもある世の諸事情。時代が変わっても変わらない、法治現代化のための考え方を、法社会学の先駆者末弘厳太郎が末弘一流の視点で語る。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部37ページ分をご覧いただけます。
2024年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
平井靖史・藤田尚志編
〈持続〉の力――ベルクソン『時間と自由』の切り開く新地平
●拡張ベルクソン主義、シリーズ最新刊
ベルクソン哲学の現代的射程は計り知れない広がりと深さを秘めている。その土台であり屋台骨となっているベルクソン独自の時間概念〈持続〉。ベルクソンの総ての革新がそこから始まった〈持続〉概念が示される『時間と自由』。その現代的読解の最前線。アレッサンドラ・カンポ/バリー・デイントン/近藤和敬ほか著。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。
2024年6月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
内野茂樹著
新聞とアメリカ革命――初期アメリカ新聞の生成発展と建国独立闘争におけるその役割
●窮極の権利闘争のための新聞――新聞が無気力を脱して激しい編集意識を持ちはじめる時
草創期のアメリカ新聞が歴史的見地において最も著しい社会的役割を担った点は、近代社会の一条件である自由の獲得のたたかいにある。単なる母国からの分離ではなく、母国の至上命令権という絶対権力の返上運動であると共に、内には有産上層の階層に対する中産無産市民の運動でもあった独立革命における新聞の意義を、初期植民地以来の新聞史のなかに位置づける。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。
2024年5月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
瀧川幸辰著
大学と政治――近代日本の大学の自治、その建設と破壊
●学問を権力、財力、俗論から守る――理念とその実践者たち
大学の自治をめぐる戦いのドラマ。大学の理念は帝国大学時代から進歩しているのか、後退しているのか。京都帝大法科の精神と瀧川事件のあとさき。死して生きる道の記録。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか45ページ分をご覧いただけます。
2024年3月
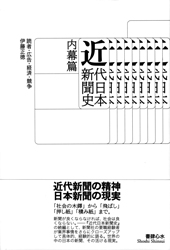
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
伊藤正徳著
近代日本新聞史 内幕篇――読者・広告・経済・競争
●近代新聞の精神/日本新聞の現実――「社会の木鐸」から「飛ばし」「押し紙」「積み紙」まで
新聞が良くならなければ、社会は良くならない。――『近代日本新聞史』の続編として、新聞社の要職経験者が業界事情をさらにクローズアップして具体的、経験的に語る、生の現実。世界の中の日本の新聞、日本社会の中の新聞、そして新聞人の人生。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか63ページ分をご覧いただけます。
2024年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ジョゼフ・シャルモン著/大澤章訳
自然法の再生
●近代から現代へ――自然法がもつ意味を問う
政治の手段、利益の技術にすぎない法のあり方への抗議。――人権・憲法・国際法を自然法が基礎づけた時代から数世紀。対立する各宗教は存続し、世界国家の成立もない現代において、宗教者にも非宗教者にも共通するべき正義の基礎、理想への信念ないし信仰としてある自然法。自然法という名の法律的理想主義の意味の変遷を説き、自然法を否定する諸学派においてもそれを避けえない事情を明るみに出す。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか60ページ分をご覧いただけます。
2024年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
穂積重遠著
近代日本判例批評集――新編 判例百話/有閑法学/続有閑法学
●人の争い、法の白黒――各話読み切りの裁判エッセー集
「日本家族法の父」の平易な名著三冊を再編。法学の素養なしに読める語り口の、庶民向け実践的法学入門。争われている「それ」は誰のもの/権利/罪なのか。人情と法の正義と慣習と、各々の論理、そしてその動揺。人生の重大事について事実と法律が矛盾してはいけないという根本問題を踏まえて論じられる法規と判例。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか35ページ分をご覧いただけます。
2023年12月
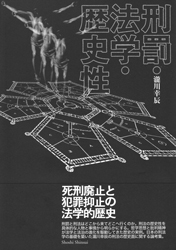
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
瀧川幸辰著
刑罰・法学・歴史性
●歴史的視点による教養の刑法入門――死刑廃止と犯罪抑止の法学的歴史
刑罰と刑法はどこから来てどこへ行くのか。刑法の歴史性を具体的な人物と事情から明らかにする。哲学思想と批判精神が法学と法治の進化を駆動してきた歴史の実例。日本の刑法学の基礎を築いた瀧川幸辰の刑法の歴史面に関する論考集。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか49ページ分をご覧いただけます。
2023年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
恒藤恭著
個人と世界と法哲学――人類史と思想史から法哲学の場所へ
●人類史のなかの法哲学――歴史的に広く見わたされた法哲学の場所と諸課題
法と哲学の関係は人間の歴史の各ステージにおいてどんな意味を持ってきたか。そして「現代」というステージにおける法哲学の役割は何か。困難な時代に左派自由主義の法哲学者として活躍した恒藤恭。保守的性格が極めて濃厚な法の世界を個人主義の哲学的立場から基礎づけ、世界戦争を経た「現代」において倫理的自由からさらに法的自由へと進む道の意味を説く。書肆心水の選定による論文集。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか41ページ分をご覧いただけます。
2023年10月
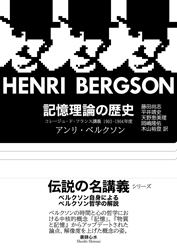
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
アンリ・ベルクソン著
記憶理論の歴史――コレージュ・ド・フランス講義 1903-1904年度
●伝説の名講義シリーズ、ついに公刊! 第二編
ベルクソン自身によるベルクソン哲学解説。ベルクソンの時間と心の哲学における中核的概念「記憶」。『物質と記憶』からアップデートされた論点、解像度を上げた概念の姿。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか35ページ分をご覧いただけます。
2023年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
伊藤正徳著
近代日本新聞史――近代新聞の誕生から敗戦占領下での再生まで
●歴史の中の新聞、歴史を作る新聞
言論(主張)と報道(事実)と国の進路。近代化と民主化の中で新聞と記者はいかに輝き、資本主義の進展と戦争の中でいかに死んだか。新聞界の重鎮として要職を歴任した著者によるリアルな記録。新聞の必要性、存在意義とは――歴史が現在を問う。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか48ページ分をご覧いただけます。
2023年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
和田小次郎編訳『国家と法と正義』
●ヨーロッパ精神における正義観念――古代ギリシャ・ローマ思想から近代民族主義思想まで
ユリウス・ビンダー/アドルフ・ラッソン/マックス・リュメリン/ジョルジオ・デル・ヴェキオ[著]
正義が共同体的なものになるとはどういうことか。ヨーロッパ精神における正義観念の法学的特徴と要所が示された数編を編訳した概説書。激動する国際状況において国家の正義を再考すべき時における国家と法と正義の関係の法哲学。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか51ページ分をご覧いただけます。
2023年6月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
和田小次郎著『人間・自然法・実定法――法の歴史性をめぐる法哲学』
●法学の二大概念と人間性から問う根本的な法哲学
尾高朝雄と共に日本法哲学会を創設し、日本の法哲学を社会に開かれたものにする試みに着手するも、尾高同様50代で突然死去し、その後「忘れられた法学者」となってしまった進歩的法学者和田小次郎。その主要著作を一書に。法規の背後で歴史的に生成変化を続けていく生きた法をとらえる理論と、法をめぐる闘争を高い次元から見る“世界史の法廷”の視点。法と法規を区別することが法論議に持つ大きな意味を示す。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか40ページ分をご覧いただけます。
2023年5月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
外務省編著/信夫淳平原著『満洲問題・日露戦争・終戦講和――小村外交と国際政局 1901-1905』
●世紀をこえる権威主義ロシアの侵略と外交の手法
日本の外務当局の立場と見解を克明に伝える第一級の外交歴史著述。多数の引用資料と旧時代式の表記を読みやすく調整した現代版。ロシアによる隣国への占領侵略から外交交渉決裂を経て戦争へ。ロシア連敗の戦局から講和会議開催への流れにおける各国の思惑と行動、その後のロシア反攻の強固な意志を見た各国の思惑と行動。濃密な五年間の軌跡を、外相小村寿太郎を軸とした具体的折衝の詳細な記録が浮き彫りにする。
小村「貴下の言はあたかも戦勝国を代表する者の如くである(笑)」。ウィッテ「ここには戦勝国なく、したがって戦敗国もない」。――敗戦と償金を断固認めないロシアとの講和の経験。いかなる条件が揃ってそれは可能になったか。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか52ページ分をご覧いただけます。
2023年4月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
田中惣五郎『天皇と軍隊――近代日本国家起動の力、その起源と確立』
●一面傲慢、一面卑屈。――この人間像を形成した国内事情と助長した国際事情
近代日本国家機構の頂点と土台、その創出と連結。――幕末の動乱から明治維新の国家統合、そして立憲君主国として先進世界と関わってゆくための道において、天皇はいかにして天皇となり、軍隊はいかにして軍隊となったか。地政学的条件が生み出したものとしての近代日本国家の天皇と軍隊の連結。日本が今なお脱しえずにいる因縁の歴史的成立事情をたどり、ゆがんだ近代性の淵源を探る。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか53ページ分をご覧いただけます。
2023年3月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
恒藤恭『国際法・国際政治・法哲学――自然法の歴史から世界法の概念まで』
●近現代世界動乱の焦点、国際法の歴史性と可能性。問われる国際法の存在/実効性の基盤を説く
国際法が関係する国際政治を論じることの難しさはどこにあるのか。その複合的で重層的な概念構造を歴史的・哲学的に示す。国際法がもつ近代性から、世界法、世界国家の概念とその可能性の意義までを視野に収めた原理的考察。革新派法哲学者恒藤恭の多数の著作の中から国際法と国際政治の関係を論じた主要論考を一冊に。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか48ページ分をご覧いただけます。
2023年2月
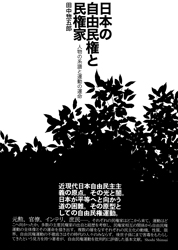
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
田中惣五郎『日本の自由民権と民権家――人物の系譜と運動の運命』
●近現代日本自由民主主義の原点。その光と闇。日本が平等へと向かう道の困難。その原型としての自由民権運動
元勲、官僚、インテリ、庶民――。それぞれの民権家はどこから来て、運動はどこへ向かったか。多数の主要民権家の出自と経歴を考察し、民権家相互の関係から自由民権運動の全体像とその運命を描き出す。複数の層をなすそれぞれの民主化の動機、性質、限界。自由民権運動の不徹底さはその時代の人々のみならず、後世子孫にまで害毒をもたらしてきたという見方を持つ著者が、自由民権運動を批判的に評価した基本文献。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか56ページ分をご覧いただけます。
2023年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ロスコー・パウンド『英米法と法の近代――法律諸体系の歴史と原理の法学的/哲学的諸解釈』(高柳賢三訳)
●主要な法律史観の批判と評価、英米法近代化の精神と力、法の歴史性と法の近代性を見据える法学の主体性
何が法律の根拠となり理念となってきたのか。宗教、哲学、民族性から政治、経済、個人の力まで、法律のありようを方向づけた主要素を批判的に評価。法律近代化の精神を示し、新しい状況の中で法律を形成/運用する力はいかにあるべきかを歴史的に説く。安定性と変化性という矛盾する課題を常に原動力とすべき法の立場、変化する現実に対応する立法、司法、法学の主体性。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか57ページ分をご覧いただけます。
2022年12月
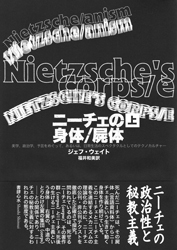
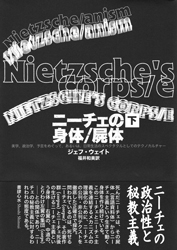
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ジェフ・ウェイト『ニーチェの身体/屍体――美学、政治学、予言をめぐって、あるいは、日常生活のスペクタクルとしてのテクノカルチャー』(上・下)
●伝染するニーチェ、ニーチェとニーチェ主義。ニーチェの政治性、ニーチェの秘教主義という難問の最深部へ。
死んだニーチェはその屍体(言語資料体)からニーチェ主義という生きて動く身体を作り続けている。このニーチェとニーチェ主義を連結するメカニズムの理論化のために、ニーチェの公刊・非公刊テクストを徹底した正確さで探究。問われているのは、死せるニーチェ(corpse)、その著作群(corpus)と、ニーチェ死後の生けるニーチェ主義という身体――右翼の、中道の、とりわけ左翼の集団(corps)――との関係であり、ニーチェの秘教主義に対する我々の態度である。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか52ページ分をご覧いただけます。
2022年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
木村泰賢『時代と無限と大乗の菩薩道――仏教研究/歴史意識/社会性』
●物質文明時代の仏教が考える歴史性と社会性――出家道と在家道の断絶を超える大乗菩薩道の「自利他利同事」
解脱とよりよき世界の建設は矛盾するか。「観念の浄土」と「実在の浄土」の対立から「生成の浄土」へ、そして大乗主義と小乗主義の対立を総合する立場。限りない欲望を苦悩の原因として捨離することのみを趣旨とする小乗的立場をこえて、欲そのものの根本をつきつめて、そこに理想の根拠を見出す菩薩道。大乗と呼ばれるようになる契機としての「自利他利同事」思想が、内へ向かう事と外へ向かう事の一致の意味を説く。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか58ページ分をご覧いただけます。
2022年10月
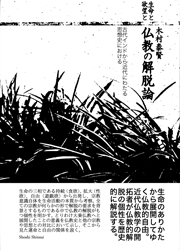
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
木村泰賢『生命と欲望と仏教の解脱論――古代インドから近代にわたる思想史における』
生命のありかたから展開する仏教的自由。近代仏教学の開拓者が、生命の三相である持続(食欲)拡大(性欲)自由(遊戯欲)から出発し、宗教意識自体を生命活動の本質から考察。全ての宗教が何らかの形で解脱の要求を背景とするものである中で仏教の解脱がもつ個性を歴史的に明らかにする。とりわけ大乗仏教へと展開したことの意義を仏教史と他の宗教や思想との対比において示し、そこから見た運命と自由の関係を説く。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか54ページ分をご覧いただけます。
2022年9月
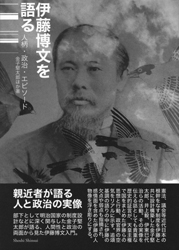
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
金子堅太郎ほか『伊藤博文を語る――人柄・政治・エピソード』
伊藤博文の国家建設に部下として深く関与した金子堅太郎が語る、人間性と政治の両面から見た伊藤博文入門。憲法と議会をはじめ近代日本の根幹をなす各制度を、伊藤と共に設計した金子堅太郎、井上毅、伊東巳代治らの活動。その実像を伝える話としても貴重な歴史的証言が、天皇主権で国をまとめた伊藤たちの思想と行動、明治政官界の課題と空気をリアルに示す。追頌基調の語りの中に伊藤の欠点や弱点も指摘され、感情面をも含めた伊藤の人物像を浮き彫りにする。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか43ページ分をご覧いただけます。
2022年8月

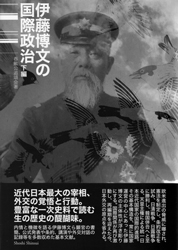
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
春畝公追頌会『伊藤博文の国際政治』上編/下編
近代日本最大の宰相、外交の覚悟と行動。豊富な一次史料で読む、生の歴史の醍醐味。
内情と機微を語る伊藤博文ら顕官の書簡、公式発表や条約、講演や外交対話の記録等を多数収めた基本文献。欧米進出の脅威に曝され、憲法を制定し、条約改正を試み、日清戦争、日露戦争に勝利し、韓国併合へと至る、天皇主権による統一日本近代国家の国際的進路。その基本構造を、常に国家運営の中心にあった伊藤博文の主体性が浮き彫りにする。国際関係が再び激動し、再編期を迎えた今、日本外交の原点を省みる縁。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
上編 45ページ分
下編 53ページ分
2022年6月
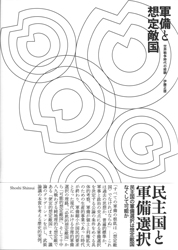
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
伊藤正徳『軍備と想定敵国――世界戦争時代の経験』
「すべての軍備の根底は〈想定敵国〉でなければならぬ」――これは過去の思想か、普遍的標準か。軍事と政治の交点にある軍備選択を決定する公論の条件をめぐる具体的考察。軍備が領土と利権拡大のための生産的事業であった時代が終わり、軍備縮小が国民的要求となった現代における合理的軍備選択の理路。「必然的想定敵国」から「可能的想定敵国」、そして十中八九戦わざる純地理的な想定敵である「便宜的想定敵国」まで、議論のグラデーションを示し、武装論議の本質を考える歴史的実例。民主国の軍備選択は「想定敵国」なくして可能なのか。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか47ページ分をご覧いただけます。
2022年5月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
林権助『極東動乱 出先外交経験秘話 ――葛藤するロシア、中国、韓国、日本』
極東地政学問題の原型、ロシア/中国/朝鮮/日本、そしてそこへの英米の関与を、対韓工作の三人男(桂太郎、小村寿太郎、林権助)と称された駐韓・駐支公使が語る。事なかれ主義官僚の枠を超えた政治判断と人情、本省との距離感、軍部との微妙な関係、そして折衝のセンスとテクニック。くだけた語りで、後代の常識からは批判される行為についても主体的に証言し、当時の空気を生々しく伝える一級の史料。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか52ページ分をご覧いただけます。
2022年3月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
高柳賢三『法律と哲学/法律の哲学 ――関係性・歴史性・普遍性』
現にある法とあるべき法――法律論になぜ哲学が必要か。歴史的で世界的な広い視野から法哲学の立場を明らかにする。
1)法律の論理的、普遍的特質を明らかにすること、2)法律の歴史的発展の基礎とその一般的特性を明らかにすること、3)法律の合理的基礎としての正義理想を内省し、これによって成定法律秩序を評価すること。――この三つの任務をもつものとしての法哲学の立場を初学者に対して示す、総合的入門書。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか40ページ分をご覧いただけます。
2022年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ラインハルト・メーリング『カール・シュミット入門』藤崎剛人訳
生けるシュミット、思想と人物、その脱神話化へ。進化を続けるシュミット研究の最先端を行く総合的概説書。積年の研究成果からシュミットの理論の発展を一つの時系列として説明、その本質と人物像に迫り、流行言説への安易な援用に再考を促す。自由主義法治国家の解体を分析したシュミットから今日の問いへ。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか33ページ分をご覧いただけます。
2022年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
高柳賢三『英米法の歴史と精神』
英米的性格の文化的基底、大陸の法典主義に対する英米の経験主義的な判例法主義とは何か。
近現代世界をリードし席捲したスーパーパワー英米の基底にある正義と秩序のセンスとテクニック。文化の各領域に見られる、理論的に対して実際的、書斎的に対して実験室的、演繹的に対して帰納的等々の言葉で表現されるアングロ・サクソン的性格の淵源であるイギリス法の伝統。抽象的理念主義思想が退潮し、歴史と経験を踏まえた実際的行動選択の精密な議論が求められる現在、回顧し参照すべき伝統。明治期に独仏大陸法を継受し、戦後は米国流憲法を制定したものの、独仏系思想の影響色濃い近現代日本の人文思想界の視野から外れがちな思想的伝統を知る基本文献。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか56ページ分をご覧いただけます。
2021年12月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
堀内干城『日中衝突三十年 現地外交の志――道義的経済政策と侵略的軍事の抗争』
二十一ヶ条要求から第二次大戦戦後処理まで、日中衝突三十年のあいだ日中外交本街道を歩み、そのうち二十年を続けて現地の実務当事者、責任者として過ごした稀有な体験から「道義派と拡張派の抗争」の歴史を語る。現地社会に密接した具体的経済外交とそれに伴う日中関係の推移、軍事的勢力の拡張が徐々に英米権益を圧迫し破局へと向かう状況、そして日本降伏後の中国における復興事業の記録。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか77ページ分をご覧いただけます。
2021年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
斎藤良衛『近代中国と列強の利権――積弱大国に展開する経済の国際政治』
錯綜する地政学的で地経学的な国際政治。ワシントン体制下、二つの世界大戦の間の時代状況を中心にアヘン戦争以来の歴史を振り返り、その先を展望する、同時代国際政治批評。協調主義から群雄割拠、合縦連衡を経て再び協調主義へ、そして……。帝国日本の満洲事変以後の拡張主義による自滅の歴史的背景となる、近代中国に展開する国際的経済事情の概要。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか83ページ分をご覧いただけます。
2021年10月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
野村吉三郎『日米開戦 最終交渉の経験と反省――駐米大使の回想日録と戦後処理』
国政における外交の意味を問う近代日本最大の経験。交渉の最前線、当事者の歴史的証言。真珠湾攻撃と前後した対米最終回答を宣戦布告とする、今なお広くみられる誤解についても終戦翌年には事実を公にした重要文献。今日多方面から明らかにされている関連史実に照らして、外交交渉の最前線で行われていた折衝はいかなる意味があったのかを反省する基本史料。ルーズヴェルト大統領とは九回、ハル国務長官とは六十余回に及んだ折衝の回想日録を中心とする『米国に使して――日米交渉の回顧』と、終戦直後の反省と課題を語った『アメリカと明日の日本――『米国に使して』の続篇』の合冊版。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか42ページ分をご覧いただけます。
2021年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『近代日本外交百年史――開国から国際連合加盟まで』外務省監修※
近代から現代へ、国の根本的なありかたが常に国際関係に左右されてきた日本。開国による国際関係への参加から、百年を経て振り出しに戻った現代日本。その構造を形成した百年の外交の一つ一つの史実の有機的関係を外交当局の視点で示す。満洲事変から日米開戦までについては三分の一の紙数を費やし特に詳述。
※外務省監修『日本外交百年小史』(1958年刊行改訂版、山田書院)の改題改版復刻(底本には1962年刊行の第六版を使用)
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか76ページ分をご覧いただけます。
2021年8月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『座談会 明治大正外交官秘話』
秋月左都夫/石井菊次郎/栗野慎一郎/幣原喜重郎/林権助/牧野伸顕/松井慶四郎/芳沢謙吉
激動する初期日本外交の機微を明かす当局者の肉声。条約改正から日清戦争、日英同盟、日露戦争、第一次世界大戦前後まで、くだけた語りから当時の外交当局における支配的理解、共通の信念やセンスが見て取れる第一級の資料。国際連盟脱退の時局において開催された座談会で示される、国際信義、国際条約の重視、誠実と穏健が近代日本の大をなしたという思想。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか90ページ分をご覧いただけます。
2021年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載
矢内原忠雄『満洲問題入門――植民・資本・政策・軍事』
ロシアの脅威の時代から中国ナショナリズムとの相克の時代へ――満洲国建国前後の問題の構造を多面的に明かす。
同時代のリアルポリティクスに学術性と批評性を標榜する研究はいかに対するか――植民政策学の泰斗による実践。ロシアの脅威に対する防衛として満洲に特別の勢力を張った段階から、中国のナショナリズムが高揚し、ワシントン会議においてアメリカ主唱の下に中国における「特殊権益」が否定され、日英同盟も廃棄された段階に至るも、いよいよ「特殊権益」の地歩を固める日本。あからさまな帝国主義的植民政策が行き詰まる時代において建国された満洲国を画期とする状況の諸問題。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか60ページ分をご覧いただけます。
2021年6月
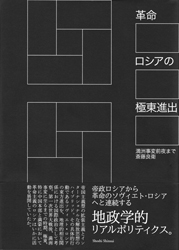
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
斎藤良衛『革命ロシアの極東進出――満洲事変前夜まで』
帝政ロシアから革命のソヴィエト・ロシアへと連続する地政学的リアルポリティクス。帝国主義型の拡張主義とインターナショナルな解放思想のハイブリッド。その具体的行動であるソヴィエト・ロシアの東方進出を、地理的相互関係における政治的問題として考察。第一次世界大戦後、満州事変に至るまでの時期、極東、とりわけ中国本部および満蒙において革命主義のロシアはいかに活動を展開していたか。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。
2021年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ウィッテ/クロパトキン/ニコライ二世/ウィルヘルム二世
大竹博吉編訳『ロシアの満洲と日露戦争』
近代日本の進路における地政学的運命、日清戦争から日露戦争への経緯をロシア側から照らし出す。当時の満洲問題と日露戦争において第一義的な役割を演じた人物自身の状況認識と行動から明らかになる、日露戦争問題の本質。ロシア内部における主戦派と反戦派の対立関係、革命への趨勢が絡み合う複合的な状況。日本側からだけでは見えない歴史の多面的な実像。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか65ページ分をご覧いただけます。
2021年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
伊藤正徳『攻める外交 加藤高明――脱元老支配と日英同盟による国際戦略』
主義主張の人、加藤高明。小村寿太郎と並び称された近代化日本外交の雄の思想と行動。「帝国」に栄光をもたらすとともに、結局は加藤の意図を超えた昭和期の戦線拡大による惨事へと到る対満蒙積極政策の道をつけた加藤の外交。今では多く知られざるその真実と意味を詳細に示す。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか87ページ分をご覧いただけます。
2021年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
尾高朝雄『法思想とは何か――法思想を法や法学や法哲学と区別することの意味』
法学史でも、法哲学史でもない、法思想史の可能性。「理想論的原理主義」と「程度論的実務主義」の背反関係をこえて、責任ある革新の条件となる法思想の歴史性を見据えた法治へ。法学のための法学をのりこえる尾高法哲学の精神。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。
2021年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
信夫淳平『大正日本外交史――覇道主義から大勢順応協調主義を経て協調破壊傾向へ』
苦難と栄光の明治と協調破壊による自滅の昭和との間、あるいは明治富国強兵の頂点たる自衛的日露戦争と昭和軍国主義による侵略的戦線拡大との間に位置する大正日本外交の概要。第一次世界大戦に参戦し、国際政治において主要大国の席を得た大正日本外交の主要論点。同時代の国際法学者が、形式的拘泥の弊に陥りやすい外交官僚的視角をこえて、批評的に時代の動きを分析。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか53ページ分をご覧いただけます。
2021年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
信夫淳平『明治二大外交 日英同盟と日露戦争――絡み合う欧米外交と日本外交』
近代日本国家外交の頂点、その真実と意味。桂太郎首相と小村寿太郎外相の時代、第二次大戦敗戦までの20世紀前半の日本国家のありようと進路を決定的に方向づけた地政学的運命、日露の緊張関係を、外交の史実から詳細に描き出す。日本はいかなる状況の中、国際政治としてどこまで押し、どこで引いたか、臨場感ある駆け引きのディテール。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか60ページ分をご覧いただけます。
2020年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
式場隆三郎『サド侯爵夫人とその夫』
日本におけるサド研究の嚆矢。夫婦関係に注目した、サド論議へのイントロダクション。横暴無類の変質者によくかしずいた「天使のような純情の女性」サド侯爵夫人が、長く獄中にあったサドに宛てた手紙を多数引用し、物語風に記された簡潔な夫妻の評伝。「サド侯爵夫人」「愛の異端者サド」の二部構成。第二部のサド篇では『ソドムの百二十日』他、サドの主要著作の梗概と歴史的背景を紹介。日本で初めて本格的にサドを論じた記念碑的著作。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ダウトオウル『文明の交差点の地政学――トルコ革新外交のグランドプラン』中田考監訳
池内恵氏推薦の辞 「知る人ぞ知るまぼろしの地政学の名著、待望の全訳が現れた。その存在を広く知られながら、主要欧米語の翻訳がなかった大著、新オスマン主義の世界戦略の書が今《蘇った》。トルコの外相・首相を歴任した文明思想家ダウトオウルが国際政治史のパワーセンター・イスタンブールを主軸に構想する、もう一つの世界帝国がもたらす新しい秩序だ。」
非欧米目線の新しい国際政治理論、その豊富な内容。歴史ある非覇権国が今もつべき主体的戦略の深度、その日本との類似性。ダイナミックで多元的な力の均衡システムへと移行しつつある状況が新たな「地政学」を要請する今、トルコ外交を革新しようとする立場から見えるグローバルな地政学問題の最前線。ポスト冷戦期の現実に即しつつ、歴史と地理の深みを視野に収めた新しい国際政治戦略により、欧米中心の世界秩序を克服しようとする政治的・実践的試みが、文明の衝突から文明の総合へのリアリズムを示す。(解説・内藤正典)
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年10月
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
ブランデンブルク『第一次世界大戦への外交史1――ビスマルクから日露戦争まで』芦田均訳
ブランデンブルク『第一次世界大戦への外交史2――建艦競争からバルカン戦争と開戦まで』芦田均訳
ヨーロッパ列強の利害による思惑と駆け引きの詳細と連鎖、現代世界の構造を形成した世界戦争に至る経緯を活写する。謀り謀られ、付いては離れ、望まざる全面戦争の渦に呑み込まれてゆくリーダーたち。力関係の論理と感情の機微を外交文書に基づき生々しく描く。(書肆心水版《芦田外交史》シリーズ完結。既刊『第二次世界大戦への外交史1・2』『両大戦間世界外交史』『第一次世界大戦外交史』)
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
芦田均『第一次世界大戦外交史――開戦前夜から講和会議と近東分割まで』
現代世界の構造を形成した世界大戦を外交から考察。日本の参戦と対中国事情、終戦後の近東分割処理をも詳説。ヨーロッパの問題はどのようにして世界化されていったのか、その大勢と機微を外交の実際から明らかにする。芦田外交史全五冊のうち第一次世界大戦を論じる部分を一巻に再構成。シリーズ既刊、『第二次世界大戦への外交史1・2』、『両大戦間世界外交史』。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
牧野伸顕『開国と興国と外交と――松濤閑談』
急速に近代化する日本国家エリートの視点とセンスと経験。中公文庫『回顧録』で広く知られる牧野伸顕、もう一つの回顧録。大久保利通の子として生まれ、10歳での岩倉使節団随行に始まり、早くから内務と外務の空気に触れて育った国家エリート中のエリートが語る、興味深い具体的事実の数々。官界・国際政治・皇室の事情に通じ、第一次世界大戦パリ講和会議では日本代表団事実上の首席として活躍。老いてなお重きをなし、5.15事件、2.26事件でともに標的にされた重要人物が語り遺した、近代化日本のリアルな風景。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
清沢洌『第二次欧洲大戦 前史と緒戦――外交・思潮・人物像』
第二次欧洲大戦が「戦闘なき戦争」と言われた頃。開戦はいかなる経緯、判断、展望においてなされたか。武力戦であるよりもむしろ外交戦に虚々実々の努力が払われた「宣戦布告の伴った外交」の分析。戦前のリベラリズム批評を代表する清沢が「戦争は善と悪との衝突ではない、正義と正義との衝突である」として、ヒトラーに対してさえも公平たらんとした同時代批評。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
杉山茂丸『山県元帥』
近代化日本の軍政を構築して統率した山県有朋。其日庵一流の語りで伝える山県の人生における情と理。山県、伊藤博文ら元老と直に交わった杉山茂丸の目に映る元老政治の舞台裏。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2020年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
式場隆三郎『民芸の意味――道具・衣食住・地方性』
今では姿を消したもの、今でも使われ続けているもの。日本諸国民芸の旅でたどる、実用の中にこそある美。柳宗悦と共に民芸運動を推進し、『二笑亭綺譚』の著者として知られる精神科医の民芸論を選択して集成。馬鹿の一つ覚え的な作業からこそ生れる美、作家的意識が生じたときに失われる美、実用とともにある美。技巧の末に堕ちた現代における民芸思想の意味。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文41ページまでをご覧いただけます。
2020年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
芦田均『両大戦間世界外交史 賠償問題・経済復興・軍備縮小』
絡み合う賠償と戦債の問題、経済復興、軍縮会議――ナチスの勃興を招来するに至った国際政治の混迷する諸折衝。ヴェルサイユ・ワシントン体制という国際新秩序、あるいは欧米ソ連、三極構造の成立期。戦後処理と再開戦準備の間に何があったのか。芦田外交史全五冊のうち両大戦間における困難な国際秩序構築の時期を論じる部分を一巻に再構成。外交官から政治家へ転身したリベラリストの同時代認識。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。
2020年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
芦田均『第二次世界大戦への外交史2 ナチスの勃興から開戦まで 1933-1939』
わかりやすく物語的に説かれたリアリティと緊迫感ある外交の現場。ヨーロッパにおける外交と戦争のグラデーションをあざやかに描写する。“芦田外交史全五冊”のうち開戦への危機の時期を論じる部分を二巻に再構成(既刊 『1 満洲事変とその前史 1919-1933』)。岩波文庫『第二次世界大戦外交史』で広く知られる芦田均の外交史論。外交官から政治家へ転身したリベラリスト芦田均の同時代認識。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。
2020年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
芦田均『第二次世界大戦への外交史1 満洲事変とその前史 1919-1933』
外交官から政治家へ転身したリベラリスト芦田均の同時代認識。“芦田外交史全五冊”のうち開戦への危機の時期を論じる部分を二巻に再構成(続刊『2 ナチスの勃興から開戦まで 1933-1939』)。岩波文庫『第二次世界大戦外交史』で広く知られる芦田均の外交史論。現在ではこれ自体も歴史の対象というべき、当事第一級の人物による同時代認識の公的証言。リベラルとされる芦田は何を知らせ、訴えていたのか。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。
2019年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
本間邦雄『時間とヴァーチャリティー――ポール・ヴィリリオと現代のテクノロジー・身体・環境』
トーチカからモバイル端末まで。技術革新で変容する“現実”。ポール・ヴィリリオの多面的議論を平易に解説し、ヴァーチャリティーなしではリアリティーが充分に構成されないような局面が各所に広がる現代の状況を掘り下げる。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と「はじめに」をご覧いただけます。
2019年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
尾高朝雄『法と世の事実とのずれ』
変わる世の中と安定性を要件とする法の間にある関係の基本構造。法と社会の主要素(道徳・経済・政治)とのダイナミックな関係を問う尾高法哲学の基本的な問題系を平易に示す、尾高法哲学入門。
「法における規範と事実のこの矛盾は、人間そのものに内在する矛盾のあらわれであるということができよう。法は人間生活の秩序の原理であり、人間の本性にはそもそも矛盾が内在しているからこそ、法の中に規範性と事実性との矛盾が著しくあらわれて来るのである。」
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。
2019年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
高柳賢三『極東裁判と国際法――極東国際軍事裁判所における弁論』
東京裁判における検察側の主張は、国家ではなく個人を国際法で、かつ事後法で裁こうとする不法行為であるとして、倫理上の罪悪、国政上の責任と、国際法上の犯罪の混同を法廷で批判した弁論。人類の近代的法治の歴史に深い傷とわだかまりを残した一大事件の現場である東京裁判の法廷で、簡潔に力強く示されたこの反駁は、政治が法治を力で押し切る現場の歴史的な記録であり、政治と法治、法と倫理の境界画定をめぐる法学的な理論闘争である。東京裁判における「侵略戦争は個人責任を伴う犯罪である」というテーゼが倫理的立場ではなく法的立場からは否定される理由とはいかなるものか。(英語原文を併録)
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。
2019年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
信夫淳平『不戦条約論』
国家間の不戦の約束は、いかなる事情で構想され、いかにして現実のものとなってきたのか。不戦の約束に伴って必要となる制度と解決すべき問題を、具体的な経緯と政治的技術に即して詳説する、パリ不戦条約前夜に刊行された歴史的著作。国際関係が不安定期に移行する現在、不戦の国際合意が実現した経緯を振り返る基本文献。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて50ページ分をご覧いただけます。
2019年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
高柳賢三『天皇・憲法第九条』
九条の異常性を直視する第三の道。日本国憲法に対してなされるべきは、大陸法的解釈か、英米法的解釈か。改憲論議における不可欠かつ第一級の知見でありながら、長くかえりみられてこなかった「日本国憲法と大陸法/英米法問題」の原点の書。九条幣原首相発案説の論拠として広く知られる本書の議論は、近代日本法学の主流である大陸法型の解釈と英米法型の解釈の対立の問題を経て、そもそも憲法という法文はいかに解釈されるべきものかという問いに及ぶ。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて43ページ分をご覧いただけます。
2019年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
小泉信三『批判的マルクス入門』
“搾取”はいかに論じるべきものであるか。マルクスの説の価値はどこにあり、初学者が真に受けてはならない説は何であるか。マルクスの言説における倫理(義憤)と科学を経済学的に峻別。昭和一桁の時代からマルクスの学理に対する本質的な批判を唱えてきた経済学者が説く、マルクス評価のためにまず知らなければならない基本的な問題点。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて71ページ分をご覧いただけます。
2019年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『時間観念の歴史――コレージュ・ド・フランス講義 1902-1903年度』
アンリ・ベルクソン、伝説の名講義、ついに公刊! 百年の時をこえて、いま我々がその講堂に着席する、恰好のベルクソン入門。哲学のアポリアは「時間」を適切に扱うことによって解決されると考えるベルクソンが、古代以来の哲学史に自己の哲学を位置づける。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。
2019年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『軍隊と自由――シビリアン・コントロールへの法制史』
軍事に詳しい法制史学者藤田嗣雄が、具体的な法制化の歴史をたどり、文民統制の歴史的厚みを示すユニークな業績。近世・近代・現代において、軍隊の制御はいかに進展してきたのか。主要各国(英米仏独日)における違いの意味を説く。「政治憲法と軍事憲法が対立する明治憲法の本質が、今次の敗戦を決定したところの、唯一の原因では、もちろんなかったとしても、憲法的見地からは、最も重要視されなければならない。」
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。
2019年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『実定法秩序論』
法哲学者・尾高朝雄が、法の効力の根拠の探究によって法哲学と実定法学を総合する、ノモス主権論の濫觴。法と道徳・宗教・政治・経済など社会の諸要素との関係、そしてさまざまな法思想の間の闘争を構造的に描き出し、法が実効性ある法として存在していることの意味を総合的に明らかにする。書肆心水による尾高朝雄復刊企画第四作。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。
2019年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『聴くヘルダーリン/聴かれるヘルダーリン』
詩作行為における「おと」をテーマに、音楽からの視点ではじめて明かされるヘルダーリンの詩作の根源。従来のアプローチとは一線を画し、詩の音楽性や、詩の音楽的要素と楽音化された音楽との関係を論じるのではなく、詩作行為において、「何か」としか言いようのないものをとらえることが「おと」を聴くという聴覚的な行為であることを論証。ピアニストでありドイツ文学研究者でもある著者子安ゆかりによる画期的労作。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。
2019年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『天皇の起源――法社会学的考察』
天皇の支配と日本国家の成立の関係は法学的にはいかに説明されるか。カール・シュミットの「場序(Ortung)」概念から出発して、権威と権力の対極性を考察し、天皇の支配の形成から日本国家の成立までを法社会学的に探究するユニークな業績。「二〇世紀後半における天皇」の章を巻末に収め、法学的に見た現代の問題をも示す。著者の藤田嗣雄は『軍隊と自由』『明治軍制』『明治憲法論』『新憲法論』等を著した法制史学者。画家の藤田嗣治は実弟。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。
2019年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『暴風来――附 普通選挙の精神 億兆一心の普通選挙』
日本という名の日本最大の宗教、その真髄を学問的に示す問題の書。――今なお私的領域あるいは公の陰の領域に広く根を張る日本的反民主主義思想の強さの秘密とは何か。天皇機関説をめぐる論戦で美濃部達吉に敗北し、日本憲法学史から葬り去られ、闇の存在とされてきた東大憲法学教授上杉愼吉。近年その存在に対する関心高まる上杉が、その思想を分かりやすく語った三書の合冊版。日本は他の国と違うという信念と日本型集団主義の精髄。民主主義の「うまくいかない現実」に対する批判として現れる「日本主義」の核心。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各篇冒頭をご覧いただけます。
2018年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『ベルクソン『物質と記憶』を再起動する――拡張ベルクソン主義の諸展望』
時代にあまりに先駆けて世に出たがゆえに難解書とされてきた『物質と記憶』を新たに読解する野心的試み。ベルクソン哲学と現代諸科学を接続する、拡張ベルクソン主義宣言のシリーズ第三弾=完結編。著者は、村上靖彦、三宅陽一郎、バリー・デイントン、フレデリック・ヴォルムスほか。シリーズ既刊は『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する――現代知覚理論・時間論・心の哲学との接続』『ベルクソン『物質と記憶』を診断する――時間経験の哲学・意識の科学・美学・倫理学への展開』です。シリーズ完結を機に、早くに品切になっていた『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する』を増刷しました。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と序論などをご覧いただけます。
2018年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『〈戦前戦中〉外交官の見た回教世界』
日本人エリートは近代化へと向かう両大戦間期のイスラーム世界をどのように見ていたか。イランで初代全権公使として活躍した笠間杲雄が「アジア興隆の指導者を以て任ずる日本国民」の「認識不足を是正する目的を以て」著した諸々のイスラーム論を集成。中東から、東南アジア、満洲まで、「東洋」として位置づけられた「回教圏」を論じます。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文各部の冒頭をご覧いただけます。
2018年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『道元伝』
道元はなぜ顕密諸宗を見限り、浄土門にくみせず、坐禅の道を歩んだのか。その問いを軸に、腐った社会と共にある腐った宗教界を離れて本当の山に入った道元の実践思想の核心をわかりやすく示した道元論の古典。道元の著作を多く引用して示した点と、仏教思想史・仏教社会史の中に道元を位置づけた点に特徴がある、読みやすい入門伝記です。道元の著作解題と年譜を附録しています。(圭室諦成著)
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文62ページまでをご覧いただけます。
2018年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『ムスリム女性に救援は必要か』
ムスリム女性を抑圧しているもの、それはイスラームなのか? ムスリム女性の権利という概念は何を覆い隠しているのか? こうした問いを出発点に、普遍的人権擁護の美名のもとに語られる〈他者〉の救済というリベラルファンタジーの強制を批判し、それにかわる、現実に即した公正さを提唱する著作です。著者はコロンビア大学教授(人類学)ライラ・アブー=ルゴド。ムスリム女性に権利があるのかと問うのではなく、ムスリム女性の権利、抑圧されたムスリム女性という概念がこの世界でどう作用しているのか、その概念を利用しているのは誰なのかを問うべきだという立場での議論です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次とイントロダクションの全文をご覧いただけます。
2018年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『時枝誠記論文選 言語過程説とは何か』
言葉が通じない。言葉が通じる。その間には何があるのか? ――言語学者時枝誠記のセレクション企画第二弾の本書には、単行本未収録の重要論文を集めました。言葉が通じることを前提とした言語学ではなく、言葉がどのようにして通じるものとなるのか、その条件を探求する言語過程説。言語過程説を成り立たせる多様で相互に連関する重要論点を執筆年順に網羅し、その思想の進化と全体像を示します。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と収録全論文の冒頭51ページ分をご覧いただけます。
2018年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『時枝言語学入門 国語学への道』
言語の本質は何かと問う時枝誠記の学問的自伝、時枝自身による時枝言語学入門です。ソシュールらを模倣した近代日本言語学を批判し、日本語に即した日本語研究として構築された「言語過程説」の由来、精神、方法、歴史を論じる、『国語学原論(正続)』『国語学史』以降の時枝思想のエッセンス。近代型普遍化主義の迷妄を学問的に批判しうる特異なポジションにある日本言語学の意義を示します。
言語を要素の結合としてでなく、表現過程そのものにおいて見ようとする過程的言語観あるいは言語過程観による、時枝誠記の「言語過程説」。ヨーロッパに発達した言語構成観に対立する、それとは全く異なった言語に対する思想から見出された言語の本質とは何か。
本書は、時枝自身による学問的自伝『国語学への道』に加えて『現代の国語学』を併録。『現代の国語学』の第一部では言語過程説の理論が正しく理解されるために明治以来の国語学の全体を叙述しつつ、言語過程説をそこに対比的に位置づけ、第二部では言語過程説に基づく国語学の体系が示されます。さらに、岩波文庫版刊行中の『国語学原論(正続)』『国語学史』をのぞく主要著作の序文類と目次などを附録。時枝の業績のアウトラインを俯瞰することができます。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて51ページ分をご覧いただけます。
2018年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『廃仏毀釈とその前史 ――檀家制度・民間信仰・排仏論』
幕藩体制三百年において変質・形骸化・堕落していった仏教。その仏教に対する批判。そしてその当然の帰結と言うべき廃仏毀釈。明治維新の混乱に乗じ、明治政府の意図をこえた極端な廃仏運動が広く展開したのは何ゆえか。幕末にはすでに発火点に達していた廃仏毀釈への傾きを、社会経済的事情と宗教が絡み合う長期の歴史において明らかにします。(圭室諦成著)
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。
2018年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『上世日本の仏教文化と政治――導入・展開・形式化』
日本の仏教の国家的な性質はなにゆえのものか。出世間的であるべき仏教がなぜ世間的になったのか。――本書が説く、仏教の導入から展開への具体的史実が、その問いへの答えを示します。史料の記述が豊富に本文に織り込まれて読みやすく、具体性に富んだ、仏教文化史研究における圧巻の古典的研究書(『日本仏教史』第一巻「上世篇」)を抄録した読本版です。著者の辻善之助は、日本仏教史研究において、政治・社会・文化の総合的観点と堅固な実証主義的方法により、それまでの教団史的水準を克服した画期的業績を遺した学者として高く評価されています。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。
2018年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『アメリカのユートピア――二重権力と国民皆兵制』
マルクス主義文芸批評の大家ジェイムソンが、ユートピアとしての国民皆兵制を提唱する問題作です。解放された社会に関する左翼のスタンダードな観念をジェイムソンが根本的に問い直す長編論文「アメリカのユートピア」を受けて、スラヴォイ・ジジェク、柄谷行人ら、編者ジジェク選定の九人の寄稿者が応答。あらゆる種類の左翼の現実政治が事実上消滅した現在、解放思想にユートピア論が持つ意味とは何か? ジェイムソンの「アメリカのユートピア」をさまざまに批判しつつも、左翼的プロジェクトの根底的再考の必要性においては一致する諸論考と「アメリカのユートピア」のあいだから浮かび上がる現代左翼理論の可能なる課題、その最前線。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。
2018年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『ドゥルーズ=ガタリにおける政治と国家――国家・戦争・資本主義』
ミクロ政治学として知られてきたドゥルーズ=ガタリにおけるマクロ政治学の力を解放すべき時代の到来を告げる画期的力作の登場です。『アンチ・オイディプス』『千のプラトー』における国家概念、戦争機械仮説の再検討を経て、現代資本主義における闘争の主体たるマイノリティへの生成変化へと議論を展開する、いまこそ見出されるべきドゥルーズ=ガタリ政治哲学の深層がここに示されています。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。
2018年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『自由・相対主義・自然法――現代法哲学における人権思想と国際民主主義』
法哲学者尾高朝雄(おたか・ともお)がノモス主権論の構築と並行して練り上げた自由論を集成しました。民主主義に対する倦怠感が兆し、リベラリズムが空洞化する時代に対する警鐘であり、かつ指針ともなる論考群です。戦後の国際秩序を支えてきた理念を無視する力による世界の再編が進行し、リベラルな国際秩序がグローバルな特権層の活動の場とみなされ、格差が再び拡大する現在、共産主義理念が国政の現実的選択肢としてはもはや存在せず、リベラルの空洞化が有害なレベルにまで達した社会にいかなる道がありうるか。近代から現代への思想史的理路を法哲学の立場から確認しつつ「現代」の基盤は何であるのかを明らかにします。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各篇の冒頭をご覧いただけます。
2017年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『雄弁の道――アリー説教集』
預言者ムハンマドなき後のイスラーム世界を統べた正統カリフ・アリーの説教集、本邦初訳です。イスラームにおける神与の聖典クルアーンと無謬の預言者の言行録ハディースに対して、本書は、イスラームの教えをカリフとして地上の社会において具体化することに生涯を捧げたアリーがその道を説いたものであり、カリフ制の統治に関する第一級、唯一の古典です。若い頃から従兄の預言者に親しみ、預言者の妻に次いで入信した、男性として最初の信者であるアリーが、ムハンマドなき後ムスリム社会はいかにあるべきかを力強く説いた言葉が記録されています。
こちらのリンク先のPDFファイルで訳者の序文と本文冒頭をご覧いただけます。
2017年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『共にあることの哲学と現実――家族・社会・文学・政治』
昨年刊行の岩野卓司編『共にあることの哲学』(フランス現代思想が問う〈共同体の危険と希望〉1 理論編)に続く第2巻の実践編。デリダ、ドゥルーズ、フーコー、バタイユ、ブランショ、レヴィナスの理論から展開し、変転する共同性の現代的状況をとらえ、その新たなありかたを問う共同研究です。著者は、岩野卓司、合田正人、郷原佳以、坂本尚志、澤田直、藤田尚志、増田一夫、宮﨑裕助の各氏。現代の世界や日本の状況を考えるうえでフランス現代思想の共同体論が参照可能かどうかを見きわめる試みです。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と編者の序文をご覧いただけます。
2017年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『ベルクソン『物質と記憶』を診断する』
ベルクソン哲学と現代諸科学を接続する拡張ベルクソン主義宣言の第二弾です。時代にあまりに先駆けて世に出たがゆえに難解書とされてきた『物質と記憶』を、最近の時間経験の哲学、意識の科学、美学、倫理学へと展開し、新たに読解する野心的試み。昨年11月刊行の『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する――現代知覚理論・時間論・心の哲学との接続』の続編です。著者は、檜垣立哉、兼本浩祐、バリー・デイントンほか。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページほかをご覧いただけます。
2017年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『インド思想から仏教へ』
日本近代仏教学の創始者高楠順次郎が、仏教誕生の経緯と当時のインド思想を照らし合わせ、インド思想の何が継承され、何が否定され、何が新たに生み出されたのかを明らかにすることにより仏教の本質を示しつつ、キリスト教・西欧哲学と比較した仏教の独自性を考察。無神論の宗教である仏教は、希望に生きる宗教ではなく、覚悟に生きる人格完成への宗教であるという立場から、諸法無我、諸行無常、三界皆苦、涅槃寂静の意味を明快に説く仏教入門です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
2017年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『明治仏教史概説――廃仏毀釈とその後の再生』
いまでは知る人も少なくなった明治期の仏教界を論じる基本文献『明治仏教史』(土屋詮教著)の全文と『明治仏教史の問題』(辻善之助著)第一題の合冊版です。徳川三百年のあいだ伝統と保護とに鼾睡してきた寺院僧侶が突然食らった廃仏毀釈の巨弾。その強烈なる刺戟によって反省自覚し再生した現代日本仏教の出発点を、史料をまじえて解説。その歴史を知ることにより、その後の日本仏教のなりゆきの意味をよく理解することができます。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各パートの冒頭をご覧いただけます。
2017年7月
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『語る大拙 鈴木大拙講演集』
くだけた語りで鈴木大拙の思想が分かりやすく示された講演集を二巻構成で刊行いたします。第一巻は「禅者の他力論」と題して、浄土門、真宗、念仏に関するものをまとめました。「仏教というものは禅宗も真宗もなし、その器根によって受け容れるものが、ああにもなり、こうにもなると思うておっていい。」とは書中の大拙の言葉です。第二巻は「大智と大悲」と題して、仏教における信仰の構造を語ったものや、世界と仏教の関係を語ったもの、および自伝談話をまとめました。「仏教と云う大建築を載せて居る二つの大支柱がある。一を般若又は大智と云い、今一を大悲又は大慈と云います。智は悲から出るし、悲は智から出ます。元来は一つ物でありますが、分別智の上で話するとき二つの物であるように分れるのです。」こちらも書中の大拙の言葉です。
下記リンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。
語る大拙 第1巻
語る大拙 第2巻
2017年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『皇室と日本』
皇室の存在が再定義されつつあるいま、歴史研究の立場から皇室をめぐる論理と感情を考察した津田左右吉のテキストを集成しました。時代に順応して変化するところにあった皇室の「恒久性」とは何なのか。敗戦後の出発点における「象徴天皇制」をめぐる議論の基本を確認し、皇室制度支持世論の持続と左翼型反天皇制論衰退の原因を探り、いまや一部の人々のものではなくなった皇室に関する議論を歴史的に考えるための一冊です。津田左右吉(つだ・そうきち)は長大な連作『文学に現はれたる我が国民思想の研究』(岩波文庫全8冊)や、その記紀研究が右翼思想家から告発されて発禁になった事件でよく知られる歴史学者です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各パートの冒頭をご覧いただけます。
2017年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『ノモス主権への法哲学』
「ノモス主権論」で知られる法哲学者尾高朝雄の三つの著作――『法の窮極に在るもの』『法の窮極にあるものについての再論』『数の政治と理の政治』――の合冊版です。実力概念から責任概念へと改鋳された主権を提唱するノモス主権論へと至る尾高法哲学の理路がこの三つの著作に示されています。
ポピュリズムが広まり、行政国家化が深まり、象徴天皇制が再定義されつつある今、民主主義はなぜ選挙が終点であってはならないのかという問いを中心に据えて、これら喫緊の諸課題を考えるために時を超えてよび出されるべきものがこの「ノモス主権への法哲学」です。
なお本書には附録として、安倍政権時代におけるノモス主権論のアクチュアリティを示し、ハンス・ケルゼン、カール・シュミット、フリードリヒ・ヘルダーリンとノモス主権論の関係を論じる寄稿論文「ノモスとアジール」(藤崎剛人著)を掲載しました。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次や各パートの冒頭などをご覧いただけます。
2017年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『最後の人間からの手紙――ネオテニーと愛、そしてヒトの運命について』
遺伝子工学時代のモラリスト、ダニ=ロベール・デュフール、初の邦訳刊行です。
性器と脳――それはどのようにしてヒトであることの、この上ないしるしである器官となったのか。知識と快楽を結び合わせる秘密の糸とはどんなものか……。哲学風の掌編物語とエッセイの中間を行く本書は、いま何が世界の将来を深刻に脅かしているのかを問うために、ヒトというあり方の歴史全体を今一度訪ねなおし、死にうることの幸福と人間が脆弱な動物として生まれることの尊さを語ります。
著者は、1947年生まれ、元パリ第八大学教授で、脱宗教化する現代の宗教(現代の神である「市場」)、ポストモダン(脱主体化)の帰結としての人間の機械化(生命工学による人種改良)、ポルノグラフィーへと変質するエロチシズム、富の集中と世界の貧困化、それらの思想的バックボーンをなすネオ・リベラリズムなどを論ずる、現代フランス思想界屈指の「フィロゾーフ」のひとりです。著書に、『神なる市場』(2007年)『頽廃の都市』(2009年)『来たるべき個人…リベラリズムのあとに』(2011年)『西洋の錯乱』(2014年)等があります。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と最初の章をご覧いただけます。
2017年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『模倣と創造――哲学と文学のあいだで』
ニーチェの詩作における文体への強いこだわりと孤独を論じる井戸田総一郎論文、タルド/カイヨワ/デリダにおけるミメーシスの星座を論じる合田正人論文、森鷗外における古伝承の再生と近代的な表現への問いを論じる大石直記論文の重層的三章構成により、芸術と思想におけるオリジナリティの重視が自明である近代における模倣の意味を探究し、近代性の深層を照射する共同研究です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文40ページほどをご覧いただけます。
2017年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『オネイログラフィア 夢、精神分析家、芸術家』
精神分析を理論に閉じ込めるのではなく、生の実践とするための、ロシア人精神分析家・美術キュレーター、ソ連アンダーグラウンド芸術の証言者である著者による、夢と視覚芸術を通したフロイトとラカンへのユニークな手引き。全てがメディア的になりゆく今、自分の夢が個人性の最後の砦であるという思想が説かれます。
新宮一成氏推薦 《フロイトに還れ、フロイトの夢に。「狼男」の夢に、そして汝自身の夢に! 開けゴマ!で開いた部屋、その中に現実界の死せる文字があり、汝の生存が記されている。生き返りつつあるその文字に向かって震撼し、汝自身を孕め! この本にそう書き残したのは、精神分析の主体であった。》
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文50ページ分をご覧いただけます。
2017年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『反訓詁学 平安和歌史をもとめて』
見るべき平安和歌史「論」はこれまで存在していないという立場から、あるべき平安和歌史像をもとめた積年の労作です。平安和歌を構造的に関係づける視点として桜の花をめぐる「貫之のカノン」を発見し、貫之から俊成女まで、歌の内在的読解によって平安和歌史を構造的に呈示する初の試み。統一的な視点から描き出した平安和歌史の構造が、平安和歌史の真の主役は誰であるかを明るみに出すユニークな成果です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文20ページ分をご覧いただけます。
2016年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『頭山満思想集成 増補新版』
書肆心水既刊『頭山満言志録』『頭山満直話集』の合冊版として2011年12月に刊行したものの増補新版です。今回の増補で「写真集」(20ページ)を附録しました。伝説的存在として脚色されがちな頭山満の真の姿と思想を伝える良質な直話のみを精選した、頭山満入門の決定版。西郷隆盛の遺訓を講評しつつ自己の思想を語る「大西郷遺訓を読む」と、同時代の人物や社会を批評する回顧談の「直話集」で構成したものです。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文50ページ分ほどをご覧いただけます。
2016年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『他力の自由』
民芸思想家として知られる柳宗悦の根底にある他力の思想、浄土門=他力門関係の随筆集です。単行本『南無阿弥陀仏』『妙好人因幡の源左』以外の随筆文を集めました。自他二分の分別を離れ、任せ切り頼り切る自由、自己から解き放たれる宗教的な「他力の自由」が民芸の美と同一であり、それこそが真の民衆救済であることを示す、柳宗悦宗教思想の核心が説かれています。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページほかをご覧いただけます。
2016年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する』
ベルクソン哲学と現代知覚理論・時間論・心の哲学を接続する拡張ベルクソン主義宣言。時代にあまりに先駆けて世に出たがゆえに難解書とされてきた『物質と記憶』ですが、最近の「意識の科学」(認知神経学・認知心理学・人工知能学)と「分析形而上学」(心の哲学・時間論)の発展により、ベルクソンがそもそも意図した「実証的形而上学」の意味で『物質と記憶』を読み解く準備がようやく整ってきたことを示す画期的論集です。平井靖史・藤田尚志・安孫子信編、郡司ペギオ幸夫・河野哲也・B.デイントンほか著。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページほかをご覧いただけます。
2016年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『現代意訳 華厳経 新装版』
「一即一切/一切即一」を説く浩瀚な華厳経の要所要所を抽出して構成した、華厳経による華厳経入門。同著者による『現代意訳 大般涅槃経』の姉妹版です。東洋的存在論、仏教宇宙観の根源、哲理の認識と実践の一致、そしてブッダになるとはいかなることか――釈尊自覚の内容を明らかにする華厳経のエッセンスを示す一書です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページをご覧いただけます。
2016年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『現代意訳 大般涅槃経』
浩瀚な涅槃経の要所要所を抽出して構成した、大般涅槃経による大般涅槃経入門。同著者による『現代意訳 華厳経』(書肆心水好評既刊)の姉妹版です。多くの大乗経典が言わんとして言い能わなかった“一切生類悉皆成仏”の旨を明らかにして、すべての大乗経典に理論的根拠を与えた涅槃経のエッセンス。「涅槃とは何か」という問いへの答えとして涅槃の四つの性質「常楽我浄」を説き、無常無我から常楽我浄へと転位する仏教の深奥を示す一冊です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページをご覧いただけます。
2016年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『玄洋社社史』
頭山満ら玄洋社の思想と行動を、同時代の資料とともに記録したものです。征韓論論争、西南戦争から自由民権運動を経て日清日露戦争と韓国併合まで、言わば「裏から見た明治大正の日本政治史」です。近現代日本における政治対立の原型である民権論/国権論の由来と経緯を、西洋列強、そして特に中国・朝鮮との関係における玄洋社の歴史が証言します。新活字と現代表記で読みやすくした復刻版です。
こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページをご覧いただけます。
2016年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『終わりなき不安夢』
自伝『未来は長く続く』に始まったルイ・アルチュセールの20年以上にわたる遺稿編集出版の最後となる本書において、妻殺害事件の核心がついに明かされます。本書は、1941年から1967年にかけて書かれた夢の記録と夢をめぐる手紙や考察、事件後の1985年に書かれた主治医作を騙る手記「二人で行われた一つの殺人」を集成したものです。
国際的なアルチュセール研究者である訳者の市田良彦による、本書を読み解くための解説二篇「エレーヌとそのライバルたち」「アルチュセールにおける精神分析の理論と実践」と長編論考「夢を読む」を加えた日本語版オリジナル編集です。年表および死後出版著作リストも併録しました。イデオロギー論で名高いアルチュセールの、イデオロギー批判の契機としての夢、哲学者の「自己への関係」を明るみに出す注目作です。
こちらのリンク先のPDFファイルで30ページほどご覧いただけます。
2016年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『フロイトの矛盾』
精神分析は創始者のトラウマから誕生したのか? デリダの序文が付いた『狼男の言語標本』で知られるマリア・トロークらがフロイト理論の根本的批判により精神分析の再生を企図した著作です。
フロイトの行なう理論化には内的なさまざまの矛盾や断裂が生じており、本書が明るみにもたらすその矛盾は、フロイトの思考方法の核心から生じています。精神分析に内在するさまざまな可能性を実りあるものにしたいという思いから提起されたフロイトへの問い。贋金事件で有罪となったフロイトの叔父のトラウマがフロイトの精神分析理論に与えた根本的な影響を分析する研究です。読みやすいスタイルで書かれています。
こちらのリンク先で目次と序論をPDFファイルでご覧いただけます。
2016年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『維摩経入門釈義』
俗塵にまみれた在家の居士にもかかわらず、釈尊の高弟たちと菩薩たちをやりこめる維摩の啖呵で名高く人気の維摩経。その一文一文に沿って詳細丁寧に読む本格的な入門書です。何が小乗で何が大乗なのかが具体的な行為において示され、生と死、是と非、善と悪、美と醜、垢と浄、世間と出世間、我と無我、生死と涅槃、煩悩と菩提などなど、維摩経のテーマとされている「不二法門」について多面的に説き明かす長篇の講釈です。論点抽出・要約型の入門書からさらに進んで全文を味読してみたいかたにおすすめの一冊です。
こちらのリンク先で25ページまでの部分をPDFファイルでご覧いただけます。
2016年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『共にあることの哲学』
格差と分断の危機に瀕する現代世界を根本的に問う二巻構成の企画の第一巻です。「フランス現代思想が問う〈共同体の危険と希望〉」がシリーズのタイトルで、今回刊行の第一巻は「理論編」です。
世界をおおう経済的寡頭支配、老人と若者の世代間格差、保守化する左翼、揺らぐEU、文明の衝突論、難民問題と人権主義の限界……。21世紀の世界で人間が共にあることの意味と困難と可能性を、フランス現代思想ならではの根源的な視点から問い直します。
第一巻では、澤田直・岩野卓司・湯浅博雄・合田正人・増田一夫・坂本尚志・藤田尚志の執筆陣が、サルトル・バタイユ・レヴィナス・ブランショ・ナンシー・デリダ・フーコー・ドゥルーズをめぐって共同体を論じます。第二巻は「状況・実践編」です。二巻全体として「現代思想は終ったのか」という問いへの回答となることを目指しています。
こちらのリンク先で編者による序文と各論文の冒頭をこちらの PDF ファイルでご覧いただけます。
2016年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『統治と文明――イスラーム・仏教・現代の危機』
先月増補新版で『イスラームの構造』を刊行した黒田壽郎さんの最新作です。グローバル支配がもたらした、世界的に深刻な格差問題の解決のためには、「政治論」をこえた「文明論」が必要であるとする問題提起の書です。長年イスラームの社会制度の歴史を研究してきた立場から、イスラーム文明においては、時々の国家的な統治がいかなるものであっても、それに左右されない公共的で公正な社会を維持するために、「交換」「徴収と配分」「贈与」を適切にアレンジする仕組みがあったことが、具体例を示しつつ明らかにされます。
現代文明は、社会を「国家」と「個人」の二極に分断し、国家と個人のあいだに存在すべき「公共」というものをほとんど消滅させてしまいました。この「公共」の領域は「贈与」の生じるところで、人間の福祉にとって重要な機能を果たすものです。本書は、その機能を社会が回復するために伝統的思考法を再利用することが重要であると指摘します。
仏教文明においては、イスラーム文明のようにその思想が社会制度として具体化することは稀ですが、自己と他者の関係の認識方法に共通するものがあり、それが現在の公共性を喪失した文明に対するオルタナティブとしてもつ意味を本書は説いています。
日本のイスラーム研究を開拓した井筒俊彦は、イスラーム思想と仏教思想を貫く東洋思想の構造を哲学的に解明しました。本書は井筒俊彦のもっぱら哲学的であった東洋思想の構造論を文明論へと拡張し、公正で公共的な文明への転換のために、イスラームと仏教を通して、文明における「聖」と「俗」の関係を根本的に見直す視座を提供するものです。
2016年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『増補新版 イスラームの構造』
2004年に初版を刊行した黒田壽郎(としお)著『イスラームの構造――タウヒード・シャリーア・ウンマ』の増補新版です。初版刊行時には「タウヒード」「シャリーア」「ウンマ」という言葉を知る人はあまり多くありませんでしたが、それから10年以上が経ち、いまではニュースでそれらの言葉を見聞きすることも珍しくなくなりました。
本書はイスラーム文明の本質を、タウヒード、シャリーア、ウンマの三極構造として解説するものです。タウヒードとはイスラームの世界観、シャリーアとはイスラームの倫理と法、ウンマとはイスラームの共同体です。昨今イスラームへの関心が高まって、シャリーアとウンマはイスラームの基本用語として広く知れられるようになり、タウヒードについても多少は語られるようになってきたようです。しかしこのイスラーム文明理解の三つの柱は、これまでそれぞれ互いに関連づけられることなく、個別に分析されるだけという状況にとどまっていました。したがってイスラームの真に固有な点、その力強さが少しも理解されないままできた嫌いがありますが、本書はこれらの三つの極が発する力を組み合わせて考察することで、イスラームの構造と力を描き出しています。
一口にイスラームといっても実に多様であるのが現状です。欧米に暮らす世俗主義的なイスラーム教徒からターリバーンやイスラーム国まで、また、二大聖地を擁するスンナ派伝統主義のサウディアラビア、力を増す現代シーア派のイスラーム共和国イラン、そして東南アジアにあり最大のイスラーム教徒人口をもつインドネシアまで、違いに目を向ければさまざまな様相があります。その多様なるイスラームの最大公約数がタウヒード、シャリーア、ウンマの三極構造であるというのが本書の主張です。本書は、イスラーム教徒ではない人でもイスラームのリアリティを感じとることができるように、イスラームの理念が具体的な社会関係や制度にいかに現象しているかという点を特にとりあげて論じています。
預言者ムハンマド在世の時代を理想とするイスラームは、失われた理想を回復するというありかたを運命付けられていますが、本書はイスラームの理想と現実の関係を構造的に把握することによって、いま現在その勢いを増しているイスラーム回帰現象のほんとうの意味を、近代化の誤った側面(欧米中心主義)に対する反省の文脈において呈示します。本来のイスラーム社会の別名であるカリフ制は急進主義勢力だけの理想ではなく、広くイスラーム教徒に共有されている理想ですが、カリフ制が弱体化した時代と不在の時代に、その理念が社会生活でいかに生きられたかを本書は論じています。そのことによって本書は、イスラーム国問題に代表される現代の危機をこえてイスラームが向うべき道、そしてイスラーム世界と非イスラーム世界のあるべき関係を示唆し、あたらしい文明のありようを提唱しています。
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2016年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『教行信証入門講話集』
ロングセラー『歎異抄講話』の著者である型破りの高僧暁烏敏が、難解な教行信証を日常に即したゆるい話題で豊かに語る、百二講・千五百枚の大河講話集です。「学者達は、聖道門だとか、浄土門の綱格だとかいうことを論じておるが、私はそんな事を論ずるのでなく、一つ一つのお言葉を今日の日暮しの上に味わい、御教えを受けてゆこうと、こんなに思っているのであります」という考えのもとに、教行信証の「意(こころ)」が示されます。
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2015年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『安楽の門』(大活字愛蔵版)
東京裁判に関するあれこれでよく知られる大川周明の自伝的な宗教論です。書名の「安楽の門」とは宗教のことで、アジア主義者大川周明が、いかにして「大川周明」となり「大川周明」を生きたかがこの本に記されています。大川周明には、研究書を含め多くの著書がありますが、大川周明の人間性について知るための本としてはこの『安楽の門』が主著であり、本書の記述は欧化時代から敗戦までの日本精神史の縮図ともいうべきものになっています。目次は次のとおりです。
◎ 人間は獄中でも安楽に暮らせる
◎ 人間は精神病院でも安楽に暮らせる
◎ 私は何うして安楽に暮らして来たか
◎ 私は何うして大学の哲学科に入つたか
◎ 私は大学時代に何を勉強したか
◎ 押川方義先生と八代六郎大将
◎ 印度人追放と頭山満翁
◎ 東洋の道と南洲翁遺訓
◎ 人間を人間たらしめる三つの感情
◎ 克己・愛人・敬天
◎ 既成宗教と『宗教』
◎ 不可思議なる安楽の門
このたび書肆心水より刊行するこの復刻版は、元本の記述をそのままに保存し後代に継承することをむねとするとともに、大活字で組んだ愛蔵版仕様で製作しました。大活字愛蔵版とはいっても、現在ほかの版が販売されているわけではありません。別ページに体裁の写真を掲載してありますのでご覧下さい。※リンク
2015年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『柳宗悦宗教思想集成――「一」の探究』
本書は、民芸思想で広く知られ愛されている柳宗悦の、本格的宗教論三部作 1200 枚を一巻に集成したものです。理性の近代において、東西を貫いて、宗教的であることの意味は何か。後年、民芸思想として展開されるものの土台が、この体系的な宗教論三部作においてはっきりとあらわれています。他力教的な独自の民芸思想を生み出す土壌となった、キリスト教、仏教等、東西の宗教を貫く宗教性の核心を、柳宗悦は「一」という言葉で表現していますが、最晩年の宗教論(『仏教美学の提唱』書肆心水既刊に収録)において述べられる、民芸思想の核心としての「他力の美」というものがどこからやってきたのか、本書における「一」の探究がそのことを理解させてくれます。
2015年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『インド哲学史』
近代日本の仏教アカデミズムを開拓した宇井伯寿の復刻企画第六作を刊行いたします。仏教はいかなる思想風土において生まれ、いかに画期的な新思想として発展したか。本書はインドの哲学思想全体を「正統婆羅門」と「一般思想界」と「仏教」との三系統に分類し、各々の特質に注意しつつ対照的に論述されたものです。宇井伯寿には同じ書名の岩波書店版『印度哲学史』がありますが、岩波版は1932年に初版が刊行されて以後、1990年代に至るまでたびたび増刷されました。岩波版の四年後に刊行された本書は、大冊の岩波版を約半分に圧縮したうえで諸所に改訂が施されたものです。この改訂は岩波版刊行以後の四年間に研究が一段の進歩をとげた結果によるもので、本書は宇井伯寿インド哲学史研究の到達点と称すべきものになっています。
2015年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『清沢満之入門』
2002年から岩波書店で新しい全集の刊行がはじまり、近年その再評価が著しい近代日本仏教の鋭鋒清沢満之の思想と人生を、直弟子の型破りな高僧暁烏敏(あけがらす・はや)が日常の言葉でタブーなく平易に語る文章を集めたものです。また、暁烏敏の選出による清沢満之の評論文と、暁烏敏による「清沢満之先生小伝」「清沢満之年譜」も収めました。倫理道徳を超越する宗教の真髄、絶対他力の思想とはいかなるものか、本書によって明快にご理解いただけるかと存じます。
「清沢先生は、この力を絶対他力とか無限他力とか言われております。こういう言葉は、親鸞聖人のお書きになられたものには、見当らないことです。先生が初めて用いられた言葉です。しかし、全体的に見れば、皆親鸞聖人の御教えなんです。」(本書中の暁烏敏の言葉)
2016年8月
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『異貌の日本近代思想 1・2』
日本近代化問題の核心――近代主義か反近代主義かという二者択一の思考停止をこえる創造的近代。右翼/左翼、保守/進歩の図式ではつかめない日本近代化問題の核心。模倣的近代でも反動的保守でもない創造的近代の思想が現在の闇を照らす。
書肆心水では2004年秋の創業以来、右翼/左翼、保守/進歩の図式を超えたところで日本における近代化はいかにありうるかということについて考えた人々の著作を再評価する仕事に力を入れてきました。版を新たに組んで表記を現代化した覆刻版、新編集による論文集、テーマでまとめた本書のような共著書の刊行です。その皮切りとなった『北一輝思想集成』刊行の2005年8月からちょうど10年のこの機に、これまで刊行してきたものからいくつかを抜き出したのが本書です。各巻独立した書物としてお読みいただけますし、おのおのの文章はみな独立したものとしてお読みいただけます。
1巻
西田幾多郎(哲学) 新しいロジックの創造へ
三木清(哲学) 東亜協同体と近代的世界主義
岸田劉生(絵画) 近代の誘惑から東洋の「卑近美」へ
高村光太郎(芸術) 美と生命からみた近代性
野上豊一郎(能楽) 近代的概念では説明できない能の美学
山田孝雄(国語学) 西洋文法では説明できない日本語文法
九鬼周造(哲学) 近代的合理性をはみだす偶然性
田辺元(哲学) 東洋思想と西洋思想との実践的媒介
2巻
三枝博音(科学技術史) 日本的技術と日本的心性の関係
狩野亨吉(古典籍・書画鑑定) 安藤昌益における「自然」の思想
権藤成卿(古制度学) 近代国家主義の官治と伝統的自治
大川周明(政治思想) 敗戦日本再建の思想
北一輝(政治思想) 日本改造法案大綱
津田左右吉(歴史学) 歴史の学における「人」の回復
生田長江(文芸批評) 新事物崇拝という近代的迷信
内村鑑三(キリスト教) 近代人――自己を神と仰ぐ者
柳宗悦(民芸・宗教) 仏教美学の悲願、美醜対立の彼岸
富士川游(医学史) なぜ医学と倫理ではなく医術と宗教なのか
北里柴三郎(細菌学) 学問の独立と国家の関係
2015年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『中国回教史論叢』
中国回教史研究を開拓した近代中国人ムスリム二人による基本文献、金吉堂著『中国回教史研究』と傅統先著『中国回教史』を合冊集成したものです。中国へのイスラームの伝入、その繁栄と衰退を中国語史料によって具体的にあとづけ、知られざる中国イスラームの歴史を伝えます。目次は次の通りです。
金吉堂著 中国回教史研究 (外務省調査部訳)
上巻・中国回教史学
第1章 中国回教史上解決すべき諸問題
第2章 中国回教史上の認識すべき各問題
第3章 中国回教史の構造
下巻・中国回教史略
第1章 回民の中国史上に於ける留寓時代
第2章 回民の中国史上に於ける同化時代
第3章 回民の中国史上に於ける普遍時代
傅統先著 中国回教史 (伊東憲訳)
第1章 回教とマホメット
第2章 回教の中国伝入
第3章 宋代の回教
第4章 元代の回教の隆盛
第5章 明代の回教
第6章 清代の回教
第7章 中華民国の回教
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2015年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『禅者列伝』
近代仏教学を開拓した碩学宇井伯寿が、僧侶と武士、栄西から西郷隆盛までを平易に語る、逸話で親しむ異色の禅入門です。一話一話が読みきりの短文集になっています。禅者中の禅者から禅の影響が見落とされている武人と為政者まで、死と向き合うことで道を切り拓いた人間の姿を活写します。附録として、坐禅書の双璧『普勧坐禅儀』『坐禅用心記』によった「坐禅の仕方」(伊藤道海著)と、宇井伯寿の仏教信仰についての考え方が簡潔にまとめられた「仏教を信ずる所以」を収録しました。
目次は次のとおりです。
建仁栄西 聖一弁円 懐弉禅師 義雲禅師 通幻寂霊禅師 上泉伊勢守 塚原卜伝 柳生但馬 宮本武蔵 荻野独園 原坦山禅師 西有穆山禅師 滴水宜牧 森田悟由禅師 峩山昌禎 維新の三舟 勝海舟 高橋泥舟 山岡鉄舟 西郷南洲の禅 沢菴宗彭 鉄眼禅師 曹洞の学匠 上杉謙信 武田信玄 菊池武時 太田道灌 五山文学の禅僧 伊達政宗 徳川家光 徳川光圀 白楽天 蘇東坡 道元禅師 白隠禅師 北条時頼 北条時宗 一休禅師 桃水和尚 良寛 山内一豊 大石良雄 井伊直弼
2015年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『増補新版 北一輝思想集成』
本書は2005年書肆心水刊行の『北一輝思想集成』に『国体論及び純正社会主義』の北一輝自筆修正を増補し、判型を四六判からA5判に変更した新版です。本書には、北一輝の三大著作『国体論及び純正社会主義』『支那革命外史』『日本改造法案大綱』のうち『国体論及び純正社会主義』『日本改造法案大綱』の二作全文を中心に、自己と自作について語った「二・二六事件調書」および対外論策数篇、遺書・絶筆を収録してあります。
北一輝は社会主義者なのか、民主主義者なのか、ファシストなのか。分類不能なその思想が、近代日本が抱えたすべての根本問題を照らし出しています。日本近代思想史において特異な光を放ち続ける北一輝生涯の思想遍歴をこの一冊で一望することができる、北一輝のエッセンスを一冊に収めた決定版です。
2015年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『日清戦勝賠償異論――失われた興亜の実践理念』
本書は、東亜同文書院の前身である日清貿易研究所を経営した軍人荒尾精(1859年生、1896年歿)の批評文集です。日清戦争の賠償方針(償金額、領土割譲等)をめぐる政府と世論の意見に対する荒尾精の異論を収録しました。荒尾精は東アジア復興のためには東アジア諸国の安定的で自律的な関係を創出すべきであると考え、それを具体化するために日清貿易の振興を企図し、上海に日清貿易研究所を設立しました(1890年)。ついで日清貿易研究所の成果を継承した日清商品陳列所を設立して(1893年)貿易事業の実施を志しましたが、日清戦争開始(1894年)により中断のやむなきに至りました。
本書収録の諸篇は日清戦争中から戦後にかけて書かれたもので、全篇を通じ、勝ちに乗じて過大な賠償を求めることは、東アジアの安定に甚大な悪影響を及ぼし、結局は日本の国益も中朝両国の国益も損ねるものである、という判断が貫かれています。なされる問題提起はみな荒尾が中国において見聞し学んだ知見に基づいて具体的になされており説得力があります。荒尾の問題提起が世にいれられなかったことは、後世から見れば、近代日本が興亜主義の理念と実践を喪失して覇権主義へと転じていくことを意味しているとも言えるでしょう。
2015年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『グリーンファーザーの青春譜』
飢餓に苦しむインドで奇跡的な緑化事業をなしとげ、インドの人々から「グリーンファーザー」と讃えられた杉山龍丸の遺作です。作家夢野久作を父に、アジア主義者杉山茂丸を祖父に持った若き陸軍学校生龍丸は、政財界の舞台裏に通じた茂丸の関係者から話を聞くうちに開戦しても勝ち目がないと覚り、対米開戦の反対運動を展開、東条暗殺までも企てました。
本書は大戦末期のフィリピンで飛行第31戦隊の整備隊長を務めた若き著者がその整備日誌に基づいて、技術職からみた戦争の真実、そして日本軍の技術・現場・戦略軽視がもたらす現実を語りのこしたものです。敗戦必至という認識において、人はいかに戦いうるのか。戦後70年のいま、杉山龍丸の遺稿を公刊し、戦争の不条理をあらためて世に示します。
推薦のお言葉を俳優の田中健氏と政治学者の施光恒氏(九州大学准教授)からいただいています。
田中健氏
かつて私は「インドのグリーンファーザー」と呼ばれた著者が緑化した広大な地域をテレビ取材し、困難に立ち向かった姿とその成果に圧倒された。この遺稿には青春時代のフィリピンでの戦争経験と未来へのメッセージが凝縮されている。是非とも読んでいただきたい。
施光恒氏
戦前の政財界に大きな影響力をもった杉山茂丸を祖父に、作家夢野久作を父にもつ著者は陸軍整備将校として戦地の記録を克明に残していた。官僚化した上層部の非合理性、若き兵士たちの熱き思い――。我が国の将来を考えるうえで必読の文献である。
2015年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『カリフ制再興――未完のプロジェクト、その歴史・理念・未来』
内田樹さんとの対談『一神教と国家』(去年2月刊)でイスラーム学者としての存在を広く知られるようになった中田考さんの最新作です。『一神教と国家』は集英社新書で既に5刷ということですので、そこで「カリフ制再興」のことを知られたかたはかなりの数にのぼると思われます。「カリフ制再興」は、著者が早くから提唱してきたものですが、「カリフ制」という言葉が世界中に広く知られるようになったのは、去年の6月29日に「イラクとシャームのイスラーム国」がカリフ制の再興を宣言したことに伴って「イスラーム国」と改称した事件以来のことです。
カリフ制はどのようなものとしてかつて存在し、なぜ失われ、どのような事情でその再興が求められてきたのか。カリフ制とイスラーム国というありかたの関係はどうなっているのか。今後の世界情勢にとってカリフ制再興はどんな意味をもつのか、本書はそうした問いにこたえるものです。
「そのへんも知りたいとは思うが、なにしろ著者はあの蛮行集団の支持者なのではないか」と、ご関心と共に疑問をお持ちのかたの場合は本書を通読されてご判断いただくのがよいと思いますが、さしあたり「あとがき」をお読みいただくとある程度のことをお察しいただけるかと思います。(目次とあとがきPDF)
現在の中東戦乱には待ったなしの救命策が必要です。と同時に、この状況は長年月の重層的な歴史の結果でもあり、過去を省みない「現実的」なオペレーションだけでは弥縫策の譏りを免れません。文明の衝突と見る向きもあるグローバル戦争、そして中東ローカルの部族戦争をこえて、統一的な法秩序によるイスラームの平和をめざす理念が「カリフ制再興」であることを本書は示しています。これは最も有力な理念ではありますが、それを具体化できるかどうかはイスラームする人々次第です。ただ、彼らに対する我々の態度がそこに及ぼす影響も少なくないというところに本書刊行の意義があります。
今この著者のほかに日本で「カリフ制再興」の問題を詳細かつ主体的に論じることができる人はいません。今後の世界を見通すために是非とも知っておくべき主張であると考えてこの機に刊行いたしました。お手にしていただければ幸いです。
2015年1月
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『百魔』 『百魔 続』
其日庵と号した杉山茂丸の主著です。2006年に書肆心水より『百魔 正続完本』として刊行したものを新版として分冊化いたしました。『百魔 正続完本』は8500円で刊行しましたが、このたびは第一分冊を4900円、第二分冊を6300円で刊行いたします。元々の本が『百魔』『百魔続篇』として別々に刊行されたものですので、それぞれ独立したものとして読むことができます。そもそも各篇に収められた各章が独立した話になっている本です。
第二分冊が特に高くなっていることを申し訳なく思いますが、今回の新版を分冊にしたのは、「正篇」のほうだけをお求めいただくことができるようにと考えてのことでした。そのため「正篇」と「続篇」の価格に差をつけて「正篇」のほうを比較的安くしました。それでも共に高いのですが、昨今、価格が高めの本は、新刊時でも店頭陳列用に仕入れて下さる書店さんがごくわずかになってしまい、(詳しい事情説明は省きますが)価格をかなり高く設定せざるをえなくなっています。
主要都市でないところにお住まいのかたには手にとって購入のご判断をいただくことができませんので、冒頭の何話かをご覧いただけるようにPDFファイルをご用意しました。また、amazon.co.jpには豊富に仕入れていただいていますので、そちらでは当面品切なくお求めいただけることと思います(色々問題もある存在なのであまりお勧めしたくはないのですが)。
「立ち読み」 PDF 『百魔』
「立ち読み」 PDF 『百魔 続』
2014年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『他者のトポロジー』
「人文諸学と他者論の現在」を副題とする共同研究の論文集です。編者はバタイユ研究者の岩野卓司氏で、内容目次は次のとおりです。
岩野卓司………裸にすることは可能なのだろうか?――フロイトにおける「裸」、「記憶」、「転移」
若森栄樹………ラカンの「論理的時間」読解――共同体における間主観的「真理」について
関 修………性的差異という罠――セクシュアリティから見た他者
石前禎幸………イギリスのヤヌス
田島正行………「自然との和解」という欺瞞――『アンティゴネー』についてのヘーゲルの解釈をめぐって
大西雅一郎………様々なる改宗あるいは転回、おそらくは深淵の上での
鈴木哲也………亡霊論あるいは歴史への参入――マイケル・ロングリーの『雪の記念碑』をめぐって
斉藤毅………石原吉郎の詩における他者のトポロジー
山田哲平………トポスなきナショナリズムから他者としての身体へ――貫之論
編者の序文より、各執筆者の論述内容を紹介した部分を以下に引用いたします。
「他者のトポロジー」の名のもとでわれわれが研究する分野は、各人それぞれの関心に応じて多岐にわたっている。哲学、精神分析、法律、政治、文学、美術の分野に縦横にクロスオーヴァーしている。最初のセクションでは、岩野卓司はフロイトの無意識を、若森栄樹はラカンの無意識と共同体の真理の関係を、関修はクイア理論で有名なティム・ディーンの性的差異を扱っている。どの研究も精神分析の言説を対象にしながら無意識にかかわる他者のトポスを探求しているが、三人の関心は同時に哲学にもかかわっている。
次のセクションでは、石前禎幸はイギリスの法における女性の抑圧のテーマを扱い、田島正行はヘーゲルによる古代ギリシャのアンティゴネーの解釈における「自然との和解」を研究し、大西雅一郎の選んだテーマは、宗教の改宗をめぐるアイデンティティとそれに収まらないものである。三人の研究は、哲学をベースにしながら、政治、歴史、文学、宗教ともかかわりながらそれぞれ「抑圧」、「和解」、「改宗」が孕まざるをえない他者性の在りかを探っている。
三番目のセクションでは、鈴木哲也はアイルランドの詩人マイケル・ロングリーの記憶の問題を「死者との対話」を通して追求し、斉藤毅はソ連で抑留された経験を持つ石原吉郎の詩の空間におけるトポスの問題を掘り下げて考察し、山田哲平は紀貫之の和歌における大陸にも日本にも属さない場を論じている。彼らの対象は文学、特に詩であるが、そこでは他者のトポスが言語を通して哲学、政治、無意識らの問題系と複雑に絡み合っている。
2014年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『仏教思潮論』
碩学宇井伯寿の浩瀚な主著『仏教汎論』二巻本を要約した入門篇です。仏教思想は、根本仏教から大乗・小乗への分化を経て日本仏教諸宗まで、一見互に矛盾し、調和することもほとんど不可能かと思われるほど広汎にわたるものですが、本書は、多岐に及ぶその学説の流れを仏・法・僧の構造から説き、仏教の一大特色である「随機説法、応病与薬」の神髄を示します。
仏教は「八万四千の法門」と称されますが、そもそもなぜそのように複雑なことになったのか。宇井伯寿が本書で説くところを下記に引用します。(仏教では、仏教で説くから真理であり、仏教以外で説くから真理でないというようには考えず、いやしくも真理であるならばそれはすべて仏教であると考えます。この考え方も下記引用に述べられるような事情と関係しているのでしょう。)
《かくの如く広汎で複雑なものがそもそもどうして起るに至ったかといえば、これは一方においては仏教が長い発達上の歴史を有するからでもあろうが、他方においては、根本的に仏教の趣意が随機説法、応病与薬というに存するからである。即ち仏教は所化の衆生の機根の相異なるに随い、その病患の不同に応じて、教法を説いて導き、看病して薬を与えるから、機根素質の相異、病患症状の不同なだけの教薬が存する道理であり、立場も種々なるものが採用せられることになったが為に、複雑なものになったに外ならぬのである。説法教化、又は嬌正善導を目的となすという点においては、仏教は広義の教育たるものであると見られ得るが、学校教育などとは異なって、一種の社会教育、公衆教育であるから、学校の如き教育機関、教育制度などを持って居ない。従って、一般人を教育するのに仏教の内に、それぞれの部門、一般人の素質の差異に応ずる適当な諸説を整えて居らねばならぬ。少なくとも、児童に対し、青年に対し、成人に対して、各々異なる説き方の思想学説を有して居て、それを適宜に活用することにせざるを得ないことは当然である。しかも同一成人級に対しても、既に所化の成人級に素質機類、教養程度の不同がある為に、同一の思想学説をも無差別に説いたのでは、その効果は十分ではない。従って、学校教育のほとんど凡てを含む材料、資料、学説に相当するものが必要となるのであるし、これによって、仏教の思想学説の多岐複雑であることが理解せられるであろう。更に考えると、初等の教育から最高の教育に至る凡てを包有するとすれば、初等の教育の場合には、これから見れば、最高の教育は必要なものでなく、又最高の教育から見れば、初等の教育は、もはや用をなさないものであるが、しかし、それは一人の被教育者の立場からのみ言えることであって、教育者の方からいえば、初等のも高等のも、また最高のも、各々それ自身の価値を有し、効力を発揮し得るもので、決して初等の教育は必要でないということにはならない。例えば、児童に親しい童話の如き、動植物が人類と同じ活動をなす世界は、成人からいえば、事実に反したもので架空無稽な不用なものであろうが、児童にとっては決してそうではないから、児童から見れば必要であり、価値もある。のみならず成人から見ても、童話の世界などには情操豊かなものがあって、捨つべからざるものを含んで居るから、如何なる成人といえども、真面目に、これを捨つべきものであるなどと考えては居ないであろう。仏教における種々なる部門の雑多な学説もまたかくの如く見るべきもので、初門としての卑近、浅略な説でも、それを要求するものには、適切なものであり、又価値のあるものであって、高尚深遠な教理のみが採用せらるべきものとなるのではない。故に、卑近な説でも、高尚な説でも、その中間のものでも、凡て仏教の中に保存せられて居るのであって、これによって複雑性を構成して居るのである。》
こちらのリンク先では詳細目次ほか、本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『語る西田哲学』
一般聴衆にむけて語られた講演を中心に、西田幾多郎の「語り」の記録を集めた談話・対談・講演集です。西田最初の著作である『善の研究』から最晩年の長篇論文「生命」「場所的論理と宗教的世界観」にいたるまで、理論的な変遷と発展を経てきた西田哲学が、一貫してこだわっていたものは何なのか。「語り」がそれを明らかに示しています。収録内容な次のとおりです。
I
鎌倉雑談〔1〕
鎌倉雑談〔2〕
人格について
時と人格
Coincidentia oppositorumと愛
宗教の立場
伝統主義に就いて
ベルグソン、シェストフ、その他 ――雨日雑談
東洋と西洋の文化の相異
西田幾多郎博士との一問一答(対談・三木清)
ヒューマニズムの現代的意義(対談・三木清)
人生及び人生哲学(対談・三木清)
II
純粋経験相互の関係及び連絡に付いて
私の判断的一般者というもの
生と実在と論理
私の哲学の立場と方法
実在の根柢としての人格概念
行為の世界
現実の世界の論理的構造〔1〕
現実の世界の論理的構造〔2〕
歴史的身体
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『文語訳 ツァラトゥストラかく語りき』 (新装復刊)
『ツァラトゥストラ』をはじめて日本語に翻訳し、その後、日本初のニーチェ全集を個人完訳で果たした生田長江は、ニーチェ諸著作のうち『ツァラトゥストラ』だけは文語調の訳文が相応しいと考えました。
中公版『ツァラトゥストラ』の訳者手塚富雄は生田長江についてこのような言葉をのこしています。――「生田長江は実存的に最も深くニーチェに親しんだのではないかと思う。ニーチェについては論述より翻訳に力を注いだようで、それは特異な張りのある文体だった。長江は、どう控え目に見てもニーチェのいわゆる高人に列する人である。」
2008年の初版刊行時も今回の新装版と同じ価格(5500円+税)でしたが、意外と好評で一年ほどで完売し、しばらく品切が続きました。このたび新装版として復刊いたします。なお、書肆心水よりの直接販売に限り、カバージャケットと帯は初版のものと今回のものとのどちらかをお選びいただけます。詳細は本のページをご覧下さい。
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『西欧化する日本 西欧化できない日本』
前近代と近代の文献を博捜し、『日本哲学思想全書』20巻『日本科学古典全書』10巻を編纂した思想史家の三枝博音が、その研究成果を縦横に活用し、日本における知性と技術と科学の関係の歴史性を描き出します。日本の知性の「古層」と西欧化以後の「新層」の関係はどうなっているのか。近代化の過程で覆いをかけられた古いものが蘇ろうとする今、将来を展望するために歴史的経緯を省みるための一冊です。
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『立憲主義の日本的困難』
まるで藩閥独裁政治が回帰したかのような状況となったいま、近代日本の立憲主義運動をリードした尾崎行雄の批評文集を刊行いたします。尾崎行雄(1858-1954)は1890年の衆議院第1回総選挙以来、連続25回の当選を果たし、「憲政の神様」と呼ばれた政治家として広く知られています。63年にわたる代議士生活のあいだに東京市長、文相、法相を歴任し、藩閥・軍閥・官閥との闘いに生涯を捧げた潔癖孤高の政治家であり、日本政治史上特異の存在と呼ぶべき人物です。
常に立憲主義の先頭に立って闘った尾崎の批評文を読むと、反立憲主義的で日本的な「党派の論理」の歴史性が見えてきます。勝てば官軍、長い物には巻かれろ、義よりも縁故と派閥。こうした古くて根深い日本の反立憲主義的心性はどこからきたか。明治維新から敗戦までの国政の経験を語る尾崎の言葉がそれをはっきりと示しています。反立憲主義への対抗も、そうした歴史認識に基づくものでなければ力ないものとなり、いつまでも同じことが続いてゆくでしょう。
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『近代日本哲学史』
日本の科学・技術思想史研究を開拓した三枝博音が、日本への哲学の移植とその展開を批判的に評価する著作です。1971年(明治4年)、中村正直(敬宇)によってJ・S・ミルの『自由の原理』が翻訳されたところから説き起こし、本書発刊の1935年頃までの状況の推移を論じています。
発刊時は戸弘柯三の変名で発表されましたので、三枝の著作としてあまり広くは知られていないものだと思われます。「日本に移入された各種哲学は、その繁栄にも凋落にも何らかの条件が存する。どの学問よりも真実なるものをつかもうとする哲学は、まず自分の運命を知らねばならない」と語る三枝が、時代と哲学移植との関係を探り、そのイデオロギー的位置を発見する仕事です。
このリンク先に書誌・目次等を掲載してあります。
こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『東洋の論理 空と因明』
本書『東洋の論理 空と因明』は、中村元が師事した近代日本仏教学の開拓者、碩学宇井伯寿による仏教論理学の基本文献です。『仏教哲学の根本問題』、『仏教経典史』に続く、当社の宇井伯寿復刊企画の第三弾です。「空」に関する研究書は豊富にありますが、「因明」を本格的に説くものは今なお本書くらいしかありません。第一部は宇井伯寿が「空」と「因明」を説くパートで、第二部には「空」と「因明」に関する原典の翻訳、竜樹(ナーガールジュナ)『中論』、陳那(ディグナーガ)『因明正理門論』、商羯羅塞縛弥(シャンカラスヴァーミン)『因明入正理論』の三篇を収録しています。
このリンク先で詳細目次と本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『新編・梅園哲学入門』
日本の科学・技術思想史研究を開拓した三枝博音による三浦梅園論集です。梅園研究の第一人者・山田慶兒氏は、中公バックス版『三浦梅園』所収の長大な論考「黒い言葉の空間」のなかで、「三枝は梅園のなかに、近代ヨーロッパの哲学者たちにいささかの遜色もない哲学的精神と哲学的思索の横溢をみた。」と述べておられます。本書は、三枝が近代西欧哲学との同時代性において梅園を考察した著作を集成したものです。
山田慶兒氏は三枝の著作についてさらに次のように述べておられます。
「かれにとって梅園〔1723-1789〕を研究することは、梅園がそうであったように、みずからの頭で考えぬくことであった。かれはカント(1724-1804)とヘーゲル(1770-1831)を介して梅園を考え、梅園を介してカントとヘーゲルを考え、この奇しくも時代の重なり合う三人の哲学者を介してみずからの哲学をきたえあげていったのである。これこそまさに梅園の哲学的精神を受け継ぐ態度であったということができよう。すくなくとも三枝の自覚においてはそうであった、とわたしは考える。三枝の梅園研究はその意味で今後も、わたしたちに大きな刺激を与えつづけてゆくだろう。」
山田慶兒氏ご指摘の点に加え、三枝が梅園の哲学に見た重要なポイントは、「科学の明るさと人間的歴史の暗さを統一的に把握する」点にありました。梅園の言葉で言えば、「理といえども、もと故(こ)の対立物(故之偶)である。理の照すは故の暗さを得てはじめて照すのである。暗いものは明を待ってはじめて暗さを獲得するのである。だから、理は冥々の地盤を得てはじめて理なのである」ということです。
(註 「理」に対する「故」は、跡という意味をもっており、時間による現象です。理そのものは跡をのこしませんが、生起するものは必ず跡をのこすのであり、故とは実際に生起する事件を意味します。事件は理そのものでなく、又抽象的な存在ではありません。必ず実質的なものですので、物質の問題はこれにつながります。梅園は、「理論をいいながら、未だ条理の故なるものが把握されていない場合が多い。その上、理論とか反理論ということに拘わり、理論の一辺に跼蹐していては、遂に死せる理論を以て活ける実質的なものに、抗弁することになる」、と言っています。)
近代化の早い時期から既に科学一辺倒の方向に問題のあることは少なからぬ人々に気づかれてはいましたが、それに対してただ反動的な態度をとるのではなく、科学の価値をさらに高めつつもいかにして次の次元を開いていくかという方向性は、今なおそれほど明確になっていません。三枝博音(1892-1963)は日本社会に科学的精神を根付かせるべき歴史段階にあった人ですが、その歴史段階においてすでに、「梅園の学説はもはや単なる科学主義ではない。彼にとっては科学と歴史的現実の交錯的形成そのものが問題である」という認識をもっていました。
現在のわれわれにとって、古いどころか、今こそ省みるべき思想がそこにあると思います。
このリンク先で詳細目次と本書のなかをいくらかご覧いただけます。
2014年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『現代アメリカ映画研究入門』
現代の映画研究をリードする二人、トマス・エルセサーとウォーレン・バックランドによる映画分析の新定番です。(原書Studying Contemporary American Film: A Guide To Movie Analysis)。
代表的な映画理論を網羅的に紹介し、一本の映画に複数の理論からアプローチすることで、理論が異なれば映画の意味も変わることを体感できるように書かれています。難解だと敬遠されがちな映画理論がぐっと身近になり、大量の映画を観ていなくても理論をツールとして使えるようになるガイドブックです。
取り上げられる映画と分析のテーマの対応関係は次の目次のようになっています。
1. 映画理論、方法、分析
2. クラシックな物語/ポスト‐クラシックな物語……ダイ・ハード
3. ミザンセン批評と統計的様式分析……イングリッシュ・ペイシェント
4. テーマ批評から脱構築分析へ……チャイナタウン
5. 『S/Z』、「読みうる」映画とビデオゲームの論理……フィフス・エレメント
6. 物語叙述(ナレーション)についての認知主義理論……ロスト・ハイウェイ
7. 写真画像とデジタル画像におけるリアリズム……ジュラシック・パークとロスト・ワールド
8. オイディプス物語とポスト‐オイディプス……バック・トゥ・ザ・フューチャー
9. フェミニズム、フーコー、ドゥルーズ……羊たちの沈黙
このリンク先で詳細目次と本書冒頭部分をご覧いただけます。
2014年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『天皇制の国民主権とノモス主権論――政治の究極は力か理念か』
法哲学者尾高朝雄による本書の主張と意義はおよそ下記の三点にあります。
1) 憲法制定時の国体論議を検証し、象徴天皇制においても国民主権が十全に機能することを示します。また、国民が望めば国民主権と並存する象徴天皇制の継続にも積極的意味があることを示します。
2) 憲法制定権力である国民の主権(国民の総意)が万能の力であることに疑問を呈します。国民主権のワイマール憲法体制は結局数の力でナチ政権の確立へと至りました。現在の日本でも国民の総意に基づく政権が強引な政治を行っています。主権が無制限の力であるならば、そのなりゆきを否定することができません。
3) 主権の所在論(国民にあるのか王にあるのか)を超えて、従来の主権概念の上位に「ノモスの理念」を組み込む事でこのアポリアに道を開き、主権概念を刷新します。
本書の底本は尾高雄著(1954年青林書院刊)『国民主権と天皇制』です(古書での入手は困難です)。初版の刊行は1947年ですが、初版刊行の後に本書の「ノモス主権論」などをめぐって尾高朝雄(東京大学教授・法哲学)と宮沢俊義(東京大学教授・憲法学)の間で論文による論争が起きました(その経緯は本書第7章第1節に記されています*1)。本書の底本は、その「親しい同僚同士の論争*2」を踏まえて第6章と第7章が加えられた増補版です。論争の中心となった「ノモス主権論」は法学の議論として大きな射程を持つもので、国民主権と天皇制の関係論にとどまるものではありません。
本書の論点を分析的に言うならば、「国民主権と天皇制の関係論」と、その議論に応用された「ノモス主権論」の二つからなっています。著者は国民主権と天皇制の関係を考察するために本書を著したのですが、法哲学者としての議論の重点はむしろ「ノモス主権論」にあったといえるでしょう。この法哲学上の大問題の帰趨に比べれば天皇制に関する問題は二次的なものにすぎないという考えを著者は示しています*3。
そこで、本書の特徴をよりよく示すために、今回刊行のこの新版においては書名を「天皇制の国民主権とノモス主権論」とし、また著者の立場の特徴を示すものとして「政治の究極は力か理念か」という副題を加えました。
尾高朝雄は論争相手の宮沢俊義にくらべ、現在一般にはほとんど無名です。その理由としては、1956年5月にペニシリン・ショックのため急逝したこと(尾高は1899年生)など、さまざまな事情が考えられるでしょうが、憲法学界にとってはその理由は明白で、尾高・宮沢論争の結果が宮沢の勝利とされて、その後、尾高の「ノモス主権論」は折にふれて振り返られることはあっても、積極的に検討されることがほとんどなくなったからであるといわれています*4。宮沢が憲法学界に大きな影響力を持ち、その学問の継承者である芦部信喜らもまた憲法学界に大きな影響力を持ったことも無関係ではないでしょう。
本書は50年以上も前の出版物ですが、国民主権と天皇制の関係を法学的に論じたものとしては、両者の関係を積極的に合理化するという点でユニークなものです。またノモス主権論についても、法哲学の議論としては、果たして尾高・宮沢論争をもって解決済というべきかどうか再検討する価値があるでしょう。
また、底本の刊行された時代と現在では国民主権と天皇制の関係を論じる条件が異なってきています。現行憲法制定時には、そもそも国民主権と天皇制が両立するものであるかどうかが問題となりましたが、憲法施行から65年以上を経た現在、「国体」というテーマをめぐって議論されることは全くなくなり、国民主権と象徴天皇制の並存は歴史的に定着したというに十分な時間が経過しています。そして国民主権も天皇制も廃される現実的な見通しは当面ないといってよいでしょう。天皇制廃止の意見をもつ最もまとまった集団である日本共産党においても、「天皇制を『容認』したとする報道が一部にみられますが、それは事実に反します」としつつ、「日本国憲法は国民主権を明記し、国民代表たる国会を通じた変革を可能とする政治制度を定めています。あらゆる進歩を阻んだ戦前の絶対主義的天皇制とは違って、天皇の制度が残ったいまの憲法のもとでも、日本共産党がめざす民主的改革は可能です。」としています*5。すでに相当な年月のあいだ現に存在し、なお今後も社会に大きな変化が生じないかぎりは継続して存在すると推測するに十分な理由がある国民主権と天皇制の並存は、どのように説明しうる事態なのでしょうか。本書はその点においてユニークな議論を展開する稀有な存在意義をもっています。この意義は、本書が刊行当時にもっていたそれとはまた違ったものであるといえるでしょう。
2014年 書肆心水
註
*1 本書246-254ページ。
*2 本書254ページ。
*3 例えば本書225ページ。「この種の考え方を克服しようとする私の『法哲学的』な理論が、実力としての主権の否定に到達することは、やむを得ない。この大問題の帰趨にくらべれば、『天皇制のアポロギヤ』のごときは第二次的な問題にすぎない。」
*4 時本義昭著「ノモス主権と理性主権」の「はじめに」。『龍谷紀要』第29巻(2008)第2号(CiNii 論文PDFオープンアクセス)。なお、この論文の冒頭に掲げられた「要旨」には次のようにある。「尾高朝雄のノモス主権論においては、抽象的な理念であるノモスに主権が帰属させられる。また、純理派は、革命期において、主権の帰属主体が『個別的で具体的』であったことが議会による無制限な支配や多数派による圧制をもたらしたとして、抽象的な存在である理性に主権を帰属させることを主張した。いずれにおいても、主権の帰属主体が抽象化されることによって主権の帰属主体自らによる主権の行使は不可能となり、その結果として主権の帰属と現実における主権の行使とが分離され、主権の行使は内在的に制限される。ところで、カレ・ド・マルベールの国民主権論における国民も抽象的な存在であることから、ノモス主権=理性主権=国民主権となる。さらに、宮沢俊義の国民主権論も、『誰でも』によって構成される国民が抽象的な存在であることから、この等式における国民主権に含まれる。その結果、意外にも、主権の帰属主体に関する限り、宮沢・尾高論争における理論的な対立要素はなくなるのである。」
*5 2004年2月4日『しんぶん赤旗』「天皇制を『容認』したか?」(https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-04/0204faq.html)
2014年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『仏教経典史』
先月の『仏教哲学の根本問題』と同じ著者、碩学宇井伯寿による著作です。本書は、仏徒でもある近代日本仏教アカデミズムの開拓者が、脱迷信の近代的批判にたえる明晰な叙述と、信仰と学的研究を峻別した立場で、仏教史理解の第一歩である各経典成立の歴史を体系的に描く基本文献です。個々の経典についてある程度の知識を得たが、経典それぞれがどういう関係になっているのかが分からないという方におすすめしたい入門書です。各経典を歴史的に位置づけることによって、各経典の意義が明らかにされています。
第一章 小乗経典
第一節 経典成立の事情と経過
第一 経という語の意味
第二 翻訳の意義
第二節 釈尊の用いた言語
第三節 律の成立
第四節 結 語
第二章 大乗経典
第一節 大乗の発達
第二節 大乗経典の区分
第三節 第一期の経典の大要
第一 般若系統
第二 法華系統
第三 華厳系統
第四 浄土、密教系統
第四節 第二期の経典の大要
第一 涅槃系統
第二 勝鬘系統
第三 深密系統
第五節 第三期の経典の大要
第一 楞伽系統
第二 密教系統
第六節 大乗戒の経典
第七節 結 語
第八節 余 論
第三章 一 切 経
第一節 シナヘの伝訳
第二節 一切経、大蔵経
第三節 大蔵経の刊行
第四節 我が国に於ける一切経
第五節 結 語
一度読んで終りという種類の本ではありませんので、再読、三読する際のお役に立つようにと、下段に本文の記述の要点を見出しとして抽出し、下段の見出しだけでも論の流れを見て取れるようにしました。本のなかをご覧いただけるPDFファイルをご用意してありますので、体裁をご覧下さい。(ここのリンクで別ページへ)
また、本文は大活字11ポイントで組みましたので、視力の弱ってきたかたにも楽にお読みいただけるかと思います。本書と同じ体裁の先月刊『仏教哲学の根本問題』(宇井伯寿著)と文庫本と比較した写真を別ページにご用意しました。(ここのリンクで別ページへ)
2014年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『仏教哲学の根本問題』
碩学宇井伯寿による濃密な仏教理論入門です。仏教に関心のあるかたなら中村元のことはご存知と思いますが、宇井伯寿は中村元を東京帝大で指導した近代日本仏教アカデミズムの開拓者で、仏徒でもあります。中村元は東大において宇井伯寿の後継者となりました。
本書は、脱迷信の近代的批判にたえる明晰な叙述により、仏教の根本キータームを有機的に解説するもので、仏教の 「全体を貫く基本的な考え方=哲学」 のハンドブックとして優れた著作です。仏教のさまざまなキータームについて大体の理解はできたが、それらがどう関係しているのかもうひとつ全体的な理解に至らない、という方に最適の、言わば第二段階の入門書です。目次は次のとおりです。
第一 因果の理
第二 事 と 理
第三 理 と 智
第四 信と宗教心
第五 無我と空
第六 善 と 悪
第七 生死と涅槃
第八 仏教の特色
一度読んで終りという種類の本ではありませんので、再読、三読する際のお役に立つようにと、下段に本文の記述の要点を見出しとして抽出し、下段の見出しだけでも論の流れを見て取れるようにしました。本のなかをご覧いただけるPDFファイルをご用意してありますので、体裁をご覧下さい。(ここのリンクで別ページへ)
また、本文は大活字11ポイントで組みましたので、視力の弱ってきたかたにも楽にお読みいただけるかと思います。文庫本と比較した写真を別ページにご用意しました。(ここのリンクで別ページへ)
2014年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『華厳哲学小論攷』
先月に引き続き、中公新書 『忘れられた哲学者』(2013年6月刊、清水真木著)で再発見された土田杏村の著作です。土田杏村(1891-1934)は土田麦僊の弟で、京大で西田幾多郎に哲学を学びました。大学院在学中に雑誌 『文化』 を創刊し、社会、教育、文学、芸術など多方面にわたる評論活動を開始して、以後定職に就くことなく世を去るまで著作活動を継続した人物です。その短い生涯のあいだに公刊した著作は60点以上にのぼります。哲学の枠内にとどまることなく、文化全般にわたる多様な領域において健筆を揮いました。(著作リストを本の詳細紹介ページのほうに記してあります。)
本書は、「事理無礙」からさらに「事々無礙」の段階へと仏教を高めた華厳思想の哲学的可能性を求めて、大乗起信論が示唆する仏教の根本問題に、阿頼耶識の意義を鍵として挑んだ小さな著作です。形而上学批判としての認識論的仏教研究と位置づけることができるでしょう。古い著作ですが、現在読んでも根本的な問題提起として生きている仕事であると考えて刊行しました。
著者は、「仏教には認識論的批判が乏しい。そして一切否定の消極神学に陥り易い。有即無などいっても、有即無である境地の認識論的研究がなければ、仏教は近代人の要求を満たすものとはなり得ない。」という立場から、阿梨耶識の認識論的考察を試みています。
また、仏教哲学上の真の問題と土田が見るものについて、次のように述べています。
「以上の如くにして私は、有=無、色=空、随縁=如常の同一性の立場を明瞭に解釈する事が、仏教哲学上最も重要の問題となっていると考えるのである。しかしこれひとり仏教哲学上の難問ではない。西洋の現代哲学もまた等しくこの難問に接しているのである。しかし私が仏教哲学に就いて特にこのことを言うのは一体何故であるか。と言うにそれは、仏教哲学の進路に大いなる障害となっている消極神学〔negative Theology〕を征服せんがために外ならない。或いは静的なる仏教教理を生かして動的たらしめんがために外ならない。仏教教理の上には、従来ただ体験にのみ依頼して論理の解明を欠いていた問題は幾つもあった。しかもそれらの問題の中の重要なる一つは、この同一性の立場を解明することであると私は思う。仏教教理を目して単に否定道を採った消極神学であると見るならば、それは最早我々に何等の暗示をも与え得ざる沈腐の哲学である。我々はその如き消極神学の哲学には意義を認めていない。しかし仏教教理の中の大乗は決してこの否定道にのみ満足しているものではない。彼等は化城の迷いを離れて、再び現実の世界に降って来た。即ち単に涅槃に堕する消極神学者ではなかったのである。しかしそれは何処までも体験の論理の上に於てであって、知識の論理の上に於てではなかった。我々は現実の浮相を漸次に否定して行って、終に渾々淪々の真如に到達した。これはスピノザが世界実体としての神に到達したと同一のものである。スピノザの実体は入ることは出来ても出ることの出来ない穴にたとえられた。仏教の否定道に就いても又同様の非難が持ち上って来る。これそもそも何が故であるか。仏教哲学者が、論理的に、先に挙げた同一性の問題を明瞭ならしめなかったからである。」
2013年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『国文学への哲学的アプローチ』
中公新書 『忘れられた哲学者』(2013年6月刊、清水真木著)で再発見された土田杏村の論文選集です。土田杏村(1891-1934)は土田麦僊の弟で、京大で西田幾多郎に哲学を学びました。大学院在学中に雑誌 『文化』 を創刊し、社会、教育、文学、芸術など多方面にわたる評論活動を開始して、以後定職に就くことなく世を去るまで著作活動を継続した人物です。その短い生涯のあいだに公刊した著作は60点以上にのぼります。哲学の枠内にとどまることなく、文化全般にわたる多様な領域において健筆を揮いました。(著作リストを本の詳細紹介ページのほうに記してあります。)
その土田が晩年特に力を入れていたのが 「国文学」 の哲学的研究で、その成果は四巻連作の 『国文学の哲学的研究』(総ページ数約1600)に収められています。このたび当社で刊行する 『国文学への哲学的アプローチ』 は、そのなかから方法論的な議論を特徴としたものを選んでまとめたものです(表記は新漢字・新仮名遣いなどで現代化しています)。
「国文学」は、思想としては旧時代の遺物視される領域となりましたが、その傾向は百年ほど前にはすでに始まっています。ちょうど土田杏村の生きた時代がそのころにあたるでしょう。そのような時代にあって、土田杏村は哲学的アプローチによって国文学の真価を賦活し、その深層を現在化することに挑んでいます。
土田杏村が国文学者としてもっとも高く評価しているのは富士谷御杖(みつえ)です。土田は、「御杖に聞くべきは、その根本哲学だ。古典を理解する時のその一般的方法論だ。だから我々はその術語などは言霊であっても何でもよい。突き進めた彼の根本思想を尋ねて見たい」 と語り、従来国文学においてなされていない哲学的な方法で新境地をひらく構えを見せています。
「御杖の言うようにして見ると、言語を以て何事をか言うは、実は殺すのである」 という言葉から、その仕事のスタイルと射程をお察しいただけるのではないかと思います。
2013年11月
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『制定の立場で省みる日本国憲法入門』
第一集 芦田均 (衆議院憲法改正特別委員会委員長)
第二集 金森徳次郎 (憲法担当国務大臣)
現行憲法制定当事者の生の声により、日本国憲法をリアルに歴史の問題として捉え直すことを意図した企画です。各巻とも制定過程の経験談と、制定関係者としての立場による逐条的解説の二部構成としました。なぜそう変わったのか、変わらなかったことは何か、議論が紛糾したことは何か――制定の事情と機微を理解すると、今なら変えてもよいところ、今でも変えてはいけないところが、いずれの立場にとっても見えてきます。
第一集には、「九条」 芦田修正で知られる元首相の芦田均が、衆議院憲法改正特別委員会での出来事を当時の個人的メモや記憶に基づき報告する 「憲法調査会(第七回総会・1957年)」 の速記録ほか二篇の回顧談と、新憲法公布時に刊行した全条文を逐条解説する単行本 『新憲法解釈』 を収録しました。
第二集には、国会において改正草案に関する答弁をほとんど一人で行った憲法担当国務大臣金森徳次郎が、憲法制定議会の前後の出来事を報告する 「憲法調査会(第二回総会・1954年)」 の速記録と、新憲法公布後の 「煩悶」 を経て最晩年に語り遺した、新憲法全体を順を追って解説し解釈する単行本 『憲法遺言』 を収録しました。
現行憲法の制定過程に関する研究は、専門の憲法学者や隣接諸学の研究者によってなされた調査業績と議論が豊富にあり、例えば 「芦田均が語る芦田修正の意図は本当に修正提案の日に芦田が考えていたことなのか、本当は後付けなのではないか」 とか、「戦力完全放棄の最初の提案者が幣原首相だということは信ずべきことかどうか」 などについてさまざまな意見や判断があります。そうした各研究者のそれぞれの議論は、その主張をなすに必要な論拠を引用してなされていますが、各論文におけるその引用は、多くの場合判断の正当性を支えるのに最低限必要な範囲の断片的なものです。制定に携わった当時者たちの生の声をまとまったかたちで聞き、その人柄を感じ取り、制定現場の「論理」は勿論のことながら、「空気」や「駆け引き」をも踏まえて言説の行間を読み取ることは、問題の議論に読者自身が参加するうえで意義あることと当社は考えました。目次等は各巻の詳細を紹介する別ページでどうぞご覧下さい。
2013年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『百フランのための殺人犯――三面記事をめぐる対談』
著者はフランス文学の牙城、ガリマール社の 『NRF』 誌を長く仕切った編集長、「黒幕」 ジャン・ポーランです。ポーランが友人と交わした対話を素材にして、精神と言語の最深部にひそむ神秘を軽妙に語り合う対談仕立てのエッセーで、精神のパラドクスとそれに及ぼす言語の不思議な効果をめぐる洞察が示されています。話題の種自体はどれもありふれたものです。例えば 「ブリアンを描いた肖像画」 という章では次のような話がとりあげられます。
――ある女性がブリアンを描いた一枚の肖像画を見せられた。彼女が言うには、「あら、これは似てないわ」 。だが、彼女はブリアンに一度も会ったことがなかったのである。彼女は、ブリアンの数々の肖像画のうち、他の一枚を知っていたにすぎない。
この女性が間違った判断をしていることは誰もが分かることですが、いっぽうこれと同じ種類の間違いは、誰もがつい犯しがちなことも事実でしょう。こうしたことがどうしておきるのかが対談型式で考察され、その原理が明かされます。上記の話題は第一印象というもののはたらきを指摘するものですが、ブリアンならブリアンという名詞が、ブリアンについての部分的な印象と一体化してブリアン全体を代表してしまう例と言えるでしょう。本書の第 I 部ではこれが 「全体性の幻想」 と名づけられ、それに関するさまざまな話題が論じられます。
こうした 「全体性の幻想」 というものは、間違った一般化という単純な側面ばかりでなくて、なかなかニュアンスのある側面も持っていることを教えてくれるのが本書の面白さです。高級官僚が実際具体的に何をしているのかを知らない庶民は、汚職や天下りのニュースに触れて 「役人は搾取階級だ」 と思いますが、では多数の高級官僚の実際をよく知る人ならば高級官僚という語に正しく対応する全体像を描けるものでしょうか。このパラドクスに関して本書で次のような話題が示されています。
――ニヴェルノワは、かつて滞在したことのあるイギリスのことはよく知っていたものの、ロシアについてはあまりよく知らず、中国については何一つ知らなかった。だが彼は、中国人についてははっきりした考えをもち、ロシア人についてはいくぶんぼんやりした考えを、そしてイギリス人についてはひどく混乱した考えしかもちあわせていないと述べていた。
――ある歴史家は、第一次大戦の歴史を書いてみるよう勧められたが、時期尚早だと答えた。そして、それよりかなり以前のドレフュス事件についても、関連したパンフレットや新聞、文書や掲示物や書物が無尽蔵にあるので、さらに五、六十年経たない限りは研究できないのではないかと思っている、と述べた。さらに、そうした資料はほとんどすべて質の悪い紙でできていて傷み始めているのだから、私たちは幸運だ、と付け加えたのである。
「全体性の幻想」 のまた一つの例として本書であげられている、「一人のイギリス人がカレ 〔フランスの港町〕 に上陸したところ、岸辺で一人の赤毛の女を見たので、手帳に、フランス人女性は赤毛だと書き記した」 という話は、ごく素朴な短絡の例であって、すこし反省の頭を働かせれば誰でも避けられる間違いのように思われます。
ところが本書の議論によれば、人間の精神は不思議なもので、第一印象に伴うそうした間違いはそう簡単に避けられるものではないというのです。このイギリス人は理不尽に物事を一般化したと批判されるでしょう。しかし、どういうことがあるべきであったかは別にして、実際に起ったことに着目すれば、このイギリス人は 「どんなフランス人女性も、たった今自分が見たばかりのフランス人女性に似ているだろう」 と考えたのではなくて、「自分の出会ったのはフランス人女性そのものなのだ」 という考えを抱いたことにはほとんど疑いの余地がないとポーランは指摘するのです。詳しい議論は本書にゆずりますが、その議論を締めくくる実例として次のような 「私」 の体験談が紹介されています。
――僕は昨日、ベルフォールのライオン祭でアルマジロを見たけれど、それはほとんど偶然だったし、アルマジロについての何の予備知識もなかった。ポスター曰く、「死体を食らう動物、驚異の七不思議」。さて、第一印象はといえば、自分はとうとうアルマジロというものを目にした、一頭の特別なアルマジロではなく、ついにほかならぬアルマジロそのものを見た、というものだったよ。
当社既刊 『言語と文学』 に収録した 『タルブの花』 同様に、いわゆる明快さとは異なった、言語の神秘――しかるべく思考することはまずもって謎にしかるべき場所を与えることであるという意味での「ゼロ」――に寄りそうジャン・ポーランの魅力がよく発揮されている一冊です。翻訳者の安原伸一朗氏にはポーランを詳しく紹介する解説文を寄せていただきました。
2013年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『カフカからカフカへ』
本書は、孤高の文芸批評家モーリス・ブランショによる自選カフカ論集成です。ブランショが自身の膨大な文芸批評のなかから一人の作家をめぐる評論集として編んだのは、この 『カフカからカフカへ』 一冊だけです。この事実はブランショにおけるカフカの存在の重要性を語っています。
本書のもう一つの特色は、巻頭に 「文学と死への権利」 という論考が収録されていることです。この論考にはカフカへの言及も数箇所ありますが、全体としてはカフカ論というよりは 「文学とは何か」 といったことを、標題の視点から論究する趣きのもので、ブランショの評論群において初期の最重要論考とされているものです。
この 「文学と死への権利」 が本書の巻頭に配されたことは、本書が単なるカフカ研究にとどまらず、ブランショの文学の最深部を開示する書物であることを意味しています。広く読まれるカフカの文学を通してブランショの特異な文学理論が開かれる、ひとつの 「ブランショ入門」 として、文学あるいは言語の根源について関心をお持ちの読者層にお薦めしたい一書です。
2013年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『玄洋社怪人伝』
本書は、玄洋社を代表する頭山満とその一派の行動、人となりを伝える文章を集めたものです。本人の談話や自伝的著作、近親者による評伝から特に面白い話を選んで構成したアンソロジーで、扱われる人物は、頭山満、来島恒喜、杉山茂丸、内田良平、奈良原至、進藤喜平太です。条約改正問題で大隈重信を襲撃した伝説的存在、来島恒喜の、事件に至る経緯と事件の詳細を記録した『来島恒喜』(的野半介監修)、玄洋社人物伝の定番『近世快人伝』(夢野久作著)の主要部分も収録しました。
杉山茂丸はある時期から玄洋社を離れて杉山個人として行動しましたが、杉山の葬儀が玄洋社葬としておこなわれたことからも分るように、終生頭山満との強い関係において活動しました。内田良平もある時期から黒龍会の主催者としての活動を主とするようになりましたが、内田の活動もまた常に玄洋社の頭山満と強く結びついたものでした。本書ではこの二人も広義の玄洋社に属するものと考えて、「玄洋社怪人伝」の書名にて全体をくくりました。
なお、本書に収めた文章のうち、頭山満本人の談話、杉山茂丸本人の著作の抄録、内田良平の部の二篇は、2008年に書肆心水より刊行した『アジア主義者たちの声(上)』にも収めたものです。(同書収録内容のうち犬養毅の部を除いた本文のほとんどが本書にも収録されています。)同書はしばらく前から品切ですので、同書ご入手ご希望の方は本書をその代わりにお求めいただければ幸いです。既に『アジア主義者たちの声(上)』をお読みの方は、本書の収録内容をよくご確認いただいてからお求めになられますようお願い致します。
2013年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『維新の思想史』
思想史の碩学、津田左右吉の最晩年の業績、幕末維新期の思想史研究論文集です。津田左右吉の研究業績は全集版で33巻(各巻500~600ページ)に及ぶ厖大なもので、その内容も記紀をはじめ、中国思想、仏教、神道などと多岐にわたっていますが、それらはいずれも、津田の代表作『文学に現われたる国民思想の研究』を軸とする「国民思想」史研究の一環と見るべきものです。
津田左右吉が一生を費やしたその(国民)思想史研究の出発点の動機は、幕末維新期の思想状況に対する疑問であったと津田自身が語っています。そして、その出発点の課題は最晩年になってようやく果たされました。本書はその成果を収めたものです。
近年、歴史学の分野で従来の幕末維新期に対する評価の見直しが進んでいますが、(例えば岩波新書の「シリーズ日本近代史1」井上勝生著『幕末・維新』など) 津田左右吉はその先駆者であったといえるでしょう。津田が今から五十年も前に、すでにこのような視角で史実を評価していたことは一般にはあまり知られていないようです。近代日本の出発点である「維新」をいかに評価するかということは、現在の状況の評価に深いところでつながっています。その点で、津田の幕末維新期の研究は現在の我々に益するところが大きいと考えて本書を刊行いたしました。
2013年8月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『行き詰まりの時代経験と自治の思想 権藤成卿批評集』
最近刊行されました中島岳志氏の『血盟団事件』でも血盟団事件に影響を与えた思想家として論じられている、「自治の思想家」権藤成卿の批評文集です。権藤が最晩年に刊行した二冊、『血盟団事件 五・一五事件 二・二六事件 その後に来るもの』と『自治民政理』で構成してあります(『自治民政理』のほうは後篇のみ収録)。
『血盟団事件 五・一五事件 二・二六事件 その後に来るもの』のほうは時局批評文で、『自治民政理(後篇)』のほうは権藤思想の理論的構造を示したものです。明治以来の官僚制国家中心主義に対する、生産=生活共同体の自治思想を提唱した権藤の思想の要所は、この二冊で知ることができます。
開国、日露戦勝、世界大戦の好景気を経た後に、不況と大震災後の行き詰まりから血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件に至るテロと戦争の時代へと墜ちた過去。そして、敗戦復興から高度成長、バブル経済を経た後に、長い不景気と大震災後の行き詰まりへと再び至った現在。かつての行き詰まりの時代経験のなかから生み出された権藤の自治思想は、「二周目後半の近代日本」に対する教訓を示していると考えて本書を刊行いたしました。
2013年7月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『アナキスト地人論 エリゼ・ルクリュの思想と生涯』
地理学の立場から人間の自由と共生を問う異色のアナキスト、エリゼ・ルクリュ(1830-1905)の思想と生涯を紹介する本を製作いたしました。グローバリゼーションという抽象的で画一的な普遍文化が世界を覆う今、「多様な地に即した多様な人間性」という人類史的現実を踏まえたエリゼ・ルクリュの共和思想がいまこそ意味を持つと考え、日本のアナキストとして著名な石川三四郎が遺した仕事を再編成して一書としたものです。石川三四郎は、ポール・ルクリュ(エリゼの甥)家において労働と生活をともにした間柄ですので、日本人としてはエリゼ・ルクリュの紹介者として最も相応しい人物です。
本書第I部の底本は、エリゼ・ルクリュ著『地人論(第1巻・人祖論)』(石川三四郎訳、1930年、春秋社)です。本書にはそのうち序文と三つの章を収録しました。原書(L'Homme et la Terre)初版は1905年から1908年にかけて6分冊4巻構成で刊行されたものです。第II部の底本は、石川三四郎著『エリゼ・ルクリュ――思想と生涯――』(1948年、国民科学社)です。
西洋中心主義、自民族中心主義を相対化し、生きたものとしての地球という視点から動植物、人間その他、全てが連帯的に存在しうる世界を提唱するエリゼ・ルクリュの思想は、今日のわれわれの課題に示唆するところが大きいと考え、本書を刊行いたしました。
2013年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『東洋的芸術精神 大西克礼美学コレクション3』
大西克礼美学コレクション完結篇です。哲学の一分野である美学を日本に導入した大西克礼(1888-1959)は、西欧美学の枠をこえて日本独自の美概念を理論的に考察し、既存の美学にそれらを組み込んで、新たな普遍美学の創造を試みました。「大西克礼美学コレクション」は、大西の諸著作のなかから日本的・東洋的美の諸概念を論じた著作を選んで三巻にまとめたものです。
第1巻『幽玄・あはれ・さび』には、書名の通り「幽玄」「あはれ」「さび」を論じたものを収めました。第2巻『自然感情の美学』には、日本文化の原点である万葉集に見られる自然感情の考察と、古今東西における自然感情の諸類型の考察を収めました。最終巻の第3巻『東洋的芸術精神』は、東洋的芸術精神のパントノミー即ち本源的綜合性とは何かを示し、生活の全面と深く一体化する芸術の心を綜合的に理論化した著作で、大西克礼美学研究の最終的到達点を明示する大作の遺稿です。
2013年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『媒介的自立の哲学 田辺哲学イントロダクション』
西田幾多郎に次ぐ「京都学派」の哲学者として活躍した田辺元の仕事は、「西田哲学」に対して「田辺哲学」と呼ばれました。田辺の哲学は、初期の科学・数理哲学、発展期の「種の論理」、転換期の「懺悔道の哲学」、そして晩年の「死」をめぐる哲学というように、論点のジャンルは広範囲にわたっています。従来、「種の論理」あるいは「絶対弁証法」をキーワードにして語られることの多かった田辺哲学ですが、このたび田辺哲学の入門書となることを意図して刊行するこの田辺の論文選では、田辺哲学への一つの入り口として「媒介的自立」というキーワードを設定し書名に掲げました。
「種の論理」、「懺悔道」、あるいは「死の哲学」というように幾つかの主要論点からなる田辺哲学の全体は「媒介」というキーワードに貫かれています。観念弁証法(ヘーゲル)と唯物弁証法(マルクス)をともにこえるための独自の「絶対弁証法」を提唱する田辺哲学が「媒介」をキーワードとするのは当然であるにしても、その「媒介」とはどのような「媒介」であるのか。
田辺哲学が新たな哲学素として提出する「媒介」は、止揚が全体化に帰結する弁証法を意味するものではなく、相容れない物同士が、止揚において個々の自立性をかえって高めるものです。
本書は、この田辺哲学の個性をわかりやすく見て取る方法として、知性および精神性諸ジャンルの、媒介的な関係性を論じたテキストを選択しました。例えば、常識と哲学と科学と宗教とはそれぞれ違うものですが、この、重なりうる部分もありながら強く対立するそれぞれ同士の関係は、田辺哲学の視点から見るとどのようなものとしてあるのか。論理と倫理、合理性と実証性といった関係もこの立場から考察され、さらには、西洋的存在論と東洋的空観との「媒介的自立関係」という、西田・田辺の時代ならではの先駆的な世界史的新課題も示されます。
2013年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『自然感情の美学 大西克礼美学コレクション2』
大西克礼(1888-1959)は、哲学の一分野である美学を日本に導入した美学者です。大西は既存の美学の枠をこえて、「幽玄」「あはれ」「さび」をはじめとする日本独自の美概念を理論的に考察し、既存の美学にそれらをも組み込んで新たな普遍美学の創造を試みました。「大西克礼美学コレクション」は、大西の諸著作のなかから日本的(東洋的)美の諸概念を論じた著作を選んで三巻にまとめるものです。
日本特有の美概念は主に文芸において練り上げられてきましたが、それらは長く理論的な考察がなされないまま、ただ体験的に論じられて来ました。大西克礼の仕事はそれらの美概念を理論的に考察した画期的なものです。国文学や美学の分野にとどまらず、日本的感性の本体を探ろうとするさまざまな立場の人々にとって、繙読して益あるものと思います。
コレクションの第1巻には、「幽玄」「あはれ」「さび」を論じたものを収めましたが、今月刊行のコレクション第2巻『自然感情の美学――万葉集論と類型論』には、日本文化の原点である万葉集に見られる自然感情の考察と、古今東西における自然感情の諸類型の考察を収めました。近刊の第3巻は、大きな枠組みにより総合的な美学理論を提出する『東洋的芸術精神』です。
2013年1月
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『北里柴三郎読本』
本書は北里柴三郎の伝記と北里自身の論説を集めて北里の事績と言説のあらましを示す「北里柴三郎読本」です。
本書に収めたテキストはいずれも北里研究所により非売品として刊行された『北里柴三郎伝』(1932年)と『北里柴三郎論説集』(1978年)から選び出したものです。『北里柴三郎論説集』のほうは1700ページほどに及ぶ超大冊で、集めえた限りのもの(単行本を除く)が叙述の形式を問わずことごとく収められています。両書ともに非売品であるためか、東京の区立図書館をはじめほとんどの公共図書館において蔵書されておらず、一般の目に触れる機会が稀です。そこで、北里自身の言葉に接してみたいという求めに応じうる本となることを意図して商品化したのが本書です。新漢字・新仮名遣いを採用して表記を現代化しました。「読本」を志向した本書では、伝染病医学に通じていない一般読者にも理解できる比較的読みやすいテキストを『論説集』から選んでいます。そして収録した各テキストを北里の人生の各局面に照らして理解しうるように、最も基礎的な伝記をあわせて収めてあります。その簡にして要を得た伝記『北里柴三郎伝』の編纂叙述は、北里の指導を受け北里と共に働いた直弟子の手になるもので、後年の各種北里伝は多くをこれに拠っています。
北里柴三郎は細菌学・伝染病研究を開拓した医学者の一人ですから、北里自身の研究史は細菌学・伝染病研究の発達史を語るものでもあります。また、北里は研究室内の学問にとどまらず伝染病予防のための社会的な事業にも力を入れましたから、北里自身の研究史は医療社会史としての側面も持っています。北里が活躍した時期の全体にわたるテキストを収める本書を通読することによって、北里の全体的真価が、1.卓越した学理的業績の面と、2.その学理探究の本来の目的である人々の健康を実現するための衛生行政の面、とを兼ね備えた両面性にあることが伝わるだろうと思います。
目次等、別途ご用意してある詳細ページでどうぞご覧下さい。
また、本の中をご覧いただけるPDFファイルもご用意してあります。
2012年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『幽玄・あはれ・さび 大西克礼美学コレクション1』
大西克礼(1888-1959)は、哲学の一分野である美学を日本に導入した美学者です。大西は既存の美学の枠をこえて、「幽玄」「あはれ」「さび」をはじめとする日本独自の美概念を理論的に考察し、既存の美学にそれらをも組み込んで新たな普遍美学の創造を試みました。「大西克礼美学コレクション」は、大西の諸著作のなかから日本的(東洋的)美の諸概念を論じた著作を選んで三巻にまとめるものです。
日本特有の美概念は主に文芸において練り上げられてきましたが、それらは長く理論的な考察がなされないまま、ただ体験的に論じられて来ました。大西克礼の仕事はそれらの美概念を理論的に考察した画期的なものです。国文学や美学の分野にとどまらず、日本的感性の本体を探ろうとするさまざまな立場の人々にとって、繙読して益あるものと思います。
コレクションの第2巻は、「幽玄」「あはれ」「さび」と不可分の「自然感情」について、日本文化の原点である万葉集に見られるそれの考察と古今東西におけるその諸類型の考察を収めた『自然感情の美学』で、第3巻は、大きな枠組みにより総合的な美学理論を提出する『東洋的芸術精神』です。
2012年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『大川周明世界宗教思想史論集』
大川周明畢生の宗教研究の精髄を集めた論集を刊行いたします。人類の宗教性はどこから来たか、そしてどこへ行くべきか。――史上一切の宗教を宗教の一連鎖として考える立場から、世界宗教の総合的進化が考察されています。目次は次の通りです。
I 世界宗教思想史
序
宗教の進化
東西に於ける覚者の出現
キリスト及びキリスト教
近代に於けるキリスト教的信仰の変遷
仏陀及び仏教
摩訶般若波羅密多心経
教祖・教法・教団
ドイツに於ける宗教思潮
信神の意義
II インド思想概説
インドの地と人
インド精神の種々相
吠陀(ヴェーダ)に現われたるインド精神
奥義書に現われたる哲学的思索
奥義書以後の思想信仰
インド精神の実践的方面
種姓制度について
現代インドの精神的復興
現代インドの政治的思潮
インド復興の将来
第 I 部は、遺稿の宗教論と1921年刊行の『宗教原理講話』(東京刊行社)中の数章で構成し、第 II 部は、1930年刊行の『大思想エンサイクロペヂア第八巻』(春秋社)に収録された「印度思想概説」の全文です。
第 I 部に収めた遺稿は、1962年刊行の全集版で公刊されたもので、その構成は次のようになっています。
第一 人格的生活の原則
第二 宗教の進化
第三 東西に於ける覚者の出現
第四 基督及び基督教
第五 近代に於ける基督教的信仰の変遷
第六 回教に於ける神秘主義(本文なし)
第七 仏陀及び仏教
第八 摩訶般若波羅蜜多心経(中断)
第九 教祖・教法・教団
第十 人生に於ける宗教の意義(本文なし)
全集版の編集委員註によれば、第五の章末までには通しでページ番号が記されていて、第六の章以降は章ごとに独立したページ番号が記されているので、第五の章までは脱稿したものと考えうるとされています。
この遺稿は全く新しく書き起こされたものではなく、『宗教原理講話』の訂正増補版と見るべきものです。『宗教原理講話』の構成は次のようになっています。
第1章 宗教とは何ぞや
第2章 原始宗教に於ける崇拝の対象
第3章 初期に於ける宗教の進化
第4章 部族的宗教より司祭宗教へ
第5章 普遍宗教の出現
第6章 預言者の宗教
第7章 預言者としての老子
第8章 預言者としての孔子及びソクラテス
第9章 基督出現以前のイスラエル宗教
第10章 耶蘇の生涯
第11章 耶蘇の宗教及び基督教(上)
第12章 耶蘇の宗教及び基督教(下)
第13章 仏陀以前の印度宗教
第14章 仏陀の生涯
第15章 仏陀の福音及び仏教の発達
第16章 独逸に於ける宗教思潮
第17章 近代欧羅巴に於ける宗教思想の変遷
第18章 教法、教祖、教会
第19章 信神の意義
遺稿と『宗教原理講話』の記述内容を対照すると、遺稿の各章は『宗教原理講話』の各章をほとんどそのまま使用している場合と、『宗教原理講話』のいくつかの章から部分的に抜き出して合成している場合の違いはありますが、遺稿で新しく計画された「六・八・十」の三つの章(二つは未起稿で一つは中断)と第一の章を除く全てが『宗教原理講話』の内容と重なっています。
遺稿の第一の章「人格的生活の原則」は1926年に刊行された『人格的生活の原則』(東京宝文館)の改訂原稿と見るべきもので、内容は大川周明本人の宗教的道徳思想の精髄を記したものです。単行本版の『人格的生活の原則』は書肆心水既刊(2008年)の『大川周明道徳哲学講話集――道』に収録してあり、遺稿の記述はそれとほとんど同じですので、本書には掲載しませんでした。
以上の事情により、本書の第 I 部には遺稿の第二~第五、第七~第九を収め、さらに『宗教原理講話』にはあって遺稿にはない二つの章「第16章 独逸に於ける宗教思潮」「第19章 信神の意義」を補いました。
なお、『宗教原理講話』の「第一章 宗教とは何ぞや」の後半部分の内容は遺稿の幾つかの章に織り込まれているので、前半部分だけを本書の「序」として使用しました。
2012年10月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『近代日本官僚政治史』
中央集権近代化の政治史を通して、官僚界の形成とその位置の変遷を概説する入門書です。官僚はいかなる事情で国政の本体を担う存在となったのか、その経緯をたどり、民意からの隔絶という伝統の淵源を幕末以来の歴史に探ります。
本書は、田中惣五郎の著作、『近代日本官僚史』(1941年、東洋経済新報社出版部刊)と『改訂・日本官僚政治史』(1954年、河出書房刊)の合冊新版です。『日本官僚政治史』は『近代日本官僚史』の改訂版として刊行されたもので、通常は改訂版の刊行により初版は基本的な価値を失うものでしょうが、以下に記す理由から、初版『近代日本官僚史』にも今日復刻する価値があると考えました。
改訂版『日本官僚政治史』は、初版『近代日本官僚史』の幕末に関する部分を省き、大幅な改訂を施したものです。二書の目次を対照しただけでも改訂が全面的なものであることが察せられるでしょう。改訂版の記述量は初版の約六割と、大幅に圧縮されています。初版と改訂版それぞれの刊行年における時局がしからしめたであろう著述態度の違いも大きなものであり、改訂版においては著者の史観による批評性が発揮されています。論じられる事柄も選択的に整理されて、著者の解釈が示された著作となっているといえるでしょう。初版には見られない史料も多く採用されています。
改訂版に対する初版の存在意義としては、改訂版で省かれた幕末の歴史があることが第一です。第二は、改訂版の記述量が減ったために省かれた史実が、初版には多く記されていることです。初版は、全般的な政治的社会的状況の歴史を語りつつ、そこから時々の官僚に求められた職能や、官僚界の位置と動向を浮かび上がらせるといった方法で著されており、主題である官僚そのものについての言及が少ないと感じられる時代もありますが、その反面、時々の官僚界のありように関わる複合的な政治状況を詳しく伝えているという利点があります。
上記の理由から、二著の全体をあわせて一冊の新版として復刻することとしました。初版と改訂版の関係なので重複する部分も多く、この二著の全体をそのまま掲載することには紙数の無駄があることは否めません。しかし、この貴重な労作を後世に継承するための一手段として合冊という選択をしました。本書はこうした事情のものですので、まずは改訂版を読んで、後に初版によってその不足を補うように使われるとよいかと思います。
2012年9月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『三木清歴史哲学コレクション』
三木清の著作には、現在も廉価版で販売されている『哲学入門』(岩波新書)『哲学ノート』(中公文庫)『人生論ノート』(新潮文庫)がありますので、日本人の哲学者としては比較的広く、長いあいだ親しまれてきた存在でしょう。このたび当社より刊行します『三木清歴史哲学コレクション』は、単行本の『歴史哲学』に加え、歴史哲学を論じた諸論考を収めたもので、三木哲学における一つの重要テーマである「歴史哲学」の全体像を一冊で見渡すことができます。
兵庫県生まれの三木は、第一高等学校入学のために上京し、在学中に西田幾多郎の『善の研究』を読んで、京大で西田について哲学を専攻しようとの意を固めました。当時、一高を出て京大に進むことは極めて異例であったと言われています。三木の歴史哲学研究は京大在学中以来のもので、晩年の主著『構想力の論理』にいたるまでその「歴史意識」は貫かれています。
西田に学んだ三木は、根本的な哲学的課題を継承し、それを三木独自のフィールドで果たしていったといえるでしょう。主体と客体は分離したものと考える従来の「論理」の限界をのりこえて、行為と物の切り離しえなさを論理化しようとする「新しい論理」への試み。それを歴史の問題として哲学的に考察した仕事が三木清の歴史哲学です。「歴史」あるいは「歴史性」という問題は、西田哲学でも一つのキーワードになってはいるものの、まとまった著作としては主題化されていません。その問題に三木は相当量の著述をもって取り組みました。その成果をまとめたものが本書です。西田哲学に強いご関心をお持ちのかたに特におすすめいたします。
2012年7月・8月
.jpg)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『津田史学の思想 津田左右吉セレクション1』
『日本文化と外来思想 津田左右吉セレクション2』
『記紀の構造・思想・記法 津田左右吉セレクション3』
古事記・日本書紀の理性的で批判的な研究を創始し、真に学問的な日本思想史を提唱した津田左右吉の入門選集です。津田左右吉は、その代表作『文学に現われたる我が国民思想の研究』(岩波文庫版・全8冊)でよく知られ、またその記紀研究が出版法違反(皇室の尊厳冒涜)で起訴されたことがよく話題になる歴史学者です。津田の研究業績は日本の思想史的研究ばかりでなく広範囲の中国思想にも及び、厖大な量の著作が残されています。
津田史学の特徴をよくあらわす一側面として、戦前の皇国史観の時代には皇国史観を批判し、戦後の唯物史観の時代には唯物史観を批判したことを指摘できるでしょう。今ではこの二つの立場が学問的な歴史学としては問題のあるものであることは明らかな常識となりましたが、この二つの史観のそれぞれが一世を風靡しているそのさなかにおいてそれを根本的に批判し否定したことの意義は大きなものです。これまでの津田左右吉評価においては皇国史観批判の側面が主に論じられ、その立場は戦後の歴史学に大きな影響を与えましたが、その反面で唯物史観批判をも含めた全体としての津田史学の評価はまだこれからの課題という部分が少なくありません。狂信的な二つの史観が交替して主導した時代を終えた第三の時代に属する現代において、参照すべき一つの立場が津田史学であると考え、津田の多様で厖大な業績のなかから入門的な観点で選択した著作をテーマごとにまとめ、「津田左右吉セレクション」として刊行いたします。各巻の目次は次の通りです。
●第1巻 津田史学の思想
必然・偶然・自由
歴史の学に於ける「人」の回復
史学は科学か
歴史の矛盾性
日本歴史の取扱いかたについて
学問の本質
歴史の考えかた
過去の生活をどう理解するか
わたくしの記紀の研究の主旨
出版法違反裁判上申書(抄)
●第2巻 日本文化と外来思想
シナ思想と日本
日本文化とシナ及び朝鮮の文化との交流
漢字と日本文化
日本思想形成の過程
日本精神について
世界文学としての日本文学 ――文学の比較研究について――
日本の神道(抄)
●第3巻 記紀の構造・思想・記法
記紀の研究の序説
研究の目的及びその方法
我々の民族とシナ人及び韓人との交渉
文字の使用と古事の伝承
記紀の由来、性質、及び二書の差異
記紀の記載の時代による差異
神代の物語
神代史の結構
神代史の潤色
神代史の性質及びその精神
神代史の述作者及び作られた年代
書紀の書きかた及び訓みかた
神とミコト
2012年6月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『朝鮮の美 沖縄の美 柳宗悦セレクション』
先月刊行の 『仏教美学の提唱』 につづく 「柳宗悦セレクション」 の第二作です。日本の民芸について多くの著作をのこした柳宗悦には、朝鮮の工芸美と沖縄の工芸美を論ずる著作も少なからずあります。本書はそれらのうち主だったものを集めて一冊にしたものです。朝鮮の美、沖縄の美はいかなる事情のもとにあらわれたのかを考察した柳は、それが民族の 「生活」 と 「自然」 に由来していることを発見します。そうした美は、技巧の末に堕ちた現代に反省を促しているようです。目次は次のとおりです。
朝鮮の美
「朝鮮民族美術館」の設立に就て
朝鮮の美術
朝鮮の品々
李朝陶磁器の特質
李朝窯漫録
李朝の壺
「高麗」と「李朝」
朝鮮茶碗
李朝陶磁の美とその性質
李朝陶磁の七不思議
朝鮮の木工品
朝鮮の石もの
沖縄の美
挿絵略解
挿絵小註
沖縄の民芸
芭蕉布物語
『沖縄織物裂地の研究』序
現在の壺屋とその仕事
琉球の富
2012年5月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『仏教美学の提唱 柳宗悦セレクション』
柳宗悦が自己の民芸思想の最終到達点として提唱した 「仏教美学」 に関するテキストの集成です。従来、柳の 「仏教美学」 については 「美の法門」 「無有好醜の願」 「美の浄土」 「法と美」 の四つのテキストが代表的なものとして岩波文庫 『新編・美の法門』 とちくま学芸文庫 『柳宗悦コレクション 3 こころ』 に収められるなどして広く知られてきましたが、柳の提唱する 「仏教美学」 の多様な具体相とニュアンスを示す著作は他にも豊富にあり、本書はそれらを集めたものです。
「人は恐らく、在銘の作を作る時より、無銘の作を作る時の方が心が自由であろう」 と考えた柳が、美醜の彼岸における 「自在の美」 「他力の美」 を、具体的な 「物」 に即して多様に語ります。「他力の美」 をもつ工芸品はどのような事情のなかで生み出されるのかが考察され、天才的・個性的な美を作り出そうとする心(自己)を離れたところに、「作り出されたもの」 としてではなく 「生み出されたもの」 としてあらわれてくる美を感じ取る心が提唱されています。目次は次のとおりです。
仏教美学の悲願
民芸美の妙義
美とは何か
美醜について
美醜以前
美の公案
美感と信心
美 と 禅
美の世界を介して
美の召命
他力門と美
自力と他力
自力と恩力
工芸に於ける自力道と他力道
物 と 法
無銘品の価値について
狭間の公案
仏法多子なし
只この一つ
只の境地
凡人と救い
無功徳の功徳
東洋的確信
伝統の価値について
人物と自然物
円空仏と木喰仏
民間の仏体
自然児棟方志功
不生の文字
版画の間接美について
模様とは何か
来月は 「柳宗悦セレクション」の第二作として 『朝鮮の美 沖縄の美』 を刊行いたします。
2012年4月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『意識と意志 西田幾多郎論文選』
書肆心水刊行の西田幾多郎論文選、第七作です。三木清との対談集 『師弟問答 西田哲学』 と、西田の手紙および日記の選集 『西田幾多郎の声 前篇・後篇』 を加えますと十作目の本となりました。
本書 『意識と意志』 は、処女作 『善の研究』 で広く知られる 「純粋経験」 の思想から、西田哲学と呼ばれるにふさわしい円熟期の 「場所の哲学」 へとその思索がブレイクスルーする過程で集中的に考察された 「意識」 と 「意志」 をテーマとする諸論文の集成です。
これまで当社より刊行しました西田幾多郎の著作は次のとおりです。詳細はリンク先の各ページにてご覧下さい。
●西田幾多郎キーワード論集
●西田幾多郎生命論集
●西田幾多郎日本論集
●種々の哲学に対する私の立場
●実践哲学について
●真善美
●意識と意志
●西田幾多郎の声 前篇
●西田幾多郎の声 後篇
●師弟問答 西田哲学
2012年3月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『和辻哲郎日本古代文化論集成』
古事記編纂1300年のこの機に、日本文化史の第一人者和辻哲郎が日本の古代の文化的側面について研究した論考を集めて刊行いたします。仏教文化の影響を受ける以前の日本文化の深層を明るみに出す和辻日本文化論の原点です。考古学的史料と神話伝説や詩歌の文献にのこされた古代人の生命の痕跡から、和辻一流の手法によって、古代人の想像力と構想力、そしてその 「湿やかな」 心情が読み出されています。
今では学術的立場において古事記や日本書紀に記された物語の全体を歴史と見る人はいないでしょう。これは和辻が活躍した時代 (大正期以降) も既に同じことでした。和辻は、本書に収めた 『日本古代文化』 の新版序文 (1951年) に次のように記しています。
《このようなことをここに書くのは、この書が大正9年に初版を出して以来、昭和20年まで25年間、日本の当局の弾圧を受けずに、何人にも読まれ得る状態にあった、ということを言いたいためである。戦後、日本の歴史の研究について、実にでたらめな浮説が行なわれている。研究の自由が全然許されていなかったとか、真相が全然おおいかくされていたとか、少しでも研究の実状を知っている人なら言われないはずのことが、公然言われていた。学校の歴史の教科書にどういうことが書かれていようと、また一部の国史家がどういうかたよった態度をとっていようと、それはまじめな国史の研究者の責任ではない。教科書に書かれていたことを種にして右のような判断を下したとすれば、それは文教当局や政治家の責任と国史の研究者の責任とを全然混同するものである。研究は自由に行なわれ得たし、その成果の発表も、今度の戦争の起こるころまでは、弾圧されはしなかった。ただ政治家や軍人や教育家などが、その研究の成果を受け容れようとしなかっただけである。》
和辻が上に述べるような 「でたらめな浮説」 は、21世紀の今もなおまま見られますので、われわれは上記の和辻の非難を銘記すべきでしょう。では、和辻はいかなる態度で記紀に対しているのでしょうか。その方法的姿勢が感じられる一説を以下に引用いたします。
《神話伝説のなかから、記録以前の古い記憶を取り出そうとする態度に対しては、根本史料批判の立場から、厳しい警戒の声が発せられている。周知の通り記紀の編纂は奈良時代の初め(712,720)のことであって、漢書の成立より六百年以上も遅れている。しかもそこに用いられた資料は、いかに古くとも、文字渡来やその使用開始の時期よりも先のものであることができない。従って日本で初めて国家が形成されたような古い時代のことは、ここに記録された神話伝説ができあがるころには、すっかり忘れ去られていた、という主張が出てくる。しかしわたくしはこの忘却説に賛成することができない。記録の行なわれない時代の伝承が強度の伝説化を受けるということ、従って実際の事情をそのまま伝えるのでないということは、もちろん認めざるを得ないことであるが、しかし伝説化は忘却ではない。それが古昔の人の記憶の仕方である。そういうことをシュリーマン以後のさまざまの発掘が実証している。ミノス王の迷宮の伝説は、それ自身としては何らの史実をも含んでいないであろうが、しかしクレータのクノッソス王宮の発掘は、この伝説全体がギリシア以前のクレータ文化を材料としていることを明らかにした。伝説の内容の非現実性、空想性などは、その伝説の根の虚構性を証拠立てるものではない。伝説の根がしっかりと現実のなかに食い入っていても、そこから生い育ってくる伝説が、恐ろしく現実ばなれをしている、ということは、実際にあるのである。われわれは神話伝説をあくまでも想像力の産物と認めるとともに、その根をほり返して歴史的現実をたぐり出さなくてはならない。記紀の神話伝説もまたこのような根を持つと考えられる。それをただその内容の非現実性、空想性のみによって、単なる仮構の物語と見てしまうのは、神話伝説の類を取り扱う正しい態度とは言えないであろう。しかしそれだからといってわれわれは、記紀の神話伝説が非常に原始的な時代の信仰の残滓であると見るのでもない。この神話伝説は、一定の時代に定位さるべき、明白な主題を持っているのである。ではその主題とは何であるか。》
このように和辻の方法は科学的実証主義とは異なるものですが、これに一理ありと感じられるかたは、古事記編纂1300年のこの機に、この先達の業績を振り返ってみてはいかがでしょうか。
2012年2月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
野上豊一郎批評集成 《文献篇》 『精解・風姿花伝』
能楽研究のパイオニア野上豊一郎(1883-1950)の主要業績を現在に蘇らせる叢書 「野上豊一郎批評集成」 の第三企画です。
第一企画は 『能とは何か(上)入門篇』 『能とは何か(下)専門篇』 として、野上豊一郎の能楽論三部作 (『能 ――研究と発見』 『能の再生』 『能の幽玄と花』) に収められた全論考を入門篇と専門篇に再編し、初学者と玄人それぞれの「能とは何か」という問いと探究心にこたえる二冊構成にて刊行いたしました。
第二企画は 『観阿弥清次』 と 『世阿弥元清』 の二冊をあわせ、《人物篇》 として刊行いたしました。能を完成させたその原点から、後世の硬直化した能を批判し、なにゆえにこの父子は空前絶後の存在であるのかを示す仕事です。役者でもあり、監督でも、作詞家でも、作曲家でも、理論家でもある人間だけが至りうる境地を発見し、世阿弥一辺倒に傾きがちな能論議をこえて、二人の関係性から 「能とは何か」 を明かすユニークな批評です。
そして今月刊行の第三企画 《文献篇》 は風姿花伝を精細に解読する仕事です。「秘スレバ花、秘セズバ花ナルベカラズ」 の言葉で知られる 『風姿花伝』 の根本思想である 「花」 とは何か。『風姿花伝』 読解の全篇をその問いで貫き通す、能楽研究のパイオニアならではの力強い批評です。全原文の純粋な姿が示され、三つの底本の全異同も示されています。
2012年1月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
辻善之助著 『日本仏教文化史入門』
本書は、実証史学としての日本仏教史を開拓した辻善之助の代表作 『日本仏教史』 全十巻の要約版と称すべきもので、日本の仏教文化の歴史を明かす入門書です。
著者の辻善之助は東京帝大国史科卒業後、同大学院を経て史料編纂掛に入所し、のち、東京帝大教授と史料編纂所初代所長を兼任した碩学です。大学院時代に 「政治の方面より観察したる日本仏教史」 を研究題目として以来、生涯にわたり日本の仏教史研究にとりくみました。政治はもとより社会・文化史的側面を重視し、かつ堅固な実証主義的方法に貫かれたその仏教史研究は、それまでの教団史的水準を克服した画期的業績となりました。代表作の 『日本仏教史』 全十巻は、今日でもこれをこえる規模の総合的な仏教史はないと高く評価されています。
本書は、「日本文化と仏教の関係を論ずることは、すなわち日本文化史のすべてを論ずることになる」 と考えている著者が日本仏教文化史を 「概観」 するものです。本格的研究者ばかりでなく一般読書子にも辻善之助の仏教史学に接していただくよすがとして恰好の一冊かと存じます。
2011年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
R・B・ボース/相馬安雄/相馬黒光著 『アジアのめざめ』
本書は 「中村屋のボース」 として知られるインド独立革命の闘士ボースの伝記文集です。ボースに親近した義弟・相馬安雄と義母・相馬黒光によって歿後八年に編まれました。日本に亡命し、日本の戦争とインド独立闘争の連携をはかったその困難な生涯を、ボース本人とボースの最も近くにいた二人の 「生の声」 によって今に伝える記録です。
本書には、ボースが亡くなる少し前に義弟の相馬安雄に語ったという次の言葉が、相馬安雄自身によって記されています。この言葉に畳み込まれた複雑な葛藤と確信が、即ちボースの苦渋に満ちた革命家としての半生であると言うべきでしょう。半世紀以上の時を隔てて今なおその意味を深く考えさせられる歴史の現実です。
――12月もおしつまったある日、私はボースの容態を案じて見舞った。ボースは話があると云って、私を枕もとに呼んだ。やせ衰えた顔に、眼だけが鋭い気魄をこめ、きらめいていた。いつもと少しちがうように見えた。ボースは苦しげな声で、「日本はもう駄目だ、負けるよ」 と云った。私には言葉もなかった。
「お前に云っておきたいことがあるのだ。おれは長い間日本にいて、日本の社会、文化、宗教、ずいぶん研究して、わかったと思っている。ただ残念なのは、日本の軍部の研究を怠ったことだ。軍部の上層の人間とだけ交際し、その言を信じた。日本の軍部は二国を相手に戦うことが出来ると、彼等は豪語していた。おれは軍部を抱きこみさえしたら、インドの独立は可能だと考えたのだ。これが間違っていた。日本の軍部がこんな実力だったら、起つのは未だ早すぎた。結論を云えば、日本はもう負けだ。
おれはインドの人間だ。しかし白人種に対抗しうる有色人種の中心は、日本人以外にはないと思っている。中国人もインド人も駄目だ。日本が負けたら、有色人種は永久に白人と対等になれなくなるよ。おれの目には、日本人は個々の人間としてさほど優秀とは思えない。ただ陛下を中心とした場合、不思議な力を持ってくる。日本が陛下を頂く国の形態を崩壊させたら、それこそおしまいだ。どこまでもこの形態を守りぬき、日本が中心になって、もう一度有色人種はたち上がらなければならない。そして白人種と戦うことだ。いいか――」。
ボースのとぎれがちな言葉には、奇妙な強さがこもっていた。だが話し終ったボースの顔には、一時に衰頽の影がおしよせてきた。
2011年12月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
頭山満著 『頭山満思想集成』
当社既刊の 『頭山満言志録』 と 『頭山満直話集』 とを合冊にした 『頭山満思想集成』 を刊行いたします。伝説的存在として脚色されがちな頭山満の真の姿と思想を伝える良質な直話のみを精選したものです。合冊化にあたり判型を四六判からA5判に改変し、若干の補訂を施して新たな版としました。 『頭山満言志録』 では底本どおりに旧仮名遣いを使用しましたが、合冊化にあたり新仮名遣いに改めました。
西郷隆盛の遺訓を講評しつつ自己の思想を語る 「大西郷遺訓を読む」 と、自己の一代を回顧しつつ同時代の人物や社会を批評する 「直話集」 の構成です。
元本については、下記のリンクでページを開いてご覧下さい。
*元本 『頭山満言志録』 のページへ
*元本 『頭山満直話集』 のページへ
2011年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
九鬼周造著
『増補新版 偶然と驚きの哲学 ――九鬼哲学入門文選』
『偶然と驚きの哲学』 の初版に二篇を増補した新版です。『「いき」の構造』 で著名な九鬼周造の哲学主著は 『偶然性の問題』 ですが、本書は、その主著以後、「偶然性」 にさらに 「驚き」 の論点が加味された、九鬼周造晩年の到達点を示す講演・論文を集めたものです。いずれも平易な文章であり、九鬼哲学への入門として恰好の一冊です。
先日小社より刊行した 『宮廷人と異端者 ――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』 にご興味をもたれた方には、関連する論点を含む本として特におすすめしたい一冊です。九鬼周造は、驚きを情緒として認めないスピノザについて、「決定論の立場からスピノザは一切の偶然を否定している」 として、批判的な立場をとっています。ライプニッツについては、「現実の世界が偶然的であることを説いた例はライプニッツに見られる」 として、「与えられた現実の世界を、唯一可能のものと考えないで、その背後に多数の可能な世界を認めた」 その立場に注目しています。
しかし九鬼はライプニッツのような立場を自己の立場としているわけではなく、ライプニッツのなかに楽天観と独断論をも見ています。「西洋の哲学がキリスト教の影響の下に立っている限りは、純粋な偶然論、純粋な驚きの形而上学は出来て来ないのである。ライプニッツは 『より善きものの原理』 に従う決定論になってしまった」 と九鬼は考えて、次のように語っています。
「与えられた現実の世界を唯一可能のものと考えないで、その背後に無数の可能な世界を認めた動的見地にライプニッツの現代的色彩がある。ライプニッツがそういう考え方へ進んで行った根柢の一方にはCombinatorikの研究があり、他方には世界創造の神学があったのであろう。彼は世界の事象を 『偶然的存在者』 と呼び、その認識を 『偶然的真理』 と云った。ライプニッツがそこまで事実に直面していながら、なお偶然性の哲学へ進み得なかったのは充足理由律とキリスト教の思想に基づく優良の原理に煩らわされたためであろう。」
スピノザに見られるような決定論的立場でもなく、ライプニッツに見られるような弁神論的立場でもない、第三の「偶然と驚きの哲学」という立場に九鬼周造は立っている、ということになるでしょう。
2011年11月
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
M・スチュアート著
『宮廷人と異端者 ――ライプニッツとスピノザ、そして近代における神』
近代の黎明期、17世紀を代表する二人の大哲学者の対決のドラマを描く、異色の評伝風哲学史です。スピノザとライプニッツの人生と著作を交錯させて解釈しなおすことによって、「偉大な哲学はすべてその作者の個人的な告白であり、思わず知らず書かれた一種の自伝である」というニーチェの言葉を裏付けるような仕事になっています。「近代における神の運命」を賭け金とした、哲学という名のゲームの勝者はライプニッツかスピノザか。読者をまきこむ面白さをもった稀有な哲学書として、難解な哲学の原作にはあまり親しめない読者にも広くおすすめしたい一冊です。また、時代を変えるほどの力ある思想の真義を知るには、その思想が何と闘うなかから生れてきたのかを知らなければならないと考える方には特に面白く読んでいただける一冊と思います。
かたや「宮廷人」ライプニッツ(1646-1716)。豪勢に着飾って諸国の王権に接近し、手練手管を尽して高給を引き出しては、その富をもって全ヨーロッパを股にかけた各種の新事業に万能の天才ぶりを発揮せんと活躍する、究極のインサイダー。
かたや「異端者」スピノザ(1632-1677)。ユダヤ人コミュニティーから無神論の危険思想として破門され、間借り暮らしでのレンズ磨きを生業としつつ近代を切り拓く前代未聞の革命的哲学を鍛え上げる、不気味に自足した賢者。
ライプニッツは誰よりも正確にスピノザ哲学という新思想の意義を理解しながら、既存のヨーロッパ的秩序に対するその危険性ゆえに、スピノザの哲学を深く憎悪しています。憎悪とはいってもライプニッツはスピノザ哲学の核心を半ば我がものとしており、否定しようとするほどに否定し得ないものとしてつきまとうスピノザ哲学との葛藤をエネルギーとして運動している――このようなライプニッツ哲学の姿を本書はいきいきと描き出しています。膨大な未邦訳のライプニッツ文書を渉猟して、従来ない大胆なスタイルで生身のライプニッツを初めて描いた、リアリティある哲学史です。
ライプニッツといえば「モナド」ですが、いったいどこからあんな考え方が出てくるのかという疑問は第一にあってしかるべきものです。本書に引用されているライプニッツの書いた言葉、「まさにモナドによってこそ、スピノザ主義は破壊されるのです。(……)もしモナドがないとしたら、スピノザが正しいことになるでしょう」という言葉に明示されているように、「モナドロジー」はスピノザ哲学との対決そのものとして読むべきだという立場を本書は鮮明にし、我々がそう考えるべき事情を詳細に説いています。「モナド」という考え方を不可解なものと感じている人は、一つの明快な答えが与えられたように思うことでしょう。
一方で本書は、ライプニッツ哲学という「保守的・反動的」な対抗者を通して見ることによって、スピノザ哲学がもつ「革命性」の真義、近代的理性の可能性の中心を際立てる仕事にもなっています。スピノザファンはスピノザへの敬意をさらに重ねることになるでしょう。また、スピノザの主著を読破するのに困難を覚えている方々には、スピノザ哲学を駆動している力というものを感じとるよすがとなるでしょう。もう大分以前からほとんど全ての著作が広く親しまれ、専門研究も相当に深まっているスピノザに対して、ライプニッツの場合は残されたテキスト原文の完全な整理・公刊もまだ果たされておらず、本書も「新しい情報の提示」という側面ではライプニッツのほうに重みがあります。しかし、本書の著者自身が、「スピノザの哲学の解釈に関して私はどのような独創性も主張しない。しかし、読者は気づくだろうが、定説とは違うところを強調している」と述べるように、本書の新しいライプニッツ像を通じて立ち現われる、反転したライプニッツの姿としてのスピノザ、言わばヴァージョンアップされたスピノザ像も一つの問題提起となっています。
本書は2006年の刊行後すぐに、その読ませる面白さを高く評価されました。本書紹介の別ページに各メディアにおける書評の断片を紹介してありますので、あわせてご覧下さい。(上掲書影からリンク先ページへ)。
また、本書の冒頭部分をPDFファイルでご用意しました。ここのリンク先ページでご覧下さい。
垣内松三著 『垣内松三著作選 国民言語文化とは何か』 を刊行いたします。(2011年10月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『垣内松三著作選 国民言語文化とは何か』 刊行にあたって (書肆心水)
垣内松三 (かいとう・まつぞう 1878-1952) の名は、かなり年配の国語教育関係の方々を除いて今では知る人もごく少ないことでしょう。垣内松三は国語教育の方法として 「センテンス・メソッド(全文法)」 を提唱し、また国語研究全般にわたる多くの著作を通じて、その時代の国語教育界と学会に大きな影響を与えました。解釈学の流れを汲み、「形象理論」 を提唱したその仕事は、学校における国語教育の範囲にとどまらない、言語思想としての大きな広がりを持っています。その仕事の特徴を一言で述べれば、「国学の可能性の中心を近代的に再理論化するもの」 と言えるでしょう。
不誠実な言葉による社会崩壊の危機が限界に達し、空疎な、しかし盛装した虚言が横行する今、そして戦後以来の転換期と目される今、垣内松三の言語思想は(再)発見されるべきものと当社は考え、ここに主だった著作をとりあげて著作選を刊行いたします。風土・歴史・生活によって結晶された言葉の実相を探り、初等教育から哲学まで、世阿弥、宣長から漱石まで、国民言語文化の諸問題と方法論が示されます。
垣内松三の主著 『国語の力』 は1922年の初版以来広く読まれ、1936年には第四十版が刊行されています。その 『国語の力』 の巻頭には次の言葉が掲げられています。
雪片を手にしてその微妙なる結晶を見んとする時掌上に在るものは一滴の水なり。
水滴を分析して結晶の形象を見んとするが如きは今の国語・国文学習の態度なり。
言語文学の本質を研究せんとせば先ず直下にその微妙なる形象を観ざるべからず。
そしてその四半世紀後、戦後ほどなくの1947年に刊行された第二の主著 『国語の力(再稿)』 の巻頭にも、ほぼ同じ言葉が掲げられています。
雪片を手にしてその精巧な結晶を見んとする時掌上に在るものは一滴の水である。
水滴を分析して結晶の形象を視んとするがごときは今の言葉の考察の態度である。
言葉の本質を把捉せんとせば先ず直下にその微妙なる形象を観なくてはならない。
この喩えの核心にある 「言語の形象性」 について、著者は次のように語っています。
形象作用は 「こころ」 と 「ことば」 とを繋ぐ作用として顕わすことができるのであるが、「こころ」 と 「ことば」 とは繋がれるものであって、これを 「繋ぐもの」 は 「繋がれるもの」 に先行しなければならぬ。理会作用はこの結晶の力である。しかし 「繋がれるもの」 なしには 「繋ぐもの」 を知ることはできない。嘗つて謂ったように、雪片を手にして、その微妙なる結晶を見んとする時、掌上に在るものは一滴の水である。もし雪片の微妙なる結晶を視んとせば、直下に観取しなければならないのである。水滴を分析して微妙なる結晶を見んとするごときは、「形象」 と 「理会」 との真相に参入するものではない。風土と歴史によりて結晶せられたる言葉の実相はこの全機を参究するのでなければ把握することはできない。
この 「言語形象性」 の理論が、宣長をはじめとする国学の 「まこと」 の精神といかに重なっていて、そのような思想が唱える 「言語共同体における真実・信実・誠実の回復」 とはいかなることであるのか、それがこの著作選所収の論考において示されています。
和辻哲郎著 『和辻哲郎仏教哲学読本』 を刊行いたします。(2011年8月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『和辻哲郎仏教哲学読本』 刊行にあたって (書肆心水)
倫理学者、日本文化史・思想史家としてよく知られる和辻哲郎は仏教の哲学的考察においても優れた著作を遺しており、本書はそれらに気軽に接していただくための「読本」を意図したものです。和辻のなかで仏教哲学の研究がどのようなところに位置づいていたのかについて、本人は次のように語っています。(本書所収「仏教哲学の最初の展開」より)
「去る昭和二十九年の末ごろに、わたくしは渡辺楳雄氏から『有部阿毘達磨論の研究』という分厚い著書の寄贈をうけ、少しく繙読しているうちに、かつて阿毘達磨論について抱いていた関心が、勃然として蘇り、燃え上がってくるのを感じた。その関心というのは、もう三四十年も前のことになるが、どうかして仏教哲学の展開のあとを一通り承知しておきたいという希望のもとに、仏教の経典に親しんだおりに、おのずと湧き起こって来たものである。元来、仏教哲学へ眼を向けたのは、そのころ初めて手をつけた日本の思想史の研究に際して、日本のすぐれた思想家を理解するためには仏教哲学の理解が前提とならなくてはならないということを痛感したせいであったが、さて接近してみて驚いたのは、西洋の哲学が教会からの独立によって近世の顕著な発達をひき起こし、同時にまた理解しやすい哲学史の成立を可能にしているのに反して、仏教の哲学がまだ教会から独立しておらず、従って信仰の立場に煩わされない哲学史もまだ成立しておらないということであった。そこでやむを得ずにわたくしは根本資料としての経典に親しみ、いろいろと瞠目の思いをさせられたのであったが、その最初のものは、阿含やニカーヤの経典によって知られる原始仏教の哲学であった。五蘊、六入、縁起などの「法」の考察は、われわれの実践的存在の基礎を解明したものとして、実際に「さとり」の名に価するものであった。わたくしは驚嘆のあまりにその部分だけを『原始仏教の実践哲学』として書き、昭和二年の初めに刊行したのであった。が、そのころには、これほどまでに突き込んで現象の基礎にある法を見破った原始仏教徒が、そこからどうして大乗仏教の哲学の方へ展開して行ったかについて、何ほどかの探究の歩をも進めていた。……」
仏教哲学の論議においても和辻らしい精密な論理と鋭い洞察が発揮され、仏教をめぐる数々の常識が覆されてゆきます。和辻の仏教哲学研究の面白さの一つは、大乗と小乗――大乗以前の思想――の関係に見るべきは断絶というよりも仏教哲学の弁証法的展開であることを、精密な具体的論証により示したところにあります。大乗の「空」の哲学はそれ以前の仏教哲学の否定ではなく、それの脱構築、逆説的根拠づけとしてあるということが和辻の緻密な読みによって明かされてゆきます。読者はそこに原始仏教から大乗仏教にいたる生きた流れを感じとることができるでしょう。
なお、本書には日本における仏教の移入と展開を考察する諸篇や、和辻の仏教思想を理解するよすがとなる小説も収めてあります。
橋川正著 『綜合日本仏教史』 を刊行いたします。(2011年6月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『綜合日本仏教史』 刊行にあたって (書肆心水)
本書『綜合日本仏教史』は、いま最もポピュラーな日本仏教史の本である新潮文庫版『日本仏教史』(末木文美士著)の文献案内で「文化史的な視点から書かれた新鮮さをもつ」と紹介されている基本的研究書です。
文化的・政治的側面を重視した個性的な仏教史である本書は、「日本の仏教がいまこのようにあるのは何ゆえか」という問いによく答えるものであり、日本の仏教の今後のあるべき道を暗示しています。著者の橋川正は1894年生まれ、真宗大谷大学で日本仏教史と真宗史を研究したのち京都帝大の国史学科に入り歴史研究の幅を広げ、真宗大谷大の教授になってからは「仏教文化史」の方面で業績をあげ、『日本仏教文化史の研究』『日本仏教と社会事業』などを著わし活躍しましたが、不幸にして三十代後半で病歿します。本書は遺稿となった最終著作です。特色ある日本仏教通史として次代に継承すべく、現代的な表記にあらためて新しい版を刊行いたします。
ヘルマン・オルデンベルク著 『仏陀』 を刊行いたします。(2011年5月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『仏 陀 ――その生涯、教理、教団』 刊行にあたって (書肆心水)
ドイツのインド学者・仏教学者ヘルマン・オルデンベルク(1854-1920)によるブッダ研究の世界的古典、『仏陀 ――その生涯、教理、教団』 を刊行いたします。本書は、ブッダの歴史的存在と原始仏教の姿を文献的に立証した研究として1881年の初版以来名声を博し、数度の改訂を経て、英語版、ドイツ語版原典は今なおペーパーバックで読み継がれている記念碑的な名著です。日本では1910年に三並良の翻訳で註を省いた本文のみの版がまず刊行され、のち1928年に木村泰賢・景山哲雄によって註を含めた全体の翻訳が刊行されました。今回当社より刊行する版は、この木村・景山訳を底本とし表記を現代化したものです。
翻訳者の木村泰賢は本書について次のように紹介しています。
「オルデンベルク氏の『仏陀とその教理』は或る意味に於て原始仏教に関する標準的研究書である。初版出版以来すでに約半世紀を経ているに関らず――この間に数次の訂正増補を経たとはいえ――今なお斯学に関する最高権威を以て目され、ほとんど古典化の域にまで高められたものである。勿論、厳格に云えば、本書は最新の研究書ではないから、今日の立場からすればこの間に首肯し難き個所も尠(すくな)くはなく、かつ余りに批評的ならんことを期した結果として、冷静過ぎて却って皮肉と思わるる解釈もありて、少なくも個々の点からすれば吾等の賛同し難い所も決して尠くはない。しかしこれを全体として見れば、その体系に於て、解釈法に於て、問題の取扱方に於て、他の追随を許さぬ特長を具備し、あらゆる類書中、嶄然頭角を抜くものであることは争うべからざる定説である。かくて、この書は今や、その所説に従うか否かは別問題として、いやしくも原始仏教を研究せんとする人にありては、少なくも一と度びは必ず通過すべきの関門を以て目せらるるものとなったのである。」
また、本書はニーチェが読んで刺激されたブッダ論として、思想史上重要な位置を占める文献でもあります。「私はヨーロッパのブッダになるかもしれない。とは言っても、もちろんそれはインドのブッダとは対蹠的人物だろうが」と書いたニーチェと仏教の関係については種々の議論がありますが、事実関係として言えば『アンチクリスト』における仏教についての言及のほとんどが本書を踏まえたものであるということが研究者により指摘されています。(例えば、新田章氏著『ヨーロッパの仏陀 ――ニーチェの問い』、1998年、理想社刊)。
村上専精著 『仏教統一論』 を刊行いたします。(2011年4月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『仏教統一論』 刊行にあたって (書肆心水)
日本近代仏教学のパイオニアによる異色の総合的仏教入門を刊行いたします。本書の刊行によって、著者村上専精は真宗大谷派の僧籍を離脱せざるを得なくなったという問題の書です。諸宗派対立の視点をこえて仏教諸説の全体的構造を示す本書は、「八万四千の法門」をもつ仏教の森で迷わぬためのよきガイドブックです。
村上専精は日本の仏教研究に歴史的視点と批評的態度を導入し、東大インド哲学科の初代教授を務めました。月刊雑誌『仏教史林』を発刊して仏教史研究の端をひらき、本書のほかの主著として、最初の近代的な仏教史と評価されている『日本仏教史綱』を著しています。
本書は村上専精の『仏教統一論 第一編 大綱論』(1901年刊)の全文と、『仏教統一論 第二編 原理論』(1903年刊)序論と、『仏教統一論 第三編 仏陀論』(1905年刊)序論とを一冊にまとめたものです。『仏教統一論』は上記の三編に第四編教系論と第五編実践論が続くと予告されましたが、第四編が出ないままに第五編が刊行されたのは遥か後の1927年でした。村上専精とその『仏教統一論』という連作(の構想とその「挫折」あるいは「変節」)がもつ思想史上の意味については、現今の仏教研究の第一人者末木文美士氏の著書『明治思想家論(近代日本の思想・再考I)』第四章「講壇仏教学の成立――村上専精」に論じられています(2004年、トランスビュー刊)。
上記末木氏の論考の末尾を以下に引用して紹介させていただきます。
「……この問題は決して村上ひとりにとどまるものではない。アカデミズムの中の仏教学は、その後西欧からインド原典を扱う方法を導入し、やがて世界の最先端を進むようになる。しかしその一方で、その根底を支える既成教団の価値観そのものに触れることをタブー視し、その上部構造に甘んじることになる。そして、その重層構造の中に閉ざされ、世間の「常識」とかけ離れた世界の中に自らを閉じ込めることになる。それは過ぎ去った過去の問題ではなく、現在なお深刻な問題として継続している。村上の提起した問題とその限界は、過去に押し込めて過ぎてしまうには、あまりになまなましい問題をはらんでいる。」
内山完造著 『内山完造批評文集 両辺倒』 を刊行いたします。(2011年3月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『内山完造批評文集 両辺倒(りゃんぺんとう)』 刊行にあたって (書肆心水)
上海内山書店主人・内山完造の現地体験に基づく批評文集を刊行いたします。内山完造は大学目薬の海外出張員として1913年に上海へ渡航し、のち書店業に転身して上海内山書店を長く経営しました。魯迅らと親交を結んだ現代日中文化交流のさきがけとしてよく知られています。
本書は、内山完造のあまたある批評的エッセーのなかから「中国人的政治・経済感覚の古層」をめぐる話を選出して一書にまとめたものです。収録文は『両辺倒』、『生ける支那の姿』、『平均有銭』、『そんへえ・おおへえ』から選びました。『生ける支那の姿』に寄せられた魯迅の序文もあわせて収めてあります。
日本人は一辺倒だが、中国人は両辺倒だ――このように言う内山の「漫談」の数々は、波立つ時局的表層の下を流れる民族的心性の底流=「二本建て主義」というものの存在を教えてくれます。内山の話をきいていると、この「二本建て主義」のバランス感覚がもたらす安定感、言いかえれば中国的「安全保障」感覚の原理が、四千年の歴史を経た庶民感覚に根ざしていることがよくわかります。日中相互理解の一つのよすがとなることを願ってここに刊行いたします。
大川周明著 『マホメット伝』 を刊行いたします。(2011年2月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『マホメット伝』 刊行にあたって (書肆心水)
日本人初の本格的イスラーム研究者、大川周明の遺稿マホメット伝を単行本として刊行いたします。アジア主義の志士でありかつ宗教学者でもあった大川周明はイスラームの原点に何を見ていたか、それをこの遺稿により知ることができます。本作は、数あるマホメット=ムハンマド伝のなかでも臨場感に富んだ物語性ある筆致が魅力の一作です。伝統的研究を堅実に踏まえた学究らしい記述、および専門研究者の枠にとどまらない思想家ならではの総合的な構成に加え、今日の研究者ならば戒めるような小説風の語りも織り交ぜての、読ませる伝記となっています。現代人の感性からは遠く隔たった古代人の感性と行為がいきいきと表現された著述といえるでしょう。たとえば、《礼拝堂の門前で彼等を迎えたマホメットは言った。「でかした!君等の顔は勝利に輝いて居る。」 「貴方のお顔も」と言って、彼等は彼の足許にカアブの首を投げた。 》 というくだりをその一例としてあげておきます。
当社ではこれまでも大川周明の、あまり光があてられていない側面の著作を刊行してまいりましたが、かつてのように「如何わしい右翼」としてタブー視されることが少なくなってきた故か、大手・中堅の出版社でも大川周明関連の著作を扱う事例が目に付くようになってきました。大川のイスラーム研究者としての主著『回教概論』が2008年にちくま文庫に入り、近年そのイスラーム研究者としての姿もクローズアップされ、評価が高まりつつあるようです。昨年は気鋭のイスラーム研究者臼杵陽氏による、「大川周明とイスラーム」の論点を前面に出した新刊『大川周明』(青土社)が大きく話題になり、一般読書界における注目度がさらに高まったようです。この遺稿『マホメット伝』もまた「大川周明とイスラーム」というテーマを論じるうえで不可欠の一作です。ご関心の向きにご覧いただければと存じます。
西田幾多郎著 『西田幾多郎の声』 を刊行いたします。(2011年1月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『西田幾多郎の声 ――手紙と日記が語るその人生』 刊行にあたって (書肆心水)
本書は「手紙と日記という西田幾多郎自身の言葉をしてその人生を語らしめる」ことを企図したもので、手紙と日記とを分類することなく、選んだ全てのものを日付順に配列しました。研究資料ではなく読み物となるように選択しています。手紙と日記のほかに、読解の助けとなるものとして、1.西田が停年退官の時点で生涯を回顧した文章「或る教授の退職の辞」、2.家族関係図、3.主要人物紹介、4.年譜、5.著書目次一覧、6.宛名索引を附録しました。
「人生いつまでも心配苦労の絶える事がない。人生はトラジックだ。」――西田幾多郎(1870-1945)はその死の年、74歳1月2日の日記にこの言葉を記しています。たしかに西田の人生は、「これがあの人気哲学者の人生であったのか」と溜息の出るような数々の家庭的不幸に見舞われた人生でした。その手紙と日記には、個としての、友としての、父としての、そして師としての高潔な姿を見ることができるとともに、人間的弱さの自覚をも見ることができます。裏表のないその人柄がよくあらわれた数々の手紙と日記から、「人間西田」を親しく感じることができるでしょう。
本書の底本とした最新版の「西田幾多郎全集」(岩波書店刊)は、書籍自体に「新版」と記されてはいませんが、出版案内の広告では「新版 西田幾多郎全集」とうたわれている全24巻構成の版です。この最新版全集は新編集による全面改版の増補新訂版であり、手紙は大幅に増補されています。「収集した書簡を基本的にすべて収録する」という方針のもとに、新たに収集されたものに加えて旧版の編集方針により不採用となったものも増補されたと推察され、また旧版では部分的に秘されたか省かれたところも新版ではあらわされています。手紙の収録通数は、直前の旧版2855通に対し、最新版では4499通となっています(旧版は日記篇1巻、書簡篇2巻の構成、最新版は日記篇2巻、書簡篇5巻の構成)。本書には996通の手紙を採用しました。そのうち最新版で加えられた手紙は163通です。
新版全集(2009年完結)で収録通数1.5倍に増補された手紙のなかには、西田の新しい横顔が見えるものもあります。新版全集の書簡篇と日記篇は各巻1万円ですので、計7巻を7万円で揃えて個人所有するのは困難です。本書は個人で持てる書簡と日記のエッセンシャル版として製作・刊行いたしました。先般文庫版で刊行された西田幾多郎歌集を味読するよすがとしても最適かと存じます。
ワーエル・B・ハッラーク著 『イスラーム法理論の歴史』 を刊行いたします。(2010年12月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『イスラーム法理論の歴史 ――スンニー派法学入門』 刊行にあたって (書肆心水)
イスラーム研究の最先端を担うハッラークの主著である本書は、イスラーム登場初期から現在まで、厳密に原資料に即して法理論の歴史的展開と現代的課題を明快に示します。今なおジャーナリスティックな評論の域にとどまる日本のイスラーム文明論を革新すべき研究者の必読の書と言えるでしょう。
ハッラーク氏は1955年生まれですが、つとにイスラーム法学研究の世界的第一人者として高く評価されています。パレスティナ生まれの氏は、渡米して苦学し、驚くべき研鑽を積みあげました。イスラーム関連資料の所蔵北米随一といわれる図書館と当代一流の教授陣とで著名なマックギル大学(モントリオール)のイスラーム研究所教授職を経て、現在はコロンビア大学人文学部教授をつとめています。
本書の訳者はハッラークの出自に関して次のような評価をしています。――《ハッラークは、パレスティナ生まれという出自から、この世界の文化的組成について、十分な体験的素養を積んでいる。それに加えて彼がキリスト教徒であるという事実も、彼の分析を客観的、構成的にしている点を強調しておくべきであろう。おそらく彼がムスリムであったならば、複雑なウスール=ル=フィクフ〔法理論〕をこれほど明晰に分析することは難しかったであろう。深い共感と、鋭い探求心によって、異質の宗教的課題を、これほど客観的に祖述しえた例は、イスラーム研究において極めて稀なことなのである。少なくとも法理論の書として本書は、このような点でこれまで唯一の、最も傑出した例であるといいうるのである。 》
※本訳書の刊行に際してハッラーク氏からよせられた「日本語版への序文」より
現在世界の人口の五人に一人は、イスラームの教えを信じている。しかし東アジア、西欧に住むわれわれは、ムスリム、ないしは彼らの文化、宗教、歴史についてほとんど知ることがない。これははなはだ不幸な事態である。なぜならばムスリムの文明は、世界の歴史を構成する最も洗練された、重要な要素に他ならないのだから。人類の歴史における最も優れた制度や知識人たちはこの文明の許に現れ、育まれてきた。現在これらについて研究することは、欧米の文物、事績について研鑽するのに劣らない重要な事柄である。ただしイスラームの文化、社会についての嘆かわしい無関心は、メディアや十分な知恵を持ち合わせない学者たちの無知によって増幅されるばかりである。われわれの書店にはイスラームに関する書籍が満ち溢れているが、もっぱら否定的なものであり、そのほとんどが「イスラームの暴力」について言及している。とりわけシャリーア、つまりイスラーム法は醜い言葉になり下がり、政治的な事柄、両手の切断や女性に対する石打の刑と結び付けられている。おびただしい数の大衆向けの書物は、シャリーアを捻じ曲げて理解し難いものにし、過去におけるその原則や実践を現在の、きわめて政治化された現象と混同させている。
七世紀にイスラームが登場して以来、シャリーアはイスラームの文化、文明の中枢の役割を担ってきた。シャリーアとは何であり、それが何を代表し、具体的にどのような機能を果たし、いかに理論的な展開を示してきたかを弁えることなしには、過去、現在のイスラームを理解することは不可能なのである。今回優れた日本の学者によって翻訳された本書は、シャリーアのその後の展開を、つまりムスリムの法学者たちが彼らの法の理論的な基礎をいかに理解し、それに知的な解釈を加えたか、また彼らがある種の法的機能を果たしうる法的推論の方法をいかに考案したか、それはいかなる条件の下においてであったかといった問題について論じている。本書はまたいかに法理論が、その抽象的思考形態において、長い世紀にわたり変化、発展し続けたか、さらにそれが現代の植民地主義の手によっていかなる危機を蒙り、おびただしい変容を迫られたかについても指摘している。
本書は十数年前に出版されているが、今なおヨーロッパ、北アメリカにおいてこの問題に関する主要な教材たり続けている。すでにアラビア語やインドネシア語に翻訳されているが、近くロシア語も刊行される予定である。本書を通読することは、シャリーアが本来いかなるものであり、それが近い過去においてどのようなものであったかを理解するには、欠かすことのできないものである。未開拓のこの分野における本書の翻訳者黒田壽郎教授の貢献は、日本の読者たちにとって特筆に値するものと思われる。彼の知的な努力に深く謝意を表する次第である。
原田霊道訳著 『現代意訳 華厳経』 を刊行いたします。(2010年11月)
『現代意訳 華厳経 新装版』のページへ
.jpg)
『現代意訳 華厳経』 刊行にあたって (書肆心水)
華厳経は、井筒俊彦も重視して論じたように、仏教的世界観に関する最も重要な経典ですが、現代の日本では華厳の宗派は辛うじて東大寺に法脈を伝えるのみで社会的勢力に乏しく、華厳経の出版状況は他の主要経典に比べて不十分な現状です。
1935年に江部鴨村が公刊した華厳経の口語全訳版が、現在は国書刊行会より写真版複製の2巻本で販売中ですが、45,875円の高額商品のため個人で買うのは大変ですし、公共図書館にも稀にしか蔵書されていません。かつて、いくつかの章を部分訳した本が出版されましたが、それも今では多くが品切れとなっています。
このような状況にあって、原田霊道の本書は (原本が1922年刊行の古いものではありますが) 口語文による全34章の全体的抄訳であるという独自の価値を持つものとして、華厳経に親しもうとする方のお役に立つことと考えました。(本書では新漢字・新仮名遣い表記にするなどして、できるだけ読みやすくしてあります)。
富士川游著 『医術と宗教』 を刊行いたします。(2010年10月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『医術と宗教』 刊行にあたって (書肆心水)
空前絶後の大業績 『日本医学史』 で日本医史学を確立した富士川游がのこしたユニークで明快な宗教論、『医術と宗教』 を刊行いたします。
なぜ本書の主題が 《医学と倫理》 ではなくて 《医術と宗教》 であるのか。そこにこの著作のユニークな価値があります。近代的医療観と現代的状況を根本的に批判しうる類なき問題提起といってよいでしょう。
本書の立場を要約的にご紹介いたしますと、――
医療は最新の実践科学であると同時に、生命の救済行為でもある。他者を救うにあたっては、倫理/道徳の次元、つまり 《ねばならない》 の次元に立つだけでは、人間が本来もつ功利性の克服 ――《私》 を去ること ――は結局 《嘘》 にとどまらざるをえず、救済は十分に果たされない。一歩を進め、誰もが生得的にもつ 《ある種の精神状態=宗教》 に立つ時に、医療は生きる。
――こういったところになるかと存じます。
大川周明著 『敗戦後』 を刊行いたします。(2010年9月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『敗戦後――大川周明戦後文集』 刊行にあたって (書肆心水)
本書は、戦後(1945-)の大川周明(1886-1957)が雑誌に発表した文章を集めて書籍化したものです。国家再出発の思想、三度の刑務所生活および東京裁判のこと、石原莞爾や北一輝との思い出などが語られています。民間人としてただ一人東京裁判のA級戦犯容疑者となった大川周明が、敗戦後に何を考えたかに焦点をあてる企画です。頭山満も北一輝も既にこの世にいない敗戦後の日本に生き残ったただ一人の「巨頭」がいかなる敗戦認識をもっていたのかを知ることができます。
敗戦後の大川の認識は、戦前の日本は終ったのであるから必要なのは「救国」ではなく「立国」、つまりゼロ地点からの再建国であるというものでした。その認識に伴う思想の基本は、次の引用文に見て取れるように、国家再出発のためには国家の土台である衣食住を堅固にしなければならないというもので、大川はその思想に基づいて、農法改善による農村復興のための農村行脚を死に至るまで行ないました。
《2600年の日本歴史は、太平洋戦争の全敗によって不幸なる段落を告げた。国家の外形は、屋根は破れ柱は傾き、土台は崩れかけたままに残骸を留めて居るが、日本はもはや戦前の日本でない。このみじめな残骸は、亡国の廃屋である。その崩れかけた土台の上に残る廃屋を修膳してアメリカ風の文化住宅に改造しようとする自由主義者、一挙廃屋を叩きこわしてロシア風の家を建てようと焦る共産主義者、ないし戦前の日本家屋に復原しようと動き初めた日本主義者、総じてこれ等の「主義者」たちの努力は、所詮砂上に楼閣を築こうとするに等しい。砂上の楼閣でも、一時の雨露を凌ぐに役立つから、決して全然無用の骨折ではないが、一層大切なることは、新たに建てらるべき国家の礎を堅固に築き上げることである。》
結局は不起訴になったとはいえ、A級戦犯容疑者となった大川は、「大物右翼」として非難にさらされ続けることになりましたが、そうした事情について本人がどう考えていたかも本書に収めた文章のなかに見ることができます。以下、冒頭部分を少し引用して紹介します。
《世間は私を右翼と呼ぶ。時には右翼の巨頭などとも呼ぶ。右翼とは左翼に対しての言葉である。左翼とは何か。それは共産主義者又は社会主義者のことである。共産主義と最も極端に対立するものは何か。それは資本主義である。果して然らば資本主義者又は財閥こそ、まさしく右翼と呼ばるべきではないか。私は年少のころ社会主義に傾倒したことはあるが、未だ曾て資本主義や財閥を謳歌した覚えはない。従って私を右翼と呼ぶことは正当でない。
私は反共産主義者でもなく反資本主義者でもない。強いて云えば非資本主義者であり、非共産主義者であり、一層適切に云えば非主義者である。私は一切の「主義」なるものを奉じない。凡そ如何なる思想でも、主義としてこれを固執すれば、必ず世に害毒を流すようになる。主義とは人間の生活内容を統一するに適当なる立場のことである。人生は不断に流動して息むことを知らない。従って統一に適する立場も、また時により場合に応じて変らざるを得ない。事ある時は軍国主義、事なき時は平和主義、国貧しければ産業主義、国豊かなれば文化主義総じて個人又は国民がそれぞれの場合に応じて取捨する立場である。然るにそれ等の立場の一つだけを万古不易の真理なるかのように主張して自余一切の立場を排撃することは、頭脳のはたらきが器械的であること、また我執の強いことから起る。それ故に主義の標榜は常に一種の挑戦である。》
ラス・ビハリ・ボース著 『革命のインド』 を刊行いたします。(2010年8月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『革命のインド』 刊行にあたって (書肆心水)
中島岳志氏による評伝『中村屋のボース』によって一躍著名になった、ラス・ビハリ・ボース(Rash Behari Bose)の著作、『革命のインド』を刊行いたします。日本のアジア主義に多大な影響を与え、その視野を東アジアから広域アジアへと拡大させた中村屋のボースによるインド解放闘争の状況研究です。長い革命の転換点、《塩の行進》の頃、完全独立のために諸勢力をナショナルな一つの力に結集すべき状況が詳しく論じられています。
今なお先進権力国に引き継がれ繰り返される、《文明化のための嚮導》という愚劣の方法的原型を、当事者の視点から具体的に暴く研究です。本書原版刊行に際してのボースの思いを、序文より引用して以下に紹介いたします。
……大正五年四月の中旬まで中村屋の一室に閉じ籠って生活をした。その後頭山先生一派と、当時の政府との間に妥協が成立し、警視庁から、英国に知れない様に余を保護する事が約され、それから凡そ八年間、余は巡査に守られて、東京中を転々として蔭れた生活をしなければならなかった。その後は漸く自由になって、公然に活動が出来るようになった。一方から見れば、余に対する退去命令は余に苦痛を感じさせたのであったが、他方では、この退去問題のために日本人がインド問題に注意する様になった故に、これは不幸中の幸と云わねばならぬ。
その時以来、日本人中の多くの人はインド及びアジア問題を研究する様になり、更に興味を持ちアジア人のためのアジアと云う主義が日毎に拡がったのである。余としてはこの方面に日本人の同志と共に出来るだけ努力し、数年前に長崎及び上海に於てアジア民族会議を開き、絶えずアジア諸国の事情を日本に紹介して来た。そして昨年、万里閣から『革命アジアの展望』〔中谷武世共著『革命亜細亜展望』〕を出版し、昨年はインド文化を紹介する目的で厚生閣から『インド頓智百譚』を出し、今度、木星社よりこの書を出版することになった。
今日、極く少数の白人が多数の有色人を支配していることは不自然で天意に叛いている。この有様を変えて、アジアから白人勢力を駆逐することは、アジア人のみならず、人類に対する愛を持っている正義、人道、自由を崇拝する人々の急務である。インドがアジアに於ける白人帝国主義及び侵略主義の基礎である。この基礎を破壊することが出来れば――インドを英国の悪政から解放することが出来れば、始めてアジアに於ける白人勢力は根絶される故に、インド問題は特に日本人として研究の必要があると思う。その目的の下に、微力ながら余はここにインド問題を論じ、そしてこれに依って僅か一人の日本人だけでもインドに関する智識を得ることが出来れば、余としては光栄に思うのである。
ジャック・デリダ著 『境域』 を刊行いたします。(2010年7月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『境 域』 刊行にあたって (書肆心水)
デリダの名高い初期三部作、『声と現象』、『グラマトロジーについて』、『エクリチュールと差異』(三作とも原書1967年)にひき続いて、『哲学の余白』(原書1972年)から始まったデリダ円熟期における主著のうち、『撒種』、『弔鐘』とともに完訳出版が待たれていた、「デリダ流文学的哲学」の代表作とでもいうべき『境域』(原書初版1986年・増補新版2003年)がようやく刊行の運びとなりました。デリダの厖大な著作群の中で、特異な位置を占める大著です。
この本はデリダの本格的ブランショ論です。かなりの量のブランショの作品の引用が織り込まれ、言葉に関する思索において最も遠くまでいったこの二人が、限りのない対話を交わしています。いまや全世界を完全に支配するに至った、アリストテレス以来のヨーロッパの思考を根柢からくつがえす、全く新しい言葉の経験がここにあります。
ブランショの本、とりわけそのフィクション作品はどうしてこうも「難解」なのか――。ブランショの批評作品の愛読者であっても、フィクション作品についてはそのような印象を抱く人が少なくないでしょう。どうも読み終えられた気がしない。無限の読解に巻き込まれてしまったような、近づくほどに遠ざかる感じ……。
実は、超人的な読書人であるデリダもまたそうした感じをもっているようで(つまりこの「感じ」はデリダほどの人でもそう感じるという性質のもののようで)、そしてその「感じ」をこそ問題の核心として、デリダはこのブランショ論を書いている――そう思わせるくだりが『境域』の序文中にあります。以下に引用してご紹介いたします。
これらの〔ブランショの〕フィクション――フィクションという名をそのままにしておくことにする――を私はすでに読んでしまったと思っていた。それらを研究し、長々しく引用し、この試論をあえて公表しようとする今日、私はそれらを読んでしまったとはこれまで以上に言えなくなっている。不適切にも文芸批評または哲学の領域に位置付けられているブランショの他の作品は、はるか前から私の歩みに付き添っている。それらが私にとって親しいものとなっているということではないが、少なくとも私はそうした年月のあいだ、ブランショの作品のうちに思考の本質的運動をすでに認めたと信ずることができた。しかしフィクション作品は、あたかもそこから魅惑的な、ほのかな光しか私には到達せず、そして時々、しかし不規則な間隙をおいてしか海岸の不可視の灯台の光が私までとどかないように、霧の中に浸っているかのように、私には接近不可能だった。私はそのような留保されたような状態から作品がついに明るみに出されたというつもりはない。まさに逆である。それらは、隠匿の形そのままに、接近不可能なものの遠ざかりそれそのものとして――なぜならそれらはそうした遠ざかりに名を与えることによって、それに直面しているから――再び私の眼前に現れてきたのだった。今や避けられぬ力、最も控えめな、したがって最も挑発的な力、憑依と確信の力をもって。真理なき真理の、これらの作品についてよく言われる魅惑を超えたところから来る命令の力をもって。こうした魅惑をブランショの作品は及ぼすのではなく、横断し、描き出すのであって、魅惑の力を使う、あるいは魅惑の力と戯れるよりは、魅惑の力について考えさせるのだ。
『岸田劉生美術思想集成 うごく劉生、西へ東へ』を刊行いたします。(2010年6月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『岸田劉生美術思想集成 うごく劉生、西へ東へ』刊行にあたって(書肆心水)
一連の「麗子像」で著名な岸田劉生が、画家の歩みを始めてから死に至るまでのあいだに書きのこした美術思想を二巻にまとめました。前篇の巻には劉生20代のものを収め、後篇の巻には劉生30代のものを収めました。
その画風の変遷に見てとれるように、劉生の美術思想は激しくうごきました。本書は、テクストを書かれた順に配列して、その思想の変遷をそのまま感じとれるようにしてあります。
子供の目には恐らく美しい絵とは思えないだろう「麗子像」の、一見気味の悪い美はいったい何事なのか。初期にはゴッホ、セザンヌのあからさまな摸倣で出発した劉生が、近代性の経験と西洋美の諸様式習得の果てに遂に目を開いたものは、中国や日本の伝統美がもつ「でろり」とした味、「卑近美」や「下品の美」、「隠された」美でした。
38歳の短い人生で激しくうごいたその美術思想は、日本人の画家としては質・量ともに抜群のもので、美術論にとどまらない、美から見た思想史的文明論となっています。38歳の短い人生とはいえ、劉生は30のときには既に手練の絵描きでした。激しいうごきのなかで強度に満ちた画家人生を送った劉生が「発見」した美、近代性を卒業した美とは何か。それは東洋への回帰なのか、世界史的進化なのか……。日本・近代性・美・文明、こうしたテーマにご関心の高い方々のための出版企画です。
前篇、後篇それぞれから、印象的なくだりを以下に引用してみます。
【前篇より】
――新しきものは概念より生れず、「心」より生るるものこそ永遠の新鮮なり――
世界中の画家が、変なものを描こうと苦心している時に、自分は、「美」を描こうと苦心している。
自分も初めは、変なものを描こうとした後ればせの(日本では初めの方の)一人だ。変なものと思っていた訳ではないが、しかしそういう風に描かなければ新鮮な力はかわらないと思っていた。アカデミックであるという事、平凡であるという事が恐ろしかった。だから物を普通見える様に描くのはいけないと思った。本当に美を見られなかったから、物をその通りにかけば、アカデミックになったのだ。こうして、変なものをかいた。真面目くさって、最も本当のものをかいている気で。しかし、変なものは結局変なものであった。そこに何となく落ちつきがなかった。自分の居所があたたかでなかった。そして段々と、その誤りを知った。
自分は美を知った。そして凡てが氷解した。自分の人生観も光を得た。自分は幸福である。自分は美を知ったら、物を、そのままで見ない人の気がしれなくなった。あんな美しいものを何故殺して、あんな変なものにするのか、ああ、それはあんな美しいものが、あそこに見えないからだ、という事も解った。
自分は新しい道に立ちもどった。自分はこの道がいつかは、世界中の美術の病気をすくう先がけになる事を信じている。
【後篇より】
私は私の内にある民族的伝統を内から味わいそれを内から生かす事を知った。しかも私は欧風審美からそこに出発したのである。私は欧風審美からとるべきものは大ていとった。その眼で私は新しく、古い東洋を見て驚いたのである。かくて私は内面的に西洋と東洋との融合を私の仕事の上でかなり完全に有機的に成し遂げつつあるのを自認している。これは決して、外面から計画したのではなく、ひとりでになったのである所へ又或る力がある。
野上豊一郎批評集成 〈人物篇〉 『観阿弥清次 世阿弥元清』を刊行いたします。(2010年4月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
野上豊一郎批評集成 〈人物篇〉 『観阿弥清次 世阿弥元清』刊行にあたって(書肆心水)
「野上豊一郎批評集成」シリーズの続刊、〈人物篇〉を刊行いたします。(シリーズ発刊時のご挨拶はこちらのリンク先にございます。どうぞあわせてご覧下さい。)
能の完成者である世阿弥、そしてその父観阿弥。なにゆえにこの父子は空前絶後の存在であるのか。――能批評のパイオニア野上豊一郎が、役者でもあり、監督でも、作詞家でも、作曲家でも、理論家でもある人間だけが至りうる境地を発見し、また、世阿弥一辺倒に傾きがちな能論議をこえて、二人の関係性から「能とは何か」を明かします。
本書は、野上豊一郎の二つの人物批評作品『世阿弥元清』と『観阿弥清次』を「野上豊一郎批評集成」シリーズの〈人物篇〉として一書に括ったものです。能の「批評」において、なぜこの二人を、「その関係性」において考察する必要があるのか。『観阿弥清次』の序文冒頭には次のように記されています。――
十年前『世阿弥元清』を書いた時、実は『観阿弥清次』を先にすべきではなかったかとも考えた。というのは、世阿弥は能楽の完成者であり、その功績の偉大は、わが国芸術史上殆んど匹儔を見出さないほどではあるけれども、しかし、譬えていえば、それは父観阿弥の築き上げた堅固な基盤の上に打ち建てられた輝かしい楼閣の如きものであるから、発展史的には、世阿弥の功績について考えて見る前に、まず観阿弥の功績について考えて見るのが順序であるように思われたからである。事実、観阿弥の仕事が行われなかったら、世阿弥の仕事も行われなかったに相違ない。その意味に於いて、世阿弥の功績は観阿弥の功績の連続とも見られる。尤も、世阿弥の方は観阿弥から入って観阿弥を出たというようなところがあり、そこに彼独自の特色があったのではあるが。もっとはっきりいえば、観阿弥は「物真似」主義者であり、同時に「幽玄」主義者でもあったが、本質的には何といっても「物真似」主義者であった。しかるに世阿弥は「物真似」主義者でもあり、また「幽玄」主義者でもあったが、より多く「幽玄」主義者であり、且つその「幽玄」そのものを恐らく観阿弥の予想だにしなかったであろう境地にまで展開させたところに特色を発揮したのであった。こういうと、いかにも世阿弥の方がえらいようでもあり、世間一般もそういう風に評価しているのであるが、しかし、此処で慎重に考えて見なければならぬことは、此の世間一般に行われている評価の裏には、能楽が今日の状態にまで展開して来た径路を最上の発展を遂げたものとして無批判に肯定している点がありはしないだろうか。言い換えれば、舞台芸術の発展の可能をもっと根本から自由に考えて見て、世阿弥の行き方だけが唯一最上の行き方だったとするのは、果して妥当であろうか。それ以外にもっと別な行き方はなかったものであろうか。たとえば、世阿弥があれほど優越した智才と感性を働かして観阿弥の「物真似」主義を更に強引に真直に推し進めたとしたならば、或いは能楽は今日見るが如き形態とは異なった別の形態のものとして発展して行ったのではなかろうか。それはどっちがよかったかは簡単にはきめられないけれども (……)
この続きは本の詳細紹介の別ページに掲載しております。
『高村光太郎秀作批評文集 美と生命』(前篇+後篇)を刊行いたします。(2010年3月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『高村光太郎秀作批評文集 美と生命』刊行にあたって(書肆心水)
前篇(1910年27歳より1939年56歳まで) 後篇(1939年56歳より1956年73歳まで)
彫刻家として、あるいは詩人として高名な高村光太郎は、非常に多くのエッセイ類を書き遺しています。それらの多くは芸術家高村光太郎一流の審美感覚を通して綴られた、「批評」の名に値するものであり、流行り廃りを超えた場所で自立しています。
この批評文集には、高村光太郎の数多ある批評文の中から、「美と生命」をメインテーマとし、かつ話題がごく一般的で文章表現も平明であるものを選定いたしました。よって個別の作者や作品を限定的に論じるもの、とりわけ専門的傾向の感じられるものは選んでおりません。各篇の配列は、本選集のモチーフとなった最晩年の一篇「生命の創造」を巻頭に掲げ、それ以外の全ては発表の年月順としてあります。
芸術の起原は生命そのものへの驚異感にほかならず、神に代ってこれを人間の手でつくり出したいという熱望が、ついに「芸術」を生み出した。――この根本思想から派生する「美と生命」をめぐる約百篇の批評文で高村の人生と思想を辿る文集、そういう本にいたしました。時期としては欧米留学帰国後から死の直前まで、論点としては衣食住から社会・自然まで、どなたでも身近にお感じになるだろう話題を精選しました。また、略年譜の付録はもちろんのことですが、キーワード索引も付録して検索の便宜をはかりました。
|
|
本文集のモチーフとなった「生命の創造」の一篇を別ページにご紹介しております。 |
山田孝雄 著 山田国語学入門選書(4)『敬語法の研究』を刊行いたします。(2010年2月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
山田国語学入門選書(4)『敬語法の研究』刊行にあたって(書肆心水)
近代日本語学に屹立する不滅の巨人、山田孝雄(よしお)の学問世界を紹介する「山田国語学入門選書」の第4巻をお届けいたします。本選書の既刊は(1)『日本文法学要論』(2)『国語学史要』(3)『日本文字の歴史』です。選書刊行時のご挨拶はこちらに記してございます(ここのリンク先ページへ)。
この第4巻は、日本語の一大特徴である「敬語使用」を、「山田文法学」のシステムに位置づける仕事で、題して「敬語法の研究」です。山田文法の最終版『日本文法学要論』(山田国語学入門選書1)において体系化されている三大論点(語論・位格論・句論)を縦糸に、敬語の種別を横糸に織り上げられた敬語法の構造が示されます。「語論・位格論・句論」がそれぞれ「単語・連語・句の組織」という節構成として立てられて、そこに「敬称・謙称」という敬語の二種別が交叉するという形式で論が構成されているといってよいでしょう。
山田のとなえる「敬語の法則」とは何であるかは本書がその全体をもって縷々叙述することですのでそれはさておいて、ここでは「敬語の法則」を探究する本書成立のモチーフとなっている二つの話をご紹介いたします。この二つの話に感ずるところおありの方ならば、本書の繙読は意義あるものとなろうかと存じます。
第一。日本語で主語が省かれがちなことは広く知られています。「ごもっともです。」という言葉は、「あなたはごもっともです。」とか「あなたのご意見はごもっともです。」といった意味を表わす標準的な言い方として昔も今も通用しています。山田は「敬語の法則」を探究するにあたってこの点にまず注目しています。
第二。山田は本書の冒頭において、敬語は尊崇の意をあらわすために限らず、親愛の意をあらわすためにも、また言語に品格あらしめるためにも用いると述べて、次のような実例を紹介しています。森鴎外が自身の訳書『ノラ』(大正2年・警醒社書店刊)の訳文について述べた意見です(『敬語法の研究』よりの引用)。
博士森林太郎氏がその訳せるイプセンのノラの中にノラの夫がクログスタツトに謂ふ詞として「わたしは君にお帰なさいと云はなくてはならぬ」といへるに対して或る評者が「お帰なさい」は丁寧にすぐるによつて「帰れ」といふべしといへるに対して次の如くいへることあり。――「併(しか)し私の『お帰なさい』と書いたのはノラの夫がクログスタツトを尊敬してゐていふ敬語でない。ノラの夫が自ら尊敬して言ふ敬語である。日本語には自家の紳士的地位のために賤しむべきものに対しても使ふ敬語がある。どうもノルヱイ語に通じてゐる評者には日本語に対する理解が乏しいやうに思はれてならない。」
アッ = タバータバーイー著 『現代イスラーム哲学――ヒクマ存在論とは何か』(黒田壽郎訳・解説)を刊行いたします。(2010年1月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『現代イスラーム哲学』刊行にあたって(書肆心水)
20世紀最高水準のイスラーム哲学を、アラビア語原典からの翻訳でお届けいたします。
「我々は、そして万物は、全てが差異的であり、全てが等位にあり、全てが関係的である」――このイスラームの根本的な思想を存在論的・哲学的にきわめてゆく学問分野は「ヒクマ(叡智の学)」と呼ばれてきました。本書は、長い歴史を持つイスラーム哲学の到達点である現代の成果を簡潔に纏めるかたちで、最も核心的な主題を扱ったものです。イスラーム世界では極めて高い評価を得ており、ヒクマを学ぶ入門書と位置づけられています。英訳版は2003年にThe Elements of Islamic Metaphysicsという書名で刊行されました。
著者のムハンマド・アッ=タバータバーイーは20世紀最高位のイスラーム哲学者と評価され、シーア派教学の総本山(イランのゴムの神学校)において研究と教育活動に従事しました(1892生~1981歿)。主著は厖大なクルァーン解釈書『秤の書』です。モッラー・サドラーの浩瀚な主著『四つの旅』の校訂・注釈の仕事もあります。
本書の論議の基本となっているのは、モッラー・サドラー(16世紀後半のイラン哲学者)が提唱した《存在の優先性》論です。その要点は井筒俊彦訳・解説の『存在認識の道』として1978年には邦訳出版がなされていますので、イスラーム思想に親しまれている読書人の中にはお読みになられた方も多いことでしょう。(岩波書店イスラーム古典叢書、のち中央公論社版井筒俊彦著作集第10巻)
モッラー・サドラーの《存在の優先性》論、そしてそれを解説するアンリ・コルバンや井筒俊彦の論は、イスラーム哲学として当然のことながら、《大文字の存在》つまり唯一の絶対者を主とする観点からのものでした。それに対してこのタバータバーイーの著作の注目すべき点は、モッラー・サドラーが切り開いたヒクマの探究がすでに三世紀あまりを経た現在、その問いの立場を、「絶対者・創造者の観点」ではなく、「被造物の観点」に切り替えているところにあります。つまり、《私》を含めこの世に存在するものは、「誰か、あるいは何か」というかたちで、たとえ卑小ではあってもまぎれもない実在のリアリティーを担っていますが、その《個別的な存在者》の側からの観点による問いの立場がとられているということです。
本文の論議は一読了解という類のものではありませんが、イスラーム文明を総体として最深部から探究し続ける訳者・黒田壽郎氏が、詳細な解説篇と適宜の註釈を附して道案内をいたします。(黒田壽郎氏の研究歴を紹介するインタビュー記事を掲載してあります。●ここのリンク先ページでご覧下さい)
イスラーム関係の新刊がごく稀であった20年前に比べますと、現在は次々とイスラーム関係書が刊行され、ずいぶん豊かな読書環境となりました。しかしイスラームの哲学的思想の側面について見れば、20年前とあまりかわっていないようです。大文明をその深みから理解するためには、哲学的思想からのアプローチも重要でしょう。ギリシャ思想・キリスト教を淵源とするヨーロッパ文明のみならず、インド仏教文明、中国儒教文明のことを思ってみてもそれは明らかではないでしょうか。大文明イスラームについてもこのような角度からの探究が欠かせないだろうと考え、本書がそうした探究に寄与する一冊としてお読みいただけることを願っております。
大川周明 訳・註釈 『文語訳 古 蘭(コーラン)』(上・下)を刊行いたします。(2009年12月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『文語訳 古 蘭(コーラン)』刊行にあたって(書肆心水)
宗教学者にして精神主義の論客・大川周明ならではの、リズム・風格・力強さある文語訳、そして充実した註釈で味わうコーランです。聖書では根強い人気のある文語訳ですが、コーランでも文語訳を楽しめる唯一の日本語版として世におくります。
ムーサーは「モーゼ」、イーサーは「イエス」、マルヤムは「マリア」、シャイターンは「サタン」……というように聖書でお馴染みの表記がされており、イスラームに親しみのない読者にも違和感なく読めるかと存じます。
大川の訳文のスタイルを現在代表的なふたつの翻訳と比較してみましょう。(2章208節)
●大川周明訳・『古蘭』
「汝等信者よ、徹底してイスラームに入れ。サタンの足跡を追ふ勿れ。げに彼等は汝等の公敵なり。」
●三田了一訳・『日亜対訳・注解 聖クルアーン』・日本ムスリム協会版
「あなたがた信仰する者よ、心を込めてイスラーム(平安の境)に入れ。悪魔の歩みを追ってはならない。本当にかれは、あなたがたにとって公然の敵である。」
●井筒俊彦訳・『コーラン』・岩波文庫版
「これ汝ら、信徒の者、みんな揃って平安〔訳註:回教の信仰を指す〕に入れよ。決してシャイターン〔訳註:サタン〕の足跡を追うでないぞ。彼こそは汝らの公然の敵であるぞ。」
大川の翻訳には豊富な註釈が本文の各段落末に挟み込まれており、上記の部分に対応しては次の註釈が施されています。――
「(1) 『徹底してイスラームに入れ』といふは、猶太教的色彩を払拭せよとの意味と思はる。同教神学者は猶太人にして回教に帰依せる者が、尚ほモーゼの律法の一部を守る者ありしによつて此の啓示ありと言ひ、ロッドウエルはメヂナの信者中に猶太人の律法の一部を守らんと欲する者ありしためならんとせり。いづれにもせよ此の一段は猶太人又は猶太教の影響に対して信者に警告せるものとすべし。但しベルは『徹底して』又は『完全に』を『全体挙りて』の意味に解し、信者に対して一致和合を求めたるものとなせり。」
本の詳細紹介ページのほうに大川の訳者序文を掲載しておきました。あわせて御覧いただければと存じます。(この記事冒頭の書影のリンク先ページへ)
野上豊一郎 著 『野上豊一郎批評集成/能とは何か』(上・下)を刊行いたします。(2009年10月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『能とは何か』刊行にあたって(書肆心水)
今はもう新刊書店の棚では売られていないようですが、『能の話』(岩波新書・1940年初版)というよい入門書があります。ごく基本的な知識をバランスよく総合的に提供するという、かつて新書に求められた役割をよく果たした名著であると思います。著者は野上豊一郎。漱石門下生の英文学者で、野上弥生子の夫です。英文学の方面よりも能の研究で多くの仕事をのこしました。岩波文庫『風姿花伝』の校閲者でもあります。
下記の引用文は『能の話』の序文の最後のあたりから抜き出したものですが、この著者が批評精神に富んだ人物であることをお感じいただけるだろうと思います。(新漢字・現代仮名遣いに変えて引用します)
《……私はそういった問題をも考慮に入れながら、これから能の話をしようと思うのであるが、その前に、私は誰を相手に話そうとしてるかについてことわって置かねばならぬ。
私は能を日本の文化の産んだ最も卓越した物の一つとして考えている。その卓越の程度は、日本の文化を十分に世界的になし得るほどのものであると確信する。だから、私の話は日本文化史の展開に役立った民族的特質を抽出することを目的として、しばしば世界文化史との対照をも問題とするであろう。それ故に、私の話しかけたい相手の人は、そういった問題に関心を持つ人であってほしい。
しかし、能はいかに卓越した芸術表現であっても要するに過去の産物であるから、それを真にわれわれの今日の生活の中に価値あるように生かすためには、何とかしなければならないであろう。それをばどうすればよいかということに考慮を費して見たいと思うような熱情の所有者に私は話しかけたいと思っている。
だから、私の話しかけようとしている人は知識人でなければならない。ところが今日の実状から見て、そういった知識人には能をあまりよく知らない人がある。中には全然知らない人さえある。能は通人たちの賞翫に独占されていると思って、たとえば骨董いじりをする人間たちに対する反感の如きものを持って、それを見ようともしない人が少なくない。また、能は今でも貴族や金持の慰み物に過ぎないかの如き思いちがいをして、恐れをなして近づこうともしない人がある。(……中略……)能は古いものではあるけれども、新しい所もある。古いといえば世の中に古くないものは一つもない。古いとか新しいとかいうことは相対的のことで、問題は良いか悪いかである。能が良い芸術であるならば、新しい良いものを心ざす人は、古い良いものをも知って置かねばならない筈である。
だから、そういった反感や偏見や躊躇をば振り捨てて、われわれは、われわれの先祖の作った此のすぐれた芸術について見て行きたいと思う。それには上に述べたような無準備の障碍もあると思われるから、私は能をまだ知らない人を相手に予想して話を進めようと思う。能をよく知っている人には迷惑であろうが、しばらく我慢していただきたい。通人に至っては、私は初めから問題にしていない。》
この野上豊一郎は、能に関する多くの著書・編著をのこしましたが、その中で主著三部作と目されているのが、『能――研究と発見』『能の再生』『能の幽玄と花』の三冊です。このたび当社が刊行いたします『野上豊一郎批評集成/能とは何か』は、この三部作収録の全論文を入門篇/専門篇に再構成し、各巻においてさらにテーマで分類(役者論・奥義論・構成論・様式論・面論・謡曲論)したものです。現在の読者に親しみやすいように表記は新漢字・新仮名遣いとし、曲名索引を付加しました。曲名索引の項目数は290にのぼりますので、一般に「能二百四十番」といわれることに照らして考えるに、野上の研究が歴史の深みにもよく分け入っていることが分かります。
本書の目次・著者紹介などは、本の紹介ページのほうをご覧下さい。論調を感じていただけるように、いくつか引用もご用意してあります。
夢野久作 著 『夢野久作の能世界――批評・戯文・小説』を刊行いたします。(2009年9月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『夢野久作の能世界』刊行にあたって(書肆心水)
夢野久作の熱心なファン以外には余り知られていないようですが、夢野久作は能に親しみが深く、喜多流謡曲教授でもありました。本書は夢野久作がのこした能に関する著作群から、特に優れたものを、ジャンルを問わず精選した、「夢野久作一流の能案内」です。第一部・「能とは何か」、第二部・「喜多流とともに」、第三部・「能と人びと」、第四部・「小説」の構成となっております。
ちょっと怪しげな魅力あふれる能のいい話の数々です。能のことをよく知らなくても「あのノロノロした舞台劇」というイメージがあるだけで充分面白く読めるユニークな能入門でもありますし、夢野久作ならではの文化・文明・芸術批評ともなっています。玄人のかたにもめずらしい面白みを感じていただけるのではないかと思います。例えば次のような話。
▼私の師匠である喜多六平太氏〔十四世〕は、筆者にコンナ話をした事がある。「熊(漢音ゆう)の一種で能(のう)という獣が居るそうです。この獣はソックリ熊の形でありながら、四ツの手足が無い。だから能の字の下に列火が無いのであるが、その癖に物の真似がトテモ上手で世界中に有りとあらゆるものの真似をすると云うのです。『能』というものは人間が形にあらわしてする物真似の無調法さや見っともなさを出来るだけ避けて、その心のキレイさと品よさで、すべてを現わそうとするもので、その能という獣の行き方と、おんなじ行き方だというので能と名付けたと云います。成る程、考えてみると手や足で動作の真似をしたり、眼や口の表情で感情をあらわしたり、背景で場面を見せたりするのは、技巧としては末の末ですからね。
ついでにもう一つ。
▼弓を弾く人は知って居られるであろう。弓を構えて、矢を打ちつがえて、引き絞って、的にあたった音を聞いてから、静かに息を抜くまでの刹那刹那に、云い知れぬ崇高な精神の緊張が、全身に均衡を取って充実して、正しい、美しい、且つ無限の高速度をもった霊的リズムのうちに、変化し推移して行く事を、自分自身に感ずるであろう。能を演ずる者の気持ちよさはそこに根柢を置いている。能の気品はそうした立脚点から生れて来るのである。
こうした「能」のあらわれは、格風を崩さぬ物の師匠の挙動、正しいコーチと場数を踏んだスポーツマンのフォームやスタイルの到るところにも発見される。……否、その様な特殊の人々のみに限らず、広く一般の人々にも、能的境界に入り、又は能的表現をする人々が多々あるので、そうした実例は十字街頭の到る処に発見される。
千軍万馬を往来した将軍の風格、狂瀾怒濤に慣れた老船頭の態度等に現わるる、犯すべからざる姿態の均整と威厳は見る人々に云い知れぬ美感と崇高感を与える。その他一芸一能に達した者、又は、或る単純な操作を繰り返す商人もしくは職人等のそうした動作の中には多少ともに能的分子を含んでいないものは無い。
筆者をして云わしむれば人間の身体のこなしと、心理状態の中から一切のイヤ味を抜いたものが「能」である。そのイヤ味は、或る事を繰返し鍛錬することによって抜き得るので、前に掲げた各例は明かにこれを裏書している。
ひっきょう「能」は吾人の日常生活のエッセンスである。すべての生きた芸術、技術、修養の行き止まりである。洗練された生命の表現そのものである。そうして、その洗練された生命の表現によって、仮面と装束とを舞わせる舞台芸術を吾人は「能」と名付けて、鑑賞しているのである。
●余談● 夢野久作の作品世界、精神世界を深層からとらえるうえで、たぶん彼の父親・杉山茂丸の存在を避けて通ることはできないでしょう。当社では杉山茂丸の主要著作を刊行しております。ついでにご覧いただければ幸いです。
●『百魔(正続完本)』の紹介ページ
●『俗戦国策』の紹介ページ
●『其日庵の世界(其日庵叢書合本)』の紹介ページ
吉田東伍 著 『地理的日本史読本』を刊行いたします。(2009年8月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『地理的日本史読本』刊行にあたって(書肆心水)
本書の著者吉田東伍は、いまなお高く評価され続ける不朽の業績、未曾有の大辞典『大日本地名辞書』を独力で編纂し、「地名の巨人」と讃えられる歴史地理学者です。本書は、その吉田が、おのおの読みきりの 61 話で日本通史を試みたユニークな日本史読本です。
「時代」「人間」「場所」が揃って初めて歴史はリアルになるという立場から、場所すなわち地理的事情が人の思惑と歴史の流れる方向を規定する様を語った、日本歴史地理学の開拓者ならではの仕事であり、地理的イメージで日本史の大きな流れをつかむことができるように構成されています。歴史理解において「時」と「人」が抜け落ちることはまずないでしょうが、「場所」は、抜け落ちるとまでは行かずとも、その具体性が軽んじられて、抽象的な歴史観に陥ってしまうことはままありがちです。それは、「いつ誰それと会う」という約束ごとがあって、「何処で会う」のかが抜けているようなものと言えましょう。
これらのことについて、著者は序文に次のように記しています。
▼歴史を学ぶ者は、絶えず年月、場所、人物についての観察を怠ってはならぬ。すべて歴史事実は、この三要素から成り立つものであるからして、これが研究は最も必要とするところである。例えば、何年何月に起った事件であって、関係した人々は何某であるという事が分っても、その場所が分らなくては事実は完全に判明しない。(……)
▼日本史の全体をこの筆法で説き試みようという事はなかなか困難な事業であるし、とうてい小冊子にまとめ難いのである。よって史上の重要な事件を選定して、これを地理学を土台にして観察することにした。内容は重複を避けて、論題の範囲を広く求めた。政治、軍事、経済、文学とあらゆるものを取って、これが解釈を試みたのである。(……)
▼歴史事実の連絡という事には重きを置かず、一章一章の読み物としたのであるが、いやしくも日本史を一度読んだものが見れば、おのずからその連絡は取れるのである。もししからずとも、この書を一読すれば一貫した歴史地理の思想は得られることと思う。
『真善美――西田幾多郎論文選』を刊行いたします。(2009年7月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『真善美――西田幾多郎論文選』刊行にあたって(書肆心水)
人みな誰もの問い「真善美」。西田哲学はどう考えたか。
――真・善・美を論題とする西田幾多郎の論文選集を刊行いたします。
「絶対矛盾的自己同一」「行為的直観」「場所的論理」等々、にわかには親しみにくい論題が多い西田哲学ですが、本書は、誰もが日々考えている問い「真」「善」「美」をテーマにした論文で構成した、もうひとつの西田哲学入門です。
本文中のキーワードを枠外下段に大量に抽出して索引化することによって、本文 → 下段見出し → 索引 → 別の箇所の同じ/あるいは類似する文脈の本文へ、という参照関係を活字化して、書物をハイパーテキストとして活用するための便宜をはかりました。
当社の西田幾多郎論文集、第6弾です。
加藤咄堂 著 『味読精読 十七条憲法』を刊行いたします。(2009年6月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『味読精読 十七条憲法』刊行にあたって(書肆心水)
本書の著者、加藤咄堂(熊一郎)は、20世紀前半に仏教・儒教・道教などの東洋思想を土台とした道徳・宗教思想の啓蒙家として活躍した人物です。出版書籍は200点以上にのぼり、最盛期には年間200回以上の講演を行ない、難解な思想や古典を平易に説き示して人気を博したと伝えられています。十七条憲法を解説する本書もその仕事のうちの一つです。
いま現在、「十七条憲法」「憲法十七条」の文言を書名に掲げてその解説を主とする単行本は、十七条憲法の知名度の高さ、そして聖徳太子論の出版点数の多さに比べると意外なほどに少なく、新刊書店で入手できるものは、花山信勝著『聖徳太子と憲法十七条』(1982年発行、大蔵出版刊)、岡野守也著『聖徳太子『十七条憲法』を読む――日本の理想』(2003年発行、大法輪閣刊)くらいのようです。
加藤咄堂によるこの「十七条憲法解説」の特色は、儒仏道の三教に詳しい加藤が、憲法中の語句の典拠となったと考えられている中国古典の文章などを引用紹介しながら、憲法中の字句の意義を解説し、おのおのの条文の意味するところを分かりやすく示している点にあります。したがって本書は、著者が十七条憲法を論じながら著者自身の思想を語るといった趣旨のものではなく、漢文で記された憲法条文の文意を精解し、それにまつわる事情を紹介するという趣旨の著作です。仏教を軸としつつも、儒教をはじめとする中国諸思想の影響も色濃い十七条憲法の解説に、加藤の素養がよく生かされています。
十七条憲法を聖徳太子の作とすることへの疑問は江戸時代からすでに生じており、現代の古代史研究の進展によってもその疑問は解決していませんが、日本書紀に記されている十七条憲法という文書が、統一王権国家構築期の朝廷において主体的に記された、日本最古の理論的政治思想文書として存在している事実はゆらぎません。
十七条憲法は、統一王権国家としての日本の出発点における指導的な政治思想・道徳論が整理されて示された、当時の他の文書に類を見ない稀少な史料であり、特定の歴史段階に属する専制君主制の官僚倫理論であるとともに、時代と政体をこえて評価され続ける超政治的宗教哲学の相をも持った文書といえるでしょう。換言すれば、それが書かれた時代状況を証言する文書であるにとどまらず、その後現在にいたるまでその思想が命脈を保ち続けている、日本思想史の個性的な重要文献です。
本書は1940年に発表された文章であるため、その口調と論調にやや古めかしい感じを受ける憾みはあるものの、十七条憲法の入門的解説書としての本質的価値は古びていないと考えてこのたび復刻いたしました。
中江兆民 著 『楽読原文 三酔人経綸問答』(併録『中江兆民奇行談』)を刊行いたします。(2009年5月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『楽読原文 三酔人経綸問答』刊行にあたって(書肆心水)
中江兆民の著作『三酔人経綸問答』(1887=明治20年、集成社書店刊)は、近代日本がその出発点において抱え込んだ葛藤をうまく表現した名作として広く知られていますが、その原文は下に掲げる画像のようなもので、いま現在の我々にとっては実に読みにくいものとなってしまいました。その近づきにくさを憂えた桑原武夫・島田虔次の両氏によって現代語訳が1965年に岩波文庫本で出版され、以後、『三酔人経綸問答』がどんな作品であるのかを知りたい人の大多数は、この両碩学による現代語訳を読むこととなりました。
ところで、翻訳というものは、それがいかに読みやすく、また文意を正確に伝えるものであっても、原文の味わいを伝えることは難しいものです。その文章が理論的な著述であるにとどまらない場合は、特にそう言えるでしょう。また、時代や作家の個性が文章表現に色濃く反映している、あるいはそれを読み取るべき作品の場合はなおさらです。
本書は、『三酔人経綸問答』をできれば原文で読みたい、ただ、あまり苦労してまで原文で読みたいとは思わない、という読者のための「楽読原文」版です。「楽読原文」とは、楽に読める原文というほどのつもりの造語ですが、文字づかいや句読点の表記を変えることなどにより、「原文」と呼べる範囲内でなるべく読みやすくしようと試みたものです。ひと言でいえば、「声に出して読んだら原文と同じ」だが、表記が違うということです。原文とどう違うのかが気になる読者のために付録資料として原文も収録しました。「楽読原文」の組体裁見本は、本の詳細紹介の別ページに掲載してあります(上掲の書影画像のリンク先ページへ)。
併録の『中江兆民奇行談』(岩崎徂堂著)は逸話集ですが、わが陰嚢を引き伸ばして杯となし、芸者に一杯のませたという戯れ事から、真剣な政治的諷刺としての奇行までが記されており、伝記的史料のきわめて少ない兆民の人物像を察するうえで貴重な文献です。
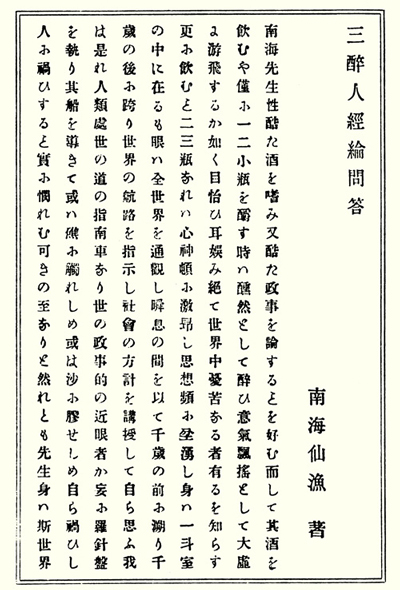
山田孝雄 著 山田国語学入門選書(3)『日本文字の歴史』を刊行いたします。(2009年4月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
山田国語学入門選書(3)『日本文字の歴史』刊行にあたって(書肆心水)
山田国語学入門選書の第3巻です。山田国語学入門選書および著者山田孝雄については、この下の記事(前回の記事)に紹介してあります。
この巻は、(1)日本人の心性と不可分の書記システムがもつ歴史性、(2)文法論や文章論からでは分からない文字づかいから見える日本語の特異相、(3)漢字導入に伴って構築・自覚された日本語、そしてそこから生れた万葉仮名というものが持つ革命性を検証するものです。「漢字+かな」表記はなぜ生れたのか、なぜ我々はそれを使い続けるのか、この問いへの答えと、その答えに至るための道すじが示されています。
狭義の日本語研究分野のみならず、日本のグラマトロジーとでも称すべき批評分野、また書道学にも役に立つユニークな一書と存じます。
山田孝雄 著
山田国語学入門選書(1)(2)
(1)『日本文法学要論』 (2)『国語学史要』 を刊行いたします。(2009年3月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
山田国語学入門選書(1)『日本文法学要論』(2)『国語学史要』刊行にあたって(書肆心水)
山田孝雄(よしお、と読みます。1875生~1958歿)の業績は、日本三大文法(ないし四大文法)の一つ「山田文法」として著名なもので、日本語文法論に関心の高い方にはよく知られるところですが、一般の方にとっては、時代の隔たりもあって、名前はきいたことがあるかどうかといったところではないでしょうか。山田孝雄は文法学を第一の仕事としましたが、その仕事の範囲は文法学にとどまらず、時代としては古代から現在まで、領域としては広く文芸・文章表現全般にわたっており、その学問の広さと深さはぬきんでたものと言ってよいでしょう。広義の《国語学者/日本語学者》の名に相応しい数少ない人物のうちの一人です。全著書の量は二万余ページにのぼると言われ、文法学上の主著二冊はそれぞれ千ページをこえるもので、また浩瀚な三巻本の『万葉集講義』の仕事もあり、谷崎訳源氏物語の校閲を依頼され担当したという話からも分かるように、まさに本格派の国語学者でした。
現在では日本語文法論もまた他の学問同様、大いに進化し、精密化していますが、そのいっぽうで山田のような大学者がもっていた「一人においての総合性」とでもいった包括的な豊かさこそがもたらす根源的な思想性からは離れていく傾向が否めないようです。このたび刊行を始めました「山田国語学入門選書」は、文法学、日本語学の専門家ではないけれども日本語に関心があり、とくに日本思想史の一面としての言語論に関心が強く、「日本語の成り立ちについて、確かな人の著述によってひと通りのことを、そして要点についてはしっかり理解したい」と考えるような読者を想定して出版するものです。最初の二冊は、山田文法の「要」と、日本語学の歴史の「要」を示した著作です。ともに「要論」ながら、碩学ならではの総合性と有機的議論に魅力があり、ポイントがつぎはぎしてあるだけのような入門書とは趣きが違います。
各巻の内容紹介、書誌、組見本などは別途設置のページに記してあります。上掲の書影のリンク先ページでご覧下さい。
山田が仕事をした時代は、日本が近代化に邁進した時代であり、西欧の学問の輸入と適用が盛んであった時代ですが、語学もまたその流れのなかにありました。日本語のどの部分が普遍的な理法でとらえうるものであり、どの部分は固有の理法でなければとらえられないかを考え始めた時代といえるでしょう。言い換えれば、「国語学」の時代から「日本語学」の時代へと変わっていく過渡期の、少し前ということになるでしょうか。「主語・述語」式の理解が日本語にとって本質的なものであるのかどうかという問題も山田文法学の一つの大きな論点になりました。昨今、「主語を抹殺した男」として再評価の高い三上章の仕事の要点も、山田を先駆者として、その延長線上にあるものと見られています。
文法論における山田の代表的成果は、「《は》が主格の助詞である」とする説を克服して、《は》という語の本質を、本居宣長が説く「かかり」の本質を読み破ることからつかみ、そこから日本語における表現の本源的な力(陳述の力)を見出したことに見ることができるといってもいいでしょう。山田自身が『日本文法学要論』において、「……日本文法の研究に殆ど半生を捧げたのであるが、その動機は『普通国語学』という書〔教科書〕に「は」を主格の助詞としてあったことにあり、その「は」が主格を示すものか否か、係ということは如何なるものかということに自分の研究の出発点があり、その係ということが確認せられた所に自分の研究の到着点があったのである」と記しています。この点、具体的にはどういうことかを、断片的ですが、『日本文法学要論』より引用して紹介いたします。(なるべく読みやすいように表記を多少現代化してあります)
●「は」という助詞は、いわゆる係詞 (かかりことば) である。「かかり」というは本居宣長の唱えた術語で、私がそれに基づいて係助詞という名目を立てたのである。その係りということの意義は本居も明言しては居ない(……)
鳥が飛ぶ。 (イ)
鳥は飛ぶ。 (ロ)
鳥が飛ぶ時 (ハ)
鳥は飛ぶ時 (ニ)
●(ハ)(ニ)の場合に「が」と「は」とは同じ作用を呈して見ゆるか否か。(ハ)の場合には多少物足らぬと思わるるが、それはこれから下にあるべき説明の語が未だあらわれないからであることは勿論だが、しかし、「が」の助詞の作用として見た場合にはそのままで十分なので、不満足の感は決して無い。これは如何なる理由によるかというに、この場合には「が」の勢力は「飛ぶ」という語に及ぶだけに止まって、時という語以下には決して及ばないからである。即ち「が」は主格を示すものであるから、その主格たる「鳥」の相手たる「飛ぶ」に関係を結べば、それでその役目が果されたので、その外には無関係であるからである。(主格の本質、随って主格の相手が何であるかということも従来の説明では不十分である。次項に説くから、ここでは立ち入っていわぬ。)即ちその関係は(ハ)の場合では既に十分に果されているからである。それ故に「鳥が飛ぶ時に空気が動く」「鳥が飛ぶ時にその姿勢を見給え」などと云っても「鳥が」と「飛ぶ」との結合はいつも同様でかわらないのである。然るに、(ニ)の場合には「鳥は」といういい方に対して「飛ぶ時」というだけでは収まりがつかない。即ち、ここには「飛ぶ時」ということをふみこえて、「飛ぶ時」にどうするかとか、どうなるかというような問いを発せねばならぬ勢いを呈している。即ちここには「飛ぶ時」といういい方で収まりがつかないので、「は」に対して或る陳述、或る説明を要求することは明らかである。即ちこの場合に、それに対する説明が無いならば、それは未だいわないのか、若しくは省略していわないのか、そうでなければ片言であるといわねばならぬ。(……)
●主格につくということは本質的のことでは無く、「は」が上にあるときにはいつも下に陳述が来なければ、収まりがつかぬということが考えらるる。かように考えて来てはじめて「は」という助詞は主格を示すということを本質としているものでは無くて、その本質は一定の陳述を要求する点にあるということが明白になるのである。本居が「係り」と云ったのは実にこの意味であり、「結び」と云ったのはそれに対する一定の陳述を云ったのである。(……)
●今日でもまだ、「係り」というのは結びの活用形を変形さする事柄をさすのであると考えているような人も往々見ゆるようであるが、さような人は「ぞ」「こそ」に対して口語では普通の終止を用いるから係りなどいうものは既に亡びたなどと思っているようである。しかしながら、さような人は外形しかわからぬ人であるといわねばならぬ。
『リオタール哲学の地平』を刊行いたします。(2009年2月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
本間邦雄著『リオタール哲学の地平』刊行にあたって(書肆心水)
初の本格的なリオタール論が本になりました。著者の本間邦雄氏は、パリ第八大学でリオタールに学び、リオタールの著作数点を翻訳出版しています。「ポストモダン」の哲学者として知られるリオタールが1998年に亡くなってからもう十年にもなり、かつての「ポストモダン・ブーム」といった流行現象も昔の話となった感がありますが、リオタールの哲学は、そうしたジャーナリスティックな際物思潮と共に忘れてしまうのに相応しくありません。
絶対的判断基準なく、それぞれがそれぞれの正当性をもって対立する《抗争》の時代。――既成のシステムを反復するのでもなく、不毛な対決を繰り返すのでもなく、《文》を連ね延ばし転成させていくことで新たな地平をひらく道を模索したリオタールの哲学が、本書の著者へと連接し、さらに新たな地平がここにひらかれています。
現象学、マルクス主義から視覚芸術、精神分析までを論じ、ドゥルーズ、デリダらの哲学との対話のなかで同時代の世界情勢に応答しつつ展開されたリオタールの哲学。本書は、前期リオタールの《リビドー的身体》と後期リオタールの《情動-文》をキーワードとしてリオタール哲学の多様な論点を横断する、リオタール哲学と著者との対話の書です。著者の論調は穏やかで堅実なものですので、「いわゆる現代思想論には関心もあるし重要なものとは思うが、煽るような気取ったスタイルのものはどうも苦手だ」というような方にもお読みいただけるものと存じます。
目次、各章の内容梗概は、本の紹介ページのほうに記してあります。序にご覧いただければ幸いです。
『生田長江批評選集 超近代とは何か 1・2』を刊行いたします。(2009年1月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『超近代とは何か』刊行にあたって(書肆心水)
◎第1巻 新と旧……新事物崇拝イデオロギー批判
◎第2巻 信と善……宗教性・解放主義・性差別論の審問
日本初のニーチェ全集を個人完訳で果たした生田長江(1882-1936)の「本業」は文芸批評、社会批評でした。本書『超近代とは何か』は、生田の「超近代」をめぐる批評文を集めたものです。「超近代」「近代の超克」というテーマは大きな広がりをもった、長期に持続している問題設定ですが、生田の立場の特徴は、日本において最も早い時期にこのテーマで社会・文芸批評を書き連ねたところにあり、《国家主義に堕する前の初期「超克派」》ということができるでしょう。「超近代」「超克派」については、反動的な逆行に過ぎないと見る向きが少なくないようですが、実際のところそうした「悪」や「愚劣」に還元されるべきものなのかどうか?――本書はその点に早くから自覚的であった、元祖超克派からの回答です。
生田の批評文の書きぶりは、今現在から見れば「大雑把」な感じは否めないものの、それだけに却って根本的な論点は何であるかが明瞭に示されてあり、また、個人の思想として確かに生き抜かれたものであるために、個々の論点がバラバラではなく相互に結び合うものとして見えるというメリットがあります。
収録文章のタイトルは本の紹介ページのほうに記してあります。
*
なお、ご関心ある向きのために、同時代の哲学者三木清が生田長江を評した言葉を引用しておきます。
《私は遂に生田長江氏と面識を得る機会をもたなかった。氏の文章は当時一介の文学青年であった私の中学時代からずいぶん愛読したものであり、後に私が哲学をやるようになった原因にも氏のニイチェ紹介の影響などが含まれている。近年は氏の思想の跡に近く接して行くことはできなかったが、いま氏の死によって種々の思い出が甦って来る。
生田氏の仕事は甚だ多方面に亘っている。氏は評論家として最も知られているようであるが、評論のほか氏は詩も作り、劇も作り、小説も書いた。またそのニイチェ全集の翻訳は日本文化史上に、永く記念さるべき業績である。氏は文学者にして思想家であった。これは我が国では類稀なることである。真の文学者はつねに同時に思想家であるとすれば、生田氏はまことに文学者らしい文学者であった。氏の評論は文明批評家的眼光をもって貫かれ、終始人生の根本に相渉るという厳粛な態度を持している。
氏は文壇というものから離れて存在し、文壇というものに対して寧ろ意識的に反抗的であった。これは氏のあの宿命的な病気にもよるであろうが、また自ら恃むこと極めて厚い氏の性格にも基くであろう。第一流の人は手心なく痛烈に、第二流の人々は努めて同情をもって批評するというレッシングの態度が批評家の心掛でなければならぬと氏は後進に向って教訓した、と佐藤春夫氏は書いている。氏は氏のいわゆる「文壇家」を嫌悪した。文壇的でないということにおいて、生田氏はその私淑していた鴎外、漱石などと軌を一にしている。ところが文学者の仕事として永続的価値を有するものはそのような文壇的でない人々の仕事に意外に多いのである。これはこの頃の文壇的なあまりに文壇的な文芸家たちにとって、また思想家などにとっても考えてみるべきことであろうと思う。文学者にせよ、思想家にせよ、先ず必要なことは自己に忠実であるということである。
けれどもこのことは決して彼等が社会と没交渉であることを意味しない。評論家や哲学者の偉大さの資格は、何か大きな問題を提げて立つということである。生田長江氏の場合にしても、氏の最も華々しい活動が展開されたのは、ちょうど日本の文壇や思想界が自然主義から人道主義へ移って行った時代であり、氏の活動もまたこれに相応している。生田氏は単に自然主義者でなかった、氏のうちには遥かに強い人道主義的要求があった。しかし純粋に理想主義的な人道主義者となるにしては氏には自然主義的要素が多かった。我が国の人道主義はやがて或る人々において著しく社会的関心を示して来たが、その頃の生田氏の批評的関心も文芸から社会にまで拡大された。『徹底人道主義』『ブルジョアは幸福であるか』等は当時の氏を記念する評論集である。氏は堺利彦、大杉栄両氏などに接近し、友愛会主催の社会問題講演会において演説したこともあった。しかし日本の社会思想がやがて明瞭にマルクス主義へ移って行くに従って、生田氏は次第にアナーキスチックな、ニヒリスチックな傾向を濃厚にして来た。それと共に氏は我が国の文芸及び思想における従来の指導的地位から退くに至った。(後略)》
三木清著「生田長江氏」より抜粋(新漢字新仮名遣いに変更)
ニイチェ著『文語訳 ツァラトゥストラかく語りき』(生田長江訳)を刊行いたします。(2008年11月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『文語訳 ツァラトゥストラかく語りき』刊行にあたって(書肆心水)
世界中で広く愛される近代古典中の古典、ニーチェの『ツァラトゥストラ(Also sprach Zarathustra)』が日本で初めて完訳出版されたのは1911年、森鴎外の序文を附した生田長江(いくた・ちょうこう/1882-1936)の訳書でした。同書はまた、ニーチェの和訳単行本の嚆矢でもありました。生田長江はその後、個人完訳で、日本初のニーチェ全集を刊行します。1916年から1929年にかけて全10巻の新潮社版が、そして新訳決定版というかたちで全12巻の日本評論社版が1935年から翌年にかけて出版されました。
生田は『ツァラトゥストラ』の最初の翻訳を二度改訳しましたが、一度目の改訳版の序文においてこのように述べています。――「『ツァラトゥストラ』の私の最初の訳本は、1909年の初夏に起稿され、凡そ二十箇月近くに亘る文字通り専心の努力を経て、1910年の暮に脱稿されたのであった。それから十年を過ぎた今年の三、四月頃になって、私は別に誰からも強いられない、のみならず、勧められさえもしない『ツァラトゥストラ』の改訳を、寂しい心持の中にひとりでこつこつとやり出した。そして殆んど以前のより以上のとさえ云いたいほどの苦心に苦心を重ねて来て、丁度今、この改訳本の最後の頁を書き上げたところである。」
そしてその序文の結びに、「……それを訳出する上に口語なる現代語の一体が、ただに上乗の物でないのみならず、むしろ甚だ不便なるものであるということだけは、私の敢て断言するに躊躇しないところのものである。」と記されているように、生田長江はこの『ツァラトゥストラ』という作品の翻訳においては、文語調を選択的に採用したのでした。
生田個人完訳のニーチェ全集は、いまでは歴史的存在としての意味しか持ち得ないものとなったでしょうが、生田訳『ツァラトゥストラ』だけは例外的に、その文語調という訳文のスタイルの故に、いまなお、否、今後長く特異な意義を持ち続ける文化遺産であると言えましょう。
「かく語りき」の文言がいかにも相応しいこの『文語訳ツァラトゥストラ』。作中の言葉である「血と箴言とをもて書くところの人は、読まるるをねがわずして諳(そらん)ぜらるるをねがう」という思想によくマッチする文語の調べ。――こうしたセンスに趣味を覚える好事家に向けて本書を世におくります。
モーリス・ブランショ著『アミナダブ』(清水徹訳)を刊行いたします。(2008年10月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『アミナダブ』刊行にあたって(書肆心水)
清水徹氏の全面改訳による、ブランショの長篇小説代表作『アミナダブ』を、単行本版として刊行いたします。(清水氏訳の『アミナダブ』は初め集英社版『世界文学全集』にジュリアン・グラック著『シルトの岸辺』と合冊というかたちで刊行され、のちに『筑摩世界文学大系 ベケット/ブランショ』にも収録されました)。
文筆家ブランショの仕事のうち「批評作品」は早くからたいへん高い評価を受け大いに論じられてきていますが、小説ないしフィクション作品(作家自身によりロマン/レシと区別されている両者)については今なお深く公に論じられることが稀であるようです。著名人による代表的言及としては、ミシェル・フーコーの「外の思考」やレヴィナスの『モーリス・ブランショ』所収論考がありますが、相当の紙数を費やしてブランショのフィクション作品を深く考察している著名人は今のところジャック・デリダただ一人と言っても差し支えないでしょう(デリダによるブランショ論の大作 Parages は若森栄樹訳『境域』として当社にて出版準備中です)。
ブランショにおける小説作品の位置づけについてはジョルジュ・バタイユの興味深い言葉が残されていますので、以下に引用して紹介いたします。このバタイユの言葉は、ブランショの代表作とされる第三評論集『文学空間』(1955)が出る前の時期のものと推定されていますから、その後いっそうの深まりと広がりと独自性を見せるようになるブランショの全批評活動を踏まえたものではないということになりますが、それでもそこに指摘されていることは、一つの本質的問題提起であると言えましょう。(1954年頃執筆と推測されている、遺稿からの発見文書。Gramma(1976)3/4 初出。訳文は『現代詩手帖』1978年ブランショ特集版、清水徹氏訳より。)
《モーリス・ブランショを、もっとも読まれているフランス作家のひとりに数えることはできない。彼の名声について語られるべきことといえば、文学の現況に通じている多くの人びとが、彼のうちに、現に活動中の批評家のうちでもっとも注目すべき存在を認めている、という以上を出ない。批評活動のほうは認められているとしても、彼の小説は読者の反感を買ったし、とくに、批評の側面と小説の側面とからなる彼の文学活動の全体的意味は、これまであらゆる人びとから理解されなかったとまで言える。」(……中略……)「彼の書く批評は、ときに唖然として言葉も出ぬほどの深まりを示す分析ぶりにどのような関心が注がれようと、彼の作品活動の二次的な、より接近しやすい側面にすぎない。》(ジョルジュ・バタイユ)
『中村屋のボースが語る インド神話ラーマーヤナ』
『シンフォニア・パトグラフィカ――現代音楽の病跡学』を刊行いたします。(2008年9月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『中村屋のボースが語る インド神話ラーマーヤナ』
『シンフォニア・パトグラフィカ』刊行にあたって(書肆心水)
ラス・ビハリ・ボースは、近年、中島岳志氏による評伝『中村屋のボース』によって一躍著名になりましたが、生前10冊ほどの著書を出版しています。1)インドの独立闘争をめぐる事情を紹介するものと、2)インド文化を紹介するものに大別されるそれら著書群のなかで、後者を代表する著作が本書です。来日したタゴールに励まされ、インド文化の紹介を志しての出版事業であったようです。ボースは、「一言にていえば、もしインドを知りたいと思われる方は、まず第一にラーマーヤナとその他の二、三の古典をお学びになるのがよい」と本書の緒言で述べています。
ラーマーヤナは、マハーバーラタと共に歴史の教科書に重要文化事項として記載されるインド古代文芸の代表作でありながら、今なお日本語全訳のない浩瀚な大叙事詩です。本書は、ボースが自身の思想も交えながらラーマーヤナを解説し、そしてその全編のあらすじをダイジェスト風に紹介する著作です。インドとの交流が進む今、知っておきたいインドの代表的古典ラーマーヤナの道案内として、インド人でありまた正義の闘士であったボースは最も相応しい人物の一人と言えるでしょう。(ボースの簡単な略歴は本書詳細ページに記してあります)
『シンフォニア・パトグラフィカ』は、クラシック音楽フリークである精神科医の小林聡幸氏(自治医科大学精神医学)が、病跡学(パトグラフィー)の立場から、現代音楽の作曲家たちを論じる著作です。病跡学あるいはパトグラフィーとは、芸術家などの創造性について精神医学やその周辺領域の知を使ってなにがしかの解明をなそうとする学問で、日本では宮本忠雄氏らによってその道がひらかれてきました。本書は現代音楽の創造者たちを病跡学の立場からまとめて扱った初めての本です。
20世紀クラシック音楽の作曲界を病跡学的に広く見渡したイントロダクションと、8人の作曲家を個別詳細に論じる8つの章の構成で、各章には音盤紹介も附されています。クラシック音楽愛好家によく知られた作曲家から、よほどの好事家でないと知らないような作曲家までを論じます。論じられるのは、ヤナーチェク、ロット、バルトーク、ランゴー、ペッテション、ナンカロウ、ツィンマーマン(B.A.)、シュニトケの8人です。
作曲家の「診断」ではなく、音楽作品からその創造者である作曲家の心、あるいは精神構造体としての作曲家の姿をたどること、そして精神医学に関心ある読者はもとより音楽を愛好する読者、音楽の「現代性」を通して20世紀という時代について考えてみたい読者に開かれたものであること――本書はそうした立場でまとめられています。
『日本哲学の黎明期』 『近世日本哲学史』 を刊行いたします。(2008年7月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『日本哲学の黎明期』 『近世日本哲学史』 刊行にあたって(書肆心水)
「開国」とともに始まった日本における「哲学」導入の風景を再現する二冊を刊行いたします。まだ150年ほどでしかない日本人と哲学のつきあいですが、その始まりはどんな様子で、どんな動機によるものであったのか?――いま現在の「哲学」イメージからは大きく隔たる当時の日本の「哲学」がもった日本思想史上の一大転機としての意義を理解させてくれる、二人の先人が遺した貴重な証言と研究成果です。
1)桑木厳翼著『日本哲学の黎明期――西周の『百一新論』と明治の哲学界』
本書は、桑木厳翼(1874-1946)の論文集ですが、著者生前にこの本自体が発行されたのではなく、著者生前の二つの出版著書『西周の百一新論』と『明治の哲学界』を底本として、その中から選んだ論文類を一書としたものです。選んだ文章は、本書の副書名に表現したように、1)「哲学」という訳語を考案した西周(にし・あまね)の業績と人物を紹介した文章、2)明治の哲学界の様子を紹介した文章、3)そしてこの二点に属する問題や話題を論じた文章です。著者自身が底本二冊のはしがき、あとがきで説明するように、底本の二冊にはそれぞれの本が主題とするところからやや離れた文章も少なからず収録されています。よって本書は、底本二冊それぞれが主題とするところの肝腎の文章を選び出し、新たに「日本哲学の黎明期――西周の『百一新論』と明治の哲学界」の書名を以てそれらを括ったという次第です。なお、本書の主題とした時代には括りえませんが、その後の展開の一風景でもあり、また著者の日本哲学界における位置を知らしめる貴重な記録でもあるものとして、著者が参加した国際哲学会議の報告類を附録しました。
著者桑木厳翼は帝国大学(後の東京帝国大学、現東京大学)でケーベル、井上哲次郎に学んだ哲学者であり、京都帝大教授、独・仏・英留学を経て東京帝大教授となり、日本のアカデミズム哲学の基礎を築いた人物です。カント研究の先駆者で、その認識論的合理主義の立場は西田幾多郎らの「京都学派」とは異なる「東京学派」とでも称すべき学風を持っていると言われています。
2)麻生義輝『近世日本哲学史――幕末から明治維新の啓蒙思想』
麻生義輝は若くして亡くなったこともあって(1901-38)、今ではほとんど知る人もない研究者だと思われますが、『西周哲学著作集』の編纂者でもあり、このテーマについては最も深く踏み込んだ研究者といっても過言ではないでしょう。丸山眞男が本書について遺した評言、「本書は日本の啓蒙哲学の形成を学問的に取扱った殆ど唯一のモノグラフィーとして永く学界に銘記さるべき労作である」、この言葉がそのことを明かしていると言えましょう。この名著を、活字を新たにし(新漢字・新仮名遣い)全文収録したものが本書です。副題の「幕末から明治維新の啓蒙思想」は本版の発行に際して説明的に付加しました。
この機に各研究室、図書室の蔵書として、貴重な遺産を次代に継承して下されば幸いです。
『地図から消えた国、アカディの記憶』を刊行いたします。(2008年6月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『地図から消えた国、アカディの記憶』(大矢タカヤス/ロングフェロー著) 刊行にあたって(書肆心水)
本書は、カナダ東海岸、ケベックとアメリカのはざまで英仏植民地争奪戦たけなわの18世紀に起きた大規模な「追放事件」に端を発し、今現在もその「記憶」が生き続けている「アカディ」という場所をめぐる問題に光をあてるものです。そのフランス系開拓民の強制追放はイギリス軍によって1755年から数年間続けられ、その結果、六千から七千人のフランス系開拓民、いわゆるアカディアンが、北米のイギリス植民地を初めとしてフランスやイギリス本国にまで追放されたと言われています。
アカディ、そんな国はどこにもありません。しかし自分がアカディアンである、その子孫であるという人は、一説では世界に300万人もいるのです。どのような経緯でそれらの人々が今や名前しか存在しない土地を故郷と思い定め、共通の絆で結び合っているのでしょうか。それに答えるためにはカナダ史の、日本ではあまり知られていない1ページを開いてみる必要があります。18世紀の半ばアカディと呼ばれていた土地からイギリス軍によって強制移住させられたフランス系開拓民たちの悲しい思い出が、一世紀のちにアメリカの詩人ロングフェローによって謳われ、この長篇詩『エヴァンジェリンヌ』が、カナダはもとよりアメリカ、ヨーロッパ各地に散りぢりになっていた子孫たちの心を強く打ったのです。
本書はロングフェローの作品『エヴァンジェリンヌ』を第一部とし、この『エヴァンジェリンヌ』に触発されてアカディの歴史を調査し、また現地取材も続けてきた大矢タカヤスによる「アカディの歴史」を第二部とする構成をとっています。
いまなお癒えていない植民地主義時代の傷、文学が歴史を動かしていく力、多言語主義と少数派言語権問題など、複合的な様相を示す「アカディ問題」にご興味をお持ちいただければ幸いです。なお、「アカディ」はフランス語で、英語では「アカディア」ということになります。
大川周明の二冊を刊行いたします。(2008年5月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『大川周明道徳哲学講話集 道』 『特許植民会社制度研究』 刊行にあたって(書肆心水)
松本健一氏をはじめとして最近の佐藤優氏、中島岳志氏にいたるまで、時々の評論家に評価され、論じられ続ける大川周明は、アジア主義者、日本主義者、宗教学者などの多様な論点を設定しうる人物で、「国家としての近代日本」という問題設定において、避けて通り難い人物です。
これまでも大いに論じられてきた大川ですが、今回当社から復刻する二冊は、これまであまり大きくはとりあげられてきていない大川の2つの側面にアプローチするための基本文献です。1つは客観的な歴史研究者としての姿を示す『特許植民会社制度研究』で、もう1つは大川の思想の根柢にある人格的な倫理思想を述べた『大川周明道徳哲学講話集 道』です。(『大川周明道徳哲学講話集 道』は、『人格的生活の原則』と『中庸新註』とを合本にして、新しい書名で括ったものです。)
『特許植民会社制度研究』は、吉野作造らを審査員とする法学博士号取得論文(大川40歳の時)ですが、その序文に次のようにあります。
「本論文の目的は、植民地統治の一形式たる、特許会社制度の意義及び価値を、植民史的事実に基きて明かにするに在り。しかしてこれがために、前後両期に於ける諸特許会社の重要なるものについて、その成立並〔ならび〕に事業を研究し、その各自の意義及び価値を検討したる後、全体としてのかくの如き制度に対して、植民政策的批判を与えたり。」
自身が満鉄東亜経済調査局編集課長であった大川周明が、植民会社というものをどのように考えていたのか? 大川周明についての理解を深めるうえでも、また過去の日本の植民政策を考えるうえでも参照する意味のある著作です。
『大川周明道徳哲学講話集 道』は、儒教的思想論という体裁をとりつつも、儒教に限らずインド哲学、イスラーム、西洋哲学の倫理思想についても知るところの深い大川ならではの「人格的な道徳哲学の原則」が示された著作です。大川は、東京裁判開廷の法廷において、脳梅毒による発狂行動を示したために裁判から除外されましたが、大川自身としては法廷で自身を弁護することを強く望んでいたことからしても、また著作に示された思想からしても、道理の闡明において何かから逃げるような姿勢はとらない人物と評価してよいと思います。
例えば性欲というものは、道徳論議においては曖昧で遠まわしな語られ方がされ、避けられることも多い難しい論点ですが、大川は本書において、性欲というものを自然法則の最も根本的な現象と位置づけたうえで、性欲と「恥」との関係について大いに論じ、「恋愛は、今日の学者がしたり顔に主張する如く、美しき仮面を被れる性欲に非ず、自然的性欲が精神化せられて高き情操となれるものである」というような判断を示しています。大川らの思想は「反科学的な精神主義」と括られて、近代化の文脈において非難されるべき思想と位置づけることがある種「常識」となっているわけですが、その「精神」というものが、実のところ、科学との関係においていかなる位置を占めるものであるかを、本書において感じ取ることができると思います。思想史の作業として「精神主義」の歴史性を定位するうえでも価値あるテキストです。
『大川周明道徳哲学講話集 道』収録の『中庸新註』には『中庸』の原文と読み下し文が併録されています。文庫本の『中庸』の原文には返り点がついていませんが、本書の原文には返り点がついていますので、ひとつの『中庸』読解入門書としてもご活用いただけると思います。
『入門セレクション アジア主義者たちの声』(全三巻)を刊行いたします。(2008年3月)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『入門セレクション アジア主義者たちの声』刊行にあたって(書肆心水)
3つの世代、3つのテーマ構成でアジア主義の流れと論点を構造的に把握する3巻構成です。ご関心に応じて各巻独立した単行本としてお読みいただけます。
■上■ 玄洋社と黒龍会、あるいは行動的アジア主義の原点
頭山満・犬養毅・杉山茂丸・内田良平 著
■中■ 革命評論社、あるいは中国革命への関与と蹉跌
宮崎滔天・萱野長知・北一輝 著
■下■ 猶存社と行地社、あるいは国家改造への試み
北一輝・大川周明・満川亀太郎 著
頭山満をはじめ、これらの名前は聞いたことがあるし、批評のたぐいは目にしたこともあるが、よくは知らない。自分の理解している日本近代史や東アジア近代史において、彼らは何かしら意味をもつだろうか。――このような関心をもつ読書人に向けて、彼ら自身の言葉によって彼らの思想と行動のアウトラインをつかむ縁となることを願って編集したのが、この選集形式の入門読本です。(入門書を意図しておりますのでこれらの著者の本を既にお持ちの方は収録文章の重複を各巻紹介ページの目次でご確認の上お求め下さい)。
この選集は、1)それぞれの人物のおよその姿、2)これら九人に代表されるような思想的政治的動向が、個別に見れば矛盾や背反を孕みながらも、全体として継世代的なひとつの流れをなしている様子、この二点をつかみとることを意図しています。このひとつの流れは、日本人の「行動的アジア主義」あるいは「在野型アジア主義」として特徴付けることもできるでしょう。「行動的」は「言論的・理念的」に対するものとして、「在野型」は「政府の国家運営」に距離を置くものとしての特徴です。このアジア主義にはさらに、彼ら言うところの「第二維新」という内政の変革が不可分に連動しているという特徴もあります。
収録する文章については主に以下五つの観点から選定することを旨としました。
◎ 各人の人格的思想が読み取れるもの。
◎ 各人の東アジア情勢の時局認識と、アジアないし東アジア復興の理念が表現されているもの。
◎ 各人の行動がどんな方面に特徴的であるかを示すもの(例えば、中国革命援助、藩閥勢力への介入、対朝鮮方面の行動などといった特徴)。
◎ 研究者的傾向もある人物については、どんな方面の研究を志向しているかが分かるもの。
◎ この選集が扱う人物相互の関係が記されているもの。
上巻 は「玄洋社と黒龍会、あるいは行動的アジア主義の原点」の括りにより、頭山満・犬養毅・杉山茂丸・内田良平の文章を収めました。この選集が扱う「流れ」における第一世代です。所属関係としては玄洋社、黒龍会に属さない人物もいますが、人間関係中心の結社横断的な協働においてなされた仕事を、玄洋社と黒龍会の名称で代表的に括りました。
●頭山満 1855-1944
●犬養毅 1855-1932
●杉山茂丸 1864-1935
●内田良平 1874-1937
中巻 は「革命評論社、あるいは中国革命への関与と蹉跌」の括りにより、宮崎滔天・萱野長知・北一輝の文章を収めました。この選集が扱う「流れ」における第二世代です。革命評論社の活動は短期間でしたが、ここで手を結んだ三人は中国革命に長く関与し、それについて最も意味ある文章を遺した人物であることから、革命評論社の名称を以てこの巻を括りました。
●宮崎滔天 1870-1922
●萱野長知 1873-1947
●北一輝 1883-1937
下巻 は「猶存社と行地社、あるいは国家改造への試み」の括りにより、北一輝・大川周明・満川亀太郎の文章を収めました。この選集が扱う「流れ」における第三世代です。北一輝の行動は中国革命と国家改造の両方に跨るため、巻においても二巻に跨りました。北一輝において「中国革命への関与から自国の改造へ」という、時代状況を踏まえたアジア主義実践課題の論点移動を見ることができます。北・大川・満川は猶存社の三位一体と呼ばれ、北との「決別」後に大川の思想を綱領として結成されたのが行地社です。
●北一輝 1883-1937
●大川周明 1886-1957
●満川亀太郎 1888-1936
この九人のごく主要な関係性を整理したのが下記の図です。最も強い協働関係にあるものが隣り合うように配置したものなので、図では接触していなくても大なり小なり交流や影響関係のある場合がほとんどで、本文の記述により読者において平面図表現の限界を補われるべきものです。
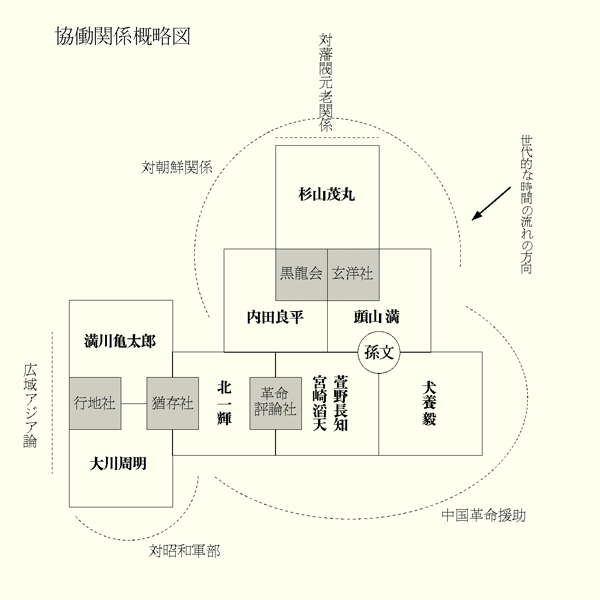
西田幾多郎論文選『種々の哲学に対する私の立場』『実践哲学について』を刊行いたします。(2008年1月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
西田幾多郎論文選『種々の哲学に対する私の立場』『実践哲学について』刊行にあたって(書肆心水)
当社では昨年秋に西田幾多郎の入門選集を「エッセンシャル・ニシダ」全3巻として刊行致しましたが、今度は、もう少し西田を読み深めてみたいという読者向けに、二つの論文選を刊行いたします。
「誰々論」という形のまとまった書物を遺さず、ひたすら自己の哲学を練り上げることに努めた西田の姿は、「エッセンシャル・ニシダ」収録の有名諸篇によく見ることができますが、一方で西田は、先行する種々の哲学者たちに対して自己の哲学をどのように位置づけているのか? これを明示する、最初期から最晩年までの論文を集めたのが『種々の哲学に対する私の立場』です。
《「デカルト哲学について」に於ては、種々なる哲学に対して私の立場を明らかにした。私の哲学に対して、種々の批評もあるが、異なった立場からの批評は、真の批評とはならないと思うのである》という西田最晩年の言葉に因んで、『種々の哲学に対する私の立場』の書名で括りました。
『実践哲学について』のほうは、従来の西田選集の類では全くとりあげられることのなかった、「実践哲学」関係の論文を集めたものです。実践と認識を二項対立的にとらえるような考え方、自己を世界の外に置く立場から、自己が世界の中にある立場への転換、あるいは観念論と唯物論をともにのりこえる「場所的弁証法」の哲学世界が示されます。西田が好んで口にした「物となって考え、物となって行なう」という謎めいた言葉は何を意味しているのか? 「我と物との矛盾的自己同一」「行為的直観」等、西田独自の概念によってそれを説く、長い論文三篇で構成しました。主体/客体二分法的論理をこえる「論理」を生涯探究し続けた西田哲学こそがなしえた「実践」概念の革新がここに示されています。
*「エッセンシャル・ニシダ」全3巻の紹介文はここのリンク先ページへ*
『波多野精一宗教哲学体系』を刊行いたします。(2007年12月)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『波多野精一宗教哲学体系』刊行にあたって(書肆心水)
波多野精一は、西田幾多郎の同僚として京大の哲学・宗教学講座草創期に活躍した、広い意味での京都学派の一員です。禅仏教系の色合いの濃い京都学派の宗教哲学のなかにあって、キリスト教をベースとした宗教哲学を展開した独自の位置を占めています。
西田幾多郎のように有名ではありませんが、お互いの仕事に対して、自己の仕事の意義を強く意識しあう関係だったようです。「波多野君の今度の本〔『宗教哲学』〕は非常に優れたものだ。しかしもう一歩先へ踏み込んで考えるべきところが残されている」という意味の西田の話し言葉が伝えられていると共に、「西田君のような学問は一夜漬けが出来るが、僕のはそれが出来ないよ」との波多野の話し言葉も伝わっています。今や知る人も少ない偉大な業績を現代に継承すべく、主著「三部作」と呼ばれる『宗教哲学序論』『宗教哲学』『時と永遠』を、「波多野精一宗教哲学体系」の書名で括って刊行いたします。
哲学と宗教がもつ歴史的な深い関係を、哲学史および自己の哲学から体系的に呈示するこの「三部作」は、哲学への関心は深いけれど宗教には違和感ある読者が、哲学との関係における西洋宗教の本質的論点を理解するのにも好適の書と存じます。「時間性と他者性」「象徴性と実在性(シンボルとリアリティ)」が全体としての論点であり、現代思想系哲学の愛読者の関心や疑問にも答える先駆性を持っています。
哲学者であることを自己の公の仕事とした波多野は、個人的な信仰生活については一切公刊していませんが、「宗教哲学は宗教的体験の理論的回顧、それの反省的自己理解でなければならぬ」というのがその揺るがない持論でした。理性を本領とする哲学と、信仰を本領とする宗教の緊張関係に深い自覚を持ち、『宗教哲学』の「序」の末尾には、「本書において著者は、宗教的体験に於て主体の対手をなすものを言表わす為め、便宜上「神」という語を用いた」という一文が記されています。波多野が独文で書いて1904年に東大大学院の卒業論文として提出した『スピノザ研究』は、安倍能成の和訳により1910年公刊されますが、日本における初の本格的スピノザ研究といえる同書をものした波多野の、後年の主著における上記の言葉は、『エチカ』を神の《定義》から始めるスピノザを連想させるとともに、理性(哲学)と信仰それぞれの意義を峻別する立場に立つスピノザの「私の哲学」と、波多野の、「宗教的体験の理論的回顧、それの反省的自己理解」を自己の仕事とする「宗教哲学」との差異を思い合わせれば、哲学と宗教の関係を考える読者には大きな問いが開かれるところでもあろうと愚考いたします。
『イデオロギーとロジック 戸坂潤イデオロギー論集成』
『日本的哲学という魔 戸坂潤京都学派批判論集』を刊行いたします。
(2007年11月)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『イデオロギーとロジック 戸坂潤イデオロギー論集成』『日本的哲学という魔 戸坂潤京都学派批判論集』
刊行にあたって(書肆心水)
戸坂潤(1900~1945)は、西田幾多郎を原点とする「京都学派」の流れに属する哲学者ですが、京都学派が全体として「日本的」な色合いが強いのに対し、マルクス主義哲学の立場から自分の哲学を練り上げた独特の位置を占めています。哲学者であると同時に批評家でもあり、『日本イデオロギー論』(岩波文庫)を代表とする時局批評にも力を入れました。1930年代に集中的に驚異的な量の著述活動を行ない、終戦を目の前にして獄死した人物です。
マルクス主義は旧来そのままの政治運動としては今や時代錯誤の感が否めませんが、戸坂の著作中の、1)普遍的な哲学的原理論と、2)日本思想史上のユニークな一論点を各々選集としてまとめました。
『イデオロギーとロジック』では、日常語としては単なる悪口として使われるだけの「イデオロギー」を、「論」の対象とした場合の豊かな可能性が示されます。鶴見俊輔氏が、「戸坂は同時代批評に移る前に、批評の方法についての原理的考察に長い時間を費やした。その成果は『イデオロギーの論理学』、『イデオロギー概論』に集められた」と評した仕事群です。鶴見氏は又、戸坂が自分の使う批評の用語を、なになに学ドイツ本店、ソヴィエト本店から借用せずに、自ら定義しつつ著述を進める姿勢をも高く評価しています。戸坂のような基本的で総合的なイデオロギー論の連作は今なお類を見ません。
『日本的哲学という魔』は、西田幾多郎、田辺元、和辻哲郎、三木清の哲学を批評する論集です。京都学派は、日本に従来存在しなかった「哲学」なるものを日本に導入するという独特の歴史段階に位置しています。その後の、輸入専業型の哲学論者とは違って、輸入と共に自前のものを組み込む、あるいは生み出す努力をした哲学者の学派です。したがって、そこには日本と哲学の関係の、歴史的に根源的な問題が存在し、勢い「日本的」なものが練り込まれてもゆくのですが、ユニヴァーサルな立場の戸坂はこの「日本的」哲学のイデオロギー性を強く批判しました。本書には戸坂の京都学派批判論を全て集め、戸坂批評の真価を呈示いたします。
『エッセンシャル・ニシダ』全3巻(西田幾多郎著)を刊行いたします。(2007年8月~9月)
●『即の巻 西田幾多郎キーワード論集』 ●『命の巻 西田幾多郎生命論集』 ●『国の巻 西田幾多郎日本論集』
.jpg)
.jpg)
.jpg)
※書影のリンク先ページに詳細を掲載
『エッセンシャル・ニシダ』刊行にあたって(書肆心水)
日本を代表する哲学者である西田幾多郎(1870-1945)には、その格に相応しい大変立派な岩波書店版全集があり、90年代には燈影舎版「西田哲学選集」も刊行されましたが、どちらも函入の高級品で、庶民は何巻もは私有しにくいものです。安定供給の廉価版として処女作『善の研究』の文庫版がありますが、『善の研究』以後、30年以上をかけて約20冊の単行本に記された西田哲学の進化、到達点を大づかみにするのがこの企画です。西田論の本はずいぶん沢山ある一方、西田自身のテクストを読める手頃な版がなさすぎると考えてのことです。
西田の哲学の単行本は「連作論文集」といった趣で、生涯一つのことをめぐってコツコツ書き連ねた論文を折々本にまとめていったものです。弟子の三木清によれば、「毎日きまって少しずつ書いてゆかれ……長篇作家が小説を書いてゆく仕方に似たところがある」ということです。単行本の書名はある時期から『哲学論文集第~』というものに統一されます(第一から第七)。したがって西田の「ベスト版」は、特定の単行本を重視するのでなく重要論文をピックアップすることにより、ちょうどミュージシャンの「ベストアルバム」のように構成することができます。この企画はそのように構成しました。
西田の哲学を評して、三木清はこのように述べています。――「先生は多くの論文を書かれながら結局一つの長篇論文を書かれているのである。そしてそれは完結することのないものである。それは多くの小説を書きながら一生の間結局一つの長篇小説を書いているにほかならぬ作家の場合に似ている。先生はいろいろなテーマについて書かれながら、結局一つの根本的なテーマを追求されているのであって、その追求の烈しさと執拗さとはまことに驚嘆のほかない。もちろん、『善の研究』このかた最近の論文に至るまで、先生の哲学には発展があり、その発展に注目することは大切である。しかしそこにまた根本的に連続的なものがある。」
この三木の評言は本物の哲学者の何たるかをよく語っているように思えます。例えばジャック・デリダは、生涯をかけて、「脱構築」の語で括られる一つのことに取り組みましたが、その仕事はただ一つのことをめぐって、差延、散種、代補、メシアニック等々のキーワードを編み出すかたちで進められました。西田の仕事の仕方もこれに似ています。生涯をかけてただ一つのこと、結局は「絶対矛盾的自己同一」と称されることになる実在のありようを探究する過程で、場所的論理、永遠の今の自己限定、弁証法的一般者、行為的直観、自覚等々、西田哲学のキーワードが生み出されました。
*
『エッセンシャル・ニシダ』各巻の特色は次のようなところです。
即の巻・キーワード論集は、一冊もののベスト版。ページはそうとう増えましたが、収めるべきものを収めました。A5判・512ページで本体2800円です。
命の巻・生命論集は、現代的・一般的なテーマでの一冊。これまで西田にご関心のなかった方にも接していただけるテーマとしてまとめてみました。「生命」のモチーフは西田哲学全体を貫いています。この巻に収録の「論理と生命」「生命」は『即の巻・キーワード論集』に収めてもよい重要作品。A5判・192ページで本体1900円です。
国の巻・日本論集は、西田が最も批判される日本論、国家論、国体論。西田論の中で話題になることは多いが、一般には眼に触れにくいと思われるテクスト群です。「問われる西田」の実際を自分で確かめたい読者のための一冊。日本型「ハイデガー問題」といった関心からも参照すべき論点です。A5判・224ページで本体2500円です。
どの巻にも「西田幾多郎全著書目次=論文名リスト」(年代順表記)を附して、西田の仕事の全過程を見通しながら、この選集に収録するそれぞれの論文が、西田の仕事全体のどこに位置づくものかが分かるようにしました。索引も一工夫して、いわゆる用語だけでなく西田一流のフレーズ、例えば「物となって考える」「自己が自己に於て自己を見る」の類も採用することにより、使える索引となることを目指しました。
絶対矛盾的自己同一の考え方は神秘主義ではない、むしろその逆、徹底的実証主義、絶対的客観主義であるという西田の訴えが読者に伝わる選集となることを願っております。
『タブーと法律』(穂積陳重著)を刊行いたします。(2007年7月)
.jpg)
『タブーと法律――法原としての信仰規範とその諸相』刊行にあたって(書肆心水)
現代の法律のように、「合理化」され、また明示的に「強制」されてはいないものの、社会の「秩序」を保つ上で大きな働きをするタブー。これは「原始人」だけのものではなく、現代社会の日常でも大いに機能しているものであることに異論はないかと思います。
昨今廃れつつあることと思いますが、手紙文で相手などに敬意を表するために改行して次の行の頭に人名を書く風習がありますが、これも「タブー」の一つの転化現象です。そもそもタブーは、身の安全を守るために「距離」をとることにその原点を持っていますが、転じて秩序の維持のために「距離」をとること、権威あるものに「近づかざること」にもなっていく現象です。年配の方はご存知のように、戦前の活字文献にはしばしば「天皇」という文字列の直前に一文字文のアキが組まれていることがありますが、これもその一種です。
さて、このタブーですが、いざ、それがいかなるものか全体的に把握してみたいと思っても、総論的なよい著作がちょっとみあたりません。タブー論の書籍は、ありそうでいて学問的なものはほとんどないのが現状と言って差し支えないのではないでしょうか。書名にタブーをもった有名な著作と言えば、フロイトの『トーテムとタブー』ですが、これは当然、精神分析の文脈にある著作で、また、西洋の著作です。このたび刊行する穂積陳重の著書は、著者がライフワークとした「法律進化論」の一部分にあてられた「タブー論」で、「法律進化論」の立場から、タブーの本質、諸相、「進化」過程などを総合的に検証した、類書なき業績です。また、日本や中国の事例(漢字表記におけるタブー実践など)を豊富に検証しているという意味でもユニークな価値があります。法律書というよりは、法人類学の著作といった趣の本です。
*
どの国でもそうであるように、近代化への大きなステップは合理的な法律を整備することでしょう。穂積陳重は開国日本に近代的法律を導入する事業の、重鎮中の重鎮でした。穂積に関して残されている有名な話の一つにこんなことがあります。死後故郷で銅像建立の話が持ち上がったが、「老生は銅像にて仰がるるより万人の渡らるる橋となりたし」の生前の穂積の言葉により、銅像はやめにして、或る橋が「穂積橋」と命名されることになった、ということです。
この話については「エライ人の美談の類というものは……」という見方もできるでしょうし、また穂積の著述についても「権威ある法学者の場合はその《実証的》言説自体がパフォーマティヴな政治性を帯びているものなのだ」といった見方もあるでしょうが、穂積の書きぶりをみていると、「銅像にて仰がるるより万人の渡らるる橋となりたし」ということがそれとなく伝わってくる気がします。個人的な批評精神というものとは別な、「学者たる者の公正さとはこういう手つきのものでもあるか」と感じさせるものです。
古いスタイルの著作で、とっつきにくにところもあるかとは思いますが、ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
『偶然と驚きの哲学』(九鬼周造著)を刊行いたします。(2007年6月)
.jpg)
『偶然と驚きの哲学――九鬼哲学入門文選』刊行にあたって(書肆心水)
『「いき」の構造』で著名な九鬼周造の哲学主著は『偶然性の問題』ですが、本書は、その主著以後、「偶然性」にさらに「驚き」の論点がリンクした、九鬼周造晩年の到達点を示す講演・論文を、九鬼哲学入門として集めたものです。
主著『偶然性の問題』は今現在、燈影舎版『京都哲学撰書第5巻 偶然性の問題・文芸論』として新本が入手できますが、『九鬼周造随筆集』(岩波文庫)の編者菅野昭正氏も同書で、《『偶然性の問題』を苦労しながら理解しようと努力しても》と述べるように、哲学主著の常で、平易とはいいかねるものです。しかしこれはユニークで魅力ある哲学世界と思います。そこで九鬼哲学への入門のための小選集として本書を製作いたしました。
『「いき」の構造』にその資質が十全に展開されているように、九鬼は「情」の領域に対する鋭い感性をもっていて、上記菅野氏の言葉を借りれば「文人哲学者」という趣、あるいは「論理と情の哲学」です。九鬼の短歌ノートに次のような歌がのこされています。
「偶然性の問題」を著して――
わくら葉のものの「はずみ」をかたくなの論理に問ひて一巻をなす
偶然論ものしおはりて妻にいふいのち死ぬとも悔ひ心なし
一巻にわが半生はこもれども繙く人の幾たりあらむ
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
『憂い顔の『星の王子さま』』(加藤晴久著)を刊行いたします。(2007年5月)
.jpg)
『憂い顔の『星の王子さま』――続出誤訳のケーススタディと翻訳者のメチエ』刊行にあたって(書肆心水)
「読みつがれて50年」、『星の王子さま』の著作権保護期間が終わり、2005年6月から2006年11月にかけて、14点もの新訳が続々現われました。ご存知の方も多いと思います。
著作権フリーになったからとはいえ、これだけたくさんの新訳が次から次へと出たのは、『王子さま』が世界的ベストセラーだからというだけではなくて、内藤濯訳『星の王子さま』は問題のある翻訳だという、「噂の」事情があったからです。「どうもそうらしいが、あれはあれでいいのだ」という説に対して、具体例を示し「いや、そうは言えない」と言うのが本書です。また、訳は問題だが日本語としてはいい文章だという立場に対しても「ノー」です。
新訳14点と英訳版3点も比較検証します。また、新訳ラッシュに関するジャーナリズムの報道も批判します。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
*本書が論じる「定番」と新訳書一覧*
内藤濯 訳『星の王子さま』、岩波少年文庫 001、岩波書店、初版1953.3.15、新版2000.6.16
小島俊明 訳『星の王子さま』、中央公論新社、2005.6.25
三野博司 訳『星の王子さま』、論創社、2005.6.30
倉橋由美子 訳『新訳 星の王子さま』、宝島社、2005.7.11
山崎庸一郎 訳『小さな王子さま』、みすず書房、2005.8.24
池澤夏樹 訳『星の王子さま』、集英社文庫、集英社、2005.8.31
川上勉・廿樂美登利 訳『プチ・プランス』、グラフ社、2005.10.25
藤田尊潮 訳『小さな王子』、八坂書房、2005.10.25
石井洋二郎 訳『星の王子さま』、ちくま文庫、筑摩書房、2005.12.10
稲垣直樹 訳 『星の王子さま』、平凡社ライブラリー 562、平凡社、2006.1.11
河野万里子 訳『星の王子さま』、新潮文庫、新潮社、2006.4.1
河原泰則 訳『小さな星の王子さま』、春秋社、2006.5.10
谷川かおる 訳『星の王子さま』、ポプラ ポケット文庫、ポプラ社、2006.7
野崎歓 訳『ちいさな王子』、光文社古典新訳文庫、光文社、2006.9.20
三田誠広 訳『星の王子さま』、講談社 青い鳥文庫、講談社、2006.11.15
『真説 レコンキスタ』(芝修身著)を刊行いたします。(2007年5月)
.jpg)
『真説 レコンキスタ――〈イスラームVSキリスト教史観〉をこえて』刊行にあたって(書肆心水)
中世スペインを舞台とする「レコンキスタ(国土回復運動)」は、8世紀、勃興するイスラーム勢力がイベリア半島に侵入し、以降その地を治めたイスラーム勢力をキリスト教国が徐々に駆逐する歴史を指す言葉ですが、これは当時の言葉ではなく19世紀の造語です。初級世界史でも習う事項で、これは従来、「西方十字軍」とも言われ、イスラーム対キリスト教としての観方が主流でした。本書はこの史観を修正する、和書(訳書も含め)では初の成果です。
西欧とイスラームの関係が語られる場合、「宗教」が過剰に前面に出る傾向があります(ブッシュの十字軍のように)。近現代のことは別にして、時間を十分に隔てた歴史の叙述においても長い間そうした偏向があったと言えるでしょう。その代表例としての「レコンキスタ観」を見直すのが本書です。
500年を要したレコンキスタは1492年のグラナダ王国の陥落で完成しますが、この年、コロンブスはスペインを出発します。大航海時代(と世界資本主義の500年)の始まりです。大航海時代の立役者となるスペインとポルトガルの国家成立を準備し、西欧世界とイスラーム世界の境界(今なお変わっていない境界)を画定したのがレコンキスタで、それは宗教的理由によるよりも、主要因から見れば、「力」を蓄えてきた晩期中世西欧世界が領土を求め拡大する、「近代」の胎動だった――本書に拠ればこうした興味深い観方に導かれます。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2007年4月は『奪われたるアジア』(満川亀太郎著)を刊行いたします。
.jpg)
『奪われたるアジア――歴史的地域研究と思想的批評』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、満川亀太郎著『奪われたるアジア』を刊行いたします。(著者紹介は書誌案内の別ページをご覧下さい
 )。
)。
『奪われたるアジア』(原本1921年=大正10年刊行)は、《日本近代史再考》の流れで当社刊行継続中のアジア主義関連書の1冊です。満川亀太郎は北一輝、大川周明とともに“革新結社”猶存社の「三尊」と称された人物です。北一輝と大川周明の強烈な個性に比べて影が薄いのですが、その穏やかな個性にふさわしい、バランス感覚ある実証的研究や批評を大量に残した重要人物です。
一口にアジア主義者といっても、その個性や思想的なポイントは多様なもので、満川の場合は「反人種差別」が彼の特色ということになるでしょう。例えば、当時はユダヤ人差別についての世の認識は甚だ低かったのですが、満川の場合は「復興アジア」を軸とする彼の課題の中に、ユダヤ人差別問題や黒人差別問題が並行的に組み込まれていて、満川には『ユダヤ禍の迷妄』『黒人問題』という著書もあります。今回解説を寄せてくれたスピルマン教授は、映画『戦場のピアニスト』の主人公のユダヤ人シュピルマンの長男ですが、スピルマン氏が満川研究に従事していることも、満川の個性を間接的に語るところと思います。
戦前日本の「左右」両方を含めた「革新」主義者たちの中で、満川のように「奪われたるアジア」というテーマを、広域的・総合的に、しかも抽象的でなく個別具体的史実を積み上げて検証した人物は稀有な存在です。復興アジアの問題を、目先の東アジアの状況だけにとらわれることなく、大きく世界史の問題に位置づける立場です。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2007年2月は『三木清批評選集 東亜協同体の哲学』と『師弟問答 西田哲学』(西田幾多郎・三木清)を刊行いたします。
.jpg)
.jpg)
『東亜協同体の哲学』 『師弟問答 西田哲学』 刊行にあたって(書肆心水)
衆目の一致するところの日本の巨人哲学者と言えば、西田幾多郎に始まり、その後は井筒俊彦、廣松渉といったところで、寂しいことにもうその後は無しなのだろうか、とも思われてしまうのですが、読者諸賢の印象は如何でしょうか。
その廣松渉は、1994年5月に亡くなる直前の3月に、「日中を軸に「東亜」の新体制を」と題した短文を『朝日新聞』に寄稿しましたが、その内容と、遺言めいたタイミングで話題を呼びました。部分引用すれば、「東亜共栄圏の思想はかつては右翼の専売特許であった。日本の帝国主義はそのままにして、欧米との対立のみが強調された。だが、今では歴史の舞台が大きく回転している。日中を軸とした東亜の新体制を! それを前提にした世界の新秩序を! これが今では、日本資本主義そのものの抜本的な問い直しを含むかたちで、反体制左翼のスローガンになってもよい時期であろう。」というものです。
「右翼/左翼」の分類図式が、この記事が話題・問題になった要因だと思われます。巨人哲学者廣松渉の心中は推し量りえぬところながら、「アジア協同」の問題は、世界資本主義(近代世界システム)がもたらした「近代」の当初から埋め込まれているものであり、その陽性の意義が自滅的に失われた過去があるだけに、未解決の課題として新たに問うに値するものと思います。
西田幾多郎の弟子である哲学者三木清は、まさにこの東アジア協同の問題に真剣に取り組んだ、しかも十五年戦争当時(1931-45)の渦中で、ものを書くのが非常に困難な状況の中で、「東亜協同体」の問題を、その「可能性の中心」において模索した稀有な人物です。これまで三木のその側面は、「右/左」「進歩/反動」の視点では微妙な問題になるが故になのでしょうか、あまり十分には論じられてきていませんが、今回出版の選集がA5判480頁になったように、長期にわたって多量の粘り強い思索を積み重ねています。
三木の立場はつづめて言えば、資本主義・自由主義・個人主義といった抽象的な世界主義を克服した、新しい世界主義としての「東亜協同体」というもので、これは対抗的民族主義(ナショナリズム)を止揚した立場であり、自身の哲学テーマ「構想力の論理」の実践的側面です。三木の「東亜協同体の哲学」は今こそ参照すべきユニークな遺産と思います。
* * *
『師弟問答 西田哲学』は、三木に根本的な影響を与えた師の西田幾多郎との珠玉の対談と三木の西田論で構成したもので、『善の研究』くらいはいちおう読んだし、西田哲学は気になっているけれども本格的なものにはまだちょっと……、という一般読書界に向けて、「西田自身が語るひとつの西田哲学入門」としておくりたいと考えているものです。
よく理解しあった師弟ならではの絶妙の問いと卒直な答えで、西田の核心的な思想が、自身の硬質な著作には見られないような分かりやすい言葉、かつ含蓄ある言葉で語られています。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
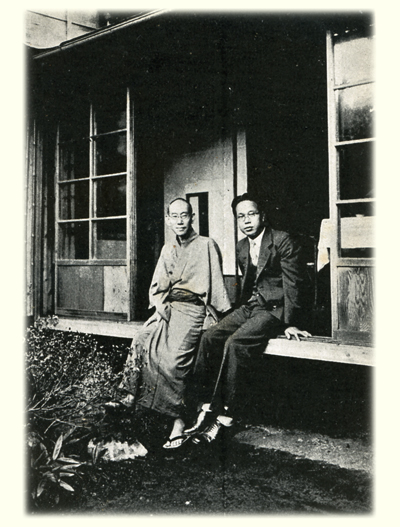
2007年1月は『犬養毅の世界』と『頭山満直話集』を刊行いたします。
.jpg)
.jpg)
『犬養毅の世界――「官」のアジア共同論者』 『頭山満直話集』 刊行にあたって(書肆心水)
今月は、二人のアジア主義者の本を刊行いたします。
犬養毅は首相経験者なので歴史の教科書にも登場する人ですが、今ではもはや、尾崎行雄と共に「憲政の神様」という賛辞で知られるか、あるいは5.15事件で銃口を向ける軍人に「話せばわかる」と対応したとの話で知られる位のところかもしれません。しかし近代日本とアジア主義の問題を再考するうえでは欠かせない重要人物です。
本書は、犬養が自身の思想を口述し、その速記原稿を校閲した稀少価値あるテキストと、犬養伝の決定版の著者が犬養の横顔・論点を示したテキスト、写真・年表で構成したもので、従来あまり重視されなかった「アジア共同論者」としての側面を浮き彫りにする試みです。
孫文やボースら、アジア解放に苦労する亡命志士をサポートしたのは、日本政府ではなく宮崎滔天や頭山満ら浪人連、つまり「民間」だったわけですが、犬養だけはその例外で、「官」の立場にありながら、アジア復興の国際連携に、口で言うだけでなく実際に何かをした人間です。犬養は書道でも有名な人ですが、東洋趣味・東洋思想に根ざす知見が中国通たらしめ、近代世界システムにおける東アジアの状況について、おおかたの政治家とは一線を画した認識を持っていました。
* * *
当社既刊『頭山満言志録』
 は、頭山満が西郷隆盛の「西郷遺訓」の解釈などから自身の思想的な核心を示すような本でしたが、今回刊行の『頭山満直話集』のほうは、回顧的な楽しい談話録という趣のもので、頭山の過ごしてきた人生の大枠の流れを知ることができる、「頭山満一代記」というような本です。
は、頭山満が西郷隆盛の「西郷遺訓」の解釈などから自身の思想的な核心を示すような本でしたが、今回刊行の『頭山満直話集』のほうは、回顧的な楽しい談話録という趣のもので、頭山の過ごしてきた人生の大枠の流れを知ることができる、「頭山満一代記」というような本です。
頭山にまつわる話というのは、1)頭山を敬愛する人々によるものはその魅力を神格化する傾きがあり、2)反対に黒いイメージで描く向きは「触らぬ神に祟りなし」的な切り捨てで、具体的論点が不在の傾向があります。
戦前には頭山語録の出版物がかなり出ていますが、これらを調べてみると、時代状況や編者の立場と思われるところによって、同一のエピソードがかなり違ったニュアンスで書かれていることがあります。頭山は細かいことにはこだわらない性質だったようで、出版物などは本業とは関係ないのだから勝手にしたまえという姿勢だったようです。この『頭山満直話集』は、それらの中で最も脚色の少ないものを選んだものです。
なお本書には、『中村屋のボース』で有名になったボースの救出事件をめぐるボースと内田良平の直話が併録されています。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。

△英国政府+日本政府の「お尋ね者」になったインド独立運動の亡命志士ボース。ボースは、危険を冒して保護してくれた恩人たちを招いて、毎年謝恩会を主催していた(昭和七年。中村屋にて)。画面右から、頭山夫人峰尾、犬養、ボース、頭山、内田良平。
2006年12月は『内村鑑三小選集 愛国心をめぐって』を刊行いたします。
.jpg)
『愛国心をめぐって――普遍の愛と個別の愛』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、内村鑑三の小選集『愛国心をめぐって』を刊行いたします。(著者紹介は書誌案内の別ページをご覧下さい
 )。
)。
愛国心は、近代日本が始まって以来、おりおり問題化されてきたテーマですが、ここにきてまた論議が高まっています。当社ではこの機に、カレントなモードの議論とはまた別に、内村鑑三の思想を手がかりにしてこの問題を考えてみたいと思い、内村の厖大な著述の内のごくわずかな分量ですが、このテーマで小さな選集を編んでみました。
内村鑑三は明治~大正~昭和に活躍したクリスチャンの評論家ですが、クリスチャンになってからも武士道の思想を重んじ、愛国者であることを強く自任し、日清戦争時の可戦論者から日露戦争時に非戦論者となった人物です。当社が他ならぬ内村に着目したのは、内村自身が言うように内村が「二つのJ(JesusとJapan)への愛に生きた」人物だったからで、そこには、普遍的な人類愛と個別的な自国愛が両立するロジックと、そのための条件があります。
愛国心問題はきわめて込み入った難しい問題ですが、昨今の状況における大きな論点は、1)政府主導の国家(=法)が個人の良心に働きかけることの是非、2)愛国心が人類愛に反した排他的なものになる傾向、というあたりではないでしょうか?
クリスチャンというありかたで人類愛を生きると同時に、武士道的愛国者であることを強く自任した内村鑑三の思索は、1)個人的良心や道徳と国家の関係性について、2)個別愛と普遍愛の両立のありようについて、時代をこえて、多様な立場から、思索の友とするに値する貴重な遺産であると考える次第です。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2006年11月は『其日庵の世界――其日庵叢書合本』(杉山茂丸著)を刊行いたします。
.jpg)
『其日庵の世界』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、ホラ丸こと其日庵・杉山茂丸の著作『其日庵の世界(其日庵叢書合本)』を刊行いたします。(人物紹介は書誌案内の別ページをご覧下さい
 )。
)。
杉山茂丸が、自身の思想をもっともあからさまにつづったエッセイ集に『其日庵叢書』というものがあります。第一編から第三編までの構成ですが、第三編は当社既刊の『百魔』に収録済みのため、第一編+第二編の合本を『其日庵の世界』として刊行いたします。杉山流の武士道死生観によって開国近代日本の病理を問うという趣きの思想論や、義太夫(浄瑠璃)と刀剣という杉山の趣味等を語ったエッセイ集です。
義太夫について申せば、岩波文庫に杉山の著作『浄瑠璃素人講釈』が入っていますが、これは先般、『週刊新潮』(9.28)の『百魔』書評
 で福田和也氏も「『浄瑠璃素人講釈』は斯界の大名著として知られる伝説的な作品です」と紹介されているもので、「素人」とは杉山らしい書名のつけかたながら、関心をもった分野には中途半端でない食い込みを見せる杉山がとりわけ愛好したのが義太夫でした。
で福田和也氏も「『浄瑠璃素人講釈』は斯界の大名著として知られる伝説的な作品です」と紹介されているもので、「素人」とは杉山らしい書名のつけかたながら、関心をもった分野には中途半端でない食い込みを見せる杉山がとりわけ愛好したのが義太夫でした。
本書収録のエッセイも、義太夫を語る文章が一個の文明論になっているところに杉山の考えの深さが感じられます。思想論は、一見ムチャクチャの「暴論」ですが、開国近代日本の病巣を深くえぐっているものでもあり、近代日本の問題化に重要な視点と当社はとらえております。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2006年10月は洪自誠原著・加藤咄堂著
『味読精読 菜根譚』前集(処世交際の道)+後集(閑居田園の楽)を刊行いたします。
.jpg)
.jpg)
『味読精読 菜根譚』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、東洋伝統思想の結晶『菜根譚』の本格的道案内、『味読精読 菜根譚』を刊行いたします。
『菜根譚』は中国の明の時代に書かれ、江戸期に日本に伝えられて以来、今日まで広く愛されてきた古典ですが、儒教と仏教と道教が渾然一体となったユニークな思想書です。陽明学や武士道的なハードな思想ではなく、平凡な穏やかさを大事にするソフトな思想が人気の理由と思われます。かといって、事なかれ主義の「まあまあ、いいじゃないですか」志向でもなく、自律的な倫理観が、よりよくあろうと考える読者層をひきつけているようです。
日本の近代化も百五十年の歴史を経てだいぶ落ち着きを見せ、国家関係にはまだ実に難しい軋轢がありますが、全体としては欧米流近代化一辺倒の傾向を抜けて、風土を近くする東アジアの一員としての自己を違和感なく見る空気になってきたようです。日常生活としても、例えば夏のネクタイなしが、エネルギー政策が主旨であるにせよ、この蒸し暑い土地柄にはどうにも不具合であることよ、という当たり前の発想を伴って受け入れられているようですが、思想面でも、長期の歴史と実績をもつ東洋思想の「もっともさ」が、個人の生活の中で静かに省みられていくのが時代の流れではないでしょうか。
伝統的に漢字文化圏であった地域には歴史に深く根ざす思想的蓄積が共通のものとして伏在していますので、政教分離の公の学校文化では難しいにしても、個人の思索においては今後おおいに参照され、東アジア地域間連携の深層で、目立ちはしないが大きな意味をもっていくと思います。自己を展開するのに長けた実証的・物質的西洋近代思想と、自己を克服するのに長けた内観的・思索的東洋伝統思想は、同程度の重要性をもって扱われる価値のある、それぞれの利点を持っています。当社では、小規模ながらもできるだけ多様な出版の切り口を立てていきたく、今後のひとつの柱として、東洋伝統思想にも取り組みたいと考えております。
東洋思想という言い方はいかにも大雑把なもので、そんなものはあるのかな?という見方もありそうですが、ソコデいかにも便利なのが『菜根譚』という書物です。儒教と仏教と道教の、俗に言えば、いいとこ取りというような著作であって、体系的にそれらの関係が示されている種類のものではないのですが、通読すればなんとなくその勘所が身に染みてきたように思えるところが、広く愛されるゆえんと思います。
本書は、儒学・禅仏教に造詣の深い加藤咄堂がその素養をいかし、あるいは語義を解説し、あるいは関連する話題を援用しながら『菜根譚』の思想を解説し敷衍する、いま望みうる最も豊かな『菜根譚』読本です。(加藤咄堂については本書紹介の別ページをご参照下さい)
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2006年9月は『死生観――史的諸相と武士道の立場』(加藤咄堂著)を刊行いたします。
.jpg)
『死生観』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、「死生観というキーワードはこの書から始まった」と目される死生観史論の古典『死生観』(1906年刊)を刊行いたします。
古代から現代まで、人間にとって、詰まるところの問題は死であると考える人は多いと思います。近代になって公的・学術的論議は科学・実証主義をベースとするものに変わりましたが、そもそも科学・実証主義で覆いきれないこの死生問題は、近現代において、前近代にはなかった種類の難しさを抱え込んだと言えるでしょう。このたび刊行の『死生観』は、思想史上の位置としては「伝統的議論の終着点と近代的議論の出発点の境界」という、稀有な位置にある著作です。
近年、武士道の価値観が注目されているようですが、武士道といえば「武士道とは死ぬことと見つけたり」の句が思い浮かぶように、死生観が思想の核に位置づいています。現代日本の最も大切にされている価値観は、個人の生存をあたう限り優先すること――死を被ることはもちろん、命をかけて(も)自ら何かをなすという考え方はつつしむこと――であるように感じられますが、この生命観からすれば武士道は現代日本の価値観とは相容れないものと思われます。いったい今の時代、武士道の価値観を時代錯誤なく生かせるのか、生かせるとすればどんな意味においてか、そもそも武士道死生観の核心はどんなものか、また武士道死生観は一つなのか多様なのか、他の思想との関係はどうなのか、こうしたことを考えるには、武士道の立場自体をよく知ると同時に比較の視点も必要です。『死生観』は、この点においてユニークな個性をもった著作です。
科学・実証主義の定着は現代社会に多大な恩恵をもたらしていますが、その一方で、科学をはみ出す問題は私的な領域に押し込められる嫌いがないでしょうか。教育・研究の世界では宗教学等の専門領域をはみださない範囲に、また世間では教団や知人友人の枠内にとどまって、研究・出版としても、俗に言えば「やや怪しい」領域と見なされがちなようです。難しい事情はあれ、この種の問題はひろく論じられてよいものだと思います。
『死生観』の著者加藤咄堂(かとう・とつどう/1870~1949)は、仏教・儒学等の東洋思想を土台とした修養思想の啓蒙家として活躍した人です。出版書籍は200点以上にのぼり、最盛期には年間200回以上の講演を行なって、難解な思想や古典を平易に説き人気を博しました。武士道論者としても修養論者としても新渡戸稲造に先立つ人物でしたが、新渡戸がキリスト教徒で、東大の教授にもなり、近代的市民であることを目指しながら控えめに日本の伝統に合致した修養を唱えた人であったのに比して、加藤は東洋大等の教職にもあったものの基本的に在野の論者であった故か、あるいはその思想が「古い」東洋思想に根ざすが故か、戦後は殆ど省みられなくなった人物です。200点以上の著作の中には、『碧巌録大講座』(15巻)『修養大講座』(14巻)といった大仕事もあります。今回の『死生観』は、自身の思想呈示の意味も強いためか、「森厳」なスタイルの著作ですが、著書の多くは平易な語り口の中に素養の厚みを感じさせるもので、東洋思想再評価の上で注目に値する著述家です。当社では引き続き加藤咄堂の著作をいくつか刊行の予定です。
現代の死生観問題は、医師・病院との関係、技術との関係、近親者との関係、現代的生命観との関係などなど、往時の日本人のそれとはだいぶ違ってきています。加藤咄堂の『死生観』は古典ですから、その意義と思想史的位置を客観化することも必要ですので、宗教学の第一人者、現代死生学研究共同プロジェクトのリーダー島薗進氏(東京大学大学院人文社会系研究科教授)の解説を付して、読解の一助といたしました。なお、新漢字・新仮名づかい等でなるたけ読みやすいように編集してあります。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2006年8月は『百魔(正続完本)』(杉山茂丸著)を刊行いたします。
.jpg)
『百魔(正続完本)』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、『ドグラ・マグラ』夢野久作の問題の父、玄洋社のシンボル頭山満の無二の盟友、其日庵杉山茂丸の幻の主著『百魔』完全版を刊行いたします。
本人言うところの「国事道楽」人生で家庭をかえりみなかった杉山茂丸(1864-1935)は、長男の夢野久作(1889-1936)にとって実に問題のある父親だったようですが、その愛憎あい半ばする親子関係は、夢野久作文学のネガ的起源とも言えるものでしょう。戦後、夢野久作を発掘し、その紹介に甚大な功績を遺された鶴見俊輔氏は、杉山茂丸の『百魔』とその親子関係について次のように評しておられます。
「その主体のもっている図式がペタッとハンコのように何の上でも押されていくわけですよね。(……)その手形を押すことのできる人間だけに彼(夢野久作:引用者注記)は興味をもった。その興味のもち方というのは、実は杉山茂丸譲りなんだ。杉山茂丸著の『百魔』というのはそういうものなんですよ。魔人とは何かというと、何やってもその仕事にバーンと自分の手形を押す人間のことなんですよ。だから成功も失敗もない。明治以降の最も成功した人間を百人書こうなんて、そんな考え全然ないわけだ。ある人間は気狂い同様で死ぬ。ある人間は木賃宿で死ぬ。そんなことはどうでもいいことなんだ。しかし彼が魔人であったかどうかだけが杉山茂丸の興味の対象で、有名も無名もないし、上昇も下降もないんだ。自分のこの生きてきた明治以降の暮らしの中で魔人をどんどん、どんどん書いていったわけだ。それが『百魔』でしょう。その観点は夢野久作に継がれていますね。」
(三一書房版『夢野久作全集3』解説対談より引用)
当社既刊の杉山茂丸著『俗戦国策』
 は茂丸の回顧録エッセイでしたが、この『百魔』はユニークな文学作品というべきもので、夢野久作ファンには見逃せない意味をもった本と言えるでしょう。また、明治~大正~昭和にかけて活躍した「政財界の影武者」杉山茂丸から見えてくる日本近代史の姿、昨今あまり直視されることのない歴史の側面が感じられる貴重な史料とも言えるでしょう。
は茂丸の回顧録エッセイでしたが、この『百魔』はユニークな文学作品というべきもので、夢野久作ファンには見逃せない意味をもった本と言えるでしょう。また、明治~大正~昭和にかけて活躍した「政財界の影武者」杉山茂丸から見えてくる日本近代史の姿、昨今あまり直視されることのない歴史の側面が感じられる貴重な史料とも言えるでしょう。
うまい言い方ができませんが、現在の日本人は、制度や理論や科学の連鎖を伸ばし巡らすことで概ね安定した世の中を生きているのに対して、杉山茂丸らが生きた時代は、個人の力量が大きな意味を持つ不安定な時代であったと思います。杉山茂丸が位置した状況に詳しい葦津珍彦氏は次のような談話を遺しています。
「しかし、明治人は政争のロジックの優劣よりも、政治を思想する主体としての人物の正否、優劣そのものを重視して進退しています。これは、中江兆民のような理論家でも、政治の実践に関しては「人間」に重点をおいています。とくに明治人のなかでも、頭山(頭山満:引用者注記)は、人間を重く見ています。ロジックが整理されていてもその精神に誠意なく、実力なきものは無視する。ロジックは多少怪しくても、乱雑でも、その精神が忠実にして力ある者は、友とするに足るとの判別で進退しました。文章のロジックのみを見て、人間の実質を見ることの乏しい現代知識人に、しばしば理解しがたいのは、そのあたりにも理由があるかと存じます。」
(葦書房刊『頭山満翁正伝(未定稿)』解説より引用)
時間的にも空間的にも近い歴史を、時代錯誤なく対象化し、学ぶべきところを学び、生かしうるところを生かす上で、杉山茂丸という奇人の持つ意味は大きいのではないかと考え、人間の底力という《魔》を謳う異色文芸『百魔』を刊行いたします。
なお、『百魔』は80年代に文庫版(上下二巻本)が一度出ましたが、それは「正篇」だけでしたので、「続篇」を加えた完本の復刻は今回が初めてとなります。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
*ご案内* 杉山茂丸を紹介する識者のウェブサイト
其日庵資料館(夢野久作をめぐる人々) https://www1.kcn.ne.jp/~orio/
谷底ライオン https://homepage2.nifty.com/tanizoko/index.html
2006年8月は『さなぎとイマーゴ』(岩切正一郎著)を刊行いたします。
.jpg)
『さなぎとイマーゴ』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、新しいボードレール論『さなぎとイマーゴ』を刊行いたします。
ボードレールとともに人間の歌は変質したと言われます。期待されたハーモニックな空間のなかに調子外れな音を呼び入れるボードレールの詩。そこには隠されていた真実の語りが書き込まれ、その詩が我々を我々自身へと送り返してくれる、と。
「ボードレールが創造するのは、近代的自我にくいこんでいる傷の痛みを持ったまま、幸福でありえる、そのような場所である」。これが本書『さなぎとイマーゴ』における著者岩切氏の基本的な視点です。古い幸福のかたちがリアリティを持ちえなくなっている時代の幸福のありようを、言語と人間の関係から考察する力作です。
岩切氏は自身詩人でもありますが、若い頃からボードレール研究を積み重ね、その成果を『さなぎとイマーゴ』にまとめました。本書の「序」は次のように書き起こされており、岩切氏のモチーフがよく感じられるように思います。
「ママ、ことばって、何」と小さな男の子が母親に質問する。「ことば……人がそのなかに住む家よ」と母親は答える。口をついて出てきたその答えに、自分もまた内側から照らされているような表情が、その面(おもて)をよぎってゆく。ゴダールの映画『彼女について私が知っている二、三の事柄』の一シーンだ。
「家」という語に、小市民的な、あるいは宗教的な臭いを嗅ぎつけることができるかもしれない。けれども私は、この定義を、子どもに言われたものとして、単純な真実として、受け取りたい。次のように言い換えることの可能な定義として。「人がそこに住むことのできないことば(langage・言語行為)は、たとえおもてむきにはことばの姿をしていても、本当の意味でのことばではない」と。
詩のことばこそは、なによりも人がそこに住むことのできることばである。住むという語は、もちろん、ただ安らぎの場にいることを意味するものではない。詩的にそこに住まうということは、そこで深く宇宙と結びつくよろこびであると同時に、そこで深く傷をひらくことでもある。
ご興味をお持ち戴ければ幸いに存じます。
2006年6月は『滔天文選』(宮崎滔天著・渡辺京二解説)を刊行いたします。
.jpg)
『滔天文選』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、滔天思想の真価を文人としての姿にみる『滔天文選』を刊行いたします。
当社既刊の渡辺京二著『評伝 宮崎滔天(新版)』
 は、本読みの達人鹿島茂氏が『週刊文春』書評エッセイ
は、本読みの達人鹿島茂氏が『週刊文春』書評エッセイ で「宮崎滔天を描き切って間然するところのない傑作評伝」と仰るように、滔天という人物をもっともよく理解し、また滔天という人物が抱え込んだ近代日本の問題を大変よく対象化した作品ですが、この作品は、滔天の思想の真価を、滔天の一風変った戯文のなかにみることができるということを教えてくれるものでもありました。
で「宮崎滔天を描き切って間然するところのない傑作評伝」と仰るように、滔天という人物をもっともよく理解し、また滔天という人物が抱え込んだ近代日本の問題を大変よく対象化した作品ですが、この作品は、滔天の思想の真価を、滔天の一風変った戯文のなかにみることができるということを教えてくれるものでもありました。
『滔天文選』は、この渡辺京二著『評伝 宮崎滔天』の示唆によって生れた作品選です。
《滔天宮崎寅蔵はふつう孫文と親交のある中国革命援助者として知られる。しかし彼には並々ならぬ文才があって、彼が書き遺した戯文は、明治・大正期のわが国の文学において、ひとつの椅子を要求してしかるべきものだと私はずっと信じて来た。》
《滔天に文章の才があったことは明白である。達意にして奇想に富み、歯切れよくしかも賑やかである。たのしんで読むに足る文章であるが、戯文はときに真摯な思考の道具ともなりうる。たのしみつつ、ときには考えを凝らして読んでいただくならば、文章家滔天は泉下にほほえむであろう。》
上記の引用文は、渡辺氏から『滔天文選』に寄せていただいた解説エッセイの冒頭と末尾ですが、そこに語られている魅力がもっともよく伝わってくる作品を厳選いたしました。『文選』に収録した滔天の文章が、そして滔天の何だかうまくいかない志士としての生涯が抱え込んでいた問題のありどころを、「近代日本の狂と夢」と表現して、副書名として添えてみました。
お手に取っていただければ幸いです。
2006年4月は『俗戦国策』(杉山茂丸著)を刊行いたします。
.jpg)
『俗戦国策』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、明治~大正~昭和にかけて活躍した「政財界の影武者」、杉山茂丸の大作主著『俗戦国策』を刊行いたします。
知る人ぞ知る奇人という感じの杉山茂丸ですが、一般には杉山自身の事績よりも、『ドグラ・マグラ』の小説家・夢野久作の父親としてその名のみが知られていると思います。著作は多数あるのですが、本書のほかに今現在一般向けの新本で売られているのは、岩波文庫の『浄瑠璃素人講釈』だけです。
杉山茂丸は、1864(元治1)年生まれの1935(昭和10)年歿。自称の号は其日庵(そのひあん)、在野の《国士》です。(今の言い方では《無職》ということになりましょうか……)。一人一党の無官無位で通し、明治・大正・昭和政財界の舞台裏で、経済・内治・外交・軍事を不可分とする経綸を生涯の仕事とした人物です。日本国内・台湾・朝鮮における鉄道・港湾開発事業や銀行の創設、満鉄株式会社の創設、外債導入などの実業面から、日清日露の開戦および終戦・講和などの軍事・外交面、さらに内閣や政党の組織工作まで、元老・要人を説き伏せ動かし、重大国事の影武者として活躍。その無私の提言が、伊藤博文、山県有朋を初めとする元老や内外の大資本家を動かしました。
杉山茂丸は、玄洋社の頭山満と根本思想を同じくする無二の親友でしたが、頭山が官僚的なものには距離をとったのに対して、杉山はむしろ政界・官界・財界の本丸に乗り込んで、要人を説き付け操るというタイプのやり方を極めた人物で、「静の頭山」「動の杉山」という評言もあったようです。交渉相手は日本の大物にとどまらず、単身アメリカに乗り込んで、大資本家J・P・モルガンからの巨額借款交渉も成立させた腕前でした。
元老政治家ら大物を動かすとはいっても、なにしろ17歳の頃からの一人一党主義。伊藤博文から警視総監就任を要請されてもこれを固辞して、生涯無官無位を貫いた杉山でしたから、カネや政党勢力を持っているわけでなし、人を動かす道具は「国家経営の道」を説くその言葉と我が身一つの行動力だけでした。大胆卓抜な発想、機転、逆理、能弁によって、私心なく要人を操るその手腕は人形遣いにもたとえられ、たわむれに「ホラ丸」とも呼ばれた人物です。豪快な人間であるいっぽう、いたずら心あふれる人物で、その「奮闘記」である『俗戦国策』には笑えるいたずら話も多く記されています。
また、「正史」には全くあらわれない舞台裏の貴重な史実証言としても極めて面白いもので、日本近代史の理解に厚みをもたせる上で重要な一書と思います。この種の人物や歴史的側面は、はっきりしない部分が多いことと、戦後学術界の政治的な価値観からは受け入れにくいことがあって、アカデミックな考察・議論ではこれまで全くといっていいほど取り上げられてきていませんが、日本近代史の貴重な証言者であることは否めないでしょう。貴重な証言者であることは、例えば、『歴代総理大臣伝記叢書・全32巻』(東京大学教授御厨貴氏監修・ゆまに書房刊)
 の山県有朋と桂太郎の巻に杉山茂丸の著作が採用されていることにも示されているように思われます。
の山県有朋と桂太郎の巻に杉山茂丸の著作が採用されていることにも示されているように思われます。
お手に取っていただければ幸いです。
*杉山論法の一例を杉山茂丸著『百魔』(当社近刊)からご紹介いたします。
日本工業化のための日米資本融通交渉を志して渡米し、当局の紹介状一本もなしに大資本家J・P・モルガンから一億三千万ドルの借款話をとりつけて、時の大蔵大臣井上馨に議を移したときの話です。杉山の献策を相手にしようとしない井上ですが……。
「《……貴下(あなた)は、貴様のような小僧といわるるが、貴下が明治八年、大蔵卿をした時は四十歳です、僕は今三十七歳です。貴下はたった三ツの違いで、僕を小僧と罵って、財政を論ずる資格がないと、どなりますか。もちろん、人間は年に関係なく賢愚はありますが、貴下は怜悧で、僕は馬鹿という。どんなメートルを持っておれば僕に対して小僧呼ばわりをしますか。また、貴下が国家に尽くすのは月給を取って賃銭片手にした国政ですよ。僕は一文も賃銭を取らず、国民が不憫じゃから自費で世話をするのですよ。貴下は勲等官爵という、国家の名誉権力を以て国政をするのですよ。僕は無位無官で国家に奉公するのですぜ。貴下は困ればしばしば辞表を出して、責任を回避しますが、僕は十六歳より今日まで、一度も国事に辞表を差し出しませぬぞ。サァ、貴下の明答を聴くまでは、敬語を以て物をいいますが、いたずらに非理を以て国家忠勤の士を罵った以上は、答えが出来ねば、僕も受けただけの恥辱は、きっと倍加して報いますぞ》と詰め寄せた。ところがこの大蔵大臣は実に人格のいい人で、非を悟ったらいかなる人にでも直ちに豁然として謝る人ゆえ、《イヤ、これは僕が悪かった。気にさえてくれたまうな。ゆっくり話も聞き、書類をも拝見しよう》といわれたので、庵主は直立して今の無礼を謝し、諄々と説いたら、非常に氷解せられて……」(漢字仮名表記等変更してあります)
2006年3月は『宮崎滔天 アジア革命奇譚集』(宮崎滔天著)と『評伝 宮崎滔天』(渡辺京二著)を刊行いたします。
.jpg)
.jpg)
『宮崎滔天 アジア革命奇譚集』『評伝 宮崎滔天』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、明治・大正時代に活躍した「元祖実践的アジア共同論者」とでも言うべき宮崎滔天の『宮崎滔天 アジア革命奇譚集』と、『逝きし世の面影』の渡辺京二氏による『評伝 宮崎滔天(新版)』を刊行いたします。
現代中国の出発点となった1911年辛亥革命に結実する革命運動のリーダーであった孫文が、最も信頼した同志の一人は日本人の宮崎滔天でした。中国革命は当時の清朝腐敗政権を倒そうという運動でしたから、孫文は中国国内にいられずに、世界を説き回りつつ革命運動の拠点を日本においていましたが、その右腕となって働いたのが滔天でした。滔天と孫文が生きた時代は、日本がすっかり軍国主義化してしまう前の時代で、迫りくる西欧植民地主義の嵐に対してアジアが課題を共有しえた時代でした。この時代まで遡って近代における「アジアの共同」の意味を考える必要がありはしないかと考えてこの二冊を刊行いたします。
『宮崎滔天 アジア革命奇譚集』には、「《新浪花節/慨世危譚》 明治国姓爺」と「狂人譚 《ナポ鉄+釈迦安+道理満》」を収録してあります。アジア革命への中国革命に挺身した滔天が、その思想をフィクションに昇華させた“隠れた名篇”です。大アジア主義と国家主義を超える可能性をはらんだ滔天の思想については、渡辺京二氏の『評伝 宮崎滔天』のなかに明快な一節があります。こちらに引用しておきましたのでご参照戴ければ幸いです。

渡辺京二氏の評伝は、「情の人、豪傑」と見られがちな宮崎滔天を、デリケートな「知の人」として論じる不朽の名著で、渡辺氏のロングセラー『北一輝』と双璧をなす氏の代表作です。この機に当社から新版で復刊させていただくことになりました。今回、新版に際して寄せていただいた「あとがき」には次のように記されています。
――「評論集『小さきものの死』、『北一輝』、それにこの本の三冊で、私は日本近代に関する自分の基本的構図をほぼ描き了えている。しかし、私も三十年前の私ではない。基本のアイデアは保持しているつもりだが、今ではもっと広い見かたができるはずだ。昔の主題をもう一度展開し直す時間はまだ残っているだろう。」
*
対中関係、アジア共同体論の模索において「歴史を鑑に」することは欠かせません。その「歴史」の範囲をもう一歩遡った時代まで拡げる試みに、今回刊行の二冊が役立てばと念じております。お手に取っていただければ幸いです。
2006年1月は『頭山満言志録』(頭山満著)を刊行いたします。
.jpg)
『頭山満言志録』刊行にあたって(書肆心水)
当社では昨年刊の『北一輝思想集成
 』を手始めに、日本近代史を考察する上で重要ながら、マイナスのイメージが大きいせいか出版が手薄なものを掘り起こして参りたいと考えておりますが、今月はそのうちの一つ、筑前玄洋社のシンボルとして著名な頭山満の言葉を編集した、『頭山満言志録』を刊行いたします。(この流れの近刊としては宮崎滔天・杉山茂丸の著作刊行準備を進めております)
』を手始めに、日本近代史を考察する上で重要ながら、マイナスのイメージが大きいせいか出版が手薄なものを掘り起こして参りたいと考えておりますが、今月はそのうちの一つ、筑前玄洋社のシンボルとして著名な頭山満の言葉を編集した、『頭山満言志録』を刊行いたします。(この流れの近刊としては宮崎滔天・杉山茂丸の著作刊行準備を進めております)
明治~大正~昭和と、国政NGOとして活躍した頭山満ですが、戦後はGHQによる「侵略戦争推進団体玄洋社」の定義に従い、言わば闇へと葬られ、マイナスイメージが大きくなって現在に至っているようです。戦後急速に転換した価値観を歴史に遡って客観化するのに相応しい時代を迎えている今、例えばこの頭山満の位置は、その存在が極めて大きかっただけに、確認する意義があると当社は考えております。
「アジア諸国といかにつながるか? しかも歴史をふまえた上で」――これが国家外交としても、民間交流としても日本の大きな課題となってきている今、近現代日本の出発点において「アジア復興のための連帯」を課題とした民間勢力の代表者である頭山満の思想の勘所は、おさえておく価値のあるものと思います。それに加えて、日本に亡命してきた朝鮮独立党の首領・金玉均や、中国民族解放革命家・孫文らを援助し、また昨今『中村屋のボース』で話題となっているインド独立運動の亡命志士ボース保護の立役者となった頭山の事績も、その思想との関係においておさえておく意味のあるものと思います。
「右翼の大物」と言って済まされがちなこの頭山については、その事績が詳細に記されている代表的出版物に『頭山満翁正伝(未定稿)』(1981年葦書房刊)があります。同書は1942年の頭山満米寿を記念して発足した「頭山満翁正伝編纂委員会」による原稿を本にしたものですが、当時出版がならなかったのは、同書「跋」に記されているところを引けば、委員の責任者が「目を通し、筆を加えて、原稿を岩波書店に渡されたのだが、岩波の神田の工場が戦禍にかかって、その原稿が焼失してしまったとか」の事情によるものです。後年控えの原稿が見つかり葦書房版として日の目を見ました。進歩的な岩波書店と頭山満に接点があったのは、今の目から見れば意外なことと感じられるかもしれません。これは一つの例でしょうが、歴史の現実は、遡って過ぎた時代のなかでその意味をつかみなおす必要があることを思わせられます。
なお本書には、若い方々にも関心をもっていただけるきっかけとなればと思い、夢野久作による面白く優れた頭山論をあわせて収録致しました。
お手にしていただけることを祈念しております。
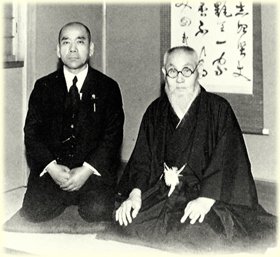
葦書房刊『頭山満翁正伝』より引用。同書写真キャプション「本書を出版するはずであった岩波茂雄と」
2005年12月は『出版巨人創業物語』(佐藤義亮・野間清治・岩波茂雄著)を刊行いたします。
.jpg)
『出版巨人創業物語』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、百年の歴史を経て今なお堂々たる大版元の業界三大個性、「文の雄・新潮社」「談の雄・講談社」「学の雄・岩波書店」の創業者による、創業期の自伝文集、『出版巨人創業物語』を刊行いたします。(著者名配列は創業順といたしました)。
佐藤義亮氏(新潮社)が、文芸雑誌『新声』をもって新声社の旗をあげたのは、1896(明治29)年のこと、文学への熱い思いを抱いて秋田から上京し、秀英舎(大日本印刷前身)校正係を務めながらの、満18歳の年でした。
野間清治氏(講談社)が、世に弁論熱高まるころ、その活字メディアの実現を志し、雑誌『雄弁』をもって大日本雄弁会の旗をあげたのは、1909(明治42)年、満31歳の年でした。
岩波茂雄氏(岩波書店)が、女学校教師を勤めるなかで「人の子を賊(そこな)う如きことよりほか出来ない教育界」に身を置く事に煩悶し、心安らかにいられる市民の生活、たまたま縁あったところの古書新刊小売の商売で「腰掛けの生活」を始めたのは、満32歳の年でした。(翌年、漱石著『こゝろ』をもって出版業に移行)。
三氏が出版の仕事を始めた時代は、日露戦争という近代日本史の大きな転換点の前後であり、維新日本が知的にも大いに丈を伸ばさんとして、階層・分野を問わす摂取すべきものに餓えていた時代であったといってよいでしょう。転じて現在。下手な譬えですが、言ってみれば知的な飽食・栄養過多と運動不足というところでしょうか。この時代における出版状況は、その世情に応じたものとなっており、三巨人が仕事を始めた時代とはだいぶん様子が違っています。
とはいうものの、この三人の「創業話」は、時代をつらぬく出版業の根元の話であるように感じました。システムが熟し自律化の度合いを高めるにしたがって、生身の人間が事を起こしにくくなるのは歴史の必然でしょうから、若い人が無謀に挑戦するのが大変困難な時代となっているわけです。しかし、そのような段階もいよいよ煮詰まった感のある現在、どの業界においても、若い人たちの小手先ではない冒険を励ましたいものです。
本書は、自社・業界関係者向けの非売品等から、企画の趣旨にかなう文章を取り集めて構成いたしました。これらの自伝文を拝読しておりますと、大物こそスタートは無謀なものだ、若さと断固たるやる気が根本であって、下手な経験や知識があっては大物にはならないのだろう、なるほどなるほど実に面白いなぁ、と感じましたので、業界外の読書人一般にも是非読んでいただきたく、また、深い活気に欠けている今の出版業界を原点からふりかえるよすがとなればと念じ、一冊の本にいたしました。
お手にしていただけることを祈念しております。
2005年11月は狩野亨吉(かのう・こうきち)著『安藤昌益』を刊行いたします。
.jpg)
『安藤昌益』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、安藤昌益の発掘者、狩野亨吉の小選集を刊行いたします。
江戸期の独創的な社会思想家である安藤昌益は、わりとよく知られた人物かと思いますが、狩野亨吉となると、聞いたことないなぁ、とお感じの方も多いと思います。じっさい、狩野亨吉は、生涯一冊の著書も出版していません(考えあってのことだったようですが)。
それなのに著名人の部類であるのは、まずは狩野が安藤昌益の発掘者だからです。江戸時代にその過激思想をひそかに綴った安藤昌益は、明治の終わりになって狩野によって「発見」されるまで無名の存在でした。狩野は若い頃から日本思想史の探究を志し、並々ならぬ古書収集を続け、そのなかで安藤を「発見」します。狩野はたまたま手に入れた『自然真営道』原稿本百巻を読み、最初は気狂いではないかと思ったそうですが、精読するうちにその独創性に驚きます。
狩野は後に、その貴重な百巻を東大図書館に売ってしまうのですが、売却したその年のうちに、関東大震災のためそのほとんどが焼失し、いま「安藤昌益全集」に収録されているのは焼失をまぬかれたごく一部分です。狩野はその百巻を精読した、後世の人が代わりえない証人となりました。その狩野が書いたのが不朽の名論文「安藤昌益」です。今なお「昌益に関心をもったら先ずこれを」という基本文献と言われながら、手に入れにくかった「安藤昌益」をこのたび小選集に収めて刊行いたします。
漱石の親友として紹介されることも多い狩野ですが、漱石と親しいから偉いということはないわけで、その偉さは他所にあります。著書もないのに多くの知識人から称賛され続けるのは、安藤の発掘者だからというだけでなく、狩野が百科全書的な比類なき思想家であること、その倫理生活が並でなかったことによっています。
官製大学勤めと学問は両立しないと考えて、一高校長~京大学長という超一流コースと43歳できっぱり決別。退官後、一時かかわった企業が破産し、その巨額の借金をひとり背負って、後半生は書画鑑定業を営みながら、書見と思索に耽った奇人です。徹底した物理学的実証精神によって、争いを用いることなく不正を抑えるコツとは何か?と考え続けた人間でした。なお、春画収集も一流、生涯独身、その意外(?)な性生活も人々の関心を引いてきました。公表論文は片手で足りる数ですが、その珠玉の数篇を小選集の形にして、読者諸賢と「狩野思想との出会い」の機会とすることができればと考えました。
書籍紹介ページに、著者略年表・読書案内などを記しました。

お手にとってご覧いただけることを祈念しております。
2005年10月は『イラン・イスラーム体制とは何か』を刊行いたします。
.jpg)
『イラン・イスラーム体制とは何か』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、本邦初の本格的現代イラン政治・国家論を刊行いたします。
アメリカ覇権主義の次なる最大ターゲットはイランであると陰に陽に語られています。対するイランでは、この六月の大統領選挙でおおかたが予想できなかった結果となり、対米最強硬派・庶民派の大統領(アフマディーネジャード)が誕生しました。新大統領はさっそく国連の場などで、妥協なき抵抗の姿勢を示しています。アメリカ覇権主義勢力は、国内事情や相変わらず不安定なイラク情勢等の課題もあって直接的な働きかけはなかなかできないでしょうが、長期的に最大の戦略的懸案としていることは明白です。
今回の大統領選までの8年にわたるハータミー政府時代には、その開放的な方向性に先進世界の期待が寄せられ、日本でも肯定的な報道・出版が目につきました。しかしイラン国内の状況としては、サッダーム・フセインが采配を振るイラクとの長い戦争で大打撃を受けた国家経済と庶民の暮らしの建て直しに依然明るい兆しはなく、イラク戦争を経た今現在、アフマディーネジャード新政権が誕生したというなりゆきです。
日本の4倍半の国土に6,800万人が暮らすイラン(イラン・イスラーム共和国 Islamic Republic of Iran)は多くの日本人の日常生活にとっては縁遠い国と感じられ、むしろペルシアの時代の彼の地のほうに親近感を覚えることもあるでしょう。日本人の中堅世代以上にとっては、79年のホメイニー(イスラーム)革命の国として、若年層の日本人にとっては首都圏の「周辺」に群がる「イラン人」としての印象くらいしかないかもしれません。79年革命当時のニュース映像に表現された最高指導者ホメイニーのイメージは今のビン・ラーディンのそれに類似したものとして目に映ったこともあるでしょうし、稼ぎのために日本にやってきたイラン人と見られる人たちを目にして身構える思いをした方もおられるかもしれません。
第二次世界大戦が終わり、帝国主義・植民地主義は徐々に克服され、大筋においてそれは過去のこととされているかもしれません。しかし、「アメリカ覇権主義に徹底して抗うイラン」という国の現在は、それが終った問題どころか、呼称や論じ方がグローバリゼーションとかユニラテラリズムとかに変更されるにせよ、また様相・度合いとしては100年前、50年前のありかたとは違ってきているにせよ、世界史上の意味としてはうねりながらも一繋がりのものであることを訴えている数少ない主権国家の存在様態であると思われます。そしてその抵抗にはイスラームという宗教・社会生活思想が基礎イデオロギーとして位置づいていることは確かです。
上記の見解は『イラン・イスラーム体制とは何か』の著者のものではなく、当社の見解なのですが、このような視角からの関心に限らず、「現代イラン」を歴史的に、客観的に、正確に、詳しく知るための貴重な一書が『イラン・イスラーム体制とは何か』であると愚考いたします。
お手にとってご覧いただけることを祈念しております。
2005年9月は『ブランショ小説選(謎の男トマ/死の宣告/永遠の繰言)』を刊行いたします。
.jpg)
『ブランショ小説選』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、モーリス・ブランショの中短篇代表作のセレクションを刊行いたします。
『言語と文学』『私についてこなかった男』に続き、当社より三点目のブランショ作品の出版です。圧倒的な才能と磨き上げられた思索をもって鳴るモーリス・ブランショの邦訳書が、現在あまり店頭で売られていないことを残念に思っておりましたので、後発の出版社にできる範囲で公刊販売の任をつとめたく、このような小説選を刊行いたしました。値段はあまり安くできませんでしたことをお詫びいたします。
小説でなく評論のほうからブランショの世界に入られた方も多いかと存じます。ブランショの小説と評論の関係については、読者それぞれお感じになるところが違うと思いますが、このたび『ブランショ小説選』の刊行に際して、ジョルジュ・バタイユの見解をご紹介いたします。ブランショの評論がお好きな方がブランショの小説にも触れてみる縁になればと思います。(この話題は当サイトにて「批評家ブランショの小説について」と題した記事として既載ですが(こちら
 )、この機にここでも紹介させていただきます。)
)、この機にここでも紹介させていただきます。)
下記バタイユの引用文が最初に掲載された出版物は、フランス(語)の雑誌 Gramma(1976)3/4です。引用文は清水徹氏のご翻訳になるものを引かせていただきます(『現代詩手帖』1978.1.20)。この文章は1954年ころに書かれたらしいと推測されています。1954年ころと言えば、ブランショの、それなりのページ数をもつ小説の大部分が出版されたあとであり、いっぽう評論集のほうはと言えば、まだ第三評論集『文学空間』(1955)がまとめられるまえの時期ということになります。
後期ブランショの出版物は評論集の比率が圧倒的に高いのですが、それらの殆どはまだ単行本としては邦訳出版されていませんので、洋書をよく読んでいる方々を除いて、まだ批評家ブランショの全貌は広く親しいものとなりえていないのが現状と思われます。この現状は、以下に引く評言を書いたバタイユの立場に比較的近いといってよいでしょう。
バタイユはそのテクストを、次のように書き起こしています。
「モーリス・ブランショを、もっとも読まれているフランス作家のひとりに数えることはできない。彼の名声について語られるべきことといえば、文学の現況に通じている多くの人びとが、彼のうちに、現に活動中の批評家のうちでもっとも注目すべき存在を認めている、という以上を出ない。批評活動のほうは認められているとしても、彼の小説は読者の反感を買ったし、とくに、批評の側面と小説の側面とからなる彼の文学活動の全体的意味は、これまであらゆる人びとから理解されなかったとまで言える。」(バタイユ)
そして、ひとくさり話を進めた句切りとして、次のように書いています。
「彼の書く批評は、ときに唖然として言葉も出ぬほどの深まりを示す分析ぶりにどのような関心が注がれようと、彼の作品活動の二次的な、より接近しやすい側面にすぎない。」(バタイユ)
2005年8月は『北一輝思想集成』を刊行いたします。
『北一輝思想集成』刊行にあたって(書肆心水)
※初版『北一輝思想集成』ページは廃止しました。
今月は、北一輝の姿をつかむ基本選集を刊行いたします。(内容ご案内ページ)

初の新漢字・ひらがな表記、補助ルビ使用などにより、読みやすさを志向した、現代版・全文収録版です。
2.26事件の軍法裁判判決による銃殺刑で広く知られる北一輝(1883-1937)については、あらためてのご紹介は必要ないかもしれません。その人生を紹介し論じた記事・作品は、出版物に限らずかなりの数にのぼるようです。また、北一輝の著作がはらんでいる思想的意義については、古くは久野収氏の優れた論考数篇、渡辺京二氏の歴史に残る名評伝一冊、それからいまや「北論者と言えばこの人」の感ある松本健一氏が連ねた大きな仕事があり、ほかにも敬重すべき仕事が多々なされています。
恐らくその人生の最期のあり方が然らしめたことでしょう、北一輝といえば「右翼の危険人物」というイメージが当時から強かったようです。そもそも「右/左」という見かたは、「右あっての左、左あっての右」という、もっとも典型的に相対的なとらえかたであるわけですが、北一輝の場合は、右からは左と見られ、左からは右と見られてきたように、「右/左」という二項対立の政争的分類はしにくい種類の人物といえるでしょう。「右/左」という規定には、北一輝本人が若い頃からかなり意識的であったことがその著作から読み取れます。同時にまた、「右/左」という規定に全く意義を見出していなかったことも読み取れます。
ドラマ的な人生の諸相にも関心はつきない北一輝ですが、その「著作」はどれほど読まれているのだろうか、という思いから、『北一輝思想集成』という一書を作成いたしました。時代が移り変わり、当然のことながら古いタイプの漢字や文体・語彙・教養はもはや受け付けない世代が増え、また本を「買う」ということが暮らしのなかでもつ意味もだいぶ変わってきたこの頃、そのことを意識して、編集と価格設定に及ばずながら努めました。
ところで北一輝をモチーフとした創作活動の一つに、手塚治虫氏の漫画『一輝まんだら』があります。『一輝まんだら』は長篇連載として構想された企画だったようですが、その企図は中途挫折しました。単行本としては二巻で出版されており(出版状況はこちらをご参照下さい
 )、主人公であるべき北一輝が登場してほどなく作品は中絶しています。単行本の『一輝まんだら』の作者あとがきには、『一輝まんだら』が長篇として構想されたものであること、連載を掲載している雑誌の方向性が変わってきて連載が続けられなくなったこと、そして、その続きをやらせてくれる媒体を求めていること、が記されています。けっきょく手塚氏に対して「申し出」はなかったのでしょうか、『一輝まんだら』は永久に途絶しています。北一輝はここでもまた、「場所なき場」を生きることになったような気がします。
)、主人公であるべき北一輝が登場してほどなく作品は中絶しています。単行本の『一輝まんだら』の作者あとがきには、『一輝まんだら』が長篇として構想されたものであること、連載を掲載している雑誌の方向性が変わってきて連載が続けられなくなったこと、そして、その続きをやらせてくれる媒体を求めていること、が記されています。けっきょく手塚氏に対して「申し出」はなかったのでしょうか、『一輝まんだら』は永久に途絶しています。北一輝はここでもまた、「場所なき場」を生きることになったような気がします。
そうしたわけで、手塚治虫氏の『一輝まんだら』では、北一輝はごく後の方であらわれるだけですが、この『一輝まんだら』という作品は、西欧植民地主義の暗雲がいよいよ厚く垂れ込めてきた時代の、清朝腐敗政権のもとで生きる中国のようす、そしてそれを克服しようとする民族解放革命運動の息吹を今に伝えるもので、東アジア現代史原点の歴史紹介に与って大いに力ある佳作です。その歴史の流れのなかに北一輝を史実どおり位置づけたところに、手塚氏の歴史認識が察せられます。手塚氏の慧眼は北一輝の「場所なき場」を感じ取り、その「場所なき場」をたいへん巧みにイメージ化しています。下手な紹介はさておき、百聞は一見にしかず、その一シーンを以下に謹んで引用させていただきたいと思います。北一輝23歳の時、とどのつまりは自分が発行者になっての自費出版しか道がなく、また、恐れていたこととはいえ発禁になってしまった千ページの大冊『国体論及び純正社会主義』の公刊を模索する北一輝の姿を描いたシーンです。
(C) 手塚治虫(引用出典『一輝まんだら』)
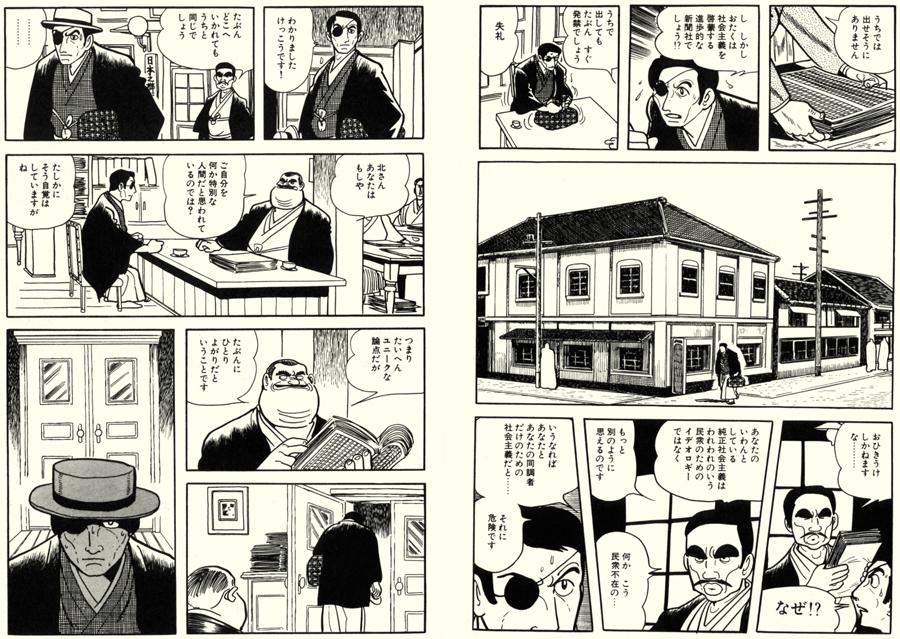
愚考するに、北一輝の「場」というものは、青年期からその死に至るまで、およそこのようなものだったのだろうという気がします。
同時にしかし、処刑の朝、看守兵に与えたとされている北一輝の絶筆は次のようなものでした。
「獄裏読誦ス妙法蓮華経、或ハ加護ヲ拝謝シ或ハ血涙ニ泣ク、迷界ノ凡夫古人亦(また)斯クノ如キ乎
八月十九日 北一輝」
個と共同体、超越的悲劇、ということを重く考えさせる数少ない人間の一人、北一輝が書きのこしたものを、皆様にもご一読いただけることを祈念しております。
2005年7月は『イスラーム概説』を刊行いたします。
『イスラーム概説』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、イスラームを知るための世界的定番を刊行いたします。
10年前には予想しにくかったことですが、近年イスラーム関係の啓蒙書が多数出版されています。しかし、『イスラームの構造』(当社刊)の書評で立花隆氏が「最近、さまざまのイスラーム論、イスラーム社会論が出ているが、イスラームの教えの核心部分に対する理解を欠いたものが多く、枝葉の説明に終始して、イスラームへの無理解がかえってはびこるばかりという黒田の指摘は、その通りだと思う」と仰るように、一種の情報過多で、むしろ良質の情報選択が難しいという状況を招いているとも言えるでしょう。
今回刊行する『イスラーム概説』は、イスラーム諸学に精通した著者が、パリ・イスラーム文化センターの求めに応じ一般向けの文明紹介として書き下ろしたもので、十数言語に翻訳されている、世界で最も定評ある正確な入門書です。
1908年にインドに生まれた著者ムハンマド・ハミードッ=ラーは、インドのイスラーム学の中心、オスマーニーヤ大学で基礎的諸学を修めたのち、ドイツのボン大学で博士号を取得(イスラーム国際法研究)、インド帰国は政治的混乱のため果たせずに、1948年以来パリの高等研究機関に所属して旺盛な研究・教育活動を続けました。1996年にアメリカに移住し、2002年に他界するまでの間に、英・独・仏語、アラビア語、ウルドゥ語等で40冊の著作、約700の論文を残し、教育面では長らく客員教授を務めたトルコで多くの優れた弟子を育成しています。
著者の業績は多岐にわたりますが、とりわけ評価が高いのが、この『イスラーム概説』とクルァーン(コーラン)の仏訳です。アラビア語の原典を深く渉猟してえられたイスラームに関する一級の知識と、長い西欧世界の滞在により体得された「他者の視線」とが織りなされて結実した『イスラーム概説』は、稀代の著者による得がたい著作といえるでしょう。
『イスラーム概説』には、聖典クルァーンの深い知識に基づいて、随所に適切なクルァーンの引用がちりばめられています。細部に拘泥して全体の構造を見失うことのない、部分と全体の関わりをおさえた内在的で包括的なこの概説書を、イスラームのアウトラインを正確につかんでみたいとお考えの皆様に謹んでおすすめ申し上げる次第です。
2005年4月は『私についてこなかった男』を刊行いたします。
『私についてこなかった男』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、モーリス・ブランショの「最後の初訳小説」を刊行いたします。
『文学空間』(現代思潮新社)『明かしえぬ共同体』(朝日出版社・ちくま学芸文庫)『ミシェル・フーコー』(哲学書房)などの評論作品でおなじみのモーリス・ブランショは、おととし95歳の長い人生を終えました。
レヴィナス、バタイユ、フーコー、デリダらと相互に深い影響を与え合った「20世紀思想・文学の極北」ブランショは、作者と作品の関係についての独特な思想から、私生活や写真を公にしないことで有名でした。死後の今、伝記の出版もあり、また秘められてきた諸相のヴェールも徐々にはずされ、ブランショ再評価の機運が熟してきました。
批評家ブランショの価値は広く認められてきたようですが、小説家ブランショの価値はあまり充分に認められてこなかったのではないでしょうか。しかし、デリダが『海域』『滞留』などの作品で示したように、ブランショのフィクションは、その評論作品同様、ブランショ・ワールドの核心を表現しています。(
 批評家ブランショの小説についての話題はこちらもご覧下さい。)
批評家ブランショの小説についての話題はこちらもご覧下さい。)
今回刊行する『私についてこなかった男』は、数あるブランショの小説作品の中で、言語の謎を探究するブランショの個性がもっとも研ぎ澄まされたかたちをとった「哲学小説」といえるでしょう。訳者は、ブランショの『望みのときに』(未来社)を翻訳された谷口博史氏です。ブランショの読み手として魅力的な仕事を書き連ねてきた谷口氏ならではの澄明な翻訳になっていると思います。
谷口氏には「漱石・ブランショ・リルケ・類似」をめぐる長篇解説を寄せていただきました。《「死」の思想家》として長く語られてきたブランショですが、谷口氏のこの長篇解説は、表立ったキーワードとしての「死」という文言が地の文にはあらわれない、画期的なブランショ論だと思います。
当社では本書を皮切りに、ブランショの小説作品をいくつか刊行する予定です。ブランショの小説はすらすら読める種類のものではありませんから、活字は大きめに、行間は広めにして、できるだけゆったりした気分で読めるような体裁を選んでみました。

2005年3月は『『モモ』と考える時間とお金の秘密』を刊行いたします。
『『モモ』と考える時間とお金の秘密』刊行にあたって(書肆心水)
今年は、『モモ』や『はてしない物語』などの人気作をとおして現代文明へのユニークな問題提起をしてきた作家、ミヒャエル・エンデが亡くなって10年の節目を迎えます。
昨年末には、エンデ日本語版の出版元・岩波書店から新しいエンデ論『エンデを旅する』(田村都志夫氏著)が刊行され、全集の第三次刊行もこの4月から始まるようです。命日の8月にむけてさまざまな動きが期待されます。
当社でもこの期に境毅著『『モモ』と考える時間とお金の秘密』を出版いたします。『モモ』からの引用、エンデ全集からのエンデの言葉の引用をまじえたやさしい記述で、『モモ』未読の人も「なるほど」と読めるように工夫しました。
いっぽう、マルクスの価値形態論・物象化論を理論的な軸にすえ、人文社会科学書としての読み応えという点も重視いたしました。数ある『モモ』論のなかでも個性ある一冊になったかと思います。著者の境氏は、生協活動や引きこもりサポートのNPOなどに従事し、『モモ』が提起している問題を日々具体的に考え続けてきた人で、それらの経験が、机上の理論ではないリアリティある語りにつながっていると思います。
エンデは『モモ』のなかで、「なぜなら時間とはいのちだからです。そしていのちは心に住まうのです」という言葉を記しています。本書はこのエンデの視点から出発して、身近でも世界でも、世の中がイライラ、カリカリしていることの深いわけを、「経済・社会・文化の問題」=「時間の問題」として考える試みです。
いま、「仕事への引きこもり」と「自室への引きこもり」へと世間が二極分化し、そのはざまでフリーター、うつ病が増加しつづけています。エンデの『モモ』と一緒に、時間、いのち、お金について考えてみませんか?
2005年1月は『イラク戦争への百年』を刊行いたします。
『イラク戦争への百年』刊行にあたって(書肆心水)
今月はイラク国民議会選挙前夜に、『イラク戦争への百年』(黒田壽郎編)を刊行いたします。
今アメリカ政府が推し進めようとしている単独主義的な「大中東構想による《民主化》」では、アメリカが望むような民主化どころか、全中東パレスティナ化の泥沼を招きかねないと懸念されます。世界の安定のために中東民主化はどうしても必要ですが、問題なのはその手続きでしょう。押しつけの民主主義は語義矛盾のそしりを免れません。
現状をめぐるジャーナリスティックな議論は百出しておりますが、事柄がひと言では片付けられない複雑な経緯と見えにくい背景を持っている以上、未来を探る上で必要なのは歴史を知り、それに学ぶことだと思われます。本書は「イラク戦争と歴史」という視点で問題に迫る仕事です。
中東およびイスラーム圏の組織的な過激派のみならず彼の地の民衆までによる絶望的な抵抗が、言葉を失う忌まわしい出来事を引き起こし続けているなか、この現実の意味するところを短い言葉で語ってしまうことは、語ろうとするその大切な意図に釣り合わない行ないだと当社は考えます。短く見ても百年の時間と、その時間そこに生きた個々の人間すべての生がそこに織り込まれていることに鑑みるならばです。ここには、起きている出来事を、「言い換えればこういうことではないか」というように語ること、あるいは現況の印象だけに拠って表現することを慎まざるを得ない厳しさがある以上、歴史を振り返るところから試みを始める以外にすべはないように思われます。
一冊の小さな書物で「百年」の意味を語りつくすことはもちろんできませんが、本書ではそのための糸口を示すことに努めました。読者の皆様とこの問題を考える縁となることを願いこの機に出版いたします。
上に述べたことと矛盾してしまいますが、値何億円のアパッチヘリコプターによる上空から砲撃に比して、地上からの小銃砲撃、あるいは身に着けた弾薬、場合によっては手で投げる石といった、比較することすら無意味と思われる行為を選ぶ人々のなかに折り畳まれたものへの想像力、なぜそういうことをせざるを得ないのか、その人は何を胸に抱いているのかに思いをいたす想像力こそが、他意なく歴史を振り返る意志となるのではないかという思いもまた否めません。
2004年12月は『言語と文学』を刊行いたします。
『言語と文学』刊行にあたって(書肆心水)
今月は、『言語と文学』と題した当社オリジナル編集の作品選を刊行いたします。著者は、モーリス・ブランショ、ジャン・ポーラン、内田樹ほかです。
独特な評論・小説で著名なモーリス・ブランショが、文芸批評家としての記念すべき第一歩を記した小さな本『文学はいかにして可能か』は、『O嬢の物語』の作者と長く噂された「文学界の黒幕」ジャン・ポーランの、言語と文学表現をめぐる名作『タルブの花――文学における恐怖政治(テロリスム)』を論じたものですが、そこには研ぎ澄まされた「言語=文学」への省察、言語と人間をめぐる謎が示されています。本書には、『文学はいかにして可能か』と問題を共有する、「言語についての探求」、「文学における神秘」の二篇をあわせ、三篇を収録いたしました。
当社では今後、力の及ぶ範囲でモーリス・ブランショの作品を出版したいと考えておりますが、上記のブランショ初期の評論が、ブランショ・ワールドの始原的な場へと読者をいざない、ブランショ(再)入門の機縁となることを念じております。ブランショの作品がほとんど新刊市場に見られない今、本書が、ことに若い世代とブランショとの出会いの場の一つとなることを祈る気持ちです。ジャック・デリダが最も敬愛し、課題を共有した文学者モーリス・ブランショの世界にぜひ触れてみて下さい。
本書収録のポーラン著『タルブの花』(野村英夫氏訳)は、かつて一度、単行本として1968年に晶文社より出版されました。著者ポーランの日本での知名度や、謎めいたその作風、またその書名の故でしょうか、長く新刊市場でこれを求めることはできなくなっていました。ある研究者からは、80年代には既に古書の入手も難しく、図書館の本をコピーして綴じたものです、との話も聞きました。作品への高い評価の一方で、国内商品としては難しい事情を抱えていたようです。ブランショの、タイトルからしてその代表作の一篇とするに相応しい「文学はいかにして可能か」が『タルブの花』論であるにもかかわらず、残念ながら売れ続けることが難しかったこの名作に今一度日の目を見させたいという思いが、この企画のそもそもの始まりにありました。
言語と文学をめぐる独自な深い思索が綴られたブランショの上記三篇は、前提となる『タルブの花』との併読によって互いに増幅しあってゆくものです。
内田樹氏には「面従腹背のテロリズム」のご寄稿をお願いしました。これは、今やレヴィナス論者・訳者として、また数々の自著にて既に名をなしておられる内田氏がブランショ研究者であったころの仕事ですが、《「文学はいかにして可能か」のもう一つの読解可能性》を探るこのユニークな論考は不朽の価値をもつものと思われます。「もう一つの読解」の迫力もさることながら、30年代に「極右」の論説を書き連ねていたブランショの、同時代思想史検証も、内田氏ならではのしっかりした知識に基づく読み応えのあるものです。ブランショが政治評論から文芸評論にシフトすることの意味を探る上での必読作と思われます。
ブランショの三篇は、単行本収録のヴァージョンについては優れた先行訳のあるものもありましたが、それも新刊市場から姿を消して久しく、また、本書では諸版対照(初出紙誌版/単行本版/評論集版)の翻訳を試みるためと、訳文の統一感を重んじるために、ブランショ研究者・山邑久仁子氏にあえて新訳を依頼しました。「諸版対照」にはやや煩雑な印象の向きもあるかと思いますが、興味深い書き換えもみられます。
拙い編集ですが、古典の力が言語と人間の謎に向き合う読者の思索をあらためて促すことを信じて、本書を出版いたします。
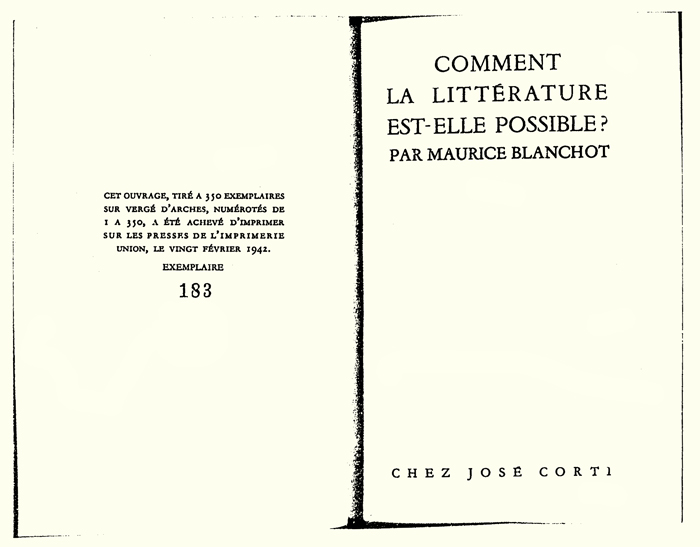
2004年11月は『ひとつの町のかたち』を刊行いたします。
『ひとつの町のかたち』刊行にあたって(書肆心水)
今月は20世紀フランス文学の巨匠、ジュリアン・グラック氏の後期主著を、初訳で刊行いたします。
1910年生まれのグラック氏は、90歳をこえる今もお元気で、読書と執筆と散策の生活をお過ごしと伺っています。氏の著作は、すでに多くの邦訳書が出版されているのですが、今ではその多くが新刊書店では買えなくなっています。
青年期にアンドレ・ブルトンをはじめとするシュルレアリストと親交を結んで作家としての歩みを始めたグラック氏ですが、氏が一躍有名になったのは、1951年に出版された小説『シルトの岸辺』(ちくま文庫)と、その年のゴンクール賞拒否騒動によってでした。ゴンクール賞は、今では百年の歴史をもつ賞で、「フランス最高の文学賞」として広く認められています。
氏は騒動の前年に『胃袋の文学』という題名の「パンフレット(攻撃文書)」を発表し、すでにそのなかで、文学賞が招く新人作家の堕落が象徴する文壇の商業主義を批判していました。 この拒否表明については、宣伝効果を狙ったのではないかと批判する声もあったとのことですが、 氏が報道陣のフラッシュを浴びながら声明文を読み上げたのはこれが最初で最後で、結局辞退者に与えられた賞が他の作家に回されることはなく、この事件はゴンクール賞百年の歴史のなかでも特筆すべき出来事として、現在も人々の記憶に残っているようです。
このエピソードからしても反骨精神旺盛なグラック氏のようですが、『ひとつの町のかたち』の書きぶりは、むしろ穏やかなもので、エキセントリックでも相対主義的でもない独特な力強さとやわらかさを持っています。
小説というジャンルがもっとも息づきやすかった近代という時代、スタンダールやバルザックの小説の主人公が社会の階段をはい上がったり転げ落ちたりするさまに読者が夢中になれた時代が終わって久しい時代、また、近代的な小説を成り立たせていた社会や人々の意識そのものの崩壊を印象づけるヌーヴォー・ロマン的な作品にすら新鮮味を感じなくなった時代に、文壇や社会から距離をとった孤高の作家と見られてきたシュルレアリスム世代のベテラン作家としてグラック氏が80年代前半に書き綴った本書は、今後の文学の可能性を探る読者にとって意味のあるものと思います。
ジュリアン・グラック未読の方もお手にとってご覧下さればと存じます。
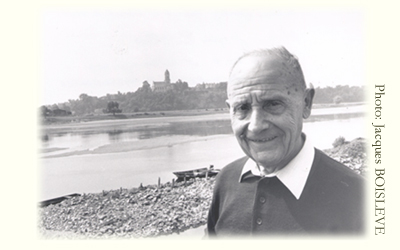
2004年10月刊『イスラームの構造』より出版活動が始まりました。
第一作『イスラームの構造』刊行にあたって(書肆心水)
当社の第一作はイスラーム論です。イラク、パレスチナの状況をはじめ、「グローバリゼーション」と呼ばれるものの負の側面、現在の世界の問題が中東情勢に集中的にあらわれていると思い、本書を旗揚げの企画に選びました。
著者は、イスラーム論の押しも押されぬ第一人者・井筒俊彦氏に導かれアラブ・イスラーム研究の世界に入り、その道を歩むこと五十年の黒田氏です。井筒氏がイスラーム哲学論等において金字塔をうちたてたのに対し、後輩の黒田氏は、哲学研究を経て、経済活動をはじめとするイスラームの社会運営全体を、その根本理念から日々の具体的な営みにいたるまでをフォローしたうえで、イスラーム文明の「構造」を、タウヒード、シャリーア、ウンマという三極構造として誰にも分かるように描き出しています。構想十年、ようやくこのたびこの企画が本になりました。
ご記憶の方も少なくないと思いますが、少し前にNHKの『イスラム潮流』という魅力的な番組と出版がありました[
 ]。「イスラムが復興している――イスラムの何が人々を惹きつけているのか」という視点によるものでしたが、本書はこの問いに、本格的な回答を与えるものと存じます。
]。「イスラムが復興している――イスラムの何が人々を惹きつけているのか」という視点によるものでしたが、本書はこの問いに、本格的な回答を与えるものと存じます。余談ながら、当社はイスラームを信仰する者ではありませんが、現在の米欧中心の世界を、本当の意味で「人びと」のものにするための社会運営の見直しに、イスラームの考え方が大いにヒントになるとも考えています。例えば、イスラームにおける利子の戒めや権威の否定と個人の平等という考え方は、道徳論的な「あるべき論」としてよりは、存在論的な客観的「現実」として考えられていることなどが本書には説かれています。また、アラブの人々がなにゆえあれほどの抵抗を示すのかの理由も分かるように書かれています。
「四人妻」などを初め、イスラームの社会というものは「遅れた不自由な社会」とされることが多かったと思いますが、それらをめぐる深い真実を、本書を通して皆様とともに考えることができればと思っております。